落語の「まくら」って?実際の傑作もご紹介します!
関連キーワード
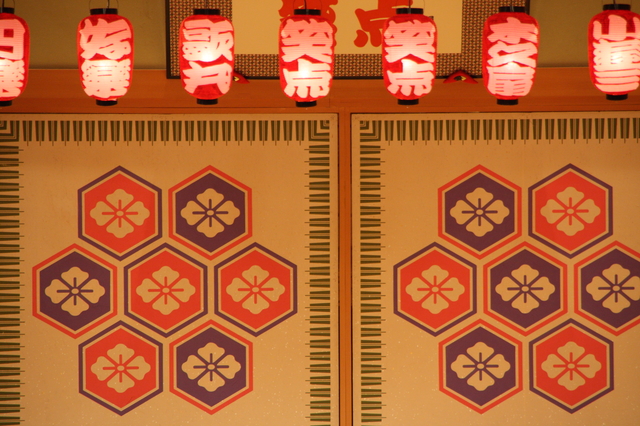
古くは江戸時代から人々に愛され続けてきた落語。そんな落語は、現在においてひそかなブームを来していることもあって、若い方から年配な方まで世代を問わず人気の伝統芸能でもあります。
そんな落語独特のワードとして、「まくら」というものをご存知でしょうか?もちろん寝る時に使用するふかふかのものではありません。実はこの「まくら」と呼ばれる部分は、とても面白く、落語を演じるにあたってなくてはならないものでもあるのです。そこで今回は、そんな落語の「まくら」について、実際に使用されている傑作ともいわれるものや、落語の仕組みなどを中心にご紹介していきたいと思います。
そんな落語独特のワードとして、「まくら」というものをご存知でしょうか?もちろん寝る時に使用するふかふかのものではありません。実はこの「まくら」と呼ばれる部分は、とても面白く、落語を演じるにあたってなくてはならないものでもあるのです。そこで今回は、そんな落語の「まくら」について、実際に使用されている傑作ともいわれるものや、落語の仕組みなどを中心にご紹介していきたいと思います。
落語に「まくら」は欠かせない?その言葉が指すものとは
まずは、落語の中でいう「まくら」とは何を指すのか、詳しくご紹介していきましょう。
落語でいうまくらとは、その演目へ入るさいの導入部分のことを言います。導入部分といっても、難しい言葉が出てくる演目などでその説明を述べたり、中には自己紹介を述べる時もあり、観衆、聴衆が本題の演目に入りやすくするための工夫の一つでもあります。
テレビ放送されている「笑点」を見たことがある方は、まくらも理解しやすいかと思います。おなじみの音楽の後、毎回異なるテーマに沿ったメンバーの自己紹介部分がありますよね。あの部分が、まくらと呼ばれる範囲となります。
まくらの多くは、古くから伝わる演目であればかわらないものであれば、本題とセットとなっています。まくらのみを変えることもあまりありませんし、またまくらのない演目もほとんどありません。通常落語家は、お話を始める前に、本題に関心を向かせるために必ずといっていいほどまくらを述べます。
落語でいうまくらとは、その演目へ入るさいの導入部分のことを言います。導入部分といっても、難しい言葉が出てくる演目などでその説明を述べたり、中には自己紹介を述べる時もあり、観衆、聴衆が本題の演目に入りやすくするための工夫の一つでもあります。
テレビ放送されている「笑点」を見たことがある方は、まくらも理解しやすいかと思います。おなじみの音楽の後、毎回異なるテーマに沿ったメンバーの自己紹介部分がありますよね。あの部分が、まくらと呼ばれる範囲となります。
まくらの多くは、古くから伝わる演目であればかわらないものであれば、本題とセットとなっています。まくらのみを変えることもあまりありませんし、またまくらのない演目もほとんどありません。通常落語家は、お話を始める前に、本題に関心を向かせるために必ずといっていいほどまくらを述べます。
「まくら」と「落ち」の関係性をご紹介!
まくらに対して、話の落としどころのことを「落ち」、そして大部分を「本題」ともいいます。
小説やお笑いでも、「はなしの落ち」などは大切だといわれていると聞きますが、落語でもそれは例外ではありません。落ちは言ってしまえばお話の結末、締めくくりです。落語がもともと「落とし噺」と呼ばれてきたように、落語はこの落ちが大切となります。
まくらは、そんな落ちへつながる本題と話しをつなげるための伏線の役割も果たしています。また、先ほどもちらっとご紹介した通り、落語では古くからの伝統芸能ならではの、難しい言葉も多く登場します。こういった言葉がわからないと、お話そのものを理解できないこともありますので、そうならないようにまくらで言葉の解説などを行うこともあります。
基本的に、落語の構成としては、まくら→本題→落ちの順番となっています。人情話や怪談話などは、滑稽な話のように落ちがないものがあるため、本題が大部分占めることがあります。また、本題に入っていない、落語家オリジナルの挿入部分のことを「くすぐり」ともいい、ほとんどが本題の内容に沿った面白おかしい内容となっています。
小説やお笑いでも、「はなしの落ち」などは大切だといわれていると聞きますが、落語でもそれは例外ではありません。落ちは言ってしまえばお話の結末、締めくくりです。落語がもともと「落とし噺」と呼ばれてきたように、落語はこの落ちが大切となります。
まくらは、そんな落ちへつながる本題と話しをつなげるための伏線の役割も果たしています。また、先ほどもちらっとご紹介した通り、落語では古くからの伝統芸能ならではの、難しい言葉も多く登場します。こういった言葉がわからないと、お話そのものを理解できないこともありますので、そうならないようにまくらで言葉の解説などを行うこともあります。
基本的に、落語の構成としては、まくら→本題→落ちの順番となっています。人情話や怪談話などは、滑稽な話のように落ちがないものがあるため、本題が大部分占めることがあります。また、本題に入っていない、落語家オリジナルの挿入部分のことを「くすぐり」ともいい、ほとんどが本題の内容に沿った面白おかしい内容となっています。
これがわかれば演目もわかる!?実際の落語のまくらをご紹介!
それでは実際に、寄席で使用されているまくらをご紹介していきましょう。
先ほどもご紹介して通り、演目によってそれぞれ使用するまくらは決まっているため、大まかな変更はほとんどありません。したがって、常連さんなどは、まくらのフレーズを聞いただけで演目が何なのかが把握できるそうです。
そうでなくても、まくらのテーマとする単語が多く登場することで、演目が何なのか把握できることもあるそうです。
たとえばまくらで茶道の話が多く出てきたら、「茶の湯」という演目であることがほとんどですし、昔の子供についてを語りだしたら「藪入り」という演目であることが多いです。
また、中にはまくらで演目を予想させておいて、いい意味で裏切ってくれる落語家の方もいます。まくら自体は決まったものが多いのですが、落語家によってオリジナル要素が盛り込まれることがほとんどですので、本題だけでなく、ほかにそういった楽しさを味わう方も多くいらっしゃるようです。
具体的に、傑作とも称されている有名なまくらをご紹介しましょう。たとえば母子の会話をテーマとして春風亭小朝師匠が取り上げたまくらは以下のようなものがあります。
子「お母さん、アメリカって遠いの?」
母「黙って泳ぎなさい」
あとは、桂枝雀師匠が赤道をテーマとして述べたまくらとして、以下のようなものもあります。
「わたくしが子供のころは海外旅行なんてのは夢のまた夢のでございましてね。あっこがれのハワイ航路なんてこと申しましてね。飛行機に乗っておりますとスッチュワーデスさんが右手の方をご覧ください、てなことを仰(おっしゃ)られまして。見ると海の上に赤っい線がずーっと、向こからこっちへズ~っと」
このように、まくらはその落語家一人ひとりで特色が出やすい部分でもあります。熟練の噺家ですと、本題だけでなくまくらもより一層楽しめるものでもあるのです。
いかがでしたか?
落語にとってのまくらは噺家の技量が出る部分でもあると思います。本題の導入部分として、ぜひまくらも堪能してみてください。
先ほどもご紹介して通り、演目によってそれぞれ使用するまくらは決まっているため、大まかな変更はほとんどありません。したがって、常連さんなどは、まくらのフレーズを聞いただけで演目が何なのかが把握できるそうです。
そうでなくても、まくらのテーマとする単語が多く登場することで、演目が何なのか把握できることもあるそうです。
たとえばまくらで茶道の話が多く出てきたら、「茶の湯」という演目であることがほとんどですし、昔の子供についてを語りだしたら「藪入り」という演目であることが多いです。
また、中にはまくらで演目を予想させておいて、いい意味で裏切ってくれる落語家の方もいます。まくら自体は決まったものが多いのですが、落語家によってオリジナル要素が盛り込まれることがほとんどですので、本題だけでなく、ほかにそういった楽しさを味わう方も多くいらっしゃるようです。
具体的に、傑作とも称されている有名なまくらをご紹介しましょう。たとえば母子の会話をテーマとして春風亭小朝師匠が取り上げたまくらは以下のようなものがあります。
子「お母さん、アメリカって遠いの?」
母「黙って泳ぎなさい」
あとは、桂枝雀師匠が赤道をテーマとして述べたまくらとして、以下のようなものもあります。
「わたくしが子供のころは海外旅行なんてのは夢のまた夢のでございましてね。あっこがれのハワイ航路なんてこと申しましてね。飛行機に乗っておりますとスッチュワーデスさんが右手の方をご覧ください、てなことを仰(おっしゃ)られまして。見ると海の上に赤っい線がずーっと、向こからこっちへズ~っと」
このように、まくらはその落語家一人ひとりで特色が出やすい部分でもあります。熟練の噺家ですと、本題だけでなくまくらもより一層楽しめるものでもあるのです。
いかがでしたか?
落語にとってのまくらは噺家の技量が出る部分でもあると思います。本題の導入部分として、ぜひまくらも堪能してみてください。


















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

