落語の基本!「ネタ」について、その仕組みや有名話をご紹介します
関連キーワード
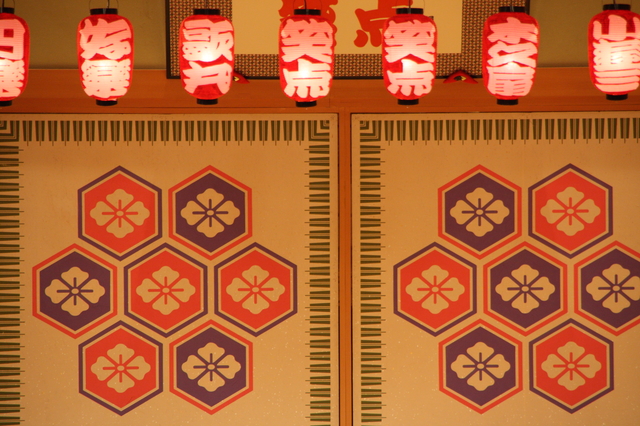
古くから日本で親しまれている伝統芸能の一つに落語があります。
落語は江戸時代に日本で成立した芸能で、今に至るまで伝わっている話芸の一種です。現在では、「落語家」と呼ばれる職業の方々がいろいろな落語を披露していますが、昔はそういった職業はなく、どんな人でも演じることができる身近なものでもありました。ここでは、そんな落語について、特に「ネタ」と呼ばれるものについて中心にご紹介していきたいと思います。
落語は江戸時代に日本で成立した芸能で、今に至るまで伝わっている話芸の一種です。現在では、「落語家」と呼ばれる職業の方々がいろいろな落語を披露していますが、昔はそういった職業はなく、どんな人でも演じることができる身近なものでもありました。ここでは、そんな落語について、特に「ネタ」と呼ばれるものについて中心にご紹介していきたいと思います。
落語のネタって?落語の仕組みをご紹介
お笑い芸人の方々も、いろいろな人に受けるようなネタ探しを挙ってされているそうですが、この「ネタ」は実は落語でも用いるものでもあります。
そもそも落語は、他の伝統芸能と比べて、観衆、聴衆の笑いを誘うような滑稽なものが多く演じられます。そのそれぞれの演目のことをネタといい、古くから伝道されているものから新しいものまで、人々を楽しませる演出がされているのです。
昔は落語というと、そういった滑稽な演目が多く演じられてきましたが、最近は怪談話や人情話なども多く演じられるようになりました。また、それぞれの話の最後の落としどころのことを「落ち」や「サゲ」、「はなし」とも呼び、それぞれ一人で何役も担当してその落ちへ観衆、聴衆を引き込むことが必要となります。
落語を実際に見たことがある方はご存知かと思いますが、落語は他の伝統芸能と比べて凝った衣装や小道具などをあまり使用しないことも特徴の一つです。歌舞伎や舞踏、能楽などは、同じ日本に古くから伝わる伝統芸能でも、衣装に凝っていたり、いろいろな小道具を使用するほか、動作も大きく、身体全体での動作が求められます。また、動作に合わせて音楽も必要となるため、たいていの場合舞台の後ろに人々が控えており、それぞれ音楽を奏でています。
それに対して、落語は扇子などを用いて身振り、手振りこそすれ、ほとんど座りきりで移動などはあまりありません。ほとんど小道具や衣装などを必要としないため、最低限の動作のみで観衆、聴衆を沸かせるような表現力も必要となってくるのです。そういった面では、落語は日本に古くからあるほかの伝統芸能と一線を画す、特殊な演芸でもあるのです。
そもそも落語は、他の伝統芸能と比べて、観衆、聴衆の笑いを誘うような滑稽なものが多く演じられます。そのそれぞれの演目のことをネタといい、古くから伝道されているものから新しいものまで、人々を楽しませる演出がされているのです。
昔は落語というと、そういった滑稽な演目が多く演じられてきましたが、最近は怪談話や人情話なども多く演じられるようになりました。また、それぞれの話の最後の落としどころのことを「落ち」や「サゲ」、「はなし」とも呼び、それぞれ一人で何役も担当してその落ちへ観衆、聴衆を引き込むことが必要となります。
落語を実際に見たことがある方はご存知かと思いますが、落語は他の伝統芸能と比べて凝った衣装や小道具などをあまり使用しないことも特徴の一つです。歌舞伎や舞踏、能楽などは、同じ日本に古くから伝わる伝統芸能でも、衣装に凝っていたり、いろいろな小道具を使用するほか、動作も大きく、身体全体での動作が求められます。また、動作に合わせて音楽も必要となるため、たいていの場合舞台の後ろに人々が控えており、それぞれ音楽を奏でています。
それに対して、落語は扇子などを用いて身振り、手振りこそすれ、ほとんど座りきりで移動などはあまりありません。ほとんど小道具や衣装などを必要としないため、最低限の動作のみで観衆、聴衆を沸かせるような表現力も必要となってくるのです。そういった面では、落語は日本に古くからあるほかの伝統芸能と一線を画す、特殊な演芸でもあるのです。
具体的な落語のネタをご紹介!
それでは実際に、具体的に行われている落語のネタについて詳しくご紹介していきましょう。落語のネタというのは、そもそも「落語の祖」とも呼ばれる「安楽庵策伝」の本が元祖であるともいわれています。それが「醒睡笑」と呼ばれる笑話集で、面白みあふれる話が全8冊にわたって、約1000話も収録されています。これらにはそれぞれ落ちがついていて、現在でも落語家の方々が演目として演じている話も掲載されているのです。
また、具体的に落語のネタとして広く知られているものとしては、「まんじゅうこわい」などが有名です。「まんじゅうが怖い」という男性にいたずらを使用として、枕元におまんじゅうを置いておいたところ、そのおまんじゅうを平らげたばかりか今度は「最後に一杯お茶が怖い」という落ちも面白い演目は、お子さんでも親しみやすい内容なため、人気も高いネタでもあります。
「時そば」という演目も有名ですよね。昔ながらの屋台のおそばやさんで、おそばを平らげた後、時間を聞くことでお勘定をごまかす男性が印象的なこちらは、まさかのお勘定が増えてしまうという落ちも面白みのある演目です。また、「時そば」で印象深いのが、なんといってもおそばをすする音のリアルさです。こちらは上手な噺家が表現すると本当におそばをすすっているような音を楽しむことができるので、お腹が減ってしまうお客さんも多いようです。
他にも、思わずほろりときてしまいそうな人情話であったり、背筋がぞくっとするような怪談話であったりと、落語のネタは数えきれないほどあり、また新しいものも増えていっていますので飽きるはずはないかと思います。寄席に行くと、いろいろな落語家たちが挙って面白いネタを披露している様子も見ることができますし、人によって話し方や表現の仕方も様々なので、何回行っても同じものはありません。
また、具体的に落語のネタとして広く知られているものとしては、「まんじゅうこわい」などが有名です。「まんじゅうが怖い」という男性にいたずらを使用として、枕元におまんじゅうを置いておいたところ、そのおまんじゅうを平らげたばかりか今度は「最後に一杯お茶が怖い」という落ちも面白い演目は、お子さんでも親しみやすい内容なため、人気も高いネタでもあります。
「時そば」という演目も有名ですよね。昔ながらの屋台のおそばやさんで、おそばを平らげた後、時間を聞くことでお勘定をごまかす男性が印象的なこちらは、まさかのお勘定が増えてしまうという落ちも面白みのある演目です。また、「時そば」で印象深いのが、なんといってもおそばをすする音のリアルさです。こちらは上手な噺家が表現すると本当におそばをすすっているような音を楽しむことができるので、お腹が減ってしまうお客さんも多いようです。
他にも、思わずほろりときてしまいそうな人情話であったり、背筋がぞくっとするような怪談話であったりと、落語のネタは数えきれないほどあり、また新しいものも増えていっていますので飽きるはずはないかと思います。寄席に行くと、いろいろな落語家たちが挙って面白いネタを披露している様子も見ることができますし、人によって話し方や表現の仕方も様々なので、何回行っても同じものはありません。
広がる落語ブーム
また、最近は落語をテーマとしたテレビドラマや漫画、アニメーションなども増えてきており、若者たちの関心も高まってきているようです。実際に、テレビメディアで取り上げられることも多く、若いイケメンの落語家たちを目当てに寄席に通う女性たちも少なくはありません。
実際に、現在は「平成の落語ブーム」ともいわれるほど、落語に関心を寄せている方々が増えてきています。平成に入ってすぐ、1993年には長い歴史上初の女性の真打が誕生したうえ、1995年には五代目桂家小さんが、そして1996年には三代目桂米朝さんが人間国宝に称されるなど、落語ファンでなくても嬉しいことが続きました。
いかがでしたか?
落語のネタは、今後もいろいろな落語家たちによって演じられ、時代背景によってより親しみやすいものへと変貌をつげていくことでしょう。ぜひ落語ブームに乗っかって、古来の伝統芸能である落語を堪能してみてください。
実際に、現在は「平成の落語ブーム」ともいわれるほど、落語に関心を寄せている方々が増えてきています。平成に入ってすぐ、1993年には長い歴史上初の女性の真打が誕生したうえ、1995年には五代目桂家小さんが、そして1996年には三代目桂米朝さんが人間国宝に称されるなど、落語ファンでなくても嬉しいことが続きました。
いかがでしたか?
落語のネタは、今後もいろいろな落語家たちによって演じられ、時代背景によってより親しみやすいものへと変貌をつげていくことでしょう。ぜひ落語ブームに乗っかって、古来の伝統芸能である落語を堪能してみてください。


















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

