黒船来航!黒い塗装の船が幕末を激震させた理由
関連キーワード

バケーションシーズンになると、海外旅行する方も多く居られると思います。
いつの時代も憧れの島・ハワイやグアム、サイパンなど、どこまでもまっすぐな水平線を眺めながら想いを馳せていると、ポツン、と黒い船影が視界に浮かび上がった経験、ありませんか?
船が混雑している東京湾などでは感じない、コンテナや軍艦がまるで怪獣のように雄々しく巨大に見える経験は、江戸末期の庶民が体感した身震いに通じるものがあるように思えます。
言葉は「黒船」といえど、その語感の中に江戸庶民は恐らく、現代の私たちで言うところの「コジラだ!」「怪物だ!」といった動転した気持ちが、噂話の端々から放たれていたのではないでしょうか。
その庶民の反応は、恐らく黒船に乗船していたペリー提督の思惑どおりだったことでしょう。
1853年夏、浦賀沖に現れたサスケハナ 、ミシシッピ(この2隻は蒸気船)、サラトガ、プリマス(この2隻は帆船)のアメリカ海軍東インド艦隊4隻は、その悠々たる威容だけで江戸幕府の武威をペシャンコにしてみせたのです。
当時の日本にあった木造船と言えば、素材の風味そのままの白木だったり、格の違いが一目でわかるようゴージャスに塗装されていたものが多かったのですが、ペリーたちの乗ってきた木造船には、その耐久率を上げるためにコールタールを基にした黒い腐食防止剤が塗り込められていました。
その物珍しいオールブラックな木造船が、黒い蒸気を上げながら停泊する姿は、かなりショッキングだったことでしょう。
いつの時代も憧れの島・ハワイやグアム、サイパンなど、どこまでもまっすぐな水平線を眺めながら想いを馳せていると、ポツン、と黒い船影が視界に浮かび上がった経験、ありませんか?
船が混雑している東京湾などでは感じない、コンテナや軍艦がまるで怪獣のように雄々しく巨大に見える経験は、江戸末期の庶民が体感した身震いに通じるものがあるように思えます。
言葉は「黒船」といえど、その語感の中に江戸庶民は恐らく、現代の私たちで言うところの「コジラだ!」「怪物だ!」といった動転した気持ちが、噂話の端々から放たれていたのではないでしょうか。
その庶民の反応は、恐らく黒船に乗船していたペリー提督の思惑どおりだったことでしょう。
1853年夏、浦賀沖に現れたサスケハナ 、ミシシッピ(この2隻は蒸気船)、サラトガ、プリマス(この2隻は帆船)のアメリカ海軍東インド艦隊4隻は、その悠々たる威容だけで江戸幕府の武威をペシャンコにしてみせたのです。
当時の日本にあった木造船と言えば、素材の風味そのままの白木だったり、格の違いが一目でわかるようゴージャスに塗装されていたものが多かったのですが、ペリーたちの乗ってきた木造船には、その耐久率を上げるためにコールタールを基にした黒い腐食防止剤が塗り込められていました。
その物珍しいオールブラックな木造船が、黒い蒸気を上げながら停泊する姿は、かなりショッキングだったことでしょう。
アメリカはなぜはるばる黒船を日本に行かせた?

アメリカはなぜ幕末に、わざわざ遠い島国・日本までやってこなければならなかったのでしょう。
まだ太平洋航路が確立されていない時代でしたから、ペリー一行ははるばる大西洋を横断した後、アフリカをぐるっと回り、シンガポール、香港、上海に寄港しつつ、約半年掛かりで琉球に到着した後、小笠原諸島なども調査しがてら、一ヶ月半ほど後の7月に浦賀へやってきます。
遠路はるばる船を走らせたこのコースを、自国の捕鯨船の乗組員たちが快適かつ安全に航行できるようにすることが、ペリー提督の目的のひとつでもあったのです。
太平洋沖にて捕鯨船でクジラを捕まえ、油を絞ってそれを売る産業が、アメリカでは盛んに行われていました。
はじめはアメリカ近海で捕まえることができたクジラでしたが、乱獲がたたってだんだんとアメリカから遠い海域まで捕鯨船で追っていかなければならなくなりました。
その頃にはアメリカ国籍の船員たちは、日本近海で捕鯨船を操りながら、寄港地のない危険な船旅をするはめになっており、日本近海でいつでも薪や水の補充や修理を安全に行える寄港地を作る必要がありました。
さらにもうひとつの理由は、中国への販路開拓にありました。
ヨーロッパ列強がすでに中国を植民地化しようと、あの手この手で領土の切り取りを画策している矢先でしたから、アメリカも遅れをとるまいと、近隣国の日本に安全な補給基地を設けたいという狙いがあったのです。
まだ太平洋航路が確立されていない時代でしたから、ペリー一行ははるばる大西洋を横断した後、アフリカをぐるっと回り、シンガポール、香港、上海に寄港しつつ、約半年掛かりで琉球に到着した後、小笠原諸島なども調査しがてら、一ヶ月半ほど後の7月に浦賀へやってきます。
遠路はるばる船を走らせたこのコースを、自国の捕鯨船の乗組員たちが快適かつ安全に航行できるようにすることが、ペリー提督の目的のひとつでもあったのです。
太平洋沖にて捕鯨船でクジラを捕まえ、油を絞ってそれを売る産業が、アメリカでは盛んに行われていました。
はじめはアメリカ近海で捕まえることができたクジラでしたが、乱獲がたたってだんだんとアメリカから遠い海域まで捕鯨船で追っていかなければならなくなりました。
その頃にはアメリカ国籍の船員たちは、日本近海で捕鯨船を操りながら、寄港地のない危険な船旅をするはめになっており、日本近海でいつでも薪や水の補充や修理を安全に行える寄港地を作る必要がありました。
さらにもうひとつの理由は、中国への販路開拓にありました。
ヨーロッパ列強がすでに中国を植民地化しようと、あの手この手で領土の切り取りを画策している矢先でしたから、アメリカも遅れをとるまいと、近隣国の日本に安全な補給基地を設けたいという狙いがあったのです。
ペリー提督のプロフィール
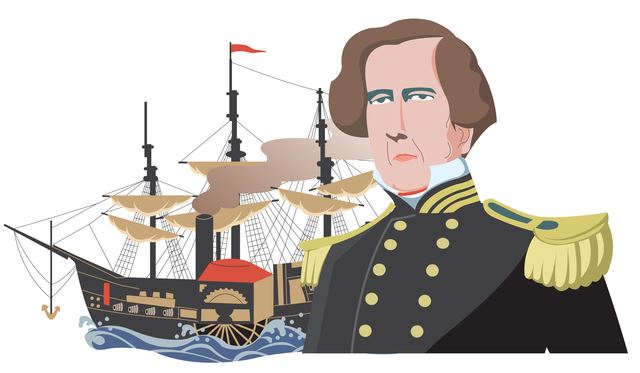
アメリカ海軍東インド艦隊を率いてきたペリー提督は、黒船の威容とともに彼自身の西洋人そのものの風貌が江戸庶民の間で話題騒然となり、浮世絵として人気を博しました。
その似顔絵は、吊り上がった巨大な眼に、天狗のような長い鼻、真っ赤な唇、けむくじゃらの姿でした。
日本の幕末史にセンセーショナルにその名を刻んだマシュー・カルブレイス・ペリーは、1794年にアメリカ合衆国ロードアイランド州に生を受けました。兄と一緒に創成期のアメリカ海軍に入隊し、蒸気機関を搭載した軍艦を数多く組み入れ、世界でも最先端の海軍力を増強する傍ら、それを操る海軍士官たちの教育にも力を注ぎました。
「蒸気船海軍の父」として尊敬を集めていたペリー提督は、1852年、58歳にて東インド艦隊司令長官に就任後、アメリカ合衆国大統領フィルモアの親書を預かり、自ら育てた海軍を引き連れて日本に向けて出航しました。
それ以前から、長期任務に備えてペリーは日本についての猛勉強をしていました。
シーボルトのまとめた『日本』という本以外にもおよそ40冊の参考資料を元にして、綿密な日本開国計画を作成しての出航でした。
その似顔絵は、吊り上がった巨大な眼に、天狗のような長い鼻、真っ赤な唇、けむくじゃらの姿でした。
日本の幕末史にセンセーショナルにその名を刻んだマシュー・カルブレイス・ペリーは、1794年にアメリカ合衆国ロードアイランド州に生を受けました。兄と一緒に創成期のアメリカ海軍に入隊し、蒸気機関を搭載した軍艦を数多く組み入れ、世界でも最先端の海軍力を増強する傍ら、それを操る海軍士官たちの教育にも力を注ぎました。
「蒸気船海軍の父」として尊敬を集めていたペリー提督は、1852年、58歳にて東インド艦隊司令長官に就任後、アメリカ合衆国大統領フィルモアの親書を預かり、自ら育てた海軍を引き連れて日本に向けて出航しました。
それ以前から、長期任務に備えてペリーは日本についての猛勉強をしていました。
シーボルトのまとめた『日本』という本以外にもおよそ40冊の参考資料を元にして、綿密な日本開国計画を作成しての出航でした。
黒船来航で盛り上がるナショナリズム
黒船来航以前の日本人は、長い鎖国政策のなか、「海外からやってくる人や物」という興味は、日常の退屈さに華を添える物珍しい娯楽程度のものだったのかもしれません。
西日本や北海道・東北地方の人々は、すでに日本の喉元にまでヨーロッパ列強の植民地支配の手が伸びていることをヒリヒリと実感していたものの、将軍家のお膝元である江戸界隈には、揺れる世界情勢の波はさざなみ程度にしか押し寄せず、いまだ太平の眠りの中にありました。
しかし、江戸庶民は「欧米の武装」をリアルタイムで目撃しました。
その黒船に乗り込む船員たちの体格や装備を見た江戸庶民たちは、自分たちが頭上高く拝していた「徳川将軍家」の武威とそれらを夢から醒めたような目で比較しました。 人々は情報を欲しました。自分たちの頭でこの先を予想し、自分たちに何が出来るか、右往左往している頼りなげな政府に苛立ち、何を要望すべきか考え出すのです。
日本人のこの目覚めが、志士たちを倒幕へと走らせ、国の舵取りを担うための思想や実力を持つものたちが「明治維新」を成し遂げることとなったのです。
西日本や北海道・東北地方の人々は、すでに日本の喉元にまでヨーロッパ列強の植民地支配の手が伸びていることをヒリヒリと実感していたものの、将軍家のお膝元である江戸界隈には、揺れる世界情勢の波はさざなみ程度にしか押し寄せず、いまだ太平の眠りの中にありました。
しかし、江戸庶民は「欧米の武装」をリアルタイムで目撃しました。
その黒船に乗り込む船員たちの体格や装備を見た江戸庶民たちは、自分たちが頭上高く拝していた「徳川将軍家」の武威とそれらを夢から醒めたような目で比較しました。 人々は情報を欲しました。自分たちの頭でこの先を予想し、自分たちに何が出来るか、右往左往している頼りなげな政府に苛立ち、何を要望すべきか考え出すのです。
日本人のこの目覚めが、志士たちを倒幕へと走らせ、国の舵取りを担うための思想や実力を持つものたちが「明治維新」を成し遂げることとなったのです。




















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

