枝豆を家庭菜園で栽培するコツは
関連キーワード

枝豆を家庭で栽培するのは簡単なのでしょうか。家庭菜園に挑戦するための方法についてご紹介します。
コツを覚えて枝豆栽培に挑戦してみませんか。よく食べる、親しみのある枝豆ですが、枝豆を作るのは難しいと思われがちです。意外と簡単に作ることができますので、枝豆栽培のコツについて見ていきたいと思います。
コツを覚えて枝豆栽培に挑戦してみませんか。よく食べる、親しみのある枝豆ですが、枝豆を作るのは難しいと思われがちです。意外と簡単に作ることができますので、枝豆栽培のコツについて見ていきたいと思います。
枝豆はどんな特徴がある?
枝豆と一言で言いますが、種類は豊富で400種類以上もあります。早生種と晩生種などがあったり、粒の大きさやさやの産毛の色が違ったりする品種などがいろいろあります。
枝豆は、大きく分けると、産毛が白い「白毛豆(青豆)」や産毛が茶色の「茶豆」、さやの中の薄皮が少し黒い「黒豆」などがあります。例えば、丹波の黒豆など産地の地域ごとに名物となっている品種も見られます。
全国的によく栽培されているのが、「白毛豆(青豆)」です。味も癖がなくて人気の一般的な枝豆です。枝豆の主な産地は関東地方だということを知っていますか。千葉県が1番の産地です。埼玉県などでもよく栽培されています。「白毛豆(青豆)」は、私たちがよく食べている枝豆ですが、一つのさやに3粒位の豆が入っているのが特徴です。
枝豆は、大きく分けると、産毛が白い「白毛豆(青豆)」や産毛が茶色の「茶豆」、さやの中の薄皮が少し黒い「黒豆」などがあります。例えば、丹波の黒豆など産地の地域ごとに名物となっている品種も見られます。
全国的によく栽培されているのが、「白毛豆(青豆)」です。味も癖がなくて人気の一般的な枝豆です。枝豆の主な産地は関東地方だということを知っていますか。千葉県が1番の産地です。埼玉県などでもよく栽培されています。「白毛豆(青豆)」は、私たちがよく食べている枝豆ですが、一つのさやに3粒位の豆が入っているのが特徴です。
枝豆は作り方が簡単!

枝豆の栽培ですが、育て方は簡単で、家庭菜園の初挑戦の方にもおすすめの野菜です。苗から育てると収穫も確実にできるため、育てやすいと言えます。
枝豆の苗ですが、育て方としては、根が浅いために、乾燥に気を付けて育てる必要があります。特に花が咲いてから実がなるまでは、乾燥させないように注意することがとても大切です。夏の暑さには強いのですが、乾燥で花が落ちてしまうことがあり、要注意となっています。また、実を収穫する時期には特によく水遣りに注意をしながら、成長させることが大切です。
枝豆は、4月〜6月に苗を植えつけ、暖かい地方では7月、寒い地方では8月に収穫することができます。収穫までが短いのも家庭菜園としての魅力と言えるでしょう。苗の植え付けから、約80〜90日程度で早く収穫することができますので、収穫も楽しみです。
栽培する際の土については、種類によって適した土が異なります。早生種は、地面の温度が上がりやすい砂質の土壌が良く、晩生種は、粘質の水分の多い土に植えるのがおすすめとなります。
枝豆の苗ですが、育て方としては、根が浅いために、乾燥に気を付けて育てる必要があります。特に花が咲いてから実がなるまでは、乾燥させないように注意することがとても大切です。夏の暑さには強いのですが、乾燥で花が落ちてしまうことがあり、要注意となっています。また、実を収穫する時期には特によく水遣りに注意をしながら、成長させることが大切です。
枝豆は、4月〜6月に苗を植えつけ、暖かい地方では7月、寒い地方では8月に収穫することができます。収穫までが短いのも家庭菜園としての魅力と言えるでしょう。苗の植え付けから、約80〜90日程度で早く収穫することができますので、収穫も楽しみです。
栽培する際の土については、種類によって適した土が異なります。早生種は、地面の温度が上がりやすい砂質の土壌が良く、晩生種は、粘質の水分の多い土に植えるのがおすすめとなります。
枝豆の実がならない時の注意点は?
枝豆は、育てやすく、肥料もあまり必要なく実をならすことができる野菜です。元肥は、窒素が多くない肥料をあげるようにしましょう。そんな育てやすい枝豆でも、枝豆の実があまりならないということもあります。そんな場合の原因についてもご紹介したいと思います。
実際には、枝豆のさやか膨らまない、実が入らないということも意外と多いケースとなっています。さやにカメムシによる被害があったりして実が入らないことがあります。家庭菜園では、虫対策も大切です。花芽が付く頃から、防虫ネットなどを早めに掛けておくのもおすすめの虫対策です。
虫の心配や水が足りているかどうかや昼夜の温度差があるかどうかが枝豆の実がしっかりできるかには影響をします。これらの点をしっかり確認しましょう。
実際には、枝豆のさやか膨らまない、実が入らないということも意外と多いケースとなっています。さやにカメムシによる被害があったりして実が入らないことがあります。家庭菜園では、虫対策も大切です。花芽が付く頃から、防虫ネットなどを早めに掛けておくのもおすすめの虫対策です。
虫の心配や水が足りているかどうかや昼夜の温度差があるかどうかが枝豆の実がしっかりできるかには影響をします。これらの点をしっかり確認しましょう。
枝豆の収穫の時期は短い!

また、枝豆の実の収穫についてですが、収穫の時期がとても短く、熟したら1週間〜10日で採ってしまうのがコツです。さやが黄色くなってしまうと、熟しすぎた状態になってしまいます。枝豆は、夏が収穫時期ですので、早めに収穫して熟しすぎないようにするのがポイントです。
美味しい枝豆についてですが、きれいな緑色のさやのものが美味しい枝豆です。さやが黄色くなっているものは良くなく、瑞々しい緑色のものが美味しい枝豆となります。また、よくうぶ毛におおわれているもの、枝にたくさんさやが付いているものもいい枝豆の証拠です。
スーパーで夏になると枝付きの枝豆が売られているのをよく見かけますが、たくさんさやがついているものを選びましょう。また、枝付きで売られているものは鮮度が良く、より新鮮に食べることができます。
そして、枝豆のさやはふっくりしているものが実が詰まっていて、いいものです。しかし、あまり実が大きくなると香りが落ちることがあります。枝豆の場合には、香りも美味しさの一つです。あまり、大きくなりすぎないうちに収穫すること、熟しすぎないことがやはり収穫の上では、大事なこととなります。
美味しい枝豆についてですが、きれいな緑色のさやのものが美味しい枝豆です。さやが黄色くなっているものは良くなく、瑞々しい緑色のものが美味しい枝豆となります。また、よくうぶ毛におおわれているもの、枝にたくさんさやが付いているものもいい枝豆の証拠です。
スーパーで夏になると枝付きの枝豆が売られているのをよく見かけますが、たくさんさやがついているものを選びましょう。また、枝付きで売られているものは鮮度が良く、より新鮮に食べることができます。
そして、枝豆のさやはふっくりしているものが実が詰まっていて、いいものです。しかし、あまり実が大きくなると香りが落ちることがあります。枝豆の場合には、香りも美味しさの一つです。あまり、大きくなりすぎないうちに収穫すること、熟しすぎないことがやはり収穫の上では、大事なこととなります。
枝豆栽培は簡単で収穫まで早いのが楽しみに!
いかがでしょうか。枝豆栽培は家庭菜園初心者でもチャレンジしやすいのが魅力です。
乾燥に気を付けたり、虫対策などをしっかり行えば、上手に育てていくことができます。何より収穫までが短いのが家庭菜園初心者としては嬉しいポイントです。収穫までの期間を楽しみに世話をしていくことができるでしょう。
さやの状態をしっかり確認しながら、枝豆を育ててみましょう。
実がしっかり入って入れば、枝豆栽培はとても楽しくて嬉しい家庭菜園となります。短い収穫時期を頑張って収穫してみましょう。
乾燥に気を付けたり、虫対策などをしっかり行えば、上手に育てていくことができます。何より収穫までが短いのが家庭菜園初心者としては嬉しいポイントです。収穫までの期間を楽しみに世話をしていくことができるでしょう。
さやの状態をしっかり確認しながら、枝豆を育ててみましょう。
実がしっかり入って入れば、枝豆栽培はとても楽しくて嬉しい家庭菜園となります。短い収穫時期を頑張って収穫してみましょう。







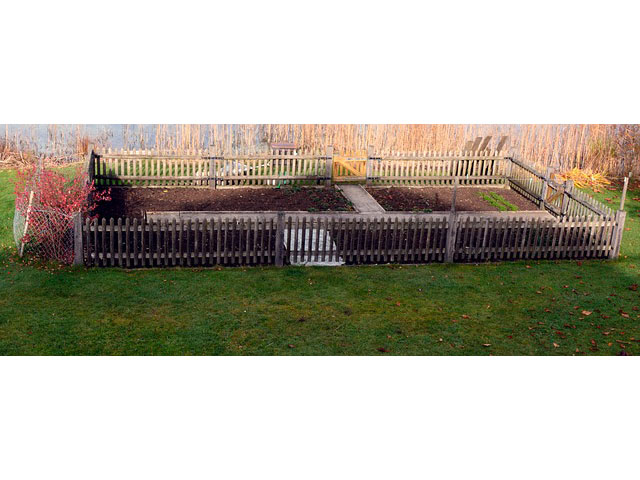















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

