感動が押し寄せる!『万葉集』に残る「よみ人知らず」名無しさんの名歌
関連キーワード

日本最古の歌集として知られる『万葉集』。皇族や貴族の歌はもとより、一般の庶民の歌が多数集録されており、当時の人々の言語や素朴な情感を記録した史料としても重要な歌集です。
『万葉集』を紐解くと、詠み手のわからない作品、すなわち「よみ人知らず」の作品が多くあることに気づきます。
和歌の巧拙が出世に影響し、貴族たちが競って和歌を詠むようになった平安時代以降、形式や技巧への執着から息苦しさを感じる和歌が増えていきますが、『万葉集』におさめられている「よみ人知らず」の歌々には、自由で素朴な味わいが残されています。また、「東歌」のように、都をはなれた地方の歌も『万葉集』の特徴で、その方言の調べは『万葉集』ならではの味わいをもたらします。
「よみ人知らず」の歌を通じて、名もない詠み手の姿、生活、そして日本人に行き渡る情感を詠みとってみませんか。
『万葉集』を紐解くと、詠み手のわからない作品、すなわち「よみ人知らず」の作品が多くあることに気づきます。
和歌の巧拙が出世に影響し、貴族たちが競って和歌を詠むようになった平安時代以降、形式や技巧への執着から息苦しさを感じる和歌が増えていきますが、『万葉集』におさめられている「よみ人知らず」の歌々には、自由で素朴な味わいが残されています。また、「東歌」のように、都をはなれた地方の歌も『万葉集』の特徴で、その方言の調べは『万葉集』ならではの味わいをもたらします。
「よみ人知らず」の歌を通じて、名もない詠み手の姿、生活、そして日本人に行き渡る情感を詠みとってみませんか。
東歌
全20巻からなる『万葉集』、その第14巻はもっぱら「東歌」に当てられています。東歌とは、京都・奈良の東側の国々、つまり田舎の歌を意味し、日々の生活の中で歌われたかのような素朴でみずみずしい歌い口が特徴です。
「東歌」には、歌の言葉としては珍しい言葉や方言が用いられており、「生活のことば」と「歌のことば」が分かれる以前の、土臭く力強い言葉遣いにも注目です。
多摩川にさらす手作りさらさらに 何そこの児のここだかなしき
訳:多摩川で晒す手織りの布のように どうしてますますこの子が愛しくおもえるのだろうか。
歌の意味はさておき、この流れるようなリズム、なんともキャッチーで、思わず口から出てしまうような自然な歌いぶりではないでしょうか。リズムの秘密は音の反復にあります。「た」まがはに「さ」らす「た」づくり「さ」ら「さ」らに?、というように「た」と「さ」が交互に頭韻を踏んでいるのです。この流れるような上の句のリズムは、もしかすると、さらさらと流れる多摩川の流れを見ている時に思いついたのかも知れませんね。
そしてこの上の句、実は「さらさらに」(更々に、なおいっそう)ということばを導くための「序詞」という役割を担っています。
しかし、清らかな多摩川と綺麗な手織りの布のイメージは、下の句にもしみわたります。下の句の「ここだ」は、古い言葉であまり見かけない言葉ですが、程度のはなはだしさをあ表す副詞です。「かなしき」は形容詞「かなし」が「何そ」を受けて係り結び変化したもので、漢字では「愛し」と書かれます。こんにちでは「悲しい」という意味ですが、古語における「かなし」はいとしくて胸にささるような気持ちを表します。
「東歌」には、歌の言葉としては珍しい言葉や方言が用いられており、「生活のことば」と「歌のことば」が分かれる以前の、土臭く力強い言葉遣いにも注目です。
多摩川にさらす手作りさらさらに 何そこの児のここだかなしき
訳:多摩川で晒す手織りの布のように どうしてますますこの子が愛しくおもえるのだろうか。
歌の意味はさておき、この流れるようなリズム、なんともキャッチーで、思わず口から出てしまうような自然な歌いぶりではないでしょうか。リズムの秘密は音の反復にあります。「た」まがはに「さ」らす「た」づくり「さ」ら「さ」らに?、というように「た」と「さ」が交互に頭韻を踏んでいるのです。この流れるような上の句のリズムは、もしかすると、さらさらと流れる多摩川の流れを見ている時に思いついたのかも知れませんね。
そしてこの上の句、実は「さらさらに」(更々に、なおいっそう)ということばを導くための「序詞」という役割を担っています。
しかし、清らかな多摩川と綺麗な手織りの布のイメージは、下の句にもしみわたります。下の句の「ここだ」は、古い言葉であまり見かけない言葉ですが、程度のはなはだしさをあ表す副詞です。「かなしき」は形容詞「かなし」が「何そ」を受けて係り結び変化したもので、漢字では「愛し」と書かれます。こんにちでは「悲しい」という意味ですが、古語における「かなし」はいとしくて胸にささるような気持ちを表します。
防人の歌
『万葉集』の時代、社会は律令制を基礎に動いていました。
そして律令制において民衆に課せられた数々の税のなかでもとりわけ厳しいものだったのが防人(さきもり)の役でした。防人に指名された農民は、道中の費用を自己負担して太宰府まで出向き、そこで3年にわたって軍役につかなければなりません。また、任期を無事遂げたとしても、労役で弱った体が故郷への帰路に耐え切れず、家族と再会できずに斃れることもありました。つまり、防人はまさに命がけの労役だったのです。当時の人々にとって、自分の家族が防人に出向く姿を見ることは、あたかも赤紙で戦地に送られる家族を見送るような気持ちであったことでしょう。『万葉集』には、防人に出向く夫を見送る妻の惜別の情を歌った短歌がいくつか収められています。そのうちの一首を紹介が次の歌です。
防人に行くは誰が背と問ふ人を 見るがともしさ物思ひもせず
訳:「防人に行くのはどなた?」と尋ねている人を見ると、うらやましい。物思いもしないで。
防人に出かける夫を、お隣さんの奥さんでしょうか、誰か近所の人が「どちらのお宅の方かしら」と興味本位で見ていたのでしょう。
しかし一方で、この歌の詠み手である防人の妻にしてみれば、一家の大黒柱との別離は痛切な感情を伴うことは想像に難くはありません。そしてこの妻は、他人事のように無邪気に問いかける人に対して「ともし」(うらやましい)という気持ちを吐露します。句末にポツンと添えられた「物思ひもせず」が、妻が不条理をかこつような余情を醸し出しています。
そして律令制において民衆に課せられた数々の税のなかでもとりわけ厳しいものだったのが防人(さきもり)の役でした。防人に指名された農民は、道中の費用を自己負担して太宰府まで出向き、そこで3年にわたって軍役につかなければなりません。また、任期を無事遂げたとしても、労役で弱った体が故郷への帰路に耐え切れず、家族と再会できずに斃れることもありました。つまり、防人はまさに命がけの労役だったのです。当時の人々にとって、自分の家族が防人に出向く姿を見ることは、あたかも赤紙で戦地に送られる家族を見送るような気持ちであったことでしょう。『万葉集』には、防人に出向く夫を見送る妻の惜別の情を歌った短歌がいくつか収められています。そのうちの一首を紹介が次の歌です。
防人に行くは誰が背と問ふ人を 見るがともしさ物思ひもせず
訳:「防人に行くのはどなた?」と尋ねている人を見ると、うらやましい。物思いもしないで。
防人に出かける夫を、お隣さんの奥さんでしょうか、誰か近所の人が「どちらのお宅の方かしら」と興味本位で見ていたのでしょう。
しかし一方で、この歌の詠み手である防人の妻にしてみれば、一家の大黒柱との別離は痛切な感情を伴うことは想像に難くはありません。そしてこの妻は、他人事のように無邪気に問いかける人に対して「ともし」(うらやましい)という気持ちを吐露します。句末にポツンと添えられた「物思ひもせず」が、妻が不条理をかこつような余情を醸し出しています。
挽歌
本居宣長は歌の発生を、抑えきれない情感の盛り上がりに見出しました。
人間は恋するとき、情景に心打たれるときなど、様々な場面で歌を詠みますが、親しい人、愛する人を亡くしたときにも人は歌を詠みます。そういった歌は、「挽歌」、英語でいえばelegy、あるいはdirgeとよばれます。最後に、『万葉集』の中から、「よみ人知らず」の挽歌を一首紹介します。
福(さきわい)のいかなる人か黒髪の 白くなるまで妹が音(こえ)を聞く
訳:ああなんと幸せなのだ、黒髪が白く染まるまでその妻の声を聞くことができる人は。
妻を亡くした夫が詠んだ歌と考えられますが、その夫が誰なのか、どういう事情で妻を亡くしたのか、知る術はありません。
しかし、それにもかかわらず、この歌は切実な響きを持ちます。「妹が音を聞く」という終止も、直接的な感情表現よりもかえって、しみじみとした情感の表出に一役買っています。なお、「妹」という言葉は『万葉集』においては妻や恋人に対する親しみのこもった呼称として使われています。
人間は恋するとき、情景に心打たれるときなど、様々な場面で歌を詠みますが、親しい人、愛する人を亡くしたときにも人は歌を詠みます。そういった歌は、「挽歌」、英語でいえばelegy、あるいはdirgeとよばれます。最後に、『万葉集』の中から、「よみ人知らず」の挽歌を一首紹介します。
福(さきわい)のいかなる人か黒髪の 白くなるまで妹が音(こえ)を聞く
訳:ああなんと幸せなのだ、黒髪が白く染まるまでその妻の声を聞くことができる人は。
妻を亡くした夫が詠んだ歌と考えられますが、その夫が誰なのか、どういう事情で妻を亡くしたのか、知る術はありません。
しかし、それにもかかわらず、この歌は切実な響きを持ちます。「妹が音を聞く」という終止も、直接的な感情表現よりもかえって、しみじみとした情感の表出に一役買っています。なお、「妹」という言葉は『万葉集』においては妻や恋人に対する親しみのこもった呼称として使われています。











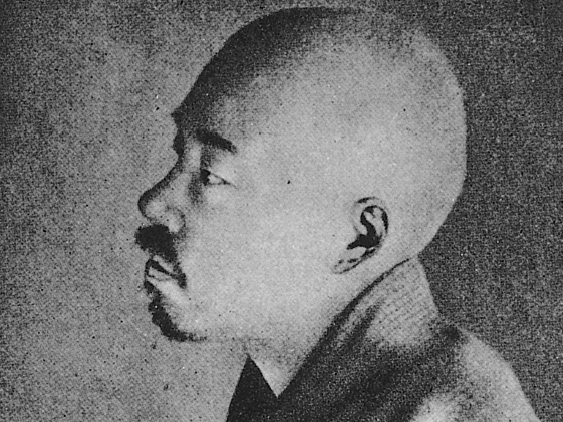

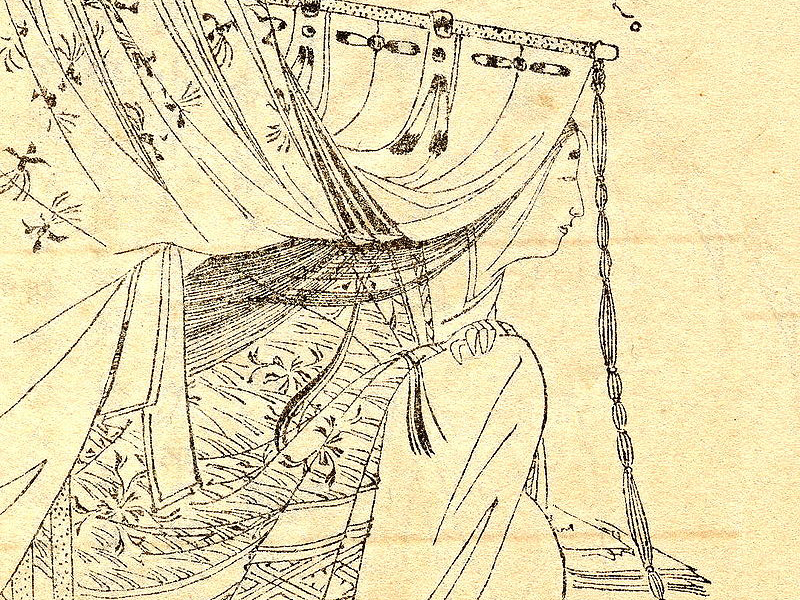




![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

