茶人としても一流!? 井伊直弼の茶道論が奥深い!
関連キーワード

出典:https://ja.wikipedia.org/|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E5%BC%BC#/media/File:Ii_Naosuke.jpg
大老、安政の大獄、彦根、日米修好通商条約、そして桜田門外の変。井伊直弼といえば、こうしたキーワードが思い浮かびます。井伊直弼というと、安政の大獄による反対派の弾圧、日米修好通商条約の違勅調印、そして、不満を買って桜田門外の変での暗殺されることから、強権的な政治家というイメージがあります。また、大河ドラマでは、悲劇の志士として描かれることの多い吉田松陰を殺してしまうので、「悪人」のイメージが定着しているようです。ためしに、いまGoogleで「井伊直弼 あ」と入力してみると、ばっちり「井伊直弼 悪人」がサジェストされます。
しかし、こうしたイメージは日本史の教科書や大河ドラマで描かれる井伊直弼にすぎません。彼の私生活を覗いてみると、意外な一面が見えてきます。なかでも、井伊直弼が熱心に嗜んでいた「茶の湯」に注目してみたいと思います。井伊直弼の茶の湯への姿勢・考えには、彼の人柄が強く感じられるからです。
茶の湯の世界で井伊直弼はどんな人柄を見せたのか。政治の表舞台からは見えない、茶室の直弼に迫ります。
しかし、こうしたイメージは日本史の教科書や大河ドラマで描かれる井伊直弼にすぎません。彼の私生活を覗いてみると、意外な一面が見えてきます。なかでも、井伊直弼が熱心に嗜んでいた「茶の湯」に注目してみたいと思います。井伊直弼の茶の湯への姿勢・考えには、彼の人柄が強く感じられるからです。
茶の湯の世界で井伊直弼はどんな人柄を見せたのか。政治の表舞台からは見えない、茶室の直弼に迫ります。
1. 井伊直弼と茶の湯
文化12年(1815)、彦根藩主井伊直中の子として井伊直弼は生まれました。 直弼には数多く兄弟がおり、加えて庶子(側室の子)であったため、彦根藩の後継ぎになる見込みはありませんでした。また、兄弟たちは養子となっていきましたが、直弼に養子の話は来ませんでした。
17歳になった直弼は、「埋木舎」という建物で生活するようになりました。「埋木舎」という名前は、直弼が詠んだ下の一首の由来します。
世の中を よそに見つつも 埋もれ木の 埋もれておらむ 心なき身は
この歌からもわかるように、埋木舎は簡素な建物で、後継ぎにも養子にもなれなかった井伊家の者が暮らす場所でした。こういう事情で直弼は、表舞台から離れたひっそりした場所に暮らす自分を「埋もれておらむ」と表現したのでしょう。
埋木舎での隠居生活は15年に及びました。その歳月の間、直弼は芸術・学問において才能を示し、静かに稽古にいそしみました。直弼の稽古は和歌、儒学、禅、剣術など多岐にわたりましたが、茶の湯も埋木舎時代の直弼が情熱を注いだことの一つでした。
井伊直弼の茶への熱意はかなりのものだったようです。茶論の古典を学ぶことはもちろん、自分の考えを盛り込みながら自らの流儀を錬成し、実践面では茶道具を自らの手で焼くなど、直弼の茶への姿勢は徹底したものでした。
17歳になった直弼は、「埋木舎」という建物で生活するようになりました。「埋木舎」という名前は、直弼が詠んだ下の一首の由来します。
世の中を よそに見つつも 埋もれ木の 埋もれておらむ 心なき身は
この歌からもわかるように、埋木舎は簡素な建物で、後継ぎにも養子にもなれなかった井伊家の者が暮らす場所でした。こういう事情で直弼は、表舞台から離れたひっそりした場所に暮らす自分を「埋もれておらむ」と表現したのでしょう。
埋木舎での隠居生活は15年に及びました。その歳月の間、直弼は芸術・学問において才能を示し、静かに稽古にいそしみました。直弼の稽古は和歌、儒学、禅、剣術など多岐にわたりましたが、茶の湯も埋木舎時代の直弼が情熱を注いだことの一つでした。
井伊直弼の茶への熱意はかなりのものだったようです。茶論の古典を学ぶことはもちろん、自分の考えを盛り込みながら自らの流儀を錬成し、実践面では茶道具を自らの手で焼くなど、直弼の茶への姿勢は徹底したものでした。
2. 井伊直弼の茶道論 『茶湯一会集』
井伊直弼は『茶湯一会集』(ちゃのゆいちえしゅう)という茶道論を残しています。『茶湯一会集』には井伊直弼の茶の湯に関する考え・姿勢が集約されています。この論考は次の一節で知られています。
そもそも、茶湯の交会は、一期一会といいて、たとえば幾度おなじ主客交会するとも、今日の会にふたたびかえらざる事を思えば、実に我一世一度の会なり、(『茶湯一会集・閑夜茶話』戸田勝久校注 岩波文庫)
「一期一会」は、千利休の言行を記した『山上宗二記』といった茶書の古典にあらわれる言葉ですが、井伊直弼は「一期一会」という言葉を再発見し、自身の茶会論の中核に据えたのです。
「一期一会」、二度と起こらない大切な時間として茶会を捉えた井伊直弼、彼にとっての茶会は、細部まで徹底して用意して挑む一度きりの真剣勝負の場でした。したがって、「主人は万事に心を配り、聊も麁末(そまつ)なきよう深切実意を尽し、客にもこの会にまた逢いがたき事を弁え」るのであり、直弼の徹底した態度はときに「必々主客とも等閑には一服をも催すまじき」といった厳しい言葉として現れます。
『茶湯一会集』は茶の湯と馴染みの薄い読者にとって面白いものではありません。井伊直弼は、基本的には茶会における作法を、古典を参照しながら、延々と説明していくばかりで、たいへん真面目なオカタイ内容です。『茶湯一会集』において井伊直弼がどんな調子で茶の湯を語っているのか、一つ例文を紹介しましょう。
濃茶点じ、茶碗を出し、ふくさ をも添えたるとき、正客座を進み、茶碗受け取り、席中に置く、ふくさをもよせて復座し、次客へ会釈して、法のごとく一口給(た)べたる時、亭主より一礼、御服加減如何、つまり申さず哉と申せば、正客、結構成る御服加減と挨拶いたし、三口、四口ばかり給べて、法のごとく次客へ渡す。尤も、次客の方へすこし向い、次客もすこし正客へ向えば、茶碗を下に置き、ふくさ添て渡すなり、次客受取り、三客へ会釈して給べ候事、順々同様なり、但し…(以下長い但し書きが続く。)
万事こんな調子。『茶湯一会集』の文章を読む限り、井伊直弼は几帳面な性格だったようです。 直弼は、茶論の古典などから学んだことをメモ(『閑夜茶話』)するなど、古典の研究にも熱心でした。そのため、説明書調の作法の解説の合間に、ときおり千利休や古田織部といった、歴史上の茶道家のエピソードが語られることもあります。たとえば、次のような一節。
利休、敷松葉に、樫の葉を交ぜて、まきし事あり、これは古歌に
樫の葉の 紅葉ぬからに 散りつもる 奥山寺の 道ぞさびしき
右の哥を面白く思われて、蒔きそめしよし、これは時宜によりての働きには然るべきなり
このほかにも、直弼は、茶論の古典や他流の流儀にあたり、非合理的だと思った作法については否定することも辞しません。このような直弼の姿勢は、有職故実を重んじる政治の世界でも大いに発揮されたのではないでしょうか。また、合理的ではないと思ったことはきっぱり否定する直弼の胆力は、強権的な政治家としての直弼のイメージを彷彿とさせます。
そもそも、茶湯の交会は、一期一会といいて、たとえば幾度おなじ主客交会するとも、今日の会にふたたびかえらざる事を思えば、実に我一世一度の会なり、(『茶湯一会集・閑夜茶話』戸田勝久校注 岩波文庫)
「一期一会」は、千利休の言行を記した『山上宗二記』といった茶書の古典にあらわれる言葉ですが、井伊直弼は「一期一会」という言葉を再発見し、自身の茶会論の中核に据えたのです。
「一期一会」、二度と起こらない大切な時間として茶会を捉えた井伊直弼、彼にとっての茶会は、細部まで徹底して用意して挑む一度きりの真剣勝負の場でした。したがって、「主人は万事に心を配り、聊も麁末(そまつ)なきよう深切実意を尽し、客にもこの会にまた逢いがたき事を弁え」るのであり、直弼の徹底した態度はときに「必々主客とも等閑には一服をも催すまじき」といった厳しい言葉として現れます。
『茶湯一会集』は茶の湯と馴染みの薄い読者にとって面白いものではありません。井伊直弼は、基本的には茶会における作法を、古典を参照しながら、延々と説明していくばかりで、たいへん真面目なオカタイ内容です。『茶湯一会集』において井伊直弼がどんな調子で茶の湯を語っているのか、一つ例文を紹介しましょう。
濃茶点じ、茶碗を出し、ふくさ をも添えたるとき、正客座を進み、茶碗受け取り、席中に置く、ふくさをもよせて復座し、次客へ会釈して、法のごとく一口給(た)べたる時、亭主より一礼、御服加減如何、つまり申さず哉と申せば、正客、結構成る御服加減と挨拶いたし、三口、四口ばかり給べて、法のごとく次客へ渡す。尤も、次客の方へすこし向い、次客もすこし正客へ向えば、茶碗を下に置き、ふくさ添て渡すなり、次客受取り、三客へ会釈して給べ候事、順々同様なり、但し…(以下長い但し書きが続く。)
万事こんな調子。『茶湯一会集』の文章を読む限り、井伊直弼は几帳面な性格だったようです。 直弼は、茶論の古典などから学んだことをメモ(『閑夜茶話』)するなど、古典の研究にも熱心でした。そのため、説明書調の作法の解説の合間に、ときおり千利休や古田織部といった、歴史上の茶道家のエピソードが語られることもあります。たとえば、次のような一節。
利休、敷松葉に、樫の葉を交ぜて、まきし事あり、これは古歌に
樫の葉の 紅葉ぬからに 散りつもる 奥山寺の 道ぞさびしき
右の哥を面白く思われて、蒔きそめしよし、これは時宜によりての働きには然るべきなり
このほかにも、直弼は、茶論の古典や他流の流儀にあたり、非合理的だと思った作法については否定することも辞しません。このような直弼の姿勢は、有職故実を重んじる政治の世界でも大いに発揮されたのではないでしょうか。また、合理的ではないと思ったことはきっぱり否定する直弼の胆力は、強権的な政治家としての直弼のイメージを彷彿とさせます。
3. 茶人 井伊直弼
上に述べたように、『茶湯一会集』にはオカタイ文章がずらりと並んでいます。しかし、ときに秘めていた感情が表出されたかのような、読む者をあっとさせる抒情的な美文もあります。たとえば、「独坐観念」について述べた次の一節は、禁欲的な抒情を湛えています。
主客とも余情残心を催し、退出の挨拶終れば、客も露地を出るに、高声に咄(はな)さず、静かにあと見かえり出て行けば、亭主はなおさらのこと、客の見えざるまでも見送るなり。(中略)今日、一期一会済みて、ふたたびかえらざる事を観念し、或るいは独服をもいたす事、この一会極意の習いなり、この時寂寞として、打語らうものとては、釜一口のみにして、外に物なし、誠に自得せざればいたりがたき境涯なり。
これを読んだ者はみな、「悪人」井伊直弼のイメージを改めざるを得なくなるはずです。
政治の表舞台で活躍する井伊直弼からは、彼の内面まではなかなか見えてきません。政治家としての体面のなかで埋もれてしまった彼の内面の心は、埋木舎での、世の中をよそに見つつ茶の湯に励んだ青春時代にこそ現れているのではないでしょうか。
主客とも余情残心を催し、退出の挨拶終れば、客も露地を出るに、高声に咄(はな)さず、静かにあと見かえり出て行けば、亭主はなおさらのこと、客の見えざるまでも見送るなり。(中略)今日、一期一会済みて、ふたたびかえらざる事を観念し、或るいは独服をもいたす事、この一会極意の習いなり、この時寂寞として、打語らうものとては、釜一口のみにして、外に物なし、誠に自得せざればいたりがたき境涯なり。
これを読んだ者はみな、「悪人」井伊直弼のイメージを改めざるを得なくなるはずです。
政治の表舞台で活躍する井伊直弼からは、彼の内面まではなかなか見えてきません。政治家としての体面のなかで埋もれてしまった彼の内面の心は、埋木舎での、世の中をよそに見つつ茶の湯に励んだ青春時代にこそ現れているのではないでしょうか。

井伊直弼は文化12年(1815年)10月29日、井伊直中の十四男として彦根城で誕生しました。
先祖は「井伊の赤鬼」として恐れられた猛将で、徳川四天王の筆頭でもあった井伊直政であり、父の直中も藩政改革の名君として名が通っていました。
しかし直弼は十四男である上、母親が側室で身分が低いということもあり、到底彦根藩を継げる立場には無く、兄弟も多いため養子先も見つけてもらえず、前半生は不遇の元に過ごしました。
直弼は自分の家に埋木舎(うもれぎのや)と名付け、自虐的なところもありましたが、それとは裏腹に茶道を始め和歌や兵学など、熱心に稽古事に励み、自らを高めて行きました。
そんな直弼に運が向いてきたのは弘化3年(1846年)、彦根藩は兄である井伊直亮が継いでいましたが子は無く、跡継ぎに定まっていた養子も亡くなったため、改めて直弼に次期当主の話が舞い込んで来ました。
そしてそれから四年後の嘉永3年(1850年)、直弼35歳の年、兄・直亮が亡くなったことにより彦根藩主となったのです。
先祖は「井伊の赤鬼」として恐れられた猛将で、徳川四天王の筆頭でもあった井伊直政であり、父の直中も藩政改革の名君として名が通っていました。
しかし直弼は十四男である上、母親が側室で身分が低いということもあり、到底彦根藩を継げる立場には無く、兄弟も多いため養子先も見つけてもらえず、前半生は不遇の元に過ごしました。
直弼は自分の家に埋木舎(うもれぎのや)と名付け、自虐的なところもありましたが、それとは裏腹に茶道を始め和歌や兵学など、熱心に稽古事に励み、自らを高めて行きました。
そんな直弼に運が向いてきたのは弘化3年(1846年)、彦根藩は兄である井伊直亮が継いでいましたが子は無く、跡継ぎに定まっていた養子も亡くなったため、改めて直弼に次期当主の話が舞い込んで来ました。
そしてそれから四年後の嘉永3年(1850年)、直弼35歳の年、兄・直亮が亡くなったことにより彦根藩主となったのです。
本当は攘夷派でいたかった井伊直弼

藩主としての直弼は、15万両もの大金を領民に施すなど、領民からは名君として慕われていました。
今まで通り鎖国下の徳川政権が続いていれば名君として一生を終えることが出来たでしょう。しかし時代はそれを許してはくれませんでした。
藩主就任から3年後の嘉永6年(1853年)、浦賀にペリー率いる黒船が来航し幕府に開国を要求したのです。
開国を主張した直弼でしたが、本来開国には反対の立場だった直弼。それでも開国を主張した直弼には訳がありました。
当時の幕府は往年の威光を失っており、水戸藩や、外様大名の島津家など、他藩の力が増していました。個々に攘夷を唱えるのです。
しかしそれではこの目でみた異国の艦隊は打ち払えない…。まずは幕府の威光を回復した後に、親藩や譜代大名を中心として艦隊を打ち払うべし。そのためにはまず時間稼ぎをと考えた訳です。
ところがそんな考えでは悠長と、老中の阿部正弘や、水戸藩の徳川斉昭などが猛反発します。
必然と攘夷派の徳川斉昭や越前の松平春嶽が外国の干渉を追い払う攘夷派として…。
対して自分は鎖国を解き外国を受け入れる開国派として徹底的に道が分かれてしまったのです。
今まで通り鎖国下の徳川政権が続いていれば名君として一生を終えることが出来たでしょう。しかし時代はそれを許してはくれませんでした。
藩主就任から3年後の嘉永6年(1853年)、浦賀にペリー率いる黒船が来航し幕府に開国を要求したのです。
開国を主張した直弼でしたが、本来開国には反対の立場だった直弼。それでも開国を主張した直弼には訳がありました。
当時の幕府は往年の威光を失っており、水戸藩や、外様大名の島津家など、他藩の力が増していました。個々に攘夷を唱えるのです。
しかしそれではこの目でみた異国の艦隊は打ち払えない…。まずは幕府の威光を回復した後に、親藩や譜代大名を中心として艦隊を打ち払うべし。そのためにはまず時間稼ぎをと考えた訳です。
ところがそんな考えでは悠長と、老中の阿部正弘や、水戸藩の徳川斉昭などが猛反発します。
必然と攘夷派の徳川斉昭や越前の松平春嶽が外国の干渉を追い払う攘夷派として…。
対して自分は鎖国を解き外国を受け入れる開国派として徹底的に道が分かれてしまったのです。
全責任を押し付けられた直弼の逆襲
そんな混乱の中の安政5年(1858年)、第13代将軍・徳川家定の鶴の一声で井伊直弼の大老就任が決定しました。
「大老」とは、平時は空席なのですが、非常時の場合のみ据えられる幕府の最高責任者です。
この難しい情勢を乗り切れるのは直弼しかいないと家定は全てを直弼に託しました。
しかしアメリカが突き着けてきた開国要求をかわすにかわして早5年、我慢の限界が来たアメリカは最後通牒を勧告します。
開国に応じなければ武力での開国も辞さん…と。
大老の直弼を筆頭とした徳川首脳部の意見は一致していました。しかし応じるにしても一つだけ懸念がありました。
それは現在の日本の天皇である、孝明天皇の許しを得られていないということ。天皇の許しがなければ全責任は幕府、ひいては自分が負わなければなりません。
3代将軍・徳川家光以来200年に渡って守られ続けてきた鎖国に終止符を打つ。幕府の全権を預かっているにしても、そう簡単には決断出来なかったのです。
しかし孝明天皇は大の攘夷派。そう簡単に説得出来ないと踏んだ直弼はその間の時間稼ぎとして、下田奉行の井上清直と目付役の岩瀬忠震をアメリカ領事のハリスのもとに派遣しました。
アメリカの圧力を分かっている井上清直は直弼に確認を取りました。
もしどうしても止むを得ない時が来れば開国の調印に応じてもいいかと。
直弼は答えました。その時は仕方ないが出来るだけ引き延ばせと。
しかしその答えが仇となってしまいました。その返答を許可とみた二人は交渉を引き延ばすことなく条約に調印。
天皇の許可無く日本に大変不利な日米修好通商条約を締結したのは井伊直弼と、攘夷派を中心に非難の的に晒されたのです。
攘夷派の急先鋒だった水戸藩の藩士らは幕府を通り越して直接朝廷に訴え、同じく開国に反対だった朝廷もそれに応じ、幕府を非難する密勅を水戸藩に授けました。
それに怒った直弼はこの件に関わった者たちを悉く捕らえました。その中には身分の上下関係無く、さらには直接関係無い者も含まれていました。
また、吉田松陰や梅田雲浜といった学者や志士だけではなく、勝手に調印した岩瀬忠震を左遷し、徳川斉昭を隠居に追い込みました。
この一連の捕縛劇は安政の大獄と呼ばれ、大老の強権に任せた捕縛劇は世間の非難に晒されました。
直弼の先祖の初代・直政の異名に掛けて、周りから「井伊の赤鬼」と揶揄されている直弼の暴走は止まりませんでした。
水戸藩に対して、朝廷より預かった密勅を幕府に渡さなければ改易すると脅したのです。
もはや止まらない直弼に対し、斉昭は渡すことを受け入れましたが、今度は水戸の藩士たちが黙っていませんでした。
「大老」とは、平時は空席なのですが、非常時の場合のみ据えられる幕府の最高責任者です。
この難しい情勢を乗り切れるのは直弼しかいないと家定は全てを直弼に託しました。
しかしアメリカが突き着けてきた開国要求をかわすにかわして早5年、我慢の限界が来たアメリカは最後通牒を勧告します。
開国に応じなければ武力での開国も辞さん…と。
大老の直弼を筆頭とした徳川首脳部の意見は一致していました。しかし応じるにしても一つだけ懸念がありました。
それは現在の日本の天皇である、孝明天皇の許しを得られていないということ。天皇の許しがなければ全責任は幕府、ひいては自分が負わなければなりません。
3代将軍・徳川家光以来200年に渡って守られ続けてきた鎖国に終止符を打つ。幕府の全権を預かっているにしても、そう簡単には決断出来なかったのです。
しかし孝明天皇は大の攘夷派。そう簡単に説得出来ないと踏んだ直弼はその間の時間稼ぎとして、下田奉行の井上清直と目付役の岩瀬忠震をアメリカ領事のハリスのもとに派遣しました。
アメリカの圧力を分かっている井上清直は直弼に確認を取りました。
もしどうしても止むを得ない時が来れば開国の調印に応じてもいいかと。
直弼は答えました。その時は仕方ないが出来るだけ引き延ばせと。
しかしその答えが仇となってしまいました。その返答を許可とみた二人は交渉を引き延ばすことなく条約に調印。
天皇の許可無く日本に大変不利な日米修好通商条約を締結したのは井伊直弼と、攘夷派を中心に非難の的に晒されたのです。
攘夷派の急先鋒だった水戸藩の藩士らは幕府を通り越して直接朝廷に訴え、同じく開国に反対だった朝廷もそれに応じ、幕府を非難する密勅を水戸藩に授けました。
それに怒った直弼はこの件に関わった者たちを悉く捕らえました。その中には身分の上下関係無く、さらには直接関係無い者も含まれていました。
また、吉田松陰や梅田雲浜といった学者や志士だけではなく、勝手に調印した岩瀬忠震を左遷し、徳川斉昭を隠居に追い込みました。
この一連の捕縛劇は安政の大獄と呼ばれ、大老の強権に任せた捕縛劇は世間の非難に晒されました。
直弼の先祖の初代・直政の異名に掛けて、周りから「井伊の赤鬼」と揶揄されている直弼の暴走は止まりませんでした。
水戸藩に対して、朝廷より預かった密勅を幕府に渡さなければ改易すると脅したのです。
もはや止まらない直弼に対し、斉昭は渡すことを受け入れましたが、今度は水戸の藩士たちが黙っていませんでした。
そして桜田門で討ち取られ…

「井伊直弼討つべし!」藩に迷惑が掛からないように脱藩した水戸藩士たちは桜田門に集結。
命を狙われているのを知っていた直弼でしたが法を犯す事を良しとせず、護衛の数も増やさずにいつもの通り江戸城に向かいました。
桜田門に差し掛かったその時、一斉に襲撃を受けました。数では勝っていた護衛でしたが突然の襲撃に大混乱し多くが遁走。
直弼の乗った駕籠は滅多刺しにされた挙句、駕籠から引きずり出されて首を撥ねられました。享年44歳。
安政7年(1860年)3月3日に起こったこの事件は後世「桜田門外の変」として語り継がれることになるのでした。
命を狙われているのを知っていた直弼でしたが法を犯す事を良しとせず、護衛の数も増やさずにいつもの通り江戸城に向かいました。
桜田門に差し掛かったその時、一斉に襲撃を受けました。数では勝っていた護衛でしたが突然の襲撃に大混乱し多くが遁走。
直弼の乗った駕籠は滅多刺しにされた挙句、駕籠から引きずり出されて首を撥ねられました。享年44歳。
安政7年(1860年)3月3日に起こったこの事件は後世「桜田門外の変」として語り継がれることになるのでした。










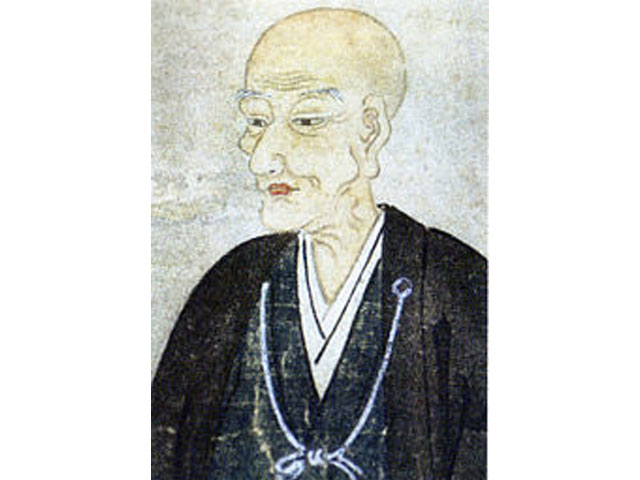





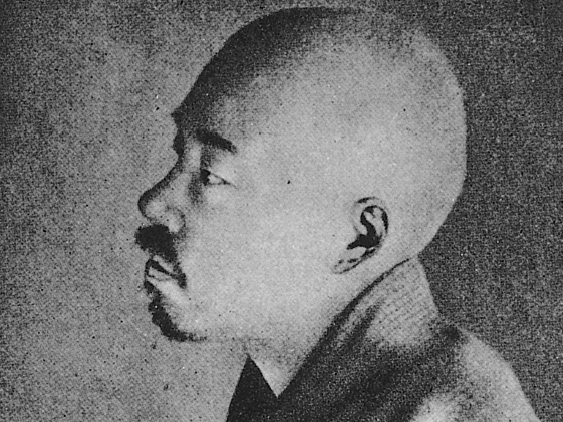

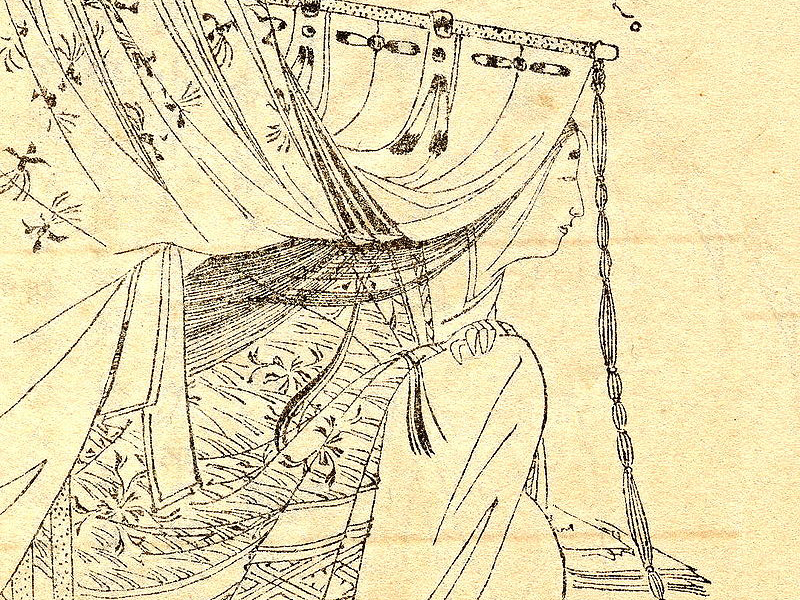





![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

