将軍にして歌詠み 源実朝の名歌とは!
関連キーワード

出典:https://upload.wikimedia.org|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Minamoto_no_Sanetomo.jpg/633px-Minamoto_no_Sanetomo.jpg
源実朝は鎌倉幕府三代将軍、そして比類なき歌詠みでした。実朝は、若い時から和歌の大家、藤原定家に教えをこい、『万葉集』や『古今集』、『新古今集』の歌に習い、本歌取りを駆使した独自の歌風を身につけました。彼の歌集『金槐和歌集』は江戸時代、賀茂真淵に注目されて以来、評価を高めてきました。正岡子規をして「実朝といふ人は三十にも足らで、いざこれからといふ処にてあへなき最期を遂げられ誠に残念致し候。あの人をして今十年も活かして置いたならどんなに名歌を沢山残したかも知れ不申候。とにかくに第一流の歌人と存じ候。」(『歌よみに与ふる書』)と言わしめています。
このように死後、歌人として名を馳せるに至った実朝ですが、日本史の教科書には(少なくとも山川出版の教科書には)、公暁によって暗殺された悲劇の鎌倉三代将軍として登場し、歌人としての一面はあまり紹介されていません。そこで、実朝の代表歌のいくつかを、意味や語注とあわせて紹介します。
このように死後、歌人として名を馳せるに至った実朝ですが、日本史の教科書には(少なくとも山川出版の教科書には)、公暁によって暗殺された悲劇の鎌倉三代将軍として登場し、歌人としての一面はあまり紹介されていません。そこで、実朝の代表歌のいくつかを、意味や語注とあわせて紹介します。
1. 世の中は 常にもがもな 渚こぐ
世の中は 常にもがもな 渚こぐ あまの小舟の 綱手かなしも
(『新勅撰集』)
<意味>
世の中は、いつも変わらずにあってほしいものだなぁ。渚(なぎさ)を漕ぎ行く漁師の引き綱をみると、胸が打たれるのだ。
<語注>
○常にもがもな…「もが」は終助詞で、「?であればなあ」と願望を意味する。 「も」と「な」はともに詠嘆を示す終助詞。
○渚…波うちぎわ。
○あま…漁師。
○綱手…舟につなぐ綱。陸から舟を引っ張る時に使う。
○かなし…「悲しい」の意味もあるが、「愛しい」の意味もあり、「胸を刺すような感情」全般を意味する。
この歌を選ばぬ手はない、というほどの実朝の代表的名歌。藤原定家の編纂した『小倉百人一首』のなかの第93番に「鎌倉右大臣」の歌として選ばれています。
万葉調を彷彿とさせるこの歌の姿・趣は、実朝が『万葉集』に歌風の範を求めていたことを裏付けます。実際、「常にもがもな」(永遠に変わらないでほしい)という表現は、『万葉集』の一首「川のへの ゆつ岩むらに 草むさず 常にもがもな 常処女(とこおとめ)にて」に見えます。さらに、下の句の「綱手かなしも」という表現も、『万葉集』の一首「みちのくは いづくはあれど 塩釜の 浦こぐ舟の 綱手かなしも」を、実朝は参考にしたのでしょう。
しかし、実朝は単なる言葉のパッチワークとしてこの歌を詠んだのではないでしょう。言葉こそ『万葉集』からの借り物ですが、そこに表された気持ちは、ほかならぬ実朝のものであったはずです。「常にもがもな」という表現は、頼家暗殺を筆頭に、日々、源将軍家の没落を感じていたに違いない実朝にとって、決して修辞的な興味から選ばれたのではないことは明らかです。実朝が肌で感じていた無常観を表現する意欲の中で選ばれた表現こそが「常にもがもな」だったのではないでしょうか。そして、漁師たちの日常的な営みに対する「かなし」という情感は、差し迫る非日常を予期した実朝の思いの裏返しであったことでしょう。
「常にもがもな」という表現が『万葉集』から引っ張り出されたほこりをかぶった表現ではなく、実朝の実感を表したみずみずしい表現として使われている、そこにこの歌の、そして実朝の魅力があるように思います。「常にもがもな」という願いむなしく、実朝は公暁によって暗殺され、二度と日常的な漁師たちの生活風景を見ることができなくなるのです。
(『新勅撰集』)
<意味>
世の中は、いつも変わらずにあってほしいものだなぁ。渚(なぎさ)を漕ぎ行く漁師の引き綱をみると、胸が打たれるのだ。
<語注>
○常にもがもな…「もが」は終助詞で、「?であればなあ」と願望を意味する。 「も」と「な」はともに詠嘆を示す終助詞。
○渚…波うちぎわ。
○あま…漁師。
○綱手…舟につなぐ綱。陸から舟を引っ張る時に使う。
○かなし…「悲しい」の意味もあるが、「愛しい」の意味もあり、「胸を刺すような感情」全般を意味する。
この歌を選ばぬ手はない、というほどの実朝の代表的名歌。藤原定家の編纂した『小倉百人一首』のなかの第93番に「鎌倉右大臣」の歌として選ばれています。
万葉調を彷彿とさせるこの歌の姿・趣は、実朝が『万葉集』に歌風の範を求めていたことを裏付けます。実際、「常にもがもな」(永遠に変わらないでほしい)という表現は、『万葉集』の一首「川のへの ゆつ岩むらに 草むさず 常にもがもな 常処女(とこおとめ)にて」に見えます。さらに、下の句の「綱手かなしも」という表現も、『万葉集』の一首「みちのくは いづくはあれど 塩釜の 浦こぐ舟の 綱手かなしも」を、実朝は参考にしたのでしょう。
しかし、実朝は単なる言葉のパッチワークとしてこの歌を詠んだのではないでしょう。言葉こそ『万葉集』からの借り物ですが、そこに表された気持ちは、ほかならぬ実朝のものであったはずです。「常にもがもな」という表現は、頼家暗殺を筆頭に、日々、源将軍家の没落を感じていたに違いない実朝にとって、決して修辞的な興味から選ばれたのではないことは明らかです。実朝が肌で感じていた無常観を表現する意欲の中で選ばれた表現こそが「常にもがもな」だったのではないでしょうか。そして、漁師たちの日常的な営みに対する「かなし」という情感は、差し迫る非日常を予期した実朝の思いの裏返しであったことでしょう。
「常にもがもな」という表現が『万葉集』から引っ張り出されたほこりをかぶった表現ではなく、実朝の実感を表したみずみずしい表現として使われている、そこにこの歌の、そして実朝の魅力があるように思います。「常にもがもな」という願いむなしく、実朝は公暁によって暗殺され、二度と日常的な漁師たちの生活風景を見ることができなくなるのです。
2. 大海の 磯もとどろに 寄する波
大海の 磯もとどろに 寄する波 われてくだけて さけて散るかも
(『金槐和歌集』)
<意味>
大海の磯の岩肌を響かせて打ち寄せる波が、割れて砕けて裂けて散ることだ。
<語注>
○とどろに…漢字にすれば「轟ろに」。ごうごうと打ち寄せる波の様子。
『万葉集』の表現に習いながら、波のごうごうと打ち寄せる情景を見事に詠みあげた一首。シラーの劇や、ベートーヴェンの音楽に代表される、ドイツの「シュトルム・ウント・ドラング」(疾風怒濤)を思わせる激烈な表現が印象的です。
「われてくだけて さけて散るかも」という畳み掛ける容赦ない表現は、さながらベートーヴェンの和音のよう。山上憶良の「男子の、名は古日に恋ひたる歌」(『万葉集』所収)の一節、「立ち踊り 足すり叫び 伏し仰ぎ 胸うち嘆き」という表現を参考にしたのかもしれません。
小林秀雄はこの歌について、『実朝』において「こういう分析的な表現が、何が壮快な歌だろうか」、といい、「いかにも独創の姿だが、独創は彼の工夫のうちにあったというよりは寧ろ彼の孤独が独創的だったと言った方がいい様に思う」と、悩める実朝の孤独を詠んだ歌であると述べています。「これが、ある日悶々として波に見入っていた時の彼の心の嵐の形でないならば、ただの洒落に過ぎまい。そういう彼を荒磯に置き去りにして、この歌の本歌やら類歌やらを求めるのは、心ないわざと思われる。」という小林の評言は、実朝の歌全般について言えることでしょう。
(『金槐和歌集』)
<意味>
大海の磯の岩肌を響かせて打ち寄せる波が、割れて砕けて裂けて散ることだ。
<語注>
○とどろに…漢字にすれば「轟ろに」。ごうごうと打ち寄せる波の様子。
『万葉集』の表現に習いながら、波のごうごうと打ち寄せる情景を見事に詠みあげた一首。シラーの劇や、ベートーヴェンの音楽に代表される、ドイツの「シュトルム・ウント・ドラング」(疾風怒濤)を思わせる激烈な表現が印象的です。
「われてくだけて さけて散るかも」という畳み掛ける容赦ない表現は、さながらベートーヴェンの和音のよう。山上憶良の「男子の、名は古日に恋ひたる歌」(『万葉集』所収)の一節、「立ち踊り 足すり叫び 伏し仰ぎ 胸うち嘆き」という表現を参考にしたのかもしれません。
小林秀雄はこの歌について、『実朝』において「こういう分析的な表現が、何が壮快な歌だろうか」、といい、「いかにも独創の姿だが、独創は彼の工夫のうちにあったというよりは寧ろ彼の孤独が独創的だったと言った方がいい様に思う」と、悩める実朝の孤独を詠んだ歌であると述べています。「これが、ある日悶々として波に見入っていた時の彼の心の嵐の形でないならば、ただの洒落に過ぎまい。そういう彼を荒磯に置き去りにして、この歌の本歌やら類歌やらを求めるのは、心ないわざと思われる。」という小林の評言は、実朝の歌全般について言えることでしょう。
3. 出でいなば 主なき宿と なりぬとも
出でいなば 主なき宿と なりぬとも 軒端の梅よ 春をわするな
(『吾妻鏡』)
<意味>
ここを出でて、ここが主人のいない宿となったとしても、軒端の梅よ、春が来たらきっと咲くんだぞ。
<語注>
○春をわするな…春になったら咲くことを忘れるな、ということ。
実は、この歌は『吾妻鏡』の創作と言われており、実朝の歌かどうかは怪しいのだそうです。しかし、かりに創作であったとしても、この歌が創作されるには、実朝の運命や歌人としての存在が必要であったことには変わりありません。その意味で、この「出でいなば」の歌を、あえて実朝の歌として紹介します。
『吾妻鏡』においては、この歌は実朝暗殺の日に詠まれた「禁忌の和歌」として登場します。「禁忌の和歌」といえば、菅原道真の歌が有名です。左遷された菅原道真が詠んだ一首「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」とこの歌の類似は偶然ではないでしょう。
歌の内容は凝ったものなく、言葉遣いも爽やか。歌集に載る歌というより、軍記物といった物語に載る歌、という趣です。「大海の 磯もとどろに 寄する波 われてくだけて さけて散るかも」という歌と比べるとインパクトは劣ります。しかし、簡素な歌であるがゆえに、自己の運命を悟り、従容と死におもむく実朝の心境が感じられるのではないでしょうか。
(『吾妻鏡』)
<意味>
ここを出でて、ここが主人のいない宿となったとしても、軒端の梅よ、春が来たらきっと咲くんだぞ。
<語注>
○春をわするな…春になったら咲くことを忘れるな、ということ。
実は、この歌は『吾妻鏡』の創作と言われており、実朝の歌かどうかは怪しいのだそうです。しかし、かりに創作であったとしても、この歌が創作されるには、実朝の運命や歌人としての存在が必要であったことには変わりありません。その意味で、この「出でいなば」の歌を、あえて実朝の歌として紹介します。
『吾妻鏡』においては、この歌は実朝暗殺の日に詠まれた「禁忌の和歌」として登場します。「禁忌の和歌」といえば、菅原道真の歌が有名です。左遷された菅原道真が詠んだ一首「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」とこの歌の類似は偶然ではないでしょう。
歌の内容は凝ったものなく、言葉遣いも爽やか。歌集に載る歌というより、軍記物といった物語に載る歌、という趣です。「大海の 磯もとどろに 寄する波 われてくだけて さけて散るかも」という歌と比べるとインパクトは劣ります。しかし、簡素な歌であるがゆえに、自己の運命を悟り、従容と死におもむく実朝の心境が感じられるのではないでしょうか。












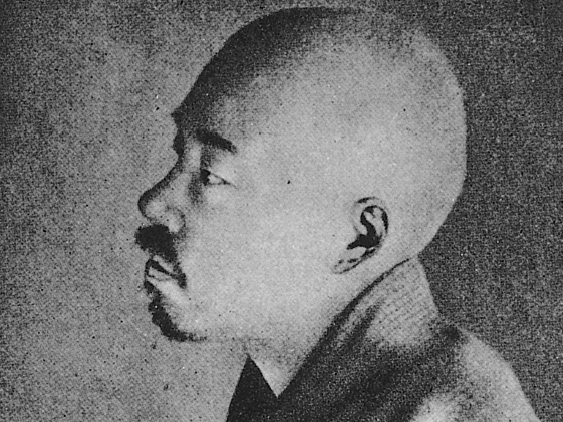

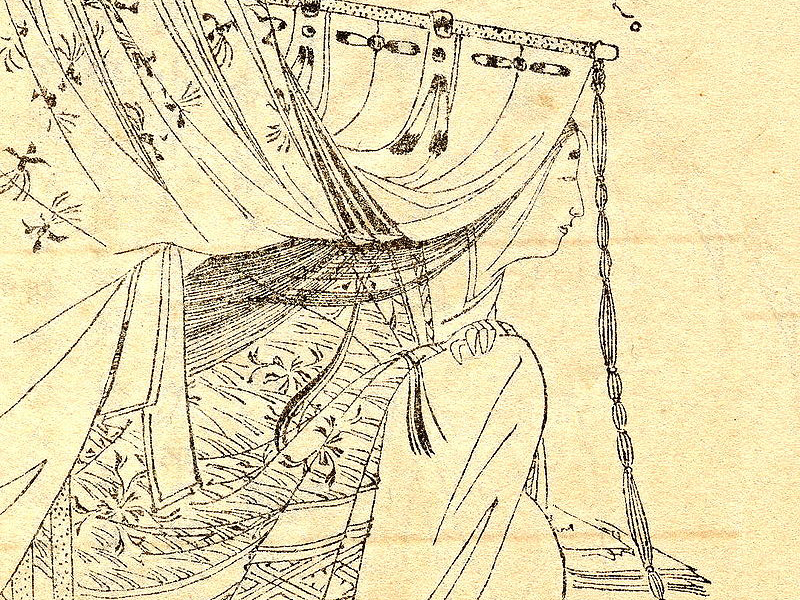





![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

