利休は秀吉をどうみていたのか?二人の関係を表すエピソード5つ
関連キーワード

足軽から関白まで上り詰めた権力者豊臣秀吉と、堺の商人でありながら茶聖と呼ばれるまでに茶の湯を極めた千利休。二人は協力して、双方の地位を高めることに力を注ぐのですが、最後は決定的に対立してしまいます。今に続く茶の湯を作り上げた利休は、秀吉をどうみていたのか。
その二人の関係を表すエピソードを5つご紹介しましょう。
その二人の関係を表すエピソードを5つご紹介しましょう。
1.黄金の茶室
千利休は、茶会などを取り仕切る茶頭の内の一人として、当初は、織田信長に仕えていました。信長が本能寺の変で亡くなると、利休は豊臣秀吉に仕えます。秀吉の下では、重要なポジションを占めるようになり、秀吉が全国統一を成し遂げると、利休も天下一の茶の宗匠という地位を得ることになりました。
農民の出身で武家の血縁を持たない秀吉は、自らの政権の正当性を主張するために、朝廷に黄金や御料地を献上し後ろ盾を得ようとします。そして、秀吉は、貴族間で起きた関白の地位をめぐる争いを利用して、自らが関白に就任しました。
関白に就任した翌年の天正14年(1586年)1月、秀吉は、年頭の参内で時の正親町天皇に献茶をします。その際に使われたのが、有名な「黄金の茶室」でした。この茶室は、 壁・天井・柱・障子の腰をすべて金張にした組み立て式で、どこにでも持ち込めるもので、利休が考案したと語られています。利休は、秀吉のもとで、今でいうプロデューサーのような仕事をしており、天皇への献茶というイベントを印象的なものにするための演出をしたのです。黄金煌めく茶室で茶を受けた天皇は、その斬新な発想とともに、秀吉の財力に驚かされたことでしょう。正親町天皇は、この年の9月に秀吉に「豊臣」の姓を与え、さらに太政大臣に任命しています。
尚、利休は、献茶で秀吉の後見をすることになりましたが、町人の身分では宮中に参内できないため、在家の仏教者を意味する居士の号「利休」を天皇より賜っています。 この頃の利休は、秀吉の権力がより大きく見えるような演出をしながら、自らの社会的地位も高めることに成功しており、二人はたいへん良好な関係を築いていたのでした。
農民の出身で武家の血縁を持たない秀吉は、自らの政権の正当性を主張するために、朝廷に黄金や御料地を献上し後ろ盾を得ようとします。そして、秀吉は、貴族間で起きた関白の地位をめぐる争いを利用して、自らが関白に就任しました。
関白に就任した翌年の天正14年(1586年)1月、秀吉は、年頭の参内で時の正親町天皇に献茶をします。その際に使われたのが、有名な「黄金の茶室」でした。この茶室は、 壁・天井・柱・障子の腰をすべて金張にした組み立て式で、どこにでも持ち込めるもので、利休が考案したと語られています。利休は、秀吉のもとで、今でいうプロデューサーのような仕事をしており、天皇への献茶というイベントを印象的なものにするための演出をしたのです。黄金煌めく茶室で茶を受けた天皇は、その斬新な発想とともに、秀吉の財力に驚かされたことでしょう。正親町天皇は、この年の9月に秀吉に「豊臣」の姓を与え、さらに太政大臣に任命しています。
尚、利休は、献茶で秀吉の後見をすることになりましたが、町人の身分では宮中に参内できないため、在家の仏教者を意味する居士の号「利休」を天皇より賜っています。 この頃の利休は、秀吉の権力がより大きく見えるような演出をしながら、自らの社会的地位も高めることに成功しており、二人はたいへん良好な関係を築いていたのでした。
2.北野大茶湯
利休のプロデューサーとしての仕事は、朝廷に対してだけ行われたわけではありません。他にも、世間をあっと驚かすようなイベントを秀吉とともに開催しています。
天正15(1587)年、京都北野天満宮境内で大茶会を催し、茶の湯に執心の者は身分を問わず参加を許可することで、多くの人を集めようと試みました。北野天満宮の拝殿に、黄金の茶室を持ち込み、そこに「似たり茄子」などの秀吉自慢の名物を陳列して、一般に公開しました。利休をはじめ、津田宗及、今井宗久という当代きっての茶人が、名物を用いて茶を提供し、秀吉自身も半日は亭主として茶をふるまいました。事前に各地に大々的に告知していたので、京都だけでなく、大阪・堺・奈良からも人が集まり、当初10日間の予定を1日で取りやめたにもかかわらず1000名もの人がこの大茶湯に参加したのでした。華やかで賑やかな茶の湯という秀吉の好みを利休は熟知しており、利休はそれに沿った大茶湯を企画したのです。 その頃の秀吉と利休の信頼関係を表す書状も遺されています。 九州の大名である大友宗麟は、島津討伐の救援を依頼するために天正14(1586)年に大坂城を訪れた際に、秀吉の弟の豊臣秀長から 「公儀のことは私に、内々のことは宗易に」 と耳打ちされたと書状に書き遺しました。 文化的な面だけでなく、政治の上でも、利休は秀吉の秘書のような立場で関わっていました。
天正15(1587)年、京都北野天満宮境内で大茶会を催し、茶の湯に執心の者は身分を問わず参加を許可することで、多くの人を集めようと試みました。北野天満宮の拝殿に、黄金の茶室を持ち込み、そこに「似たり茄子」などの秀吉自慢の名物を陳列して、一般に公開しました。利休をはじめ、津田宗及、今井宗久という当代きっての茶人が、名物を用いて茶を提供し、秀吉自身も半日は亭主として茶をふるまいました。事前に各地に大々的に告知していたので、京都だけでなく、大阪・堺・奈良からも人が集まり、当初10日間の予定を1日で取りやめたにもかかわらず1000名もの人がこの大茶湯に参加したのでした。華やかで賑やかな茶の湯という秀吉の好みを利休は熟知しており、利休はそれに沿った大茶湯を企画したのです。 その頃の秀吉と利休の信頼関係を表す書状も遺されています。 九州の大名である大友宗麟は、島津討伐の救援を依頼するために天正14(1586)年に大坂城を訪れた際に、秀吉の弟の豊臣秀長から 「公儀のことは私に、内々のことは宗易に」 と耳打ちされたと書状に書き遺しました。 文化的な面だけでなく、政治の上でも、利休は秀吉の秘書のような立場で関わっていました。
3.紅梅の花びら
秀吉は利休の審美眼にたいへんな信頼を寄せていたのですが、一方で、利休の美的センスを試すようなことを仕掛けています。
ある日、秀吉は大きな鉢に水を入れて、傍らに紅梅を一枝置き、利休に「花を入れてみよ」と命じます。鉢が大きいので、紅梅一輪さしてもバランスがとれません。利休がどのように活けるか、秀吉は試してみたのです。利休は、秀吉の意図をくみ取り、紅梅の枝を逆さに持ち、枝をしごきました。水面には、花びらと蕾とが入り交じって浮かび、たいへん美しい景色が表れました。こういった凡人には思いつかない利休の機転を、秀吉は高く評価しており、利休も、秀吉の期待を喜んで受け入れ、それに十分応えていたのでした。
ある日、秀吉は大きな鉢に水を入れて、傍らに紅梅を一枝置き、利休に「花を入れてみよ」と命じます。鉢が大きいので、紅梅一輪さしてもバランスがとれません。利休がどのように活けるか、秀吉は試してみたのです。利休は、秀吉の意図をくみ取り、紅梅の枝を逆さに持ち、枝をしごきました。水面には、花びらと蕾とが入り交じって浮かび、たいへん美しい景色が表れました。こういった凡人には思いつかない利休の機転を、秀吉は高く評価しており、利休も、秀吉の期待を喜んで受け入れ、それに十分応えていたのでした。
4.一輪の朝顔
利休と秀吉の逸話で、有名な話の一つが朝顔の件でしょう。
利休の家の露地の朝顔が一面に咲いて美しいという噂を聞いた秀吉は、早速、利休に「朝顔がみたい」と朝の茶会を開くように命じます。
早朝、秀吉が利休の家へ出かけると、秀吉が楽しみにしていた露地の朝顔は残らず引き抜かれ一輪もありません。秀吉は、腹をたてながら茶室に入ると、床には見事な朝顔が一輪だけ入れてありました。秀吉は、その美しさに感心し、利休の大胆な趣向を評価したという話です。
しかし、秀吉は、本当に一輪だけの朝顔を喜んでいたのでしょうか?秀吉は、一面に咲く朝顔を楽しみに、利休の茶室に出かけたはずです。確かに、最高の一輪に注目を集めるための趣向は、秀吉を驚かせ、その美しさには、秀吉も文句の言いようがなかったことでしょう。
しかし、権力者となった秀吉の心の中には「自分の希望を素直に聞き入れない利休」という気持ちが芽生えていたのではないでしょうか。利休は、黄金の茶室、大規模な茶会など秀吉の派手な好みを知り尽くしているはずです。それまでは、秀吉の美意識を受け入れてきたにも関わらず、この時ばかりは、朝顔一輪だけを飾ったというのは、何か心の変化があったのでしょうか。この頃から、秀吉と利休の関係に、密かにひびが入り始めたのでした。
利休の家の露地の朝顔が一面に咲いて美しいという噂を聞いた秀吉は、早速、利休に「朝顔がみたい」と朝の茶会を開くように命じます。
早朝、秀吉が利休の家へ出かけると、秀吉が楽しみにしていた露地の朝顔は残らず引き抜かれ一輪もありません。秀吉は、腹をたてながら茶室に入ると、床には見事な朝顔が一輪だけ入れてありました。秀吉は、その美しさに感心し、利休の大胆な趣向を評価したという話です。
しかし、秀吉は、本当に一輪だけの朝顔を喜んでいたのでしょうか?秀吉は、一面に咲く朝顔を楽しみに、利休の茶室に出かけたはずです。確かに、最高の一輪に注目を集めるための趣向は、秀吉を驚かせ、その美しさには、秀吉も文句の言いようがなかったことでしょう。
しかし、権力者となった秀吉の心の中には「自分の希望を素直に聞き入れない利休」という気持ちが芽生えていたのではないでしょうか。利休は、黄金の茶室、大規模な茶会など秀吉の派手な好みを知り尽くしているはずです。それまでは、秀吉の美意識を受け入れてきたにも関わらず、この時ばかりは、朝顔一輪だけを飾ったというのは、何か心の変化があったのでしょうか。この頃から、秀吉と利休の関係に、密かにひびが入り始めたのでした。
5.利休の最期の言葉
天正19(1591)年、利休は突然秀吉の逆鱗に触れ、堺に蟄居を命じられます。その理由は諸説ありますが、明確なことはわかっていません。秀吉も、当初は利休が謝れば許す気持ちがあったようで、北政所のとりなしで、秀吉に謝罪すれば良いという話も出来上がっていました。しかし、利休は「女性のとりなしを受けてまで生きたいとは思わない」と言って断ってしまいました。
結果、利休は切腹を命じられ、その首は一条戻橋で晒されるというひどい仕打ちを受けるのです。
利休は切腹の前に、遺偈を残しました。 それは、「うぉおー」という叫びと、「バカもの!」と叱りつける言葉で始まり、大きな怒りと凄味が感じられるものでした。お互いの才能を認め、信頼しあっていた秀吉と利休の関係は、いつからか崩れてしまい、怒りを双方ぶつけあった上、利休の切腹で終焉を迎えるのでした。
結果、利休は切腹を命じられ、その首は一条戻橋で晒されるというひどい仕打ちを受けるのです。
利休は切腹の前に、遺偈を残しました。 それは、「うぉおー」という叫びと、「バカもの!」と叱りつける言葉で始まり、大きな怒りと凄味が感じられるものでした。お互いの才能を認め、信頼しあっていた秀吉と利休の関係は、いつからか崩れてしまい、怒りを双方ぶつけあった上、利休の切腹で終焉を迎えるのでした。









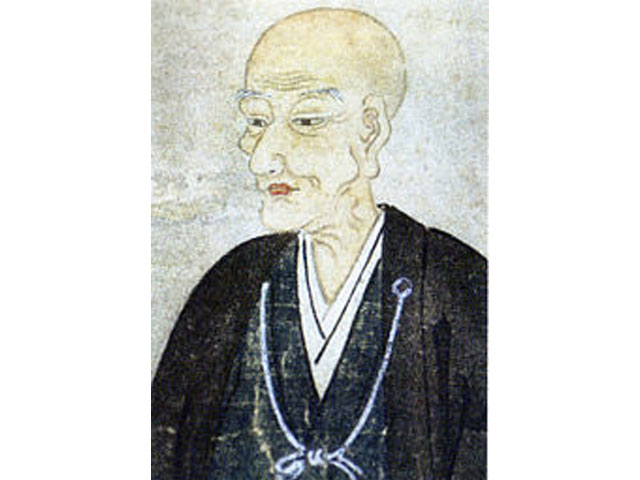







![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

