茶人達に愛された備前焼の特徴
関連キーワード

茶褐色の地肌に、作意のない様々な模様が浮き出る備前焼は、その飾り気のなさが評価され、茶人達に愛されてきた焼き物です。備前焼は、歴史も古く、平安時代より多数の器類を作成してきました。その歴史や特徴とともに、茶道具として愛された備前焼についてご紹介していきます。
備前焼の歴史
備前焼とは、岡山県備前市周辺で生産される無釉薬の焼締陶器です。備前焼の歴史は平安時代に遡り、日本の六古窯の一つに上げられます。鎌倉時代には、現在のような茶褐色の陶器が焼かれていたと言われています。
桃山時代、茶道が発展し千利休が侘茶を大成すると、素朴な風情の備前焼は茶道具として評価されるようになります。水指を中心に茶人の間では人気が高まり、他にも、茶入、花入などが作成されました。しかし、江戸時代になると茶道具の作成は衰退し、鉢や酒徳利など実用品の生産が中心になっていきました。
備前焼が、芸術性の高い作品として見直され再評価を受けるには。昭和に入り、金重陶陽が現れるまで待たねばなりませんでした。陶陽は、桃山時代の作陶に回帰することで、備前焼を復興させます。そして、「備前焼中興の祖」と呼ばれるようになり、備前焼の陶工として初めて人間国宝に認定されました。
さらに、陶陽は、多くの弟子を育成しました。藤原啓は、40歳で陶芸の世界に足を踏み入れて陶陽から指導を受け、後には、息子の雄とともに、備前焼の伝統に新しい感性を加えた作品を追及します。また、ろくろの名手といわれた山本陶秀は、繊細優美な作風で知られ、陶陽や藤原親子と共に備前焼復興を支えました。藤原啓、雄、山本陶秀の3人は、人間国宝に認定されました。
備前焼は、「使い込むほどに味が出る」と言われるように、飽きのこない焼物として現代でも多くの人に愛されています。現在は、2004年に人間国宝に認定された伊勢崎淳を中心に、多くの陶芸家たちが備前焼の伝統的な製法を守りつつも、芸術制の高い作品に取り組み、新たな備前焼を生みだしているのです。
桃山時代、茶道が発展し千利休が侘茶を大成すると、素朴な風情の備前焼は茶道具として評価されるようになります。水指を中心に茶人の間では人気が高まり、他にも、茶入、花入などが作成されました。しかし、江戸時代になると茶道具の作成は衰退し、鉢や酒徳利など実用品の生産が中心になっていきました。
備前焼が、芸術性の高い作品として見直され再評価を受けるには。昭和に入り、金重陶陽が現れるまで待たねばなりませんでした。陶陽は、桃山時代の作陶に回帰することで、備前焼を復興させます。そして、「備前焼中興の祖」と呼ばれるようになり、備前焼の陶工として初めて人間国宝に認定されました。
さらに、陶陽は、多くの弟子を育成しました。藤原啓は、40歳で陶芸の世界に足を踏み入れて陶陽から指導を受け、後には、息子の雄とともに、備前焼の伝統に新しい感性を加えた作品を追及します。また、ろくろの名手といわれた山本陶秀は、繊細優美な作風で知られ、陶陽や藤原親子と共に備前焼復興を支えました。藤原啓、雄、山本陶秀の3人は、人間国宝に認定されました。
備前焼は、「使い込むほどに味が出る」と言われるように、飽きのこない焼物として現代でも多くの人に愛されています。現在は、2004年に人間国宝に認定された伊勢崎淳を中心に、多くの陶芸家たちが備前焼の伝統的な製法を守りつつも、芸術制の高い作品に取り組み、新たな備前焼を生みだしているのです。
備前焼の特徴
備前焼は、釉薬を使わず、堅く焼しめられることが特長です。その魅力の一つは、茶褐色の地肌です、備前焼の肌は、鉄分が入った土が「酸化焔焼成」されることで、赤身の強い茶褐色になるのです。
そして、表面に生じた窯変の模様がさらなる魅力が生みだします。窯変とは、焼成時に窯の中で灰や炭が焼き物に付着し、その部分が変化して生じた模様のことです。窯の中の場所や炎の強さ、灰の量によって模様が変化するため、窯を開けて作品を取り出してみるまでは、どんな模様に仕上がるかは作者でもわかりません。自然が生みだす模様が備前焼の魅力なのです。
窯変には以下のような模様があります。
1.胡麻
窯焚の最中に、薪の灰が融けて生地につく事によりできる模様です。
2.緋襷
まるで襷がけをしたように入る、直線的な赤い模様を緋襷と呼びます。これは、作品に藁を巻き付け、さらに鞘などに詰めて直接火の当たらない場所で焼成することででき上がります。生地全体は白く、藁のあった部分が赤い模様になるのです。大胆に入った緋襷は、赤と白のコントラストが美しく、大変人気のある模様です。
3.牡丹餅
一度の火入れで多くの作品を焼成するためには、作品を重ねて窯に入れる必要があります。当然、重なっていた部分は、直接火が当たらず、模様のように跡が残ります。例えば、大きな皿に、小さなぐい呑みを乗せて焼成すれば、皿にぐい呑みの形が残り、その丸い跡が皿に盛り付けた牡丹餅のように見えることがあります。これを、茶人達は「牡丹餅」と読んで愛し、懐石道具として珍重しました。
そして、表面に生じた窯変の模様がさらなる魅力が生みだします。窯変とは、焼成時に窯の中で灰や炭が焼き物に付着し、その部分が変化して生じた模様のことです。窯の中の場所や炎の強さ、灰の量によって模様が変化するため、窯を開けて作品を取り出してみるまでは、どんな模様に仕上がるかは作者でもわかりません。自然が生みだす模様が備前焼の魅力なのです。
窯変には以下のような模様があります。
1.胡麻
窯焚の最中に、薪の灰が融けて生地につく事によりできる模様です。
2.緋襷
まるで襷がけをしたように入る、直線的な赤い模様を緋襷と呼びます。これは、作品に藁を巻き付け、さらに鞘などに詰めて直接火の当たらない場所で焼成することででき上がります。生地全体は白く、藁のあった部分が赤い模様になるのです。大胆に入った緋襷は、赤と白のコントラストが美しく、大変人気のある模様です。
3.牡丹餅
一度の火入れで多くの作品を焼成するためには、作品を重ねて窯に入れる必要があります。当然、重なっていた部分は、直接火が当たらず、模様のように跡が残ります。例えば、大きな皿に、小さなぐい呑みを乗せて焼成すれば、皿にぐい呑みの形が残り、その丸い跡が皿に盛り付けた牡丹餅のように見えることがあります。これを、茶人達は「牡丹餅」と読んで愛し、懐石道具として珍重しました。
備前焼の茶道具
備前焼は、その飾り気のない素朴な風情が侘茶に適うとして、桃山時代に茶道具として使用されるようになります。特に水指、茶入、花入、建水が、数多く作られました。茶碗もありますが、数は多くはありません。釉薬をかけず焼締めるため、どうしても表面がザラつき、口当たりが滑らかでないことや、茶筅が擦れて傷みやすいということが影響しているのでしょう。
他に、懐石道具として、徳利、ぐい呑み、大皿などが、近世以降の茶人に愛用されたことが、当時の茶会記などより明らかになっています。
備前焼の水指では、現在、畠山記念館が所蔵する備前火襷水指が重要文化財に指定されていて、茶人の間によく知られています。轆轤で薄手に整形され、肩が丸く、腰から裾にかけて少し細くしまった美しい形をしています。白っぽく焼成された肌に、備前焼特有の赤い火襷文様が美しく表れているのが特徴です。
備前焼の茶入は、桃山時代から名物として伝わるものがあり、大正時代に高橋箒庵が編纂した『大正名器鑑』には、備前焼茶入が5点、同じ産地である伊部焼茶入が2点掲載されています。中でも「布袋」はよく知られており、千利休が博多で見出し、「布袋」と銘を付けたと伝わっています。また「さび助」は古田織部の好みと言われ、松花堂昭乗に伝わります。その後、姫路の酒井家を経て、大名茶人として著名な松平不昧の手に渡り、以後大切に同家で扱われ維新後まで伝わっています。
現代でも、備前焼の水指、花入れは茶道具として人気が高く、多くの作品が作られ、また茶会などで使用されています。この中からも、後世まで名品と呼ばれるものが数多く出てくることでしょう。
他に、懐石道具として、徳利、ぐい呑み、大皿などが、近世以降の茶人に愛用されたことが、当時の茶会記などより明らかになっています。
備前焼の水指では、現在、畠山記念館が所蔵する備前火襷水指が重要文化財に指定されていて、茶人の間によく知られています。轆轤で薄手に整形され、肩が丸く、腰から裾にかけて少し細くしまった美しい形をしています。白っぽく焼成された肌に、備前焼特有の赤い火襷文様が美しく表れているのが特徴です。
備前焼の茶入は、桃山時代から名物として伝わるものがあり、大正時代に高橋箒庵が編纂した『大正名器鑑』には、備前焼茶入が5点、同じ産地である伊部焼茶入が2点掲載されています。中でも「布袋」はよく知られており、千利休が博多で見出し、「布袋」と銘を付けたと伝わっています。また「さび助」は古田織部の好みと言われ、松花堂昭乗に伝わります。その後、姫路の酒井家を経て、大名茶人として著名な松平不昧の手に渡り、以後大切に同家で扱われ維新後まで伝わっています。
現代でも、備前焼の水指、花入れは茶道具として人気が高く、多くの作品が作られ、また茶会などで使用されています。この中からも、後世まで名品と呼ばれるものが数多く出てくることでしょう。









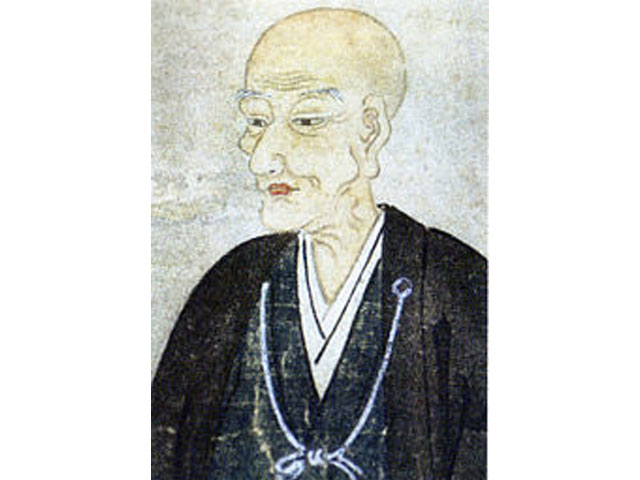







![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

