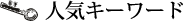文学作品が伝える関東大震災から見えてくるもの!"
関連キーワード

日本は地震大国。歴史のなかで幾度も大地震に見舞われてきました。古くは1185年の文治地震が大きな地震と知られ、鴨長明の『方丈記』における「おほなゐ」(大地震)の記述をはじめ、多くの日記・随筆に記録が残されています。
また、地震は上の画像のような「鯰絵」も生み出しました。鯰絵とは、地震から守る魔除けとして1855年の安政の大地震の後流行した錦絵です。当時、「鯰が地震をおこす」という民間信仰があったことに由来しますが、今でも「鯰は地震を予知する」などといわれ、鯰と地震のつながりへの信仰は未だ健在です。
数ある日本史上の大地震のなかでも桁違いの被害と印象を残したのが、1923年(大正12)9月1日の白昼に起きた関東大震災。200万人ちかくが被災し、10万人を超える人が命を失ったといわれる未曾有の災害として記憶されています。この関東大震災は当時の社会に強い衝撃を与えたことはいうまでもありませんが、当時の文学者たちはこの災害をどう見たのでしょうか。関東大震災に居合わせた文人、居合わせなかった文人の、関東大震災にまつわる作品を紐解くと、これからの災害への教訓が得られるかもしれません。
また、地震は上の画像のような「鯰絵」も生み出しました。鯰絵とは、地震から守る魔除けとして1855年の安政の大地震の後流行した錦絵です。当時、「鯰が地震をおこす」という民間信仰があったことに由来しますが、今でも「鯰は地震を予知する」などといわれ、鯰と地震のつながりへの信仰は未だ健在です。
数ある日本史上の大地震のなかでも桁違いの被害と印象を残したのが、1923年(大正12)9月1日の白昼に起きた関東大震災。200万人ちかくが被災し、10万人を超える人が命を失ったといわれる未曾有の災害として記憶されています。この関東大震災は当時の社会に強い衝撃を与えたことはいうまでもありませんが、当時の文学者たちはこの災害をどう見たのでしょうか。関東大震災に居合わせた文人、居合わせなかった文人の、関東大震災にまつわる作品を紐解くと、これからの災害への教訓が得られるかもしれません。
1.寺田寅彦
寺田寅彦(1878-1935)は多才な人物でした。物理学者として世界的に活躍したほか、夏目漱石と交流があり、俳句や随筆の分野でも傑作を残しました。『三四郎』において、帝国大学で研究に励む物理学者、野々宮宗八のモデルとなったといわれているのも、寺田寅彦です。
寺田寅彦は1923年9月1日、東京上野の二科会展にいました。この時の地震体験について、寺田は『震災日記より』において、次のように書いています。
T君と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品画「I崎の女」に対するそのモデルの良人からの撤回要求問題の話を聞いているうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけている両足のうらを下から木槌で急速に乱打するように感じた。多分その前に来たはずの弱い初期微動を気が付かずに直ちに主要動を感じたのだろうという気がして、それにしても妙に短週期の振動だと思っているうちにいよいよ本当の主要動が急激に襲って来た。同時に、これは自分の全く経験のない異常の大地震であると知った。その瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされていた土佐の安政地震の話がありあり想い出され、丁度船に乗ったように、ゆたりゆたり揺れるという形容が適切である事を感じた。仰向あおむいて会場の建築の揺れ工合を注意して見ると四、五秒ほどと思われる長い週期でみし/\みし/\と音を立てながら緩やかに揺れていた。それを見たときこれならこの建物は大丈夫だということが直感されたので恐ろしいという感じはすぐになくなってしまった。そうして、この珍しい強震の振動の経過を出来るだけ精しく観察しようと思って骨を折っていた。
主要動が始まってびっくりしてから数秒後に一時振動が衰え、この分では大した事もないと思う頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が来て、二度目にびっくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになった。
「土佐の安政地震」というのは、鯰絵が流行するきっかけとなった、江戸の安政地震に先立つ1854年に南海で起きた大地震を指しています。一流の物理学者にして名随筆家の寺田寅彦らしく、地震に遭っても持ち前の観察眼と分析力を発揮しています。「初期微動」と「主要動」は今でこそテレビを通じて周知の事実となっていますが、当時、地震のパニック状態にあって、寺田のような冷静な分析ができた人が果たしていたでしょうか。また、「四、五秒ほどと思われる長い週期」を確認して、「これならこの建物は大丈夫だということが直感されたので恐ろしいという感じはすぐになくなってしまった。」という部分は、いかにも物理学者。現代では、長周期振動が高層ビルの固有振動数と共振し、ビルの高層階に被害をもたらす危険が言われるようになりました。そして、一度揺れが収まった後にもう一度強い揺れが来た、という最後の記述は、東日本大震災においても見られたことでした。
関東大震災の後、寺田は地震の調査を行いました。この時の経験をもとに、寺田は地震や防災に関する記事を書き、なかでも『天災と国防』は時代を経てない意義を失わない示唆に富んだ作品として読まれ続けています。防災のためには過去の経験・歴史に学ぶことが肝要だ、と寺田は『天災と国防』で述べており、「天災は忘れた頃にやって来る」という格言は寺田寅彦の言葉として、世に広く知られています。震災に直接的には関係しませんが、デマについて考察した『流言蜚語』というエッセイにも大震災の経験が反映されています。
寺田寅彦は1923年9月1日、東京上野の二科会展にいました。この時の地震体験について、寺田は『震災日記より』において、次のように書いています。
T君と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品画「I崎の女」に対するそのモデルの良人からの撤回要求問題の話を聞いているうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけている両足のうらを下から木槌で急速に乱打するように感じた。多分その前に来たはずの弱い初期微動を気が付かずに直ちに主要動を感じたのだろうという気がして、それにしても妙に短週期の振動だと思っているうちにいよいよ本当の主要動が急激に襲って来た。同時に、これは自分の全く経験のない異常の大地震であると知った。その瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされていた土佐の安政地震の話がありあり想い出され、丁度船に乗ったように、ゆたりゆたり揺れるという形容が適切である事を感じた。仰向あおむいて会場の建築の揺れ工合を注意して見ると四、五秒ほどと思われる長い週期でみし/\みし/\と音を立てながら緩やかに揺れていた。それを見たときこれならこの建物は大丈夫だということが直感されたので恐ろしいという感じはすぐになくなってしまった。そうして、この珍しい強震の振動の経過を出来るだけ精しく観察しようと思って骨を折っていた。
主要動が始まってびっくりしてから数秒後に一時振動が衰え、この分では大した事もないと思う頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が来て、二度目にびっくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになった。
「土佐の安政地震」というのは、鯰絵が流行するきっかけとなった、江戸の安政地震に先立つ1854年に南海で起きた大地震を指しています。一流の物理学者にして名随筆家の寺田寅彦らしく、地震に遭っても持ち前の観察眼と分析力を発揮しています。「初期微動」と「主要動」は今でこそテレビを通じて周知の事実となっていますが、当時、地震のパニック状態にあって、寺田のような冷静な分析ができた人が果たしていたでしょうか。また、「四、五秒ほどと思われる長い週期」を確認して、「これならこの建物は大丈夫だということが直感されたので恐ろしいという感じはすぐになくなってしまった。」という部分は、いかにも物理学者。現代では、長周期振動が高層ビルの固有振動数と共振し、ビルの高層階に被害をもたらす危険が言われるようになりました。そして、一度揺れが収まった後にもう一度強い揺れが来た、という最後の記述は、東日本大震災においても見られたことでした。
関東大震災の後、寺田は地震の調査を行いました。この時の経験をもとに、寺田は地震や防災に関する記事を書き、なかでも『天災と国防』は時代を経てない意義を失わない示唆に富んだ作品として読まれ続けています。防災のためには過去の経験・歴史に学ぶことが肝要だ、と寺田は『天災と国防』で述べており、「天災は忘れた頃にやって来る」という格言は寺田寅彦の言葉として、世に広く知られています。震災に直接的には関係しませんが、デマについて考察した『流言蜚語』というエッセイにも大震災の経験が反映されています。
2.芥川龍之介
1923年8月31日、風邪ぎみの芥川龍之介は布団で森鴎外の『渋江抽斎』を読んでいました。その時の日記には、
嘗て小説「芋粥」を草せし時、「殆ど全く」なる語を用ひ、久米(注:芥川の友人、久米正雄)に笑はれたる記憶あり。今「抽斎」を読めば、鴎外先生も亦また「殆ど全く」の語を用ふ。一笑を禁ずる能はず。
(『大震日記』
と実に他愛のないことが書かれています。その翌日、芥川は被災します。落ち着きを払って周囲を観察した寺田寅彦とは対照的に、『大震日記』には、芥川の当時の行動や、火災に見舞われる東京の様子が写実的に書かれています。一方で、『大震雑記』には震災後の経験が生々しく、しかし淡々と書かれています。自らを「散文的に出来てゐる」(『廃都東京』)と評する芥川の大震災に対する意見は全体として淡々としたもので、東京に対しての愛郷心もなく、作家に与える影響もそれほど決定的なものではない、と述べています。地震についても、「ただ大地だいちの動いた結果、火事が起つたり、人が死んだりしたのにすぎない」(『震災の文芸に与ふる影響』)とかなり「散文的」です。
芥川龍之介の地震経験がもとになっているであろう短編作品に『ピアノ』(1925)があります。『ピアノ』冒頭、震災によって捨てられたままのピアノが描写されます。
或雨のふる秋の日、わたしは或人を訪ねる為に横浜の山手を歩いて行つた。この辺の荒廃は震災当時と殆ど変つてゐなかつた。若し少しでも変つてゐるとすれば、それは一面にスレ-トの屋根や煉瓦の壁の落ち重なつた中に藜(あかざ)の伸びてゐるだけだつた。現に或家の崩れた跡には蓋をあけた弓なりのピアノさへ、半ば壁にひしがれたまま、つややかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいた藜の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。
誰にも弾かれなくなったピアノですが、「わたし」は不意にこのピアノが音を奏でるのを聴きます。実はこのピアノ、「震災以来、誰も知らぬ音を保つてゐたピアノ」だったのです。自然のなかに一体となったピアノが、どのようにして音を出していたのか、それはこの小説の眼目ですから、読んでのお楽しみとしておきます。
或雨のふる秋の日、わたしは或人を訪ねる為に横浜の山手を歩いて行つた。この辺の荒廃は震災当時と殆ど変つてゐなかつた。若し少しでも変つてゐるとすれば、それは一面にスレ-トの屋根や煉瓦の壁の落ち重なつた中に藜(あかざ)の伸びてゐるだけだつた。現に或家の崩れた跡には蓋をあけた弓なりのピアノさへ、半ば壁にひしがれたまま、つややかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいた藜の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。
誰にも弾かれなくなったピアノですが、「わたし」は不意にこのピアノが音を奏でるのを聴きます。実はこのピアノ、「震災以来、誰も知らぬ音を保つてゐたピアノ」だったのです。自然のなかに一体となったピアノが、どのようにして音を出していたのか、それはこの小説の眼目ですから、読んでのお楽しみとしておきます。

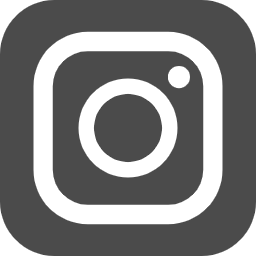
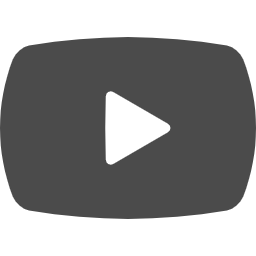

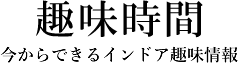















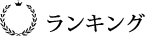

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)