ハプスブルク家のマリアテレジア、その憧れの系譜
関連キーワード

「ヨーロッパのお姫様と言えば?」と質問された時、多くの日本人がイメージするのは「マリー・アントワネット」ではないでしょうか。
その「ザ・お姫様」マリー・アントワネットの母がマリア・テレジアです。
彼女には息子が5人、娘が11人いて、マリー・アントワネットは末娘(下から2番目)でした。
彼女が生きた時代、フランス革命前夜のヨーロッパは、全盛期であった絶対王政を司る国王たちによる飽くなき権力闘争と領土侵略、そして富と不満が蓄積した平民出身の新階級の台頭により、不安定な情勢下にありました。
1740年にカール6世が世を去り、男系が途絶えたオーストラリア系ハプスブルグ家では、激しい後継争いが起こりました。長女のマリア・テレジアが相続した王の座を狙ったヨーロッパ各国によって、7年にも及ぶ「オーストリア継承戦争」が勃発します。この戦いに敗れたことで、領土の一部や「神聖ローマ皇帝」の帝冠を奪われてしまったマリア・テレジアでしたが、彼女は負けませんでした。
磨きぬかれた政治センスで王国と実質的な女帝として国政を背負い、ヨーロッパ情勢の荒波を泳ぎました。
その「ザ・お姫様」マリー・アントワネットの母がマリア・テレジアです。
彼女には息子が5人、娘が11人いて、マリー・アントワネットは末娘(下から2番目)でした。
彼女が生きた時代、フランス革命前夜のヨーロッパは、全盛期であった絶対王政を司る国王たちによる飽くなき権力闘争と領土侵略、そして富と不満が蓄積した平民出身の新階級の台頭により、不安定な情勢下にありました。
1740年にカール6世が世を去り、男系が途絶えたオーストラリア系ハプスブルグ家では、激しい後継争いが起こりました。長女のマリア・テレジアが相続した王の座を狙ったヨーロッパ各国によって、7年にも及ぶ「オーストリア継承戦争」が勃発します。この戦いに敗れたことで、領土の一部や「神聖ローマ皇帝」の帝冠を奪われてしまったマリア・テレジアでしたが、彼女は負けませんでした。
磨きぬかれた政治センスで王国と実質的な女帝として国政を背負い、ヨーロッパ情勢の荒波を泳ぎました。
ハプスブルク家はなぜ憧れの家系なの?
スイスの小さな村ブルックには、「鷹の城」と呼ばれる11世紀の古城の一部が残されています。「鷹の城」はドイツ語で言うと「ハビヒツブルク」となり、一帯を支配していたオットーが「ハプスブルク伯」と称するようになったことが、ハプスブルグ家の発祥とされています。
ハプスブルグ王朝の祖・ルドルフ1世は、1273年にドイツ国王に選出され、実質的に神聖ローマ皇帝の座につきました。ルドルフ1世が亡き後、1452年に再びフリードリヒ3世がドイツ国王に即位し、ローマ教皇から正式に神聖ローマ皇帝に任ぜられました。それ以降、ハプスブルグ家は代々神聖ローマ皇帝の座を継承する名家となったのです。
ハプスブルグ家の栄華の源泉は、武力によるものではなく、ヨーロッパ王家や名家をぬい合わせるように婚姻関係を結ぶことにありました。
スペインとブルグント(ベネルクス三国とフランス・ブルゴーニュ地方周辺)とボヘミア=ハンガリーの王をハプスブルグ家の血縁者が席捲していた時代、「日没なき世界帝国」と謳われるほどの広大な領地は、婚姻関係を結んだ諸王家に不幸があり、その所領が次々にハプスブルグ家に転がり込んできたことで叶ったものです。
1516年に皇帝となったカール5世によって、広大な領土を分割統治するためにオーストリア系とスペイン系に分かれ、それぞれがヨーロッパ諸王家を背後から動かす政治力を保ち続けていました。
ハプスブルグ王朝の祖・ルドルフ1世は、1273年にドイツ国王に選出され、実質的に神聖ローマ皇帝の座につきました。ルドルフ1世が亡き後、1452年に再びフリードリヒ3世がドイツ国王に即位し、ローマ教皇から正式に神聖ローマ皇帝に任ぜられました。それ以降、ハプスブルグ家は代々神聖ローマ皇帝の座を継承する名家となったのです。
ハプスブルグ家の栄華の源泉は、武力によるものではなく、ヨーロッパ王家や名家をぬい合わせるように婚姻関係を結ぶことにありました。
スペインとブルグント(ベネルクス三国とフランス・ブルゴーニュ地方周辺)とボヘミア=ハンガリーの王をハプスブルグ家の血縁者が席捲していた時代、「日没なき世界帝国」と謳われるほどの広大な領地は、婚姻関係を結んだ諸王家に不幸があり、その所領が次々にハプスブルグ家に転がり込んできたことで叶ったものです。
1516年に皇帝となったカール5世によって、広大な領土を分割統治するためにオーストリア系とスペイン系に分かれ、それぞれがヨーロッパ諸王家を背後から動かす政治力を保ち続けていました。
芸術を守護するハプスブルク家の帝王たち

現代の日本に住む私たちにとって、「ハプスブルク家」という言葉に抱くイメージは「帝王一族」という血なまぐさいものよりもまず、「洗練された美意識を持つトレンドリーダー」が先立つのではないでしょうか。
日本で開催される博物館や美術館の特別展のテーマでも、「ハプスブルク家の」で始まる企画物は、常に人気を博しています。
芸術の都ウィーンにある「ウィーン美術史美術館」は、世界三大美術館の一つです。
威厳ある佇まいを見せるマリアテレジア像を中心にした「マリアテレジア広場」の他に、「マリアテレジア」という名前は、ウィーンのあちらこちらで目にすることからも、今もなお民衆から敬愛されていることがうかがえるのですが、そもそもハプスブルグ家の血を引く代々の王たちは、絵画や建築、音楽や演劇にいたるまで、天性の芸術センスに溢れた人材を数多く輩出していました。
ハプスブルグ家といえば「バロック芸術」です。
ウィーン美術史美術館に足を踏み入れると、すでにその建物自体が美術品として完成されており、自分が美の中を浮遊している気分を味わえるのです。彫刻やレリーフ、フレスコ画など、豊かな富と美術センス、帝王の自信に満ち溢れたバロック芸術が堪能できます。
2017年は、マリア・テレジア生誕300年。ウィーンでは様々な祝賀行事や特別展が企画されており、なかでおおすすめなのが「シェーンブルン宮殿のマリア・テレジア ・ツアー」です。
マリア・テレジアの私室や執務室など、ファンにはたまらないスペシャルツアー、ぜひウィーン旅行の際にはチェックしてみてください。
日本で開催される博物館や美術館の特別展のテーマでも、「ハプスブルク家の」で始まる企画物は、常に人気を博しています。
芸術の都ウィーンにある「ウィーン美術史美術館」は、世界三大美術館の一つです。
威厳ある佇まいを見せるマリアテレジア像を中心にした「マリアテレジア広場」の他に、「マリアテレジア」という名前は、ウィーンのあちらこちらで目にすることからも、今もなお民衆から敬愛されていることがうかがえるのですが、そもそもハプスブルグ家の血を引く代々の王たちは、絵画や建築、音楽や演劇にいたるまで、天性の芸術センスに溢れた人材を数多く輩出していました。
ハプスブルグ家といえば「バロック芸術」です。
ウィーン美術史美術館に足を踏み入れると、すでにその建物自体が美術品として完成されており、自分が美の中を浮遊している気分を味わえるのです。彫刻やレリーフ、フレスコ画など、豊かな富と美術センス、帝王の自信に満ち溢れたバロック芸術が堪能できます。
2017年は、マリア・テレジア生誕300年。ウィーンでは様々な祝賀行事や特別展が企画されており、なかでおおすすめなのが「シェーンブルン宮殿のマリア・テレジア ・ツアー」です。
マリア・テレジアの私室や執務室など、ファンにはたまらないスペシャルツアー、ぜひウィーン旅行の際にはチェックしてみてください。
マリアテレジアの16人の子どもたちはどんな人?

オーストリア大公、ハンガリー女王、ボヘミア女王など様々な統治者を兼任し、それぞれの国民から深く愛された国母マリア・テレジアは、その政治的有能さの他にも、子だくさんとして有名です。先ほどもご紹介したとおり、16人の子どもを出産しました。(そのうち6人は幼いうちに亡くなっています。)9歳年上の夫・フランツ1世シュテファンとは彼女が6歳の時に出会い、その頃から初恋が芽生え、少女漫画そのもののラブストーリーを繰り広げた後、恋愛結婚を遂げます。夫婦仲は生涯良く、良妻賢母として夫を献身的に支えたそうです。
そんなマリア・テレジアの長男ヨーゼフ2世は、国の形を古びた中世のカトリック中心のスタイルから脱却し、プロテスタント出身といったよりバラエティに富んだ人材を確保し、来るべき近代化に即した国づくりを推進しました。有名なフランス王妃マリー・アントワネット以外にも、兄弟姉妹たちはヨーロッパ諸国王家と婚姻関係で結ばれ、ハプスブルグ家の安定と繁栄のための礎となったのです。
家庭円満も仕事もバリバリこなし、国民への優しさと労わりを忘れず、「夫大好き」を貫いたマリア・テレジアは、夫と死別して以降、彼を偲んでずっと喪服で過ごしたそうです。
そんな一途で愛情が濃やかな女性に、生まれながらの政治的決断力が備わっていたからこそ、国家のために身を粉にして働くことができたのではないでしょうか。
そんなマリア・テレジアの長男ヨーゼフ2世は、国の形を古びた中世のカトリック中心のスタイルから脱却し、プロテスタント出身といったよりバラエティに富んだ人材を確保し、来るべき近代化に即した国づくりを推進しました。有名なフランス王妃マリー・アントワネット以外にも、兄弟姉妹たちはヨーロッパ諸国王家と婚姻関係で結ばれ、ハプスブルグ家の安定と繁栄のための礎となったのです。
家庭円満も仕事もバリバリこなし、国民への優しさと労わりを忘れず、「夫大好き」を貫いたマリア・テレジアは、夫と死別して以降、彼を偲んでずっと喪服で過ごしたそうです。
そんな一途で愛情が濃やかな女性に、生まれながらの政治的決断力が備わっていたからこそ、国家のために身を粉にして働くことができたのではないでしょうか。







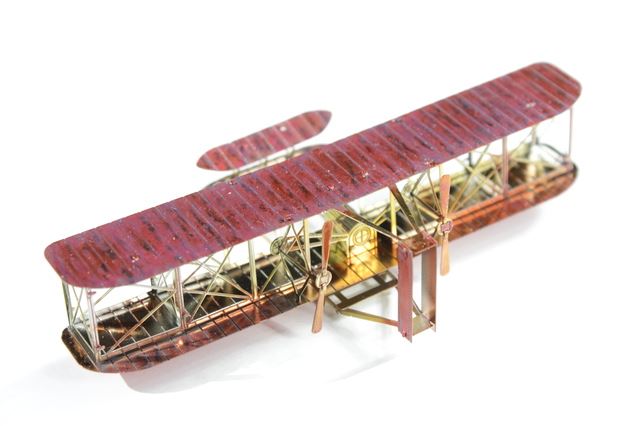













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

