北海道・千島列島および樺太とカムチャッカ半島で暮らしていた知られざるアイヌ民族の歴史とは
関連キーワード

近年、アイヌ民族の伝統文化や風習などが注目され、後世に伝えていこうという活動が北海道を中心に行われています。
しかしアイヌ民族の歴史や伝統的な文化、風習などは、特に本州に住む人にはあまり知られていないのではないでしょうか。今回は、そんなアイヌの歴史に触れていきたいと思います。
しかしアイヌ民族の歴史や伝統的な文化、風習などは、特に本州に住む人にはあまり知られていないのではないでしょうか。今回は、そんなアイヌの歴史に触れていきたいと思います。
「アイヌ」とはアイヌ語で“人間”
アイヌの文化が成立したのは13〜14世紀だという説が今のところ有力ですが、アイヌ民族は文字を持っていなかったため文献記録が乏しく、いまだ不明な点も多いそうです。しかしもともと北海道の広い範囲で浸透していた擦文(さつもん)文化と呼ばれる文化と、オホーツク海沿岸で広まっていたオホーツク文化とが融合して完成したのがアイヌ文化だと言われており、北海道や千島列島及び樺太島、カムチャッカ半島南部の先住民族の1つでした。
また、当時アイヌ民族は自由に貿易を行っていたことが近年明らかになってきています。実際に17世紀初頭のキリスト教宣教師の記録にもアイヌ民族との貿易により松前が繁栄していた様子が記されているほか、アイヌ民族が津軽海峡を渡って和人(日本列島に居住する民族)との貿易を行っていたこともあったそうです。
しかし1457年に和人とアイヌ民族との間で「コシャマインの戦い」が勃発すると、勝利した蠣崎氏を祖とする松前藩が貿易を独占することとなり、アイヌ民族は自由に貿易することができなくなってしまっただけでなく、交易品の価格も一方的に下げられてしまいました。続く1669年に生じた「シャクシャインの戦い」もアイヌ側の敗北に終わり、その後は多くのアイヌ民族たちが過酷な状況下で労働を強いられるようになったそうです。その後もさらに和人による支配は強まっていくこととなりますが、アイヌ民族の信仰や伝統文化は失われず維持されていました。
また、当時アイヌ民族は自由に貿易を行っていたことが近年明らかになってきています。実際に17世紀初頭のキリスト教宣教師の記録にもアイヌ民族との貿易により松前が繁栄していた様子が記されているほか、アイヌ民族が津軽海峡を渡って和人(日本列島に居住する民族)との貿易を行っていたこともあったそうです。
しかし1457年に和人とアイヌ民族との間で「コシャマインの戦い」が勃発すると、勝利した蠣崎氏を祖とする松前藩が貿易を独占することとなり、アイヌ民族は自由に貿易することができなくなってしまっただけでなく、交易品の価格も一方的に下げられてしまいました。続く1669年に生じた「シャクシャインの戦い」もアイヌ側の敗北に終わり、その後は多くのアイヌ民族たちが過酷な状況下で労働を強いられるようになったそうです。その後もさらに和人による支配は強まっていくこととなりますが、アイヌ民族の信仰や伝統文化は失われず維持されていました。
明治時代から今に至るまでのアイヌ文化
明治時代に入ると、蝦夷地は「北海道」の名に改称され、本格的に日本の領土として組み込まれていくこととなります。当時、明治政府による北海道の開拓が本格的に開始されると、和人たちが多く北海道に移り住むこととなりました。
アイヌ民族は政府に「平民」として戸籍を与えられることとなりましたが、実際には「土人」と呼ばれることもあり、区別されていたそうです。さらに伝統的なシカ猟やサケ漁も禁止されたほか、土地も優先的に和人に払い下げられるようになってしまい、アイヌ民族の生活は困窮の道を辿っていくこととなります。
このような状況を踏まえ、政府は1899年に「北海道旧土人保護法」を制定し、アイヌ民族に一定の農地を与えるように定めましたが、実際に彼らに与えられた土地は農業に適していなかったり、十分な農業指導が行われなかったりした例も多く、効果はなかったと言われています。
アイヌ民族は政府に「平民」として戸籍を与えられることとなりましたが、実際には「土人」と呼ばれることもあり、区別されていたそうです。さらに伝統的なシカ猟やサケ漁も禁止されたほか、土地も優先的に和人に払い下げられるようになってしまい、アイヌ民族の生活は困窮の道を辿っていくこととなります。
このような状況を踏まえ、政府は1899年に「北海道旧土人保護法」を制定し、アイヌ民族に一定の農地を与えるように定めましたが、実際に彼らに与えられた土地は農業に適していなかったり、十分な農業指導が行われなかったりした例も多く、効果はなかったと言われています。
北海道アイヌ協会の成立後、アイヌ文化振興法へ

1946年、アイヌの社会的地位の向上や文化の保存、伝承及び発展を図ることを目的とし、「北海道アイヌ協会」が成立しました。彼らを中心に「北海道旧土人保護法」の廃止と新しい法律の制定を求める運動が加速し、1997年にアイヌ文化振興法が制定されるとアイヌ文化振興と普及啓発に関わる様々な事業が行われるようになりました。
今でも北海道に行くと、アイヌ民族の文化に触れられる場所は多くあります。アイヌ民族の歴史に思いを馳せながら、ぜひいろいろな場所を回ってみてください。
今でも北海道に行くと、アイヌ民族の文化に触れられる場所は多くあります。アイヌ民族の歴史に思いを馳せながら、ぜひいろいろな場所を回ってみてください。






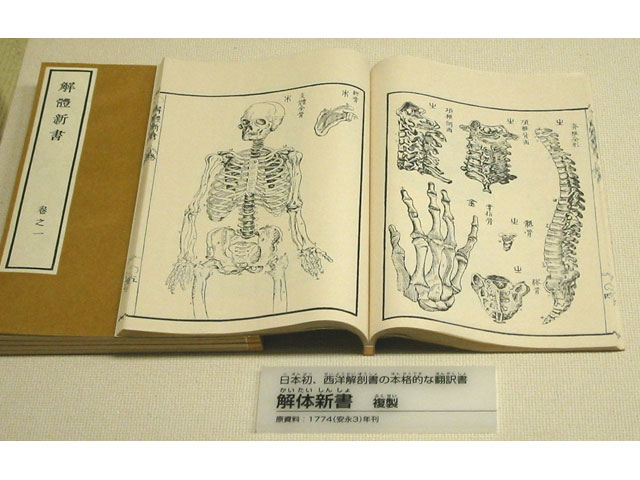
















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

