心配したって始まらない!明暦の大火で学んだ江戸の防火対策
関連キーワード

強い北西の風が砂塵を舞い上がらせていく、明暦3年1月18日(1657年3月2日)、本郷にある本妙寺から出火し江戸の町に突如として広がった炎の海は、瞬く間に町と人を飲み込みました。商家の屋根瓦や崩落した建物、荷車に積んだ家財道具や逃げ出した馬が、人々のゆく手を阻み、多くの避難民が負傷し炎と煙に巻かれて亡くなったと言います。
武家屋敷や寺院、吉原の遊郭や歌舞伎小屋などあらゆる建物を焼きながら、やがて炎は江戸城に燃え移ります。天守閣や本丸は巨大な火柱となり、真っ黒な煙が空を覆い隠しました。亡くなった人数は諸説ありますが3万人~10万人とも言われ、被害の大きさを物語っています。わずか二日間で江戸の町が焦土と化したこの火事を「明暦の大火」と呼び、日本史上最大の火災として人々に記憶されています。
武家屋敷や寺院、吉原の遊郭や歌舞伎小屋などあらゆる建物を焼きながら、やがて炎は江戸城に燃え移ります。天守閣や本丸は巨大な火柱となり、真っ黒な煙が空を覆い隠しました。亡くなった人数は諸説ありますが3万人~10万人とも言われ、被害の大きさを物語っています。わずか二日間で江戸の町が焦土と化したこの火事を「明暦の大火」と呼び、日本史上最大の火災として人々に記憶されています。

この明暦の大火の後、幕府はその反省と経験から改善すべき点を見つけ、江戸の町を再興していきます。市民たちもさまざまな工夫を凝らして火事に備えるようになりました。
幕府はまずは水桶の設置を指示します。雨水をためておく水溜桶や水を張った手桶を常備しておき、火災の際にはこの水で素早い初期消火に務めるよう御触れを出したのです。
また、炎が燃え広がるのを防ぐために、「火除け地」「広小路」が設けられました。これらは要するに空き地のことで、天守閣や本丸まで失った苦い経験を活かし、類焼を防ぐため市内だけではなく江戸城の周りにも通例的に設けられました。多い時で江戸には13か所もあったといわれ、「広小路」などの地名で今もその痕跡が残っています。ふだんは馬場などに利用されていたそうです。また人々が逃げる際に「車長持」という下に車輪の付いた長持(衣類や寝具などを収納する箱)で家財道具を運んだために渋滞が起き多くの命が失われたことを踏まえ、車長持の製造が禁止されました。
ほかにも、燃えにくい土や漆喰で家の壁を固める土蔵造りや瓦屋根が推奨されましたが、一般家屋ではそうそう贅沢されず、板葺きや板の壁が主流でした。それでも品物を扱う商家などはそれぞれ土蔵を作り売り物を炎から守る工夫をしています。
多くの避難民や死傷者が出た明暦の大火では、その後の支援や埋葬地の問題が出てきました。
粥を配給する「粥施行」や、亡くなった人の埋葬地と、念仏堂・庫裏の設営が行われ、幕府は災害の後処理の大切さを認識したようです。
しかし、災害による避難民を受け入れる施設「お救い小屋」の設置はまた大きな大火のあった文明(1806年)時代を待たなければいけませんでした。
幕府はまずは水桶の設置を指示します。雨水をためておく水溜桶や水を張った手桶を常備しておき、火災の際にはこの水で素早い初期消火に務めるよう御触れを出したのです。
また、炎が燃え広がるのを防ぐために、「火除け地」「広小路」が設けられました。これらは要するに空き地のことで、天守閣や本丸まで失った苦い経験を活かし、類焼を防ぐため市内だけではなく江戸城の周りにも通例的に設けられました。多い時で江戸には13か所もあったといわれ、「広小路」などの地名で今もその痕跡が残っています。ふだんは馬場などに利用されていたそうです。また人々が逃げる際に「車長持」という下に車輪の付いた長持(衣類や寝具などを収納する箱)で家財道具を運んだために渋滞が起き多くの命が失われたことを踏まえ、車長持の製造が禁止されました。
ほかにも、燃えにくい土や漆喰で家の壁を固める土蔵造りや瓦屋根が推奨されましたが、一般家屋ではそうそう贅沢されず、板葺きや板の壁が主流でした。それでも品物を扱う商家などはそれぞれ土蔵を作り売り物を炎から守る工夫をしています。
多くの避難民や死傷者が出た明暦の大火では、その後の支援や埋葬地の問題が出てきました。
粥を配給する「粥施行」や、亡くなった人の埋葬地と、念仏堂・庫裏の設営が行われ、幕府は災害の後処理の大切さを認識したようです。
しかし、災害による避難民を受け入れる施設「お救い小屋」の設置はまた大きな大火のあった文明(1806年)時代を待たなければいけませんでした。








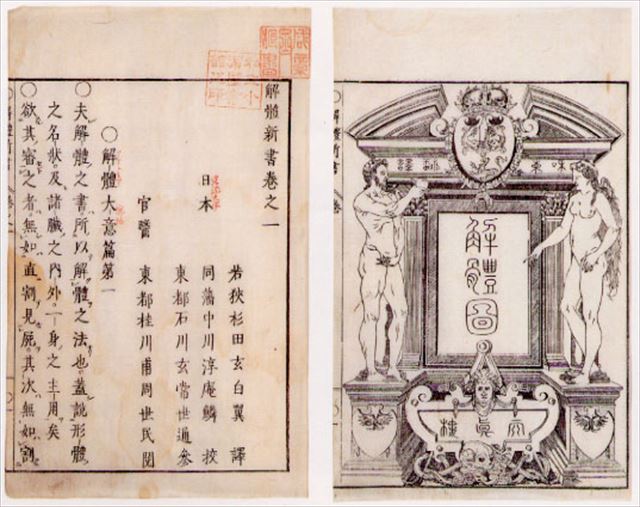













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

