鳥取県で伝統工芸に触れる 〜温かみが感じられる因州和紙〜
関連キーワード

因州和紙は、和紙としては日本で初めて経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定された鳥取県特産の伝統工芸品です。因州和紙のはっきりとした起源はわかっていませんが、その歴史は古く、日本で最古となる奈良時代のものも確認されているそうです。今回は、長い歴史を持つ伝統工芸品である因州和紙の魅力に迫っていきたいと思います。
画仙紙の生産量は日本一
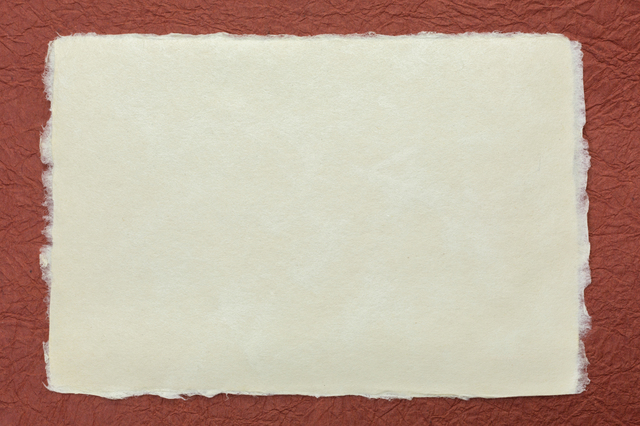
因州和紙の明確な起源は不明ですが、奈良時代の正倉院文書の中にあるものが現存する最古のものだとされています。その後、平安時代にまとめられた格式である「延喜式」には、因幡国(現在の鳥取県東部)から朝廷へと和紙が献上された記録が残っていることからも、因幡国がこのころ既に紙の産地として成り立っていたことがわかります。
江戸時代に入ると、因州和紙は藩の御用紙としてだけでなく、庶民が使う紙としても広く浸透していったと言われています。さらに明治時代には近代的な紙の漂白技術や、合理的な生産方式が導入されるようになり、因州和紙の生産量は飛躍的に増加しました。その勢いは大正末期まで続きましたが、戦後の生活様式の激変により、因州和紙も大打撃を受けることになります。
しかしその後、因州和紙は画仙紙等の書道用紙や工芸紙・染色紙の生産に力を注ぎ、その優れた紙質は高く評価されました。特に、丁寧に手で漉いた楮(こうぞ) 実際に因州和紙は書き心地が良く、他の和紙で1枚書くうちに2枚書けるうえ、墨の減りも少ないことから、「因州筆切れず」とも称されています。また。現在、因州和紙の画仙紙の生産量は全国の6〜7割程度を占めており、日本一となっています。
江戸時代に入ると、因州和紙は藩の御用紙としてだけでなく、庶民が使う紙としても広く浸透していったと言われています。さらに明治時代には近代的な紙の漂白技術や、合理的な生産方式が導入されるようになり、因州和紙の生産量は飛躍的に増加しました。その勢いは大正末期まで続きましたが、戦後の生活様式の激変により、因州和紙も大打撃を受けることになります。
しかしその後、因州和紙は画仙紙等の書道用紙や工芸紙・染色紙の生産に力を注ぎ、その優れた紙質は高く評価されました。特に、丁寧に手で漉いた楮(こうぞ) 実際に因州和紙は書き心地が良く、他の和紙で1枚書くうちに2枚書けるうえ、墨の減りも少ないことから、「因州筆切れず」とも称されています。また。現在、因州和紙の画仙紙の生産量は全国の6〜7割程度を占めており、日本一となっています。
日本の音風景100選に選ばれている紙漉き
現在、因州和紙は鳥取市佐治町と、同じく鳥取市の青谷町の2か所で生産されています。また、因州和紙の紙漉きは、1996年に「日本の音風景100選」に選ばれました。紙漉きの製造現場における、水に溶かした繊維を漉きあげる際の「チャポン、チャポン」とした音が、「伝統的な地場産業の音で、生活とのかかわりが深い」との評価を得たそうです。
「鳥取市あおや和紙工房」で紙すき体験
因州和紙の生産地である鳥取市青谷町にある「鳥取市あおや和紙工房」では、伝統的な紙すきの体験が常時可能です。工房では体験教室だけでなく、因州和紙の過去と未来を覗ける常設展示室やカフェ、ミュージアムショップも併設されているので、ぜひ足を運んでみてください。
鳥取市あおや和紙工房
住所:鳥取県鳥取市青谷町山根313
電話:0857-86-6060
開館時間:9:00〜17:00(体験受付は16:00まで)
休館日:月曜日(月曜が祝祭日の場合は、翌平日)、年末年始(12/29〜1/3)
入館料:常設展は無料。企画展観覧料は一般100円〜300円、小・中・高校生50円〜150円
公式HP:http://www.tbz.or.jp/aoya-washi/
「鳥取市あおや和紙工房」で紙すき体験
因州和紙の生産地である鳥取市青谷町にある「鳥取市あおや和紙工房」では、伝統的な紙すきの体験が常時可能です。工房では体験教室だけでなく、因州和紙の過去と未来を覗ける常設展示室やカフェ、ミュージアムショップも併設されているので、ぜひ足を運んでみてください。
鳥取市あおや和紙工房
住所:鳥取県鳥取市青谷町山根313
電話:0857-86-6060
開館時間:9:00〜17:00(体験受付は16:00まで)
休館日:月曜日(月曜が祝祭日の場合は、翌平日)、年末年始(12/29〜1/3)
入館料:常設展は無料。企画展観覧料は一般100円〜300円、小・中・高校生50円〜150円
公式HP:http://www.tbz.or.jp/aoya-washi/





















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

