コンポストの作り方と注意点は?
関連キーワード

コンポストを作ってみたいと思っている人もいるでしょう。ただ、面倒だという思いや作り方がよくわからないという風に思っている人も多いでしょう。
コンポストの作り方と注意点について詳しくご紹介します。
コンポストの作り方と注意点について詳しくご紹介します。
コンポストとは?
生ごみなどをコンポストで肥料に変えることができるということで、コンポストに興味がある人もいるでしょう。コンポストとは、生ごみなどの有機物を微生物の働きによって分解して肥料を作ることです。
そのための環境を人為的に作ってあげることで、短時間に肥料を作ることができます。自然界でゆっくり分解されることをコンポストで行う仕組みです。
そのための環境を人為的に作ってあげることで、短時間に肥料を作ることができます。自然界でゆっくり分解されることをコンポストで行う仕組みです。
コンポストのデメリットと作るための考え方とは
ただ、コンポストにもデメリットがいろいろありますので、まずそれをきちんと知った上で、やはり作りたいと思った場合に作るようにするのがおすすめです。
コンポストのデメリットには、まず、肥料にするにはやはりある程度の時間がかかるということで、2か月~半年以上かかります。そして毎日の手間がかかる、臭いが発生する、防虫対策をしないと虫が湧いてくるなどの様々なことがあります。どれも大変でやっかいなことですので、デメリットを覚悟した上で行いましょう。
家庭菜園をやりたいや環境のために生ごみを自分で処理したいなど、しっかりとした考え方を持って、手間を惜しまない人はやってみるといいでしょう。
コンポストのデメリットには、まず、肥料にするにはやはりある程度の時間がかかるということで、2か月~半年以上かかります。そして毎日の手間がかかる、臭いが発生する、防虫対策をしないと虫が湧いてくるなどの様々なことがあります。どれも大変でやっかいなことですので、デメリットを覚悟した上で行いましょう。
家庭菜園をやりたいや環境のために生ごみを自分で処理したいなど、しっかりとした考え方を持って、手間を惜しまない人はやってみるといいでしょう。
コンポストの具体的な作り方は?

作り方としては、4つの方法があります。段ボール式、土中式、密閉式、ミミズ式などです。ベランダで作るには庭に置かなくてもいい、段ボール式や密閉式がおすすめです。
まず、段ボール式は、段ボールの中でかき混ぜることができ、あまり臭いもしなくて済むのがいい点です。防虫ネットも付いているものが通販でも売られています。ビートモスと籾殻くんたんを使い、生ごみを入れるたびにかき混ぜます。温度も10度以下にならないように管理する必要がありますので手間はかかります。
土中式は、庭がある人向けで、プラスチックの容器をそのまま土に埋めます。枯れ葉や枯れ草を使いますので、それを処理したい人などには向いているでしょう。発酵に3か月ほど時間がかかりますが、ぼかしや米ぬか、発酵剤を入れることで発酵を早めることもできます。週に1回程度かき混ぜればいいことや温度管理が必要ないのがいい点です。庭があって、ゆっくり肥料を作る人には向いています。
密閉式は、ぼかしまたは米ぬかを入れて、密閉することで発酵を早く進め2週間程度で肥料を作ることができます。ただ、その過程で酸っぱい臭いがしてきます。混ぜたり、温度管理の必要がなかったりするのはいい点ですが、臭いには気を付けましょう。特にベランダでは臭い対策が必要かもしれません。
最後にミミズ式は、ミミズが苦手な人にはできないものです。屋外でミミズを段ボール式コンポストに入れて、ミミズに生ごみを食べてもらって、肥料にする方法です。ココナッツ繊維を湿らせて敷き、牛糞堆肥かピートモス、おがくず、新聞紙などを混ぜ、たくさんのミミズを準備します。かき混ぜたりする必要はなく温度を10度~25度に保つだけですので、便利です。3~4か月と長くかかりますが、ミミズの管理をしながら待っているだけでできます。
まず、段ボール式は、段ボールの中でかき混ぜることができ、あまり臭いもしなくて済むのがいい点です。防虫ネットも付いているものが通販でも売られています。ビートモスと籾殻くんたんを使い、生ごみを入れるたびにかき混ぜます。温度も10度以下にならないように管理する必要がありますので手間はかかります。
土中式は、庭がある人向けで、プラスチックの容器をそのまま土に埋めます。枯れ葉や枯れ草を使いますので、それを処理したい人などには向いているでしょう。発酵に3か月ほど時間がかかりますが、ぼかしや米ぬか、発酵剤を入れることで発酵を早めることもできます。週に1回程度かき混ぜればいいことや温度管理が必要ないのがいい点です。庭があって、ゆっくり肥料を作る人には向いています。
密閉式は、ぼかしまたは米ぬかを入れて、密閉することで発酵を早く進め2週間程度で肥料を作ることができます。ただ、その過程で酸っぱい臭いがしてきます。混ぜたり、温度管理の必要がなかったりするのはいい点ですが、臭いには気を付けましょう。特にベランダでは臭い対策が必要かもしれません。
最後にミミズ式は、ミミズが苦手な人にはできないものです。屋外でミミズを段ボール式コンポストに入れて、ミミズに生ごみを食べてもらって、肥料にする方法です。ココナッツ繊維を湿らせて敷き、牛糞堆肥かピートモス、おがくず、新聞紙などを混ぜ、たくさんのミミズを準備します。かき混ぜたりする必要はなく温度を10度~25度に保つだけですので、便利です。3~4か月と長くかかりますが、ミミズの管理をしながら待っているだけでできます。
コンポストを作る際の注意点
コンポストの4つの方法には、それぞれに大変さもあります。そして、それぞれに共通した注意点もありますので、ご紹介します。
まず、水分量です。生ごみを肥料に変えるのですが、生ごみの水分量が多すぎると、肥料になる前に、カビや腐敗になってしまいます。水が多すぎることで、空気に触れずに腐敗に繋がります。生ごみのまず水を切ることが大切なことです。
直射日光には注意をしましょう。発酵の際に、微生物が活躍しますが、直射日光で死んでしまうと肥料も作れなくなります。あまり暑くならないように夏はシートなどを被せて暑さ対策をしましょう。また、乾燥しすぎるのもよくありませんので、夏の暑さには気を付けるのが注意点です。
まず、水分量です。生ごみを肥料に変えるのですが、生ごみの水分量が多すぎると、肥料になる前に、カビや腐敗になってしまいます。水が多すぎることで、空気に触れずに腐敗に繋がります。生ごみのまず水を切ることが大切なことです。
直射日光には注意をしましょう。発酵の際に、微生物が活躍しますが、直射日光で死んでしまうと肥料も作れなくなります。あまり暑くならないように夏はシートなどを被せて暑さ対策をしましょう。また、乾燥しすぎるのもよくありませんので、夏の暑さには気を付けるのが注意点です。
虫対策はどうする?
コンポストの場合には、虫対策も重要です。生ごみで虫が発生したらとても嫌なことですよね。虫が発生しないためには、土をしっかり生ごみに被せておくことが大切です。生ごみを追加するごとに、土を被せることを忘れないようにしましょう。うじが発生したりしたら最悪なことになります。
虫対策としては、生ごみを入れる時は一度にたくさんは入れないこと、土の中に埋められる量にし、全部中に入れてしまうこと、また、虫が卵を産まないように細かな編み目のネットで覆ってしまうのもいい方法です。
虫対策としては、生ごみを入れる時は一度にたくさんは入れないこと、土の中に埋められる量にし、全部中に入れてしまうこと、また、虫が卵を産まないように細かな編み目のネットで覆ってしまうのもいい方法です。
コンポストの作り方と注意点をしっかり守って

コンポストの作り方と注意点をご紹介しました。作り方はそれぞれに特徴があって、どれがいいかを場所やお好みで決めるといいでしょう。ただ、どれも簡単にすぐに作れるわけではありません。作る際には、ポリシーを持って、家庭菜園に使うなど使い道を考えて始めることが大切です。
そして、注意点をしっかり守って、臭い対策や虫対策も気を付けましょう。これらのことができて世話もできるようでしたら、始めてみるといいでしょう。
そして、注意点をしっかり守って、臭い対策や虫対策も気を付けましょう。これらのことができて世話もできるようでしたら、始めてみるといいでしょう。







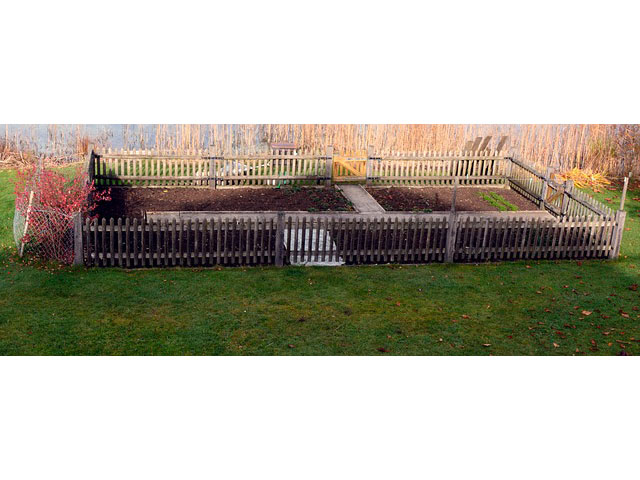















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

