初心者でも作れる山もみじの盆栽
関連キーワード

山もみじの盆栽は、秋の紅葉が素晴らしい盆栽です。秋になると小さな盆栽鉢の中で葉の色が毎日鮮やかに変化し、美しい紅葉を楽しませてくれます。同じ山もみじの紅葉でも、葉が濃い色や薄い色の部分が点在し、様々な色が盆栽鉢の中で彩っています。
山もみじは比較的夏や冬の気候にも強いので、盆栽初心者でも管理がしやすい樹木です。また、園芸店などでは山もみじの苗木だけでなく、盆栽仕立てに必要な鉢なども一緒に購入することができるので盆栽初心者でも意外と簡単に盆栽に仕立てることができるので、自分で作った山もみじの盆栽で秋の紅葉を楽しむことができます。
山もみじは比較的夏や冬の気候にも強いので、盆栽初心者でも管理がしやすい樹木です。また、園芸店などでは山もみじの苗木だけでなく、盆栽仕立てに必要な鉢なども一緒に購入することができるので盆栽初心者でも意外と簡単に盆栽に仕立てることができるので、自分で作った山もみじの盆栽で秋の紅葉を楽しむことができます。
山もみじの盆栽づくりには何が必要?
山もみじの盆栽作り必要な主なものは、山もみじの苗木、鉢、盆栽用の針金とやっとこ、鉢穴用防虫ネット、盆栽用の用土、苔、洗いおけ、ピンセット、剪定はさみ、ジョウーロなどです。
山もみじの苗木を選ぶ際のポイントとして、盆栽鉢に植える時の苗木の正面や作りたい盆栽の大きさをイメージしながら苗木を見つけることが大事です。また、山もみじは自然の山に自生しているので盆栽に仕立てた場合、盆栽鉢の中で山に自生している自然の風景が再現しやすいような苗木を選ぶことも大事です。
山もみじの苗木を選ぶ際のポイントとして、盆栽鉢に植える時の苗木の正面や作りたい盆栽の大きさをイメージしながら苗木を見つけることが大事です。また、山もみじは自然の山に自生しているので盆栽に仕立てた場合、盆栽鉢の中で山に自生している自然の風景が再現しやすいような苗木を選ぶことも大事です。
山もみじの盆栽の作り方
山もみじの盆栽を作る場合、盆栽仕立てにする苗木の正面を決めることから始めます。そして、苗木をポットから盆栽鉢に移し替えて、季節にあった管理をしながら、山もみじの苗木を盆栽に仕立てて行きます。
‐山もみじの盆栽の正面の決め方
山もみじの苗木をポットから盆栽鉢に植え替える際は、最初に苗木を盆栽鉢の上に置いて正面を決めることが盆栽つくりの第一歩です。
正面の決め方として、ポットから移した山もみじの苗木を盆栽鉢の上に置き、真上から、次に真横から一周して観ながら幹の立ち上がり、根張り、樹木の幹模様、枝ぶりや樹形が全体的に一番良く見えるところが正面になります。その反対側は裏面になります。盆栽の裏面は、奥行きがあり枝ぶりが良い状態になるように作ります。
しかしながら、山もみじの苗木を盆栽鉢に移し替えをした時、すぐに正面を決めることが出来なくても大丈夫です。また、なかなか気に入った山もみじの樹木の正面が見つからない場合でも、数年かけて自分の好みに仕立てていく過程で、根張り、枝ぶり、幹模様や樹形全体のバランスをみながら正面を決めることも出来るので、急いで決める必要はないです。数年かけて正面を決めることも一つの選択です。
‐山もみじの盆栽づくりの手順
最初に、買ってきた山もみじの苗木をポットから抜き出します。その際、根や幹を傷めないように注意しながら抜きます。土が硬くて抜きにくい場合は、ポットの周りや底を押すと、抜けやすくなります。軽く叩いても良いですが、枝や幹を傷めないように注意が必要です。
ポットから抜き出した苗木は根が詰まっていたり、絡まっていたりしている場合が多いので、根を傷めないように根の周りに付いている土を取り除きます。山もみじの根は細くて繊細なので丁寧にほぐしていかないと、根を痛めたり切ったりしてしまいます。ある程度、ポットに入っていた古い土を取り除いたら、大きめの洗い桶に水を入れて、山もみじの根についている残りの土を丁寧に取り除きます。苗木の根をほどく時に根かき専門の道具を使用することもできますが、苗木の根はできるだけ手で丁寧にほぐしながら古い土を取り、最後にきれいな水で洗い流していくと、根を傷めることが少ないので無難です。根かきの道具は慣れていないと、根を切ったり痛めたりしてしまいます。
次に、鉢底の穴に防虫ネットを置いて針金を使って取り付けます。全体の1/3位の盆栽用土を入れます。その用土の上に山もみじの苗木をのせて、残りの用土をかけ、土を湿らす程度に水をかけ、最後に苔をのせます。苔は小さくパッチワークのように小さく切ってのせるのではなく、できるだけ鉢上全体を1枚の大きさでかぶせることができるサイズの苔を用意することがポイントです。
また、深鉢ではなく浅い盆栽鉢の場合は、用土を入れる前に鉢底の穴から針金を通して苗木を固定することにより、樹木が安定して根つきも良くなります。初めての場合は、針金での樹木の固定は難しいですが、周りの枝や幹を傷めないように注意をしながら行います。最初に樹木を針金でしっかりと固定すると、用土をいれてもぐらつきがないです。
‐盆栽に仕立てた後の管理
盆栽鉢に植えた山もみじの剪定は、梅雨と秋の落葉後に行うことができます。剪定の手順として、新芽を残しながら幹から出た枝の2~3節目ぐらいを残して剪定します。また、枝の先端が2つにわかれている枝は、片方を切り落として整枝し、不揃いな細かい枝も揃えたり整えたりすることで、4月頃からでる新芽もきれいに出揃い、葉の大きさも同じように揃うので、樹形が整った美しい盆栽に仕立てることができます。
山もみじの植替えは根張りの状態にもよりますが、2~3年に一度の植替えで大丈夫です。
山もみじは、育てやすい樹種ですが、害虫の影響を受けやすいです。春の新芽が出た頃から秋の紅葉時期までは、特に注意が必要です。新芽が出る4月頃から11月頃までは、アブラムシやシンクイムシがつきやすいです。シンクイムシは、幹の中に入り込んで穴をあけてしまうので、山もみじを枯らしてしまう恐れがあります。見つけたら、ノズルの長い殺虫剤を穴の中に入れて、虫を退治します。また、夏の終わりから秋の初めはうどんこ病にかかりやすいので、予防薬の散布をします。
山もみじの盆栽は、出来るだけ陽当たりや風通しが良い屋外に置いて、育てると良いです。夏の時期は、強い日差しによって山もみじの葉が日焼けしやすいので、半日陰で風通しの良い所に置きます。この時期に葉が日焼けをしてしまうと、葉先が枯れて丸まってしまい、美しい秋の紅葉を期待することが難しくなってしまいます。
冬の時期は、寒い強風や霜が当たらない軒下に置き、日中は暖かい陽射しが当たる場所に置くことが良いですが、夕方になったら軒下に戻すことも忘れずに行います。
山もみじは自然の山に原生している植物なので、水を必要とします。水やりをする際は、鉢底から水が流れ出るまで与えます。鉢の表面に苔を敷き詰めてある山もみじの盆栽は、苔が乾いたら水を与えるように心がけることが大事です。苔によっては水を弾いてしまい、土の中に水が行き渡らないこともあるので、必ず鉢穴から水が出てくるまで水を与えます。新芽が出る春と紅葉が始まる秋は、1日1~2回位、冬は3日1回位、夏は朝夕の2回位が水やりと葉水を与えます。
施肥の時期は、新芽が出る4月から7月まで、夏の暑い時期はお休みして9月になったら月に1回位のペースで固形タイプの有機肥料を与えます。しかしながら、9月の終りから10月の中旬ごろに山もみじの紅葉が始まったら、置いてある固形肥料は取り除きます。紅葉を楽しむ間は、固形肥料は美観を損なうので鉢の根元もきれいにして、鑑賞します。
‐山もみじの盆栽の正面の決め方
山もみじの苗木をポットから盆栽鉢に植え替える際は、最初に苗木を盆栽鉢の上に置いて正面を決めることが盆栽つくりの第一歩です。
正面の決め方として、ポットから移した山もみじの苗木を盆栽鉢の上に置き、真上から、次に真横から一周して観ながら幹の立ち上がり、根張り、樹木の幹模様、枝ぶりや樹形が全体的に一番良く見えるところが正面になります。その反対側は裏面になります。盆栽の裏面は、奥行きがあり枝ぶりが良い状態になるように作ります。
しかしながら、山もみじの苗木を盆栽鉢に移し替えをした時、すぐに正面を決めることが出来なくても大丈夫です。また、なかなか気に入った山もみじの樹木の正面が見つからない場合でも、数年かけて自分の好みに仕立てていく過程で、根張り、枝ぶり、幹模様や樹形全体のバランスをみながら正面を決めることも出来るので、急いで決める必要はないです。数年かけて正面を決めることも一つの選択です。
‐山もみじの盆栽づくりの手順
最初に、買ってきた山もみじの苗木をポットから抜き出します。その際、根や幹を傷めないように注意しながら抜きます。土が硬くて抜きにくい場合は、ポットの周りや底を押すと、抜けやすくなります。軽く叩いても良いですが、枝や幹を傷めないように注意が必要です。
ポットから抜き出した苗木は根が詰まっていたり、絡まっていたりしている場合が多いので、根を傷めないように根の周りに付いている土を取り除きます。山もみじの根は細くて繊細なので丁寧にほぐしていかないと、根を痛めたり切ったりしてしまいます。ある程度、ポットに入っていた古い土を取り除いたら、大きめの洗い桶に水を入れて、山もみじの根についている残りの土を丁寧に取り除きます。苗木の根をほどく時に根かき専門の道具を使用することもできますが、苗木の根はできるだけ手で丁寧にほぐしながら古い土を取り、最後にきれいな水で洗い流していくと、根を傷めることが少ないので無難です。根かきの道具は慣れていないと、根を切ったり痛めたりしてしまいます。
次に、鉢底の穴に防虫ネットを置いて針金を使って取り付けます。全体の1/3位の盆栽用土を入れます。その用土の上に山もみじの苗木をのせて、残りの用土をかけ、土を湿らす程度に水をかけ、最後に苔をのせます。苔は小さくパッチワークのように小さく切ってのせるのではなく、できるだけ鉢上全体を1枚の大きさでかぶせることができるサイズの苔を用意することがポイントです。
また、深鉢ではなく浅い盆栽鉢の場合は、用土を入れる前に鉢底の穴から針金を通して苗木を固定することにより、樹木が安定して根つきも良くなります。初めての場合は、針金での樹木の固定は難しいですが、周りの枝や幹を傷めないように注意をしながら行います。最初に樹木を針金でしっかりと固定すると、用土をいれてもぐらつきがないです。
‐盆栽に仕立てた後の管理
盆栽鉢に植えた山もみじの剪定は、梅雨と秋の落葉後に行うことができます。剪定の手順として、新芽を残しながら幹から出た枝の2~3節目ぐらいを残して剪定します。また、枝の先端が2つにわかれている枝は、片方を切り落として整枝し、不揃いな細かい枝も揃えたり整えたりすることで、4月頃からでる新芽もきれいに出揃い、葉の大きさも同じように揃うので、樹形が整った美しい盆栽に仕立てることができます。
山もみじの植替えは根張りの状態にもよりますが、2~3年に一度の植替えで大丈夫です。
山もみじは、育てやすい樹種ですが、害虫の影響を受けやすいです。春の新芽が出た頃から秋の紅葉時期までは、特に注意が必要です。新芽が出る4月頃から11月頃までは、アブラムシやシンクイムシがつきやすいです。シンクイムシは、幹の中に入り込んで穴をあけてしまうので、山もみじを枯らしてしまう恐れがあります。見つけたら、ノズルの長い殺虫剤を穴の中に入れて、虫を退治します。また、夏の終わりから秋の初めはうどんこ病にかかりやすいので、予防薬の散布をします。
山もみじの盆栽は、出来るだけ陽当たりや風通しが良い屋外に置いて、育てると良いです。夏の時期は、強い日差しによって山もみじの葉が日焼けしやすいので、半日陰で風通しの良い所に置きます。この時期に葉が日焼けをしてしまうと、葉先が枯れて丸まってしまい、美しい秋の紅葉を期待することが難しくなってしまいます。
冬の時期は、寒い強風や霜が当たらない軒下に置き、日中は暖かい陽射しが当たる場所に置くことが良いですが、夕方になったら軒下に戻すことも忘れずに行います。
山もみじは自然の山に原生している植物なので、水を必要とします。水やりをする際は、鉢底から水が流れ出るまで与えます。鉢の表面に苔を敷き詰めてある山もみじの盆栽は、苔が乾いたら水を与えるように心がけることが大事です。苔によっては水を弾いてしまい、土の中に水が行き渡らないこともあるので、必ず鉢穴から水が出てくるまで水を与えます。新芽が出る春と紅葉が始まる秋は、1日1~2回位、冬は3日1回位、夏は朝夕の2回位が水やりと葉水を与えます。
施肥の時期は、新芽が出る4月から7月まで、夏の暑い時期はお休みして9月になったら月に1回位のペースで固形タイプの有機肥料を与えます。しかしながら、9月の終りから10月の中旬ごろに山もみじの紅葉が始まったら、置いてある固形肥料は取り除きます。紅葉を楽しむ間は、固形肥料は美観を損なうので鉢の根元もきれいにして、鑑賞します。
まとめ
山もみじの盆栽は、秋の紅葉だけでなく、一年を通して日本の四季折々の美しさを見せてくれます。山もみじは童謡の歌詞にもなっているので、山もみじの盆栽を鑑賞していると、その童謡の歌詞も秋の里山の風景と一緒に思い出されます。
1本の山もみじの苗木を盆栽鉢に植えることも良いですが、数本の苗木を寄せ植えにした山もみじが盆栽に仕立て上がると、里山の美しい秋の紅葉が思い出される盆栽になります。
1本の山もみじの苗木を盆栽鉢に植えることも良いですが、数本の苗木を寄せ植えにした山もみじが盆栽に仕立て上がると、里山の美しい秋の紅葉が思い出される盆栽になります。






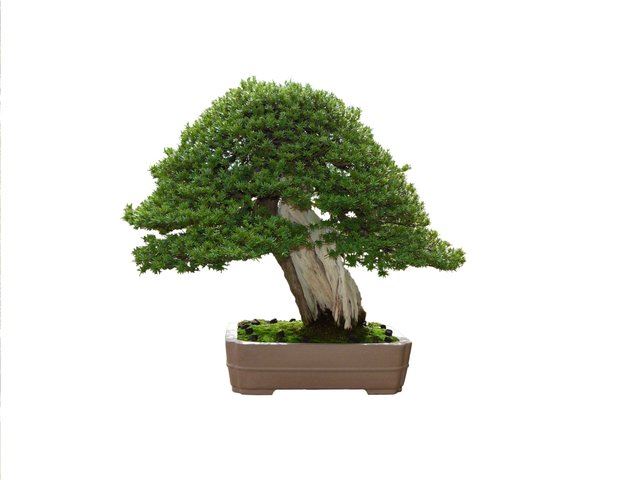
















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

