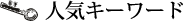イタリア「ミケランジェロ」は万能の人! ダ・ヴィンチと並ぶ天才の孤独とは
関連キーワード

「ミケランジェロ」と言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチと一緒に名前の挙がる、西洋美術史に特筆すべき異能の芸術家です。
あまたの芸術家を生み出したルネサンス期を代表する「万能の人」ミケランジェロですが、レオナルド・ダ・ヴィンチのイメージが放つキラキラした開放感や面白さに比べ、芸術がそれほど得意ではない人々の間では「何を考えているかよくわからない、気難しそうな芸術家」といった思い込みがあるかもしれません。
「神から愛された男 (Il Divino)」と呼ばれたミケランジェロは、生前からすでに有名で影響力の強い芸術家でした。そして、同時代を生きた人々によってリアルタイムで伝記(芸術家でもあったジョルジョ=ヴァザーリによる『画家・彫刻家・建築家列伝』)が書かれるほど、その言動は日々大きく注目されていたのです。
詩人としても名を馳せていたミケランジェロが残した言葉の中から、彼の生き方を端的に表現したような名言をひとつご紹介します。
「Beauty is the purgation of superfluities.」
“美とは、余分なものの浄化である。”
「万能の人」といえども、ミケランジェロのもっとも得意とする分野は「彫刻」でした。巨大な白亜の大理石を見つめながらイメージを膨らませ、大理石の中に閉じ込められて眠っている姿を救出するような思いで鑿を振り上げ、精巧で美しいピエタ像やダヴィデ像を生み出した彼らしい名言ではないでしょうか。余計なものでライフスタイルを飾り立ててしまう現代の私たちにとって、耳の痛い言葉でもあります。
さらにもうひとつ、名言をご紹介します。
「Genius is eternal patience.」
“天才とは永遠の忍耐である。”
ミケランジェロとは、同時代の芸術家からも変人扱いされるほどのストイックな仕事人間でした。自分を自由に表現できる仕事をする時間以外には執着のない彼にとって、仕事とは最大の喜びであり、かつ没頭しすぎるあまり肉体を酷使してしまう恐れを常に伴っていたため、与えられた才能を支えるための自主的な苦労を我慢する精神力が必要だったのです。さらに、生きているだけで嫉妬され、普通の人々からいわれのない差別を受けるのもまた我慢しなければいけません。
「天才とは、1%のひらめきと99%の努力」という言葉をトーマス・エジソンも残しています。
神から与えられた豊かな才能を支えるため、永遠に努力と我慢ができる人が、天才なのかもしれません。
あまたの芸術家を生み出したルネサンス期を代表する「万能の人」ミケランジェロですが、レオナルド・ダ・ヴィンチのイメージが放つキラキラした開放感や面白さに比べ、芸術がそれほど得意ではない人々の間では「何を考えているかよくわからない、気難しそうな芸術家」といった思い込みがあるかもしれません。
「神から愛された男 (Il Divino)」と呼ばれたミケランジェロは、生前からすでに有名で影響力の強い芸術家でした。そして、同時代を生きた人々によってリアルタイムで伝記(芸術家でもあったジョルジョ=ヴァザーリによる『画家・彫刻家・建築家列伝』)が書かれるほど、その言動は日々大きく注目されていたのです。
詩人としても名を馳せていたミケランジェロが残した言葉の中から、彼の生き方を端的に表現したような名言をひとつご紹介します。
「Beauty is the purgation of superfluities.」
“美とは、余分なものの浄化である。”
「万能の人」といえども、ミケランジェロのもっとも得意とする分野は「彫刻」でした。巨大な白亜の大理石を見つめながらイメージを膨らませ、大理石の中に閉じ込められて眠っている姿を救出するような思いで鑿を振り上げ、精巧で美しいピエタ像やダヴィデ像を生み出した彼らしい名言ではないでしょうか。余計なものでライフスタイルを飾り立ててしまう現代の私たちにとって、耳の痛い言葉でもあります。
さらにもうひとつ、名言をご紹介します。
「Genius is eternal patience.」
“天才とは永遠の忍耐である。”
ミケランジェロとは、同時代の芸術家からも変人扱いされるほどのストイックな仕事人間でした。自分を自由に表現できる仕事をする時間以外には執着のない彼にとって、仕事とは最大の喜びであり、かつ没頭しすぎるあまり肉体を酷使してしまう恐れを常に伴っていたため、与えられた才能を支えるための自主的な苦労を我慢する精神力が必要だったのです。さらに、生きているだけで嫉妬され、普通の人々からいわれのない差別を受けるのもまた我慢しなければいけません。
「天才とは、1%のひらめきと99%の努力」という言葉をトーマス・エジソンも残しています。
神から与えられた豊かな才能を支えるため、永遠に努力と我慢ができる人が、天才なのかもしれません。
「万能の人」はどうやって作られた?メディチ家の富と文化
1745年にイタリアのカプレーゼで生まれたミケランジェロは、13歳でフィレンツェにて画家見習いになりました。当時フィレンツェで最も有名な画家のひとりであったギルランダイオの工房で腕を磨いた彼は、15歳の時、その煌くような天賦の才をロレンツォ・デ・メディチに見出されたのです。
イスラム世界とヨーロッパ世界を繋ぐ玄関口であったイタリアで、世界に散逸していた古代ギリシア・ローマの美術品を収集し、ルネサンスを花開かせる原動力となった大富豪・メディチ家の庭には、その彫刻たちが所狭しと並んでいたようです。
多くの才能ある少年たちと一緒に、ミケランジェロは古代ギリシア・ローマの美術品をお手本に、来る日も来る日も大理石を刻んで、彫刻の修行をしていました。そして1498?1499年、ローマでピエタ像をつくり、それが大評判となりました。
メディチ家が没落した後もミケランジェロへの依頼は引きもきらず、1504年にはダヴィデ像を、1508~1512年には教皇ユリウス二世の命を受け、4年がけでシスティーナ礼拝堂の大天井画を描きました。
1564年にローマで89歳という長命で亡くなるまで、絵画、彫刻、建築、詩他、数多くの芸術を残し、後世にその巨大な足跡を残したのです。
メディチ家が古代ギリシア・ローマの美術品を、その豊富な財力と交易力で収集しなければ、ミケランジェロの天才性は磨かれなかったことでしょう。
イスラム世界とヨーロッパ世界を繋ぐ玄関口であったイタリアで、世界に散逸していた古代ギリシア・ローマの美術品を収集し、ルネサンスを花開かせる原動力となった大富豪・メディチ家の庭には、その彫刻たちが所狭しと並んでいたようです。
多くの才能ある少年たちと一緒に、ミケランジェロは古代ギリシア・ローマの美術品をお手本に、来る日も来る日も大理石を刻んで、彫刻の修行をしていました。そして1498?1499年、ローマでピエタ像をつくり、それが大評判となりました。
メディチ家が没落した後もミケランジェロへの依頼は引きもきらず、1504年にはダヴィデ像を、1508~1512年には教皇ユリウス二世の命を受け、4年がけでシスティーナ礼拝堂の大天井画を描きました。
1564年にローマで89歳という長命で亡くなるまで、絵画、彫刻、建築、詩他、数多くの芸術を残し、後世にその巨大な足跡を残したのです。
メディチ家が古代ギリシア・ローマの美術品を、その豊富な財力と交易力で収集しなければ、ミケランジェロの天才性は磨かれなかったことでしょう。
絵画を彫刻のように掘り起こすのがミケランジェロ
彫刻とは、作品に宿る陰影と素材の重みを鑑賞して楽しむ芸術でもあります。
現代はインターネットや写真集などで簡単にその写真をチェックすることができるとしても、やはり実物をみなければ、ミケランジェロが侵食を忘れて削った鑿の痕跡、そして自らを限界まで追い込んで作り上げた光と影の美しさを味わうことはできません。
ミケランジェロの美しい絵画は「クロスハッチング」と呼ばれる、細かな斜線をいくつもクロス(交差)させて構築していく立体的な描き方が特徴です。石の中から像を削りだすがごとく、脳内で作り上げた立体を紙の上に起こしていくような素描から生まれています。
現代はインターネットや写真集などで簡単にその写真をチェックすることができるとしても、やはり実物をみなければ、ミケランジェロが侵食を忘れて削った鑿の痕跡、そして自らを限界まで追い込んで作り上げた光と影の美しさを味わうことはできません。
ミケランジェロの美しい絵画は「クロスハッチング」と呼ばれる、細かな斜線をいくつもクロス(交差)させて構築していく立体的な描き方が特徴です。石の中から像を削りだすがごとく、脳内で作り上げた立体を紙の上に起こしていくような素描から生まれています。
ミケランジェロの作品が観たい!どこに行けばいい?

ルネサンスやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロなどとともに、ミケランジェロをテーマにした展示会は、毎年日本各地で開催されているため、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
今年(2017年)おすすめなのは、
■レオナルド×ミケランジェロ展(2017年6月17日(土)~9月24日(日))
三菱一号館美術館(東京・丸の内)で開催されるこの特別展は、ルネサンスの巨匠ふたりの有名な作品を比較しながら鑑賞できるスペシャルな企画です。
■大塚国際美術館(徳島県鳴門市)
ミケランジェロの『最後の審判』を陶板複製画にし、システィーナ礼拝堂オリジナルに近い展示方法がされているので、頭上を覆うミケランジェロの傑作が発する威圧感を、視覚のみならず肌感覚で味わうことができます。
今年(2017年)おすすめなのは、
■レオナルド×ミケランジェロ展(2017年6月17日(土)~9月24日(日))
三菱一号館美術館(東京・丸の内)で開催されるこの特別展は、ルネサンスの巨匠ふたりの有名な作品を比較しながら鑑賞できるスペシャルな企画です。
■大塚国際美術館(徳島県鳴門市)
ミケランジェロの『最後の審判』を陶板複製画にし、システィーナ礼拝堂オリジナルに近い展示方法がされているので、頭上を覆うミケランジェロの傑作が発する威圧感を、視覚のみならず肌感覚で味わうことができます。
ベートーヴェンとミケランジェロ 二人の天才の孤独

ミケランジェロとベートーヴェン。時代と活躍の場を異にするこの二人の天才の生涯は、苦難に満ちたものでした。
フランスのロマン・ロランは、ミケランジェロとベートーヴェン、そしてトルストイの生涯を文学作品へと昇華させました。彼にとってのミケランジェロとベートーヴェンは、聳え立つ山巓であり、悩める人々にとっての友でした。ロマン・ロランにとって二人の人生は、「ほとんど常に永い受苦の歴史」であり、彼らが教えてくれるのは「人生というものは、苦悩の中においてこそ最も偉大で実り多くかつまた最も幸福である」という事実でした。(『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳。)
なかでも、二人にとって「孤独」は避けられぬ苦難でした。一方でこの「孤独」こそ、彼ら天才たちの刻印でもありました。「孤独」をキーワードに、二人の生涯と作品を読み解きます。
フランスのロマン・ロランは、ミケランジェロとベートーヴェン、そしてトルストイの生涯を文学作品へと昇華させました。彼にとってのミケランジェロとベートーヴェンは、聳え立つ山巓であり、悩める人々にとっての友でした。ロマン・ロランにとって二人の人生は、「ほとんど常に永い受苦の歴史」であり、彼らが教えてくれるのは「人生というものは、苦悩の中においてこそ最も偉大で実り多くかつまた最も幸福である」という事実でした。(『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳。)
なかでも、二人にとって「孤独」は避けられぬ苦難でした。一方でこの「孤独」こそ、彼ら天才たちの刻印でもありました。「孤独」をキーワードに、二人の生涯と作品を読み解きます。
1. ミケランジェロの孤独
天才はとかく孤独に悩みます。一方で、天才は孤独を必要とする、とも言えるでしょう。孤独に耐えて歩み続ける強さがなければ、余人の及ばぬ境地に辿り着くことはできないからです。いわば孤独は天才の宿命。ミケランジェロもベートーヴェンも例外ではありませんでした。
ミケランジェロは孤独を愛しました。もっとも、イタリア法王庁の高官や文筆家との交流があり、イタリア中の人々が彼の才能に敬意を払っていました。しかし、彼はあくまでも自分に正直な自由人でいることを好み、世間的な栄誉を有難がったり、権力者へ追従したりといったことは、彼のあえてしない事であったようです。ロマン・ロランは、次のように書いています。
彼はやむを得ない時にだけ世間と交わり、それも知性的関係だけで、彼の内部に立ち入ることを許さなかった。法王も王侯も文学者も芸術家も彼の生活の中ではほとんど場所を占めていなかった。本当に共感したわずかの人々とさえ、長い友情がつづいたことは稀だった。彼は友人を愛し、彼らに寛大だったが、彼の激しい気性、自尊心、猜疑心のために、深く世話してやった者までが生涯の敵になってしまった。(『ミケランジェロの生涯』高田博厚訳 pp.112-113)
彼が友人として好んだのは、素朴で無邪気な人間でした。とくに、助手たちには愛情をもって接しました。ミケランジェロは助手の一人ウルビーノの死に深く悲しみ、その悲しみや「彼と天国で会う希望しかもう私には残っていない。」とまで書き残すほどでした。また、詩人ヴィットリア・コロンナとの麗しい恋はミケランジェロの心に慰めを与えました。
このようにわずかな友好関係はありましたが、彼の孤独は、老年に至るにつれて深まるばかりでした。彼の孤独を癒すものは、夜の静寂、自然、神、そして死でした。これらの友はしかし、ミケランジェロを内省と神への信仰へと向けました。彼は幾度も死の安らぎへのあこがれを語りました。しかし、彼は88歳まで生き続けました。天才は「彼に襲いかかって屈服させてしまった征服者」(同上、p.13)であり、ミケランジェロをして彼の天分と肉体を尽くさしめずにはおかなかったのです。
ミケランジェロの孤独は、システィーナ礼拝堂の天井画を生みました。1508年から4年をかけて完成されたこの人類史上の傑作は、ミケランジェロの孤独の戦いの記録でもありました。システィーナのフレスコ画は、数人の助手を率いて礼拝堂にこもったミケランジェロの、自らの天才に身を尽くした、足場の上での孤独な4年間の記念碑でもあるのです。
ミケランジェロは孤独を愛しました。もっとも、イタリア法王庁の高官や文筆家との交流があり、イタリア中の人々が彼の才能に敬意を払っていました。しかし、彼はあくまでも自分に正直な自由人でいることを好み、世間的な栄誉を有難がったり、権力者へ追従したりといったことは、彼のあえてしない事であったようです。ロマン・ロランは、次のように書いています。
彼はやむを得ない時にだけ世間と交わり、それも知性的関係だけで、彼の内部に立ち入ることを許さなかった。法王も王侯も文学者も芸術家も彼の生活の中ではほとんど場所を占めていなかった。本当に共感したわずかの人々とさえ、長い友情がつづいたことは稀だった。彼は友人を愛し、彼らに寛大だったが、彼の激しい気性、自尊心、猜疑心のために、深く世話してやった者までが生涯の敵になってしまった。(『ミケランジェロの生涯』高田博厚訳 pp.112-113)
彼が友人として好んだのは、素朴で無邪気な人間でした。とくに、助手たちには愛情をもって接しました。ミケランジェロは助手の一人ウルビーノの死に深く悲しみ、その悲しみや「彼と天国で会う希望しかもう私には残っていない。」とまで書き残すほどでした。また、詩人ヴィットリア・コロンナとの麗しい恋はミケランジェロの心に慰めを与えました。
このようにわずかな友好関係はありましたが、彼の孤独は、老年に至るにつれて深まるばかりでした。彼の孤独を癒すものは、夜の静寂、自然、神、そして死でした。これらの友はしかし、ミケランジェロを内省と神への信仰へと向けました。彼は幾度も死の安らぎへのあこがれを語りました。しかし、彼は88歳まで生き続けました。天才は「彼に襲いかかって屈服させてしまった征服者」(同上、p.13)であり、ミケランジェロをして彼の天分と肉体を尽くさしめずにはおかなかったのです。
ミケランジェロの孤独は、システィーナ礼拝堂の天井画を生みました。1508年から4年をかけて完成されたこの人類史上の傑作は、ミケランジェロの孤独の戦いの記録でもありました。システィーナのフレスコ画は、数人の助手を率いて礼拝堂にこもったミケランジェロの、自らの天才に身を尽くした、足場の上での孤独な4年間の記念碑でもあるのです。
2.ベートーヴェンと孤独
ベートーヴェンも孤独に悩まされました。ベートーヴェンの孤独は、自ら孤独に向かっていったミケランジェロと比べると、強いられた孤独であったといえるでしょう。彼は幼いころから酒飲みの父に苦しみながら育ち、避難所であった母も早くに亡くしてしまいました。一家の大黒柱としての責任を背負わされたベートーヴェンですが、生涯の友人ヴェーゲラーや、ベートーヴェンを暖かく迎えたブロイニング一家、大げんかするもののパトロンであり続けたリヒノフスキー公爵といった友好関係に恵まれました。しかし、ベートーヴェンは、耳が悪くなるにつれ孤独に逃げ込まざるを得ませんでした。彼の嘆きは書簡や、悲痛な叫びが支配する『ハイリゲンシュタットの遺書』に表出されています。
ああ、今僕の聴力が少しもそこなわれていないとしたら、僕はどんなにか幸福だろうに!しかし僕はすべてから隠れて生きることを余儀なくさせられている。僕の最も美しい年月がむなしく流れ去る。天分と力とが命ずるだけの仕事を僕が果たしもしないうちに!――悲しいあきらめ、それを僕は隠れ家としなければならないのだ!(1801年6月1日、ヴィーン カルル・アメンダ宛 片山敏彦訳)
社交の楽しみにも応じやすいほど熱情的で活溌な性質をもって生まれた私は、早くも人々から孤り遠ざかって孤独の生活をしなければならなくなった。[…]人々の集まりの中へ交じって元気づいたり精妙な談話を楽しんだり、話し合って互いに感情を流露させることが私には許されないのだ。まるで放逐されている人間のように私は生きなければならない。人々の集まりへ近づくと、自分の病状を気づかれはしまいかという恐ろしい不安が私の心を襲う。(1802年10月、『ハイリゲンシュタットの遺書』片山敏彦訳)
悲嘆に暮れるベートーヴェンの友となったのは、ミケランジェロと同じく「自然」でした。ベートーヴェンは『田園交響曲』を作曲したように、自然を深く愛しました。
自己の内部に閉じこもり、一切の人々から切り離された彼は、ただ自然の中に浸ることだけを慰めとした。「自然がベートーヴェンの唯一の友であった」とテレーズ・フォン・ブルンスヴィックはいっている。自然が彼の安息所であった。(『ベートーヴェンの生涯』p.57)
ベートーヴェンは自然のなかに憩いを見出したのみならず、神をも見出しました。『田園』とベートーヴェン自ら標題を与えた、交響曲第6番のスケッチ帳に記された次の一節は、自然への愛と信仰心の融合は、晩年のミケランジェロを思わせます。
全能なる神よ!――森の中で私は幸福である――そこではおのおのの樹がおんみの言葉を語る。――神よ、何たるこの壮麗さ!――この森の中、丘の上の――この静寂よ――おんみにかしずくためのこの静寂よ!(同上、p.58)
v ベートーヴェンを孤独に打ち克たせたものはやはり芸術でした。彼は交響曲第9番で、“alle menschen werden bruder”(人類みながら兄弟)と高らかに歌い、ミサソレムニスの冒頭には、“Von Herzen - Moge es wieder - Zu Herzen gehn”(心より、願わくば再び、心に入らんことを。)という言葉を書き記し、芸術に孤独の克服の可能性を託しました。一方で、ベートーヴェンの晩年の作品からは深い孤独の嘆きも聞こえてくるのは事実です。ピアノソナタ第31番、<嘆きの歌>とよばれる部分には、孤独の深淵を感ぜざるを得ません。弦楽四重奏第14番の悲痛な呻きは、孤独のなかでしか生まれないとさえ思われます。しかし、晩年のベートーヴェンは、新しい光を見出し、悲しみの重みから解き放たれたかのように、天上を目ざして駆け上がることができました。彼の3つの最後のピアノソナタはどれも、最後には孤独や苦しみを克服して終わります。晩年、病重りゆくベートーヴェンが孤独を克服することができたか、それはわかりません。しかし、ことに彼の芸術においては、晩年に至って孤独を克服し、新たな境地に至ったこと、彼の晩年の音楽はそのことを雄弁に語っています。
ああ、今僕の聴力が少しもそこなわれていないとしたら、僕はどんなにか幸福だろうに!しかし僕はすべてから隠れて生きることを余儀なくさせられている。僕の最も美しい年月がむなしく流れ去る。天分と力とが命ずるだけの仕事を僕が果たしもしないうちに!――悲しいあきらめ、それを僕は隠れ家としなければならないのだ!(1801年6月1日、ヴィーン カルル・アメンダ宛 片山敏彦訳)
社交の楽しみにも応じやすいほど熱情的で活溌な性質をもって生まれた私は、早くも人々から孤り遠ざかって孤独の生活をしなければならなくなった。[…]人々の集まりの中へ交じって元気づいたり精妙な談話を楽しんだり、話し合って互いに感情を流露させることが私には許されないのだ。まるで放逐されている人間のように私は生きなければならない。人々の集まりへ近づくと、自分の病状を気づかれはしまいかという恐ろしい不安が私の心を襲う。(1802年10月、『ハイリゲンシュタットの遺書』片山敏彦訳)
悲嘆に暮れるベートーヴェンの友となったのは、ミケランジェロと同じく「自然」でした。ベートーヴェンは『田園交響曲』を作曲したように、自然を深く愛しました。
自己の内部に閉じこもり、一切の人々から切り離された彼は、ただ自然の中に浸ることだけを慰めとした。「自然がベートーヴェンの唯一の友であった」とテレーズ・フォン・ブルンスヴィックはいっている。自然が彼の安息所であった。(『ベートーヴェンの生涯』p.57)
ベートーヴェンは自然のなかに憩いを見出したのみならず、神をも見出しました。『田園』とベートーヴェン自ら標題を与えた、交響曲第6番のスケッチ帳に記された次の一節は、自然への愛と信仰心の融合は、晩年のミケランジェロを思わせます。
全能なる神よ!――森の中で私は幸福である――そこではおのおのの樹がおんみの言葉を語る。――神よ、何たるこの壮麗さ!――この森の中、丘の上の――この静寂よ――おんみにかしずくためのこの静寂よ!(同上、p.58)
v ベートーヴェンを孤独に打ち克たせたものはやはり芸術でした。彼は交響曲第9番で、“alle menschen werden bruder”(人類みながら兄弟)と高らかに歌い、ミサソレムニスの冒頭には、“Von Herzen - Moge es wieder - Zu Herzen gehn”(心より、願わくば再び、心に入らんことを。)という言葉を書き記し、芸術に孤独の克服の可能性を託しました。一方で、ベートーヴェンの晩年の作品からは深い孤独の嘆きも聞こえてくるのは事実です。ピアノソナタ第31番、<嘆きの歌>とよばれる部分には、孤独の深淵を感ぜざるを得ません。弦楽四重奏第14番の悲痛な呻きは、孤独のなかでしか生まれないとさえ思われます。しかし、晩年のベートーヴェンは、新しい光を見出し、悲しみの重みから解き放たれたかのように、天上を目ざして駆け上がることができました。彼の3つの最後のピアノソナタはどれも、最後には孤独や苦しみを克服して終わります。晩年、病重りゆくベートーヴェンが孤独を克服することができたか、それはわかりません。しかし、ことに彼の芸術においては、晩年に至って孤独を克服し、新たな境地に至ったこと、彼の晩年の音楽はそのことを雄弁に語っています。
ベートーヴェンとミケランジェロ 二人の天才の孤独

ミケランジェロとベートーヴェン。時代と活躍の場を異にするこの二人の天才の生涯は、苦難に満ちたものでした。
フランスのロマン・ロランは、ミケランジェロとベートーヴェン、そしてトルストイの生涯を文学作品へと昇華させました。彼にとってのミケランジェロとベートーヴェンは、聳え立つ山巓であり、悩める人々にとっての友でした。ロマン・ロランにとって二人の人生は、「ほとんど常に永い受苦の歴史」であり、彼らが教えてくれるのは「人生というものは、苦悩の中においてこそ最も偉大で実り多くかつまた最も幸福である」という事実でした。(『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳。)
なかでも、二人にとって「孤独」は避けられぬ苦難でした。一方でこの「孤独」こそ、彼ら天才たちの刻印でもありました。「孤独」をキーワードに、二人の生涯と作品を読み解きます。
フランスのロマン・ロランは、ミケランジェロとベートーヴェン、そしてトルストイの生涯を文学作品へと昇華させました。彼にとってのミケランジェロとベートーヴェンは、聳え立つ山巓であり、悩める人々にとっての友でした。ロマン・ロランにとって二人の人生は、「ほとんど常に永い受苦の歴史」であり、彼らが教えてくれるのは「人生というものは、苦悩の中においてこそ最も偉大で実り多くかつまた最も幸福である」という事実でした。(『ベートーヴェンの生涯』片山敏彦訳。)
なかでも、二人にとって「孤独」は避けられぬ苦難でした。一方でこの「孤独」こそ、彼ら天才たちの刻印でもありました。「孤独」をキーワードに、二人の生涯と作品を読み解きます。
1. ミケランジェロの孤独
天才はとかく孤独に悩みます。一方で、天才は孤独を必要とする、とも言えるでしょう。孤独に耐えて歩み続ける強さがなければ、余人の及ばぬ境地に辿り着くことはできないからです。いわば孤独は天才の宿命。ミケランジェロもベートーヴェンも例外ではありませんでした。
ミケランジェロは孤独を愛しました。もっとも、イタリア法王庁の高官や文筆家との交流があり、イタリア中の人々が彼の才能に敬意を払っていました。しかし、彼はあくまでも自分に正直な自由人でいることを好み、世間的な栄誉を有難がったり、権力者へ追従したりといったことは、彼のあえてしない事であったようです。ロマン・ロランは、次のように書いています。
彼はやむを得ない時にだけ世間と交わり、それも知性的関係だけで、彼の内部に立ち入ることを許さなかった。法王も王侯も文学者も芸術家も彼の生活の中ではほとんど場所を占めていなかった。本当に共感したわずかの人々とさえ、長い友情がつづいたことは稀だった。彼は友人を愛し、彼らに寛大だったが、彼の激しい気性、自尊心、猜疑心のために、深く世話してやった者までが生涯の敵になってしまった。(『ミケランジェロの生涯』高田博厚訳 pp.112-113)
彼が友人として好んだのは、素朴で無邪気な人間でした。とくに、助手たちには愛情をもって接しました。ミケランジェロは助手の一人ウルビーノの死に深く悲しみ、その悲しみや「彼と天国で会う希望しかもう私には残っていない。」とまで書き残すほどでした。また、詩人ヴィットリア・コロンナとの麗しい恋はミケランジェロの心に慰めを与えました。
このようにわずかな友好関係はありましたが、彼の孤独は、老年に至るにつれて深まるばかりでした。彼の孤独を癒すものは、夜の静寂、自然、神、そして死でした。これらの友はしかし、ミケランジェロを内省と神への信仰へと向けました。彼は幾度も死の安らぎへのあこがれを語りました。しかし、彼は88歳まで生き続けました。天才は「彼に襲いかかって屈服させてしまった征服者」(同上、p.13)であり、ミケランジェロをして彼の天分と肉体を尽くさしめずにはおかなかったのです。
ミケランジェロの孤独は、システィーナ礼拝堂の天井画を生みました。1508年から4年をかけて完成されたこの人類史上の傑作は、ミケランジェロの孤独の戦いの記録でもありました。システィーナのフレスコ画は、数人の助手を率いて礼拝堂にこもったミケランジェロの、自らの天才に身を尽くした、足場の上での孤独な4年間の記念碑でもあるのです。
ミケランジェロは孤独を愛しました。もっとも、イタリア法王庁の高官や文筆家との交流があり、イタリア中の人々が彼の才能に敬意を払っていました。しかし、彼はあくまでも自分に正直な自由人でいることを好み、世間的な栄誉を有難がったり、権力者へ追従したりといったことは、彼のあえてしない事であったようです。ロマン・ロランは、次のように書いています。
彼はやむを得ない時にだけ世間と交わり、それも知性的関係だけで、彼の内部に立ち入ることを許さなかった。法王も王侯も文学者も芸術家も彼の生活の中ではほとんど場所を占めていなかった。本当に共感したわずかの人々とさえ、長い友情がつづいたことは稀だった。彼は友人を愛し、彼らに寛大だったが、彼の激しい気性、自尊心、猜疑心のために、深く世話してやった者までが生涯の敵になってしまった。(『ミケランジェロの生涯』高田博厚訳 pp.112-113)
彼が友人として好んだのは、素朴で無邪気な人間でした。とくに、助手たちには愛情をもって接しました。ミケランジェロは助手の一人ウルビーノの死に深く悲しみ、その悲しみや「彼と天国で会う希望しかもう私には残っていない。」とまで書き残すほどでした。また、詩人ヴィットリア・コロンナとの麗しい恋はミケランジェロの心に慰めを与えました。
このようにわずかな友好関係はありましたが、彼の孤独は、老年に至るにつれて深まるばかりでした。彼の孤独を癒すものは、夜の静寂、自然、神、そして死でした。これらの友はしかし、ミケランジェロを内省と神への信仰へと向けました。彼は幾度も死の安らぎへのあこがれを語りました。しかし、彼は88歳まで生き続けました。天才は「彼に襲いかかって屈服させてしまった征服者」(同上、p.13)であり、ミケランジェロをして彼の天分と肉体を尽くさしめずにはおかなかったのです。
ミケランジェロの孤独は、システィーナ礼拝堂の天井画を生みました。1508年から4年をかけて完成されたこの人類史上の傑作は、ミケランジェロの孤独の戦いの記録でもありました。システィーナのフレスコ画は、数人の助手を率いて礼拝堂にこもったミケランジェロの、自らの天才に身を尽くした、足場の上での孤独な4年間の記念碑でもあるのです。
2.ベートーヴェンと孤独
ベートーヴェンも孤独に悩まされました。ベートーヴェンの孤独は、自ら孤独に向かっていったミケランジェロと比べると、強いられた孤独であったといえるでしょう。彼は幼いころから酒飲みの父に苦しみながら育ち、避難所であった母も早くに亡くしてしまいました。一家の大黒柱としての責任を背負わされたベートーヴェンですが、生涯の友人ヴェーゲラーや、ベートーヴェンを暖かく迎えたブロイニング一家、大げんかするもののパトロンであり続けたリヒノフスキー公爵といった友好関係に恵まれました。しかし、ベートーヴェンは、耳が悪くなるにつれ孤独に逃げ込まざるを得ませんでした。彼の嘆きは書簡や、悲痛な叫びが支配する『ハイリゲンシュタットの遺書』に表出されています。
ああ、今僕の聴力が少しもそこなわれていないとしたら、僕はどんなにか幸福だろうに!しかし僕はすべてから隠れて生きることを余儀なくさせられている。僕の最も美しい年月がむなしく流れ去る。天分と力とが命ずるだけの仕事を僕が果たしもしないうちに!――悲しいあきらめ、それを僕は隠れ家としなければならないのだ!(1801年6月1日、ヴィーン カルル・アメンダ宛 片山敏彦訳)
社交の楽しみにも応じやすいほど熱情的で活溌な性質をもって生まれた私は、早くも人々から孤り遠ざかって孤独の生活をしなければならなくなった。[…]人々の集まりの中へ交じって元気づいたり精妙な談話を楽しんだり、話し合って互いに感情を流露させることが私には許されないのだ。まるで放逐されている人間のように私は生きなければならない。人々の集まりへ近づくと、自分の病状を気づかれはしまいかという恐ろしい不安が私の心を襲う。(1802年10月、『ハイリゲンシュタットの遺書』片山敏彦訳)
悲嘆に暮れるベートーヴェンの友となったのは、ミケランジェロと同じく「自然」でした。ベートーヴェンは『田園交響曲』を作曲したように、自然を深く愛しました。
自己の内部に閉じこもり、一切の人々から切り離された彼は、ただ自然の中に浸ることだけを慰めとした。「自然がベートーヴェンの唯一の友であった」とテレーズ・フォン・ブルンスヴィックはいっている。自然が彼の安息所であった。(『ベートーヴェンの生涯』p.57)
ベートーヴェンは自然のなかに憩いを見出したのみならず、神をも見出しました。『田園』とベートーヴェン自ら標題を与えた、交響曲第6番のスケッチ帳に記された次の一節は、自然への愛と信仰心の融合は、晩年のミケランジェロを思わせます。
全能なる神よ!――森の中で私は幸福である――そこではおのおのの樹がおんみの言葉を語る。――神よ、何たるこの壮麗さ!――この森の中、丘の上の――この静寂よ――おんみにかしずくためのこの静寂よ!(同上、p.58)
v ベートーヴェンを孤独に打ち克たせたものはやはり芸術でした。彼は交響曲第9番で、“alle menschen werden bruder”(人類みながら兄弟)と高らかに歌い、ミサソレムニスの冒頭には、“Von Herzen - Moge es wieder - Zu Herzen gehn”(心より、願わくば再び、心に入らんことを。)という言葉を書き記し、芸術に孤独の克服の可能性を託しました。一方で、ベートーヴェンの晩年の作品からは深い孤独の嘆きも聞こえてくるのは事実です。ピアノソナタ第31番、<嘆きの歌>とよばれる部分には、孤独の深淵を感ぜざるを得ません。弦楽四重奏第14番の悲痛な呻きは、孤独のなかでしか生まれないとさえ思われます。しかし、晩年のベートーヴェンは、新しい光を見出し、悲しみの重みから解き放たれたかのように、天上を目ざして駆け上がることができました。彼の3つの最後のピアノソナタはどれも、最後には孤独や苦しみを克服して終わります。晩年、病重りゆくベートーヴェンが孤独を克服することができたか、それはわかりません。しかし、ことに彼の芸術においては、晩年に至って孤独を克服し、新たな境地に至ったこと、彼の晩年の音楽はそのことを雄弁に語っています。
ああ、今僕の聴力が少しもそこなわれていないとしたら、僕はどんなにか幸福だろうに!しかし僕はすべてから隠れて生きることを余儀なくさせられている。僕の最も美しい年月がむなしく流れ去る。天分と力とが命ずるだけの仕事を僕が果たしもしないうちに!――悲しいあきらめ、それを僕は隠れ家としなければならないのだ!(1801年6月1日、ヴィーン カルル・アメンダ宛 片山敏彦訳)
社交の楽しみにも応じやすいほど熱情的で活溌な性質をもって生まれた私は、早くも人々から孤り遠ざかって孤独の生活をしなければならなくなった。[…]人々の集まりの中へ交じって元気づいたり精妙な談話を楽しんだり、話し合って互いに感情を流露させることが私には許されないのだ。まるで放逐されている人間のように私は生きなければならない。人々の集まりへ近づくと、自分の病状を気づかれはしまいかという恐ろしい不安が私の心を襲う。(1802年10月、『ハイリゲンシュタットの遺書』片山敏彦訳)
悲嘆に暮れるベートーヴェンの友となったのは、ミケランジェロと同じく「自然」でした。ベートーヴェンは『田園交響曲』を作曲したように、自然を深く愛しました。
自己の内部に閉じこもり、一切の人々から切り離された彼は、ただ自然の中に浸ることだけを慰めとした。「自然がベートーヴェンの唯一の友であった」とテレーズ・フォン・ブルンスヴィックはいっている。自然が彼の安息所であった。(『ベートーヴェンの生涯』p.57)
ベートーヴェンは自然のなかに憩いを見出したのみならず、神をも見出しました。『田園』とベートーヴェン自ら標題を与えた、交響曲第6番のスケッチ帳に記された次の一節は、自然への愛と信仰心の融合は、晩年のミケランジェロを思わせます。
全能なる神よ!――森の中で私は幸福である――そこではおのおのの樹がおんみの言葉を語る。――神よ、何たるこの壮麗さ!――この森の中、丘の上の――この静寂よ――おんみにかしずくためのこの静寂よ!(同上、p.58)
v ベートーヴェンを孤独に打ち克たせたものはやはり芸術でした。彼は交響曲第9番で、“alle menschen werden bruder”(人類みながら兄弟)と高らかに歌い、ミサソレムニスの冒頭には、“Von Herzen - Moge es wieder - Zu Herzen gehn”(心より、願わくば再び、心に入らんことを。)という言葉を書き記し、芸術に孤独の克服の可能性を託しました。一方で、ベートーヴェンの晩年の作品からは深い孤独の嘆きも聞こえてくるのは事実です。ピアノソナタ第31番、<嘆きの歌>とよばれる部分には、孤独の深淵を感ぜざるを得ません。弦楽四重奏第14番の悲痛な呻きは、孤独のなかでしか生まれないとさえ思われます。しかし、晩年のベートーヴェンは、新しい光を見出し、悲しみの重みから解き放たれたかのように、天上を目ざして駆け上がることができました。彼の3つの最後のピアノソナタはどれも、最後には孤独や苦しみを克服して終わります。晩年、病重りゆくベートーヴェンが孤独を克服することができたか、それはわかりません。しかし、ことに彼の芸術においては、晩年に至って孤独を克服し、新たな境地に至ったこと、彼の晩年の音楽はそのことを雄弁に語っています。

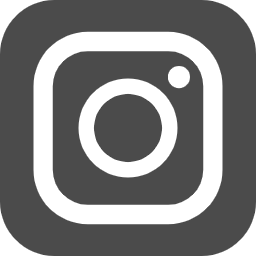
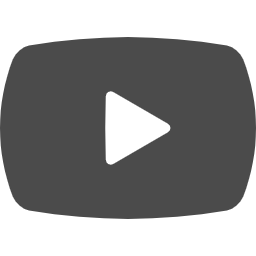

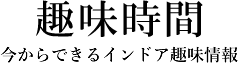















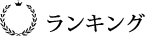

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)