ご存知ですか?仏道が掲げる慈悲、本来の意味
関連キーワード
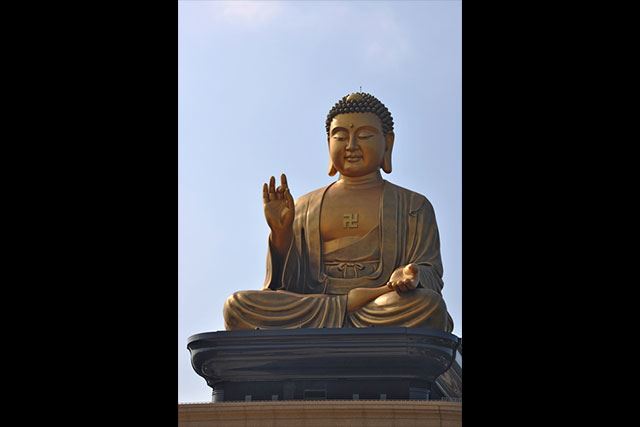
聞くだけでほっとする言葉があります。慈悲もそんな言葉の一つと言っていいでしょう。仏教だけでなくキリスト教などでも使われていますが、仏教においては修行の意味もあったのをご存知ですか?
仏教での慈悲とは
慈悲というものは、一般的には優しさや情けをかける意味で使われます。仏教では、大まかに言って憐れみと慈しみという意味です。慈悲は、真理を悟る智慧と共に仏教の二本柱とも言えます。具体的に言えば、他者、そしてあらゆる生物に対する慈しみの心です。お釈迦様も人を苦しみから救うべく、慈悲の心で教えを説きました。
個々の言葉だった・四無量心
慈悲は元々別々の言葉であり、熟語ではありませんでした。「慈」は与楽を表し、「悲」は抜苦を表します。
与楽とは他者の安楽を望むことで、抜苦とは他者の不利益、苦しみ取り除くことを望む心です。「幸せになってほしい、病気が治ってほしい」と言った気持ちですね。人間相手でなく、すべての生き物にこの思いを抱くのが慈悲なのです。これに、他人の幸福を見て自分も幸せな気持ちになる喜、差別心を起こさない捨が加わった四無量心が大乗仏教の根幹の一つになります。
四無量心とは上から目線で「救ってやるぞよ」という気持ちではなく、誰でも実践できるものです。別名を利他行と言います。
与楽とは他者の安楽を望むことで、抜苦とは他者の不利益、苦しみ取り除くことを望む心です。「幸せになってほしい、病気が治ってほしい」と言った気持ちですね。人間相手でなく、すべての生き物にこの思いを抱くのが慈悲なのです。これに、他人の幸福を見て自分も幸せな気持ちになる喜、差別心を起こさない捨が加わった四無量心が大乗仏教の根幹の一つになります。
四無量心とは上から目線で「救ってやるぞよ」という気持ちではなく、誰でも実践できるものです。別名を利他行と言います。
菩薩は慈悲の体現者
悟りを得て仏(如来)となれるのに、敢えて衆生救済の為にランクアップを行わないのが菩薩です。
「仏様だし、上の存在では?」と思ってしまいますよね。しかし、菩薩は衆生と一緒に修行をしているのです。確かに、六道世界を全て回ったり変化したりもしますが、それでも修行中であり完全に悟りきっていないという点は人間と同じと言えます。そもそも菩薩は、一般的には仏の位と認識されますが、実際には悟りを開く為の修行者のことなのです。お釈迦様にも菩薩時代はありました。
菩薩の修行法は六波羅蜜と呼ばれますが、この中にも慈悲が関連する修行があります。それは、布施です。
「仏様だし、上の存在では?」と思ってしまいますよね。しかし、菩薩は衆生と一緒に修行をしているのです。確かに、六道世界を全て回ったり変化したりもしますが、それでも修行中であり完全に悟りきっていないという点は人間と同じと言えます。そもそも菩薩は、一般的には仏の位と認識されますが、実際には悟りを開く為の修行者のことなのです。お釈迦様にも菩薩時代はありました。
菩薩の修行法は六波羅蜜と呼ばれますが、この中にも慈悲が関連する修行があります。それは、布施です。
布施とは何ぞや

「お坊さんに何かをあげることでしょう?」それも間違いではありません。
本来の意味は他者に物を施すことです。お金、食糧、その他何でもいいから見返りを求めずに与えること。これがお布施です。「恋人になりたいから」と物を貢いだりするのは、布施ではなく単なる下心ですね。自分の利益を期待しているようではいけません。そして受け取る方も「これだけ?ケチだなー」などと言ってはいけないのです。布施目当てでウロウロするのもいけません。「よかったらどうぞ」「ありがとう」が理想です。
布施は何も物に限ったことではありません。「取り立てて上げる物がない」からとスルーするのが悪いとは言いませんが、無財の七施というものがあります。つまり、「物はないけど、せめて」との気持ちから来る慈悲の実践です。直や物がない時などに行われます。
【和顔施】
柔和な表情で他者に接することです。ムッツリしていたら開いても嫌な気持ちになります。それが和やかな表情だと安心を覚える物です。
【眼施】
和顔施とほぼ同じく、優しい目線で見ることを言います。目は口程に物を言うとも言いますし、目付きは意外と重要です。
【言施】
他者を気遣い、思いやりある言葉を使うことです。同じ状況でも、どんな言葉を掛けられるかで心境も変わってきますね。例えば仕事で失敗した時。「何であんな間違いをしたんだ、二度と同じ間違いをするな」と言われるより「次はよく検討して、同じ間違いをしないようにしようね。一緒に頑張ろう」と言われた方がいくらか気が楽ですし、モチベーションも上がるでしょう。
【心施】
他者を心の底から思いやることです。ボランティア活動などは主に心施(しんせ)と呼ばれる物に近いでしょう。しかし、心から、真摯に取り組まなくては意味がありません。
【身施】
何もない分、自分にできることをするとの意味です。ボランティアは心施と身施の両立とも言えましょう。本格的なボランティアでなくともいいのです。エレベーターに乗る時、大急ぎで誰かが走って来たら「開」ボタンを押して待つと言った小さなことでも慈悲と言えます。
【床座施】
バスや電車などで、お年寄りや妊婦さんといった、席を必要とする人々が乗って来た場合など、席を譲っることを言います。
【房舎施】
自分の家に人を止まらせたり、休ませたりすることです。『ブッダ』を描いた漫画家の手塚治虫氏は戦時中、空腹に耐えかねてまったく面識のない家に行き食事を出してもらったことがあるとか。結局その恩人には二度と会えなかったようですが、戦時中の物のない時代、見も知らない若者に食事を出した恩人の心には確かに慈悲があったかもしれません。
本来の意味は他者に物を施すことです。お金、食糧、その他何でもいいから見返りを求めずに与えること。これがお布施です。「恋人になりたいから」と物を貢いだりするのは、布施ではなく単なる下心ですね。自分の利益を期待しているようではいけません。そして受け取る方も「これだけ?ケチだなー」などと言ってはいけないのです。布施目当てでウロウロするのもいけません。「よかったらどうぞ」「ありがとう」が理想です。
布施は何も物に限ったことではありません。「取り立てて上げる物がない」からとスルーするのが悪いとは言いませんが、無財の七施というものがあります。つまり、「物はないけど、せめて」との気持ちから来る慈悲の実践です。直や物がない時などに行われます。
【和顔施】
柔和な表情で他者に接することです。ムッツリしていたら開いても嫌な気持ちになります。それが和やかな表情だと安心を覚える物です。
【眼施】
和顔施とほぼ同じく、優しい目線で見ることを言います。目は口程に物を言うとも言いますし、目付きは意外と重要です。
【言施】
他者を気遣い、思いやりある言葉を使うことです。同じ状況でも、どんな言葉を掛けられるかで心境も変わってきますね。例えば仕事で失敗した時。「何であんな間違いをしたんだ、二度と同じ間違いをするな」と言われるより「次はよく検討して、同じ間違いをしないようにしようね。一緒に頑張ろう」と言われた方がいくらか気が楽ですし、モチベーションも上がるでしょう。
【心施】
他者を心の底から思いやることです。ボランティア活動などは主に心施(しんせ)と呼ばれる物に近いでしょう。しかし、心から、真摯に取り組まなくては意味がありません。
【身施】
何もない分、自分にできることをするとの意味です。ボランティアは心施と身施の両立とも言えましょう。本格的なボランティアでなくともいいのです。エレベーターに乗る時、大急ぎで誰かが走って来たら「開」ボタンを押して待つと言った小さなことでも慈悲と言えます。
【床座施】
バスや電車などで、お年寄りや妊婦さんといった、席を必要とする人々が乗って来た場合など、席を譲っることを言います。
【房舎施】
自分の家に人を止まらせたり、休ませたりすることです。『ブッダ』を描いた漫画家の手塚治虫氏は戦時中、空腹に耐えかねてまったく面識のない家に行き食事を出してもらったことがあるとか。結局その恩人には二度と会えなかったようですが、戦時中の物のない時代、見も知らない若者に食事を出した恩人の心には確かに慈悲があったかもしれません。
お釈迦様が息子に伝授した、慈悲瞑想

仏教は大きく上部座仏教、大乗仏教とに分かれます。「出家をして修行をして、いずれ阿羅漢になる」ことを目的とした上部座仏教に対し、大乗仏教は「出家していなくても、皆助けられるべきではないか」との考えです。比較的大乗仏教の方が新しく、その分洗練されています。
慈悲を善く表しているように思われますが、慈悲は等しく、どちらの形態の仏教の大きな柱なのです。慈悲がお釈迦様の時代からあったことは既に記しましたが、上部座仏教に伝わるパーリ仏典には、慈悲瞑想なる修行法が記されています。「人間だけでなく、全ての生物(衆生)が幸福であるように」という慈悲の基本精神を見つめ、瞑想する修行です。「自分の子供を守るように、色々な命を守り救いましょう」とも書かれていますが、できるところからコツコツと。初めに、自分自身の幸福を願います。
次に、幸福を得る対象を他者へと移行。つまり、他者の幸福を願う瞑想に写るわけです。ここでは「幸せになって」と思いやすい、大切な人が対象になります。続いてに全ての衆生の幸福を祈るようになりますが、ここで終わりじゃありません。仏弟子だって「アンニャロ、気に食わない」という人もいるでしょう。そんな人の幸福も願うのが慈悲瞑想なのです。
お釈迦様は息子で十大弟子の一人、ラーフラにこの慈悲瞑想についてこう語りました。「四無量心の瞑想をしなさい。そうすれば、怒りだって残忍な心だって芽生えないから」慈悲の対極にあるもの、それは仏教の三大煩悩こと三業の一つ、瞋恚(怒り)です。従って、慈悲瞑想をし、慈悲の心で満たされれば怒りも芽生えない、ということになります。怒りとはワガママの境地です。まさに、他者の幸福を心から願い喜ぶ慈悲とは真逆と言えます。
慈悲を善く表しているように思われますが、慈悲は等しく、どちらの形態の仏教の大きな柱なのです。慈悲がお釈迦様の時代からあったことは既に記しましたが、上部座仏教に伝わるパーリ仏典には、慈悲瞑想なる修行法が記されています。「人間だけでなく、全ての生物(衆生)が幸福であるように」という慈悲の基本精神を見つめ、瞑想する修行です。「自分の子供を守るように、色々な命を守り救いましょう」とも書かれていますが、できるところからコツコツと。初めに、自分自身の幸福を願います。
次に、幸福を得る対象を他者へと移行。つまり、他者の幸福を願う瞑想に写るわけです。ここでは「幸せになって」と思いやすい、大切な人が対象になります。続いてに全ての衆生の幸福を祈るようになりますが、ここで終わりじゃありません。仏弟子だって「アンニャロ、気に食わない」という人もいるでしょう。そんな人の幸福も願うのが慈悲瞑想なのです。
お釈迦様は息子で十大弟子の一人、ラーフラにこの慈悲瞑想についてこう語りました。「四無量心の瞑想をしなさい。そうすれば、怒りだって残忍な心だって芽生えないから」慈悲の対極にあるもの、それは仏教の三大煩悩こと三業の一つ、瞋恚(怒り)です。従って、慈悲瞑想をし、慈悲の心で満たされれば怒りも芽生えない、ということになります。怒りとはワガママの境地です。まさに、他者の幸福を心から願い喜ぶ慈悲とは真逆と言えます。
まとめ

いくらか優しくすることはできても、他人の為にそこまでできるだろうか?と思う人もいるでしょう。しかし無理に怒りを抑え込むのではなく、そのような気持ちを起こさせないようにするのが慈悲です。「誰かの為に何かできるかな?」という気持ちが少しでもあれば、慈悲を実践できるでしょう。人は誰しも慈悲の体現者、菩薩なのですから。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

