望郷の詩人【阿倍仲麻呂】中国での交友関係がすごい!
関連キーワード

“天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも”
(天をふり仰いで見れば月がのぼっている。あの月は、(奈良の)春日の三笠山に登っていた月と同じものだろうか)
百人一首にも納められているこの有名な和歌を詠んだのは、阿部仲麻呂です。遣唐使として唐に渡りそのまま帰国することなく生涯を閉じた彼は、「望郷の詩人」とも呼ばれています。
日本を恋しく思う反面、唐に自分の居場所を見つけ活躍していた阿倍仲麻呂。今回はそんな阿倍仲麻呂の唐での日々と豊かな交友関係についてご紹介していきたいと思います。
(天をふり仰いで見れば月がのぼっている。あの月は、(奈良の)春日の三笠山に登っていた月と同じものだろうか)
百人一首にも納められているこの有名な和歌を詠んだのは、阿部仲麻呂です。遣唐使として唐に渡りそのまま帰国することなく生涯を閉じた彼は、「望郷の詩人」とも呼ばれています。
日本を恋しく思う反面、唐に自分の居場所を見つけ活躍していた阿倍仲麻呂。今回はそんな阿倍仲麻呂の唐での日々と豊かな交友関係についてご紹介していきたいと思います。
仲麻呂、遣唐使として唐に渡る
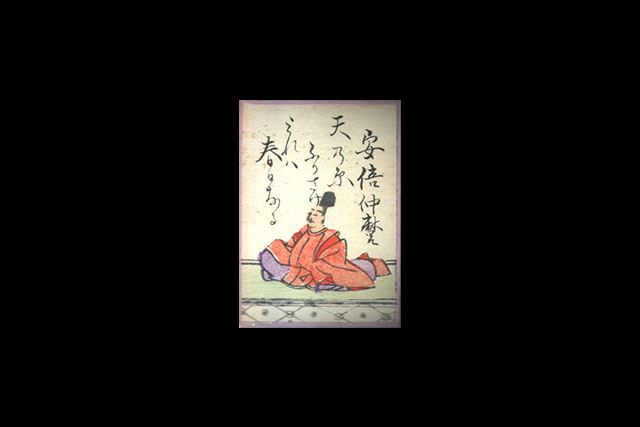
717年、557人もの人を乗せて第9次遣唐使船が日本を発ちました。その中には、希望に燃えた若き秀才たちも数多く同乗し、帰国後日本の律令体制の確立に大きな貢献をする吉備真備や玄昉、そして日本人でありながら唐朝廷の高官として活躍する阿倍仲麻呂の姿がありました。
無事唐に就いた阿倍仲麻呂は、太学という官立の高等教育機関で学び、官僚登用試験である「科挙(かきょ)」に合格します。科挙は中国人でも大変難しい試験で合格するとエリート官僚への道が開けました。そして玄宗皇帝に仕え重用されます。唐朝廷で官僚の道を歩き始めた阿倍仲麻呂は、「晁衡(ちょうこう)」という唐名を得ます。次々と学問・文学分野の官職に付き、文化の華開く朝廷内で唐の詩人たちとの交流が始まりました。
唐文化の隆盛期に、日本と唐の若者はお互い刺激をしあいながら成長していったのかもしれません。
無事唐に就いた阿倍仲麻呂は、太学という官立の高等教育機関で学び、官僚登用試験である「科挙(かきょ)」に合格します。科挙は中国人でも大変難しい試験で合格するとエリート官僚への道が開けました。そして玄宗皇帝に仕え重用されます。唐朝廷で官僚の道を歩き始めた阿倍仲麻呂は、「晁衡(ちょうこう)」という唐名を得ます。次々と学問・文学分野の官職に付き、文化の華開く朝廷内で唐の詩人たちとの交流が始まりました。
唐文化の隆盛期に、日本と唐の若者はお互い刺激をしあいながら成長していったのかもしれません。
唐での交友関係
仲麻呂がとくに親しく交流をしていたのは、日本でも有名な李白や王維などの唐詩人です。唐のずっと後世に編纂された「全唐詩」という900巻にも及ぶ漢詩集に、この時代の詩人たちが仲麻呂のことを詠んだ歌が多く残っています。
ここで、仲麻呂王維と李白について、少し紹介しておきましょう。
【王維】
唐が全盛を誇った、盛唐時代を代表する詩人。自然を読み込んだ優雅で静謐な作風から「詩仏」と呼ばれました。また、詩のみならず画、書、音楽と多彩な才能を表した王維は、水墨画にすぐれ後世の詩人であり書家でもある蘇軾に「詩中に画あり、画中に詩あり」と高く評価されています。
【李白】
同時代の杜甫と共に、中国詩史上において最高の存在として君臨しています。「詩仙」と呼ばれており、日本でも“白髪三千丈”の書きだしで有名な「秋浦歌」や“朝に辞す白帝 彩雲の間”と始まる「早発白帝城」など、国語の教科書に載っている詩も多くあります。
ここで、仲麻呂王維と李白について、少し紹介しておきましょう。
【王維】
唐が全盛を誇った、盛唐時代を代表する詩人。自然を読み込んだ優雅で静謐な作風から「詩仏」と呼ばれました。また、詩のみならず画、書、音楽と多彩な才能を表した王維は、水墨画にすぐれ後世の詩人であり書家でもある蘇軾に「詩中に画あり、画中に詩あり」と高く評価されています。
【李白】
同時代の杜甫と共に、中国詩史上において最高の存在として君臨しています。「詩仙」と呼ばれており、日本でも“白髪三千丈”の書きだしで有名な「秋浦歌」や“朝に辞す白帝 彩雲の間”と始まる「早発白帝城」など、国語の教科書に載っている詩も多くあります。
仲麻呂、ついに帰国を許される

733年、遣唐使船が来唐した際、玄宗皇帝に帰国を願い出たものの許されず、そのまま唐の高官であり続けます。このとき、共に日本から渡ってきた吉備真備と玄昉は帰国します。
そして752年、第12次遣唐使船が唐にやってきます。仲麻呂が唐に来てから35年の歳月が経っていました。皇帝に再び帰国を願い出ると今度は許され、ついに日本に帰ることが決まりました。このとき、王維は別れを惜しみ、「秘書晁衡の日本国へ還るを送る」という長い詩を読んでいます。
ところが、仲麻呂の乗った船は嵐にあい、遭難してしまいます。
現在のベトナムのあたりに漂着し、命を取り留めた仲麻呂は、その後長安へ戻ります。
このとき、長安には仲麻呂が死亡した、との誤報が流れます。李白は非常に悲しみ追悼の「哭晁卿衡」という七言絶句を作りました。友の死を嘆く美しくも悲しい慟哭に胸が締め付けられる思いです。
『 哭晁卿衡 李白 』
“日本晁卿辞帝都
(日本の晁卿は帝都長安を離れ)“
“征帆一片遶蓬壷
(帆を張った船は蓬莱山をめぐって行った)
“明月不帰沈碧海”
(明月のような君は青い海に沈んで帰らず)
“白雲愁色満蒼梧”
(白い雲が浮かび憂いが蒼梧に満ちている)
この後、長安に戻った仲麻呂は再び官職に戻ります。結局二度と日本の地を踏むことなく、770年73歳で亡くなりました。
現在の中国陝西省西安市の公園に、阿倍仲麻呂の記念碑があります。
日中関係の曖昧な昨今、両国の友好に尽くした仲麻呂の姿は現代の人々にどのように映っているのでしょうか。
そして752年、第12次遣唐使船が唐にやってきます。仲麻呂が唐に来てから35年の歳月が経っていました。皇帝に再び帰国を願い出ると今度は許され、ついに日本に帰ることが決まりました。このとき、王維は別れを惜しみ、「秘書晁衡の日本国へ還るを送る」という長い詩を読んでいます。
ところが、仲麻呂の乗った船は嵐にあい、遭難してしまいます。
現在のベトナムのあたりに漂着し、命を取り留めた仲麻呂は、その後長安へ戻ります。
このとき、長安には仲麻呂が死亡した、との誤報が流れます。李白は非常に悲しみ追悼の「哭晁卿衡」という七言絶句を作りました。友の死を嘆く美しくも悲しい慟哭に胸が締め付けられる思いです。
『 哭晁卿衡 李白 』
“日本晁卿辞帝都
(日本の晁卿は帝都長安を離れ)“
“征帆一片遶蓬壷
(帆を張った船は蓬莱山をめぐって行った)
“明月不帰沈碧海”
(明月のような君は青い海に沈んで帰らず)
“白雲愁色満蒼梧”
(白い雲が浮かび憂いが蒼梧に満ちている)
この後、長安に戻った仲麻呂は再び官職に戻ります。結局二度と日本の地を踏むことなく、770年73歳で亡くなりました。
現在の中国陝西省西安市の公園に、阿倍仲麻呂の記念碑があります。
日中関係の曖昧な昨今、両国の友好に尽くした仲麻呂の姿は現代の人々にどのように映っているのでしょうか。
もしも、仲麻呂が帰国していたら?

阿部仲麻呂の乗った船がもしも、順調に航海をすすめ無事に帰国していたら、どうなっていたでしょうか。少し想像してみましょう。
仲麻呂が帰国のため唐を離れたのは753年12月。
そのころの日本は、天平時代と呼ばれ、聖武天皇の治世にあたります。災害や疫病が流行し、それに呼応するように仏教文化が花咲いた時期です。聖武天皇による度重なる遷都や大仏建立、国分寺国分尼寺の造営により、民衆は疲弊し都市は荒廃していました。朝廷内も藤原氏の専横が始まっています。
そんな時に、大帝国唐の高官として活躍していた壮年の阿倍仲麻呂が帰国していたとしたら。日本の朝廷は仲麻呂の才覚を持て余したかもしれませんね。新たな権力闘争の火種になったり、場合によっては命を狙われる可能性もあります。考え過ぎでしょうか。
IFを想像してみるのも、歴史の楽しみ方の1つ。みなさんはいかがでしょうか。
仲麻呂が帰国のため唐を離れたのは753年12月。
そのころの日本は、天平時代と呼ばれ、聖武天皇の治世にあたります。災害や疫病が流行し、それに呼応するように仏教文化が花咲いた時期です。聖武天皇による度重なる遷都や大仏建立、国分寺国分尼寺の造営により、民衆は疲弊し都市は荒廃していました。朝廷内も藤原氏の専横が始まっています。
そんな時に、大帝国唐の高官として活躍していた壮年の阿倍仲麻呂が帰国していたとしたら。日本の朝廷は仲麻呂の才覚を持て余したかもしれませんね。新たな権力闘争の火種になったり、場合によっては命を狙われる可能性もあります。考え過ぎでしょうか。
IFを想像してみるのも、歴史の楽しみ方の1つ。みなさんはいかがでしょうか。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

