日本人はなぜこんなにも【源義経】に惹かれるのか。「判官びいき」の心理とは
関連キーワード

鎌倉時代に生きそして散った武者【源義経】。強い武将だったものの実の兄に疎まれ、さらには味方の裏切りにあり命を落としたその生涯から、悲劇のヒーローというイメージが定着しています。激動の生きざまは後世の多くの創作にインスピレーションを与えました。
「判官びいき」という言葉があることでも分かるように、私たち日本人は「源義経」が好きです。それはいったいどうしてでしょうか。義経の生涯を追いつつ、私たちが義経に惹かれる理由を一緒に考えていきましょう。
「判官びいき」という言葉があることでも分かるように、私たち日本人は「源義経」が好きです。それはいったいどうしてでしょうか。義経の生涯を追いつつ、私たちが義経に惹かれる理由を一緒に考えていきましょう。
源義経の一生<ダイジェスト版>
源義経は、1159年、平治の乱がおこった年に9男として誕生します。父は源義朝、母は常磐御前です。平治の乱により、父、義朝は討ち死にしてしまいます。母の常磐は幼名牛若といった義経と、今若、乙若という2人の兄と共に大和へ逃れます。11歳の義経は鞍馬寺に入りますが、出家を嫌い、奥州の藤原秀衡を頼って平泉へ下ります。
1180年義経21歳の時、打倒平氏を掲げた兄頼朝が東国で挙兵します(治承。寿永の乱)それに呼応して義経も頼朝の元へと馳せ参じました。一の谷、屋島、壇ノ浦と快進撃をかさね、平氏を滅ぼします。
しかし、強すぎる身内はいずれに身の破滅を招くとばかりに、頼朝は義経を疎み、ついには義経討伐命が下されました。朝的となった義経はかつて過ごした奥州平泉を再び頼ります。
しかし、義経を庇護していた藤原秀衡が亡くなり、子の泰衡の代になると状況は一変。頼朝の追求に秀衡は義経が居住していた衣川館を襲撃、義経や妻子従者を自害に追い込みました。義経は31歳でその命を散らせたのです。
平家を滅ぼした源氏のヒーローから一転、身内と信じた人の裏切りに合い自害とは・・・悲劇のヒーローだ、ということがよく分かります。
1180年義経21歳の時、打倒平氏を掲げた兄頼朝が東国で挙兵します(治承。寿永の乱)それに呼応して義経も頼朝の元へと馳せ参じました。一の谷、屋島、壇ノ浦と快進撃をかさね、平氏を滅ぼします。
しかし、強すぎる身内はいずれに身の破滅を招くとばかりに、頼朝は義経を疎み、ついには義経討伐命が下されました。朝的となった義経はかつて過ごした奥州平泉を再び頼ります。
しかし、義経を庇護していた藤原秀衡が亡くなり、子の泰衡の代になると状況は一変。頼朝の追求に秀衡は義経が居住していた衣川館を襲撃、義経や妻子従者を自害に追い込みました。義経は31歳でその命を散らせたのです。
平家を滅ぼした源氏のヒーローから一転、身内と信じた人の裏切りに合い自害とは・・・悲劇のヒーローだ、ということがよく分かります。
判官びいきの心理とは
判官びいきとは、と辞書で調べてみると、“源義経のような不遇な英雄に同情し、贔屓すること。また、弱い者や負けた者を第三者がひいきすること”とあります(旺文社・国語辞典)。
素晴らしい働きをしたのに、良かれと思ってしたのに、いじめられちゃって可愛そう!という心理ですね。ちなみに判官とは、義経の役職名に由来します。
実は、よく資料を読んでみると、勝手なふるまいや越権行為、横暴な態度など、義経も頼朝の不評を買うようなことをしているようです。それでも、横暴な態度を取ったことを頼朝に報告した梶原景時という人物や、追悼令を出した頼朝も「自分の身可愛さに、義経を利用するだけしてから討伐した、肝っ玉の小さいやつ」みたいな印象になってしまっています。
その理由はどうやら、吾妻鏡という歴史書にあるようです。吾妻鏡は鎌倉幕府の編纂によって作成されましたが、頼朝の義父である北条氏の立場から書かれたものです。梶原家を滅亡に追い込んだ北条氏が正当化されるには、梶原景時を悪役としなくてはなりません。すると相対的に義経が善玉化してくのですね。このようにして判官びいきの概念が生まれていきました。
素晴らしい働きをしたのに、良かれと思ってしたのに、いじめられちゃって可愛そう!という心理ですね。ちなみに判官とは、義経の役職名に由来します。
実は、よく資料を読んでみると、勝手なふるまいや越権行為、横暴な態度など、義経も頼朝の不評を買うようなことをしているようです。それでも、横暴な態度を取ったことを頼朝に報告した梶原景時という人物や、追悼令を出した頼朝も「自分の身可愛さに、義経を利用するだけしてから討伐した、肝っ玉の小さいやつ」みたいな印象になってしまっています。
その理由はどうやら、吾妻鏡という歴史書にあるようです。吾妻鏡は鎌倉幕府の編纂によって作成されましたが、頼朝の義父である北条氏の立場から書かれたものです。梶原家を滅亡に追い込んだ北条氏が正当化されるには、梶原景時を悪役としなくてはなりません。すると相対的に義経が善玉化してくのですね。このようにして判官びいきの概念が生まれていきました。
多くの創作を生んだ、キャラクターとしての「源義経」

悲劇のヒーロー義経像が、国民に浸透していった理由の一つに忘れてはならない物語があります。それは「義経記」と呼ばれる軍記物語です。軍記ものとはいえ、内容は義経の生涯に厚くページが割かれており史実とフィクションが混じり合った物語となっています。歴史的資料としての信憑性はあまり期待できないのですが、多くの義経に関する創作物はこの「義経記」の人物イメージを参考にしていると言われています。歌舞伎や人形浄瑠璃、能などの演目にも、「判官もの」というジャンルがあるくらいです。
ここで、1人の哲学者の言葉を思い出します。
「悲劇が観客の心に恐れと憐れみの感情を呼び起こすことで、精神的な浄化・カタルシスを得ることができる―」古代ギリシャの哲学者アリストテレスの「悲劇論」の中の一節です。
また、精神科医のフロイトも「悲惨な話を聞いて泣くことで心理的浄化を得る」といっています。
たしかに、私たちは義経の悲劇的な話を聞いてカタルシスを得ているのかもしれません。
ここで、1人の哲学者の言葉を思い出します。
「悲劇が観客の心に恐れと憐れみの感情を呼び起こすことで、精神的な浄化・カタルシスを得ることができる―」古代ギリシャの哲学者アリストテレスの「悲劇論」の中の一節です。
また、精神科医のフロイトも「悲惨な話を聞いて泣くことで心理的浄化を得る」といっています。
たしかに、私たちは義経の悲劇的な話を聞いてカタルシスを得ているのかもしれません。
北方に根強く残る義経「生存説」

義経はモンゴルに渡ってチンギス・ハーンになった、という話を聞いたことはありませんか?ほかにも、アイヌの村に救われて伝説の英雄になった、だとか、北海道に義経神社がある、とかロシアで義経の家紋が発見されたとか・・・調べてみると本当にたくさんさまざまな生存説があるようです。
この生存説の多さは、やはり「義経に死なないでいてほしかった」という判官びいきの表れだと見ることができます。まだ若くして潔く散っていった姿にも、もちろん票が集まります。あの衣川で泰衡軍に攻められたとき、うまく立ち回って泰衡を懐柔することができたとしたら?敵の隙をついて、逃げ延びることができたら?おそらくこれほどの人気はなかったことでしょう。
「滅びの美学」というなんとも耳に甘くシュールな言葉が日本にはあります。義経の太く短い生涯に、まさに日本人は「美」を見出すのでしょう。
この生存説の多さは、やはり「義経に死なないでいてほしかった」という判官びいきの表れだと見ることができます。まだ若くして潔く散っていった姿にも、もちろん票が集まります。あの衣川で泰衡軍に攻められたとき、うまく立ち回って泰衡を懐柔することができたとしたら?敵の隙をついて、逃げ延びることができたら?おそらくこれほどの人気はなかったことでしょう。
「滅びの美学」というなんとも耳に甘くシュールな言葉が日本にはあります。義経の太く短い生涯に、まさに日本人は「美」を見出すのでしょう。








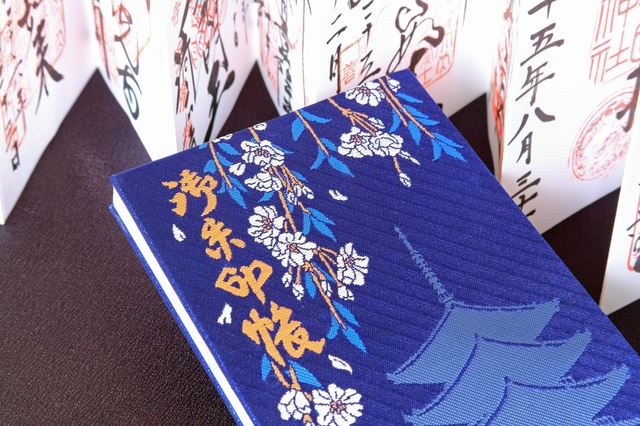













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

