身分制度の否定!武士のアイデンティティがはく奪された「廃刀令」
関連キーワード

近年「刀剣」がブームですね。津々浦々の博物館では刀剣展が催され、一見硬派なイメージとは裏腹に、ゲームやアニメのモチーフとして取り上げられることもあります。
今でこそ鑑賞用として人気の刀剣ですが、長い日本の歴史の中で見る刀剣は「武士だけに許された特別な持ち物」として彼らの矜持を支えていた存在でもあります。
今でこそ鑑賞用として人気の刀剣ですが、長い日本の歴史の中で見る刀剣は「武士だけに許された特別な持ち物」として彼らの矜持を支えていた存在でもあります。

日本に「武士」というもの台頭し始めたのは今から約1200年も前、奈良時代です。743年に墾田永年私財法という「開拓した土地は永遠に所有者のものですよ」という法令が出されてから、荘園が発達しました。そして荘園で得た領地やその財を守るためにつくられた自警団が武士の始まりです。
それからの長い間、武士は戦うための武器として刀剣を携えてきました。同時に弓矢や槍などの武器も確かにありましたが、武士たるもの腰に刀を帯びるスタイルは変わりませんでした。
戦国時代を収めた徳川家康が幕府を開いた江戸時代になると、大きな内戦も少なくなり武士が実質的な戦闘員である必要性がなくなってきました。代わりに、確固たる身分制度が形成され、武士とは民の上に立つ高い身分として保証されていくことになります。まさに刀剣は、武器というよりも「武士身分の象徴」としての色合いが強くなっていきました。
それからの長い間、武士は戦うための武器として刀剣を携えてきました。同時に弓矢や槍などの武器も確かにありましたが、武士たるもの腰に刀を帯びるスタイルは変わりませんでした。
戦国時代を収めた徳川家康が幕府を開いた江戸時代になると、大きな内戦も少なくなり武士が実質的な戦闘員である必要性がなくなってきました。代わりに、確固たる身分制度が形成され、武士とは民の上に立つ高い身分として保証されていくことになります。まさに刀剣は、武器というよりも「武士身分の象徴」としての色合いが強くなっていきました。
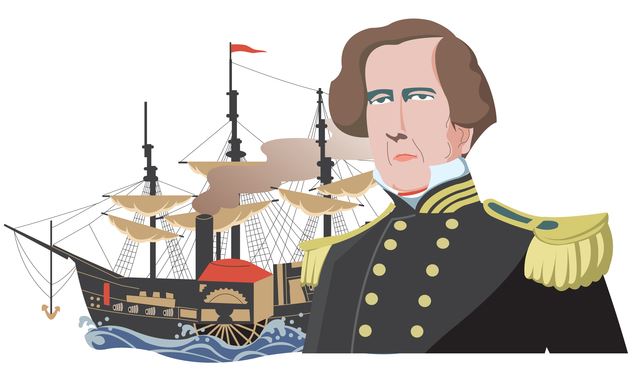
1583年、アメリカのペリー提督率いる黒船が来航しました。日本人がいままで見たこともないほどの巨大な機関船から聞こえたその砲音は、鎖国制度で守られた島国を無理やり目覚めさせ、太平の江戸時代の終焉を告げるかのようでした。以来、幕府の弱体化が問題視されていくようになります。弱腰外交の幕府にはもう任せられない!という気運がますます高まってきたのです。
やがて明治維新を経て訪れた明治時代では、西洋式の近代化が急速に進み、江戸時代に見られた士・農・工・商という明確な線引きのあった身分制度は実質上瓦解します。身分ではなく法の下で四民は平等とされたのです。
廃刀令が出されたのは、明治9年。これまで何百年もの歳月をかけて守り続けてきた「武士」そのものが、否定された瞬間でした。いつでも使える状態で武器を持っているというのは、外国人からは「蛮習」と捉えられていたことも関係しています。
当然、士族の間では反発も大きく四民平等に反対する動きもみられました。新しい政府の元で行き場と矜持を失くしてしまった士族たちが武力蜂起した「神風連の乱」「秋月の乱」「萩の乱」などの反乱が頻発し、ついには最後の内戦として知られる「西南戦争」へと繋がっていきました。
やがて明治維新を経て訪れた明治時代では、西洋式の近代化が急速に進み、江戸時代に見られた士・農・工・商という明確な線引きのあった身分制度は実質上瓦解します。身分ではなく法の下で四民は平等とされたのです。
廃刀令が出されたのは、明治9年。これまで何百年もの歳月をかけて守り続けてきた「武士」そのものが、否定された瞬間でした。いつでも使える状態で武器を持っているというのは、外国人からは「蛮習」と捉えられていたことも関係しています。
当然、士族の間では反発も大きく四民平等に反対する動きもみられました。新しい政府の元で行き場と矜持を失くしてしまった士族たちが武力蜂起した「神風連の乱」「秋月の乱」「萩の乱」などの反乱が頻発し、ついには最後の内戦として知られる「西南戦争」へと繋がっていきました。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

