三重県伊賀市生まれの松尾芭蕉 忍者説もあるその生涯とは
関連キーワード

「日本人なら知らない人はいない」と言っても過言ではないほど有名な俳人・松尾芭蕉。
伊賀国(現在の三重県伊賀市)生まれである松尾芭蕉は偉大な俳人であるだけではなく、実は忍者であったとされる隠密説や江戸幕府のスパイだったとされる説もあるほど謎に包まれてる人物でもあります。
今回は、そんな松尾芭蕉の生涯や作品の魅力、出身地について紹介していきましょう。
伊賀国(現在の三重県伊賀市)生まれである松尾芭蕉は偉大な俳人であるだけではなく、実は忍者であったとされる隠密説や江戸幕府のスパイだったとされる説もあるほど謎に包まれてる人物でもあります。
今回は、そんな松尾芭蕉の生涯や作品の魅力、出身地について紹介していきましょう。
世界に知られている松尾芭蕉の俳句
松尾芭蕉と聞くと代表作「奥の細道」を連想する方も多いと思います。そもそも松尾芭蕉とは今ある俳句の元である「俳諧」を芸術的に完成させ、「蕉風」という句風を確立させた江戸時代前期の人物です。よく知られた「芭蕉」という名は、実は俳号という俳人が名乗る雅号(別名)であり、彼自身の本名は松尾忠右衛門宗房と言います。
そんな松尾芭蕉が初めて俳句を詠んだのは19歳の時だと言われています。芭蕉は29歳で発句集「貝おほひ」を伊勢上野天満宮に奉納した後、伊勢の国から江戸へと渡り、多くの俳人たちと交流を持ちながらたくさんの俳句を詠んだそうです。そして1689年、芭蕉は「奥の細道」の旅へと出発し、諸国を回りながら代表作となる多くの俳句を詠んだとされています。「夏草や 兵どもが 夢の跡」「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」などの有名な俳句もこの時期に詠まれたものとなります。
また、芭蕉が詠んだ俳句の中でも「古池や 蛙(かわず)飛び込む 水の音」という作品は特に有名ですよね。こちらの俳句のように、聞くと頭の中で自然とその情景がイメージできるような親しみやすさも芭蕉の作品の魅力の一つと言えます。
ちなみに松尾芭蕉は日本のみならず、世界的に有名な俳人でもあります。実際に海外の教科書でも松尾芭蕉は多く取り上げられているほか、海外で発行された小説に松尾芭蕉をモチーフにしたキャラクターが登場するものもいくつか存在します。
そんな松尾芭蕉が初めて俳句を詠んだのは19歳の時だと言われています。芭蕉は29歳で発句集「貝おほひ」を伊勢上野天満宮に奉納した後、伊勢の国から江戸へと渡り、多くの俳人たちと交流を持ちながらたくさんの俳句を詠んだそうです。そして1689年、芭蕉は「奥の細道」の旅へと出発し、諸国を回りながら代表作となる多くの俳句を詠んだとされています。「夏草や 兵どもが 夢の跡」「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」などの有名な俳句もこの時期に詠まれたものとなります。
また、芭蕉が詠んだ俳句の中でも「古池や 蛙(かわず)飛び込む 水の音」という作品は特に有名ですよね。こちらの俳句のように、聞くと頭の中で自然とその情景がイメージできるような親しみやすさも芭蕉の作品の魅力の一つと言えます。
ちなみに松尾芭蕉は日本のみならず、世界的に有名な俳人でもあります。実際に海外の教科書でも松尾芭蕉は多く取り上げられているほか、海外で発行された小説に松尾芭蕉をモチーフにしたキャラクターが登場するものもいくつか存在します。
松尾芭蕉の出生地である伊賀国とは
松尾芭蕉の出身地である伊賀上野の赤坂は、今でいう三重県伊賀市上野赤坂町にあたります。
伊賀国と言えば有名な忍者の流派である「伊賀流忍者」の本拠地であったことでも有名ですよね。実は芭蕉自身も伊賀流忍者だったという説も存在します。
なぜなら「奥の細道」の旅において45歳の芭蕉が歩いた距離は5か月間でおよそ2400kmという、並大抵の人間では難しい距離だからです。
そもそも隠密だった芭蕉が、江戸幕府のスパイとして諸国の大名たちを監視していたのではないか?という説もあるほど、芭蕉は謎に包まれた人物でもあります。
伊賀国と言えば有名な忍者の流派である「伊賀流忍者」の本拠地であったことでも有名ですよね。実は芭蕉自身も伊賀流忍者だったという説も存在します。
なぜなら「奥の細道」の旅において45歳の芭蕉が歩いた距離は5か月間でおよそ2400kmという、並大抵の人間では難しい距離だからです。
そもそも隠密だった芭蕉が、江戸幕府のスパイとして諸国の大名たちを監視していたのではないか?という説もあるほど、芭蕉は謎に包まれた人物でもあります。
伊賀市にお越しの際は松尾芭蕉ゆかりの地も訪ねてみては

三重県伊賀市の上野公園内には、「芭蕉翁記念館」という松尾芭蕉に関する記念館もあります。
こちらでは松尾芭蕉が詠んだ連歌や俳諧に関する資料や芭蕉直筆の色紙、遺言状などの展示をご覧いただけます。
また、伊賀市には松尾芭蕉生誕300年を記念して建立された「俳聖殿」という見事な木造建築もあります。
こちらは旅姿の芭蕉をモチーフに建てられており、2010年には国の重要文化財にも指定されています。
ぜひ伊賀市へお越しの際は、芭蕉ゆかりの地も訪ねてみてください。
こちらでは松尾芭蕉が詠んだ連歌や俳諧に関する資料や芭蕉直筆の色紙、遺言状などの展示をご覧いただけます。
また、伊賀市には松尾芭蕉生誕300年を記念して建立された「俳聖殿」という見事な木造建築もあります。
こちらは旅姿の芭蕉をモチーフに建てられており、2010年には国の重要文化財にも指定されています。
ぜひ伊賀市へお越しの際は、芭蕉ゆかりの地も訪ねてみてください。







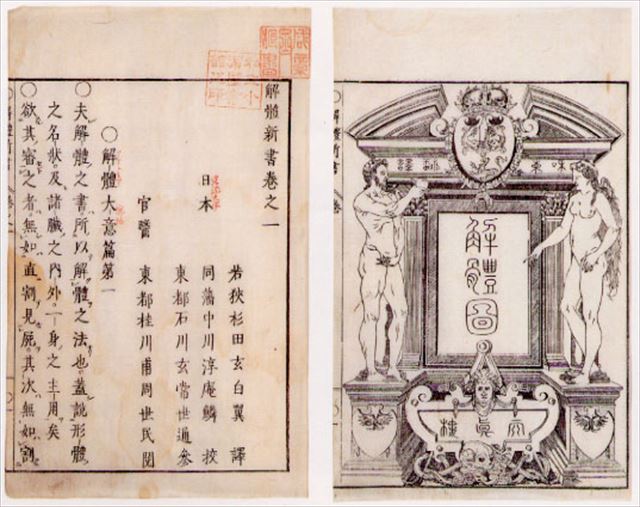














![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

