禅の心が生んだ、世界・宇宙を感じさせる枯山水の美学
関連キーワード

宗教心や仏教の修行とは関わりなく、単なる健康法や精神安定法と割り切って座禅を組んでいる人も多いようです。
実際、海外のビジネスマンは宗教とは関係なく、アジアの瞑想法ととらえています。カトリックの修道尼など、キリス教の指導者という立場の方にも、熱心な座禅愛好者がいるそうです。
せっかく座禅を組むのなら、せめて禅の心、禅の文化は大切にしたいもの。
禅文化に深く親しむことで、座禅を行うときに見えてくるものもあるかもしれません。禅文化の象徴として、独特なものに枯山水があります。枯山水の歴史や魅力から、禅文化を見てみましょう。
実際、海外のビジネスマンは宗教とは関係なく、アジアの瞑想法ととらえています。カトリックの修道尼など、キリス教の指導者という立場の方にも、熱心な座禅愛好者がいるそうです。
せっかく座禅を組むのなら、せめて禅の心、禅の文化は大切にしたいもの。
禅文化に深く親しむことで、座禅を行うときに見えてくるものもあるかもしれません。禅文化の象徴として、独特なものに枯山水があります。枯山水の歴史や魅力から、禅文化を見てみましょう。
ゲームボードで人気「枯山水」の魅力とは
New Games Orderというボードゲーム会社が発売した「枯山水」というゲームボードをご存じでしょうか。
プレイヤーが各自15マスのボードの中に、砂紋の一部が書かれたタイルや石を配置して、美しい庭づくりを競うゲームです。徳ポイントがあって「座禅」でボイントを獲得できたり、他人の石を奪うとポイントが減少したりもします。最終的には砂紋がつながっているなどの美しさで得点がきまります。勝敗を争うゲームながら、相手の石を奪うと徳が下がるというジレンマで悩んだり、ゲーム後には相手の庭の美しさをほめあったりなど、変わった楽しみ方ができると評判になりました。
枯山水は、このゲームボードで表現されているとおり、白砂と石組によって、水を用いないで山水の風景を象徴的に表現した庭園です。白砂に砂紋をつくって流れを表現し、石を配置して山を表現するなど、抽象的な表現で世界を作り出しています。峻烈な山々の谷合を流れおちてくる急流の済んだ川、大海にゆったりと浮かぶ小島の風景など、庭ごとにどんな風景が見えてくるのか、想像をめぐらすのも楽しいものです。
プレイヤーが各自15マスのボードの中に、砂紋の一部が書かれたタイルや石を配置して、美しい庭づくりを競うゲームです。徳ポイントがあって「座禅」でボイントを獲得できたり、他人の石を奪うとポイントが減少したりもします。最終的には砂紋がつながっているなどの美しさで得点がきまります。勝敗を争うゲームながら、相手の石を奪うと徳が下がるというジレンマで悩んだり、ゲーム後には相手の庭の美しさをほめあったりなど、変わった楽しみ方ができると評判になりました。
枯山水は、このゲームボードで表現されているとおり、白砂と石組によって、水を用いないで山水の風景を象徴的に表現した庭園です。白砂に砂紋をつくって流れを表現し、石を配置して山を表現するなど、抽象的な表現で世界を作り出しています。峻烈な山々の谷合を流れおちてくる急流の済んだ川、大海にゆったりと浮かぶ小島の風景など、庭ごとにどんな風景が見えてくるのか、想像をめぐらすのも楽しいものです。
平安時代に始まり、室町時代の禅寺で完成した枯山水
禅文化の象徴とされている「枯山水」。
実は平安時代の書物にも、すでに「枯山水」という記述があります。平安時代には後代のような石と白砂を主に構成された庭を作ることはありませんでしたが、庭園の一部、石の配置法としての「枯山水」が存在したようです。鎌倉期に入ると、乾山水、唐山水という記述もあります。現在残っているような枯山水の庭園が完成したのは、やはり室町時代になってからです。
かつて寺院の方丈の南側は、儀式か行われる場であるために清浄が求められ、白砂が敷き詰められていました。やがて儀式は外から広縁、室内にと移動することにより、南側は儀式の場の意味を失い、白砂を活かした園庭になりました。そこで座禅、瞑想の場である禅寺にふさわしい園庭として造園され、現在の枯山水の様式が完成しました。 室町時代の禅宗寺院、江戸時代の大名屋敷では、園内を散策しながら眺める回遊式庭園が多く作られています。中でも多く作られたのが、池を作り、そのまわりに園路をめぐらして、築山・橋・島に見立てた岩などを配置した池泉四季回遊庭園です。それとは対照的に、枯山水は散策して楽しむ庭ではなく、広縁から、室内から、眺めるための庭です。余分なものはそぎおとされながら、世界、宇宙を感じさせる広がりがあります。
白砂に描かれる砂紋には、漣紋・うねり紋・片男波紋・青海波紋・市松紋などさまざまな種類があります。
直線が水面の穏やかな流れを表しているのに対し、うねりや渦巻き、波頭など、急流の川面や大海の荒波の表情を表現しています。石組は当時の思想や祈りを象徴しています。大小の石を使った石組で仙人が住むという蓬莱山のある理想郷を表現したり、3つの石を釈迦三尊や不動三尊に見立て、仏教の世界観を表現するなどの工夫が凝らされています。方丈の中から、縁側から、別の部屋から、円窓からと、見る場所によって違う眺めに見えるのも枯山水の特徴です。円は尊いものという意味があり、円窓で切り取られた風景は理想の世界でもあります。
実は平安時代の書物にも、すでに「枯山水」という記述があります。平安時代には後代のような石と白砂を主に構成された庭を作ることはありませんでしたが、庭園の一部、石の配置法としての「枯山水」が存在したようです。鎌倉期に入ると、乾山水、唐山水という記述もあります。現在残っているような枯山水の庭園が完成したのは、やはり室町時代になってからです。
かつて寺院の方丈の南側は、儀式か行われる場であるために清浄が求められ、白砂が敷き詰められていました。やがて儀式は外から広縁、室内にと移動することにより、南側は儀式の場の意味を失い、白砂を活かした園庭になりました。そこで座禅、瞑想の場である禅寺にふさわしい園庭として造園され、現在の枯山水の様式が完成しました。 室町時代の禅宗寺院、江戸時代の大名屋敷では、園内を散策しながら眺める回遊式庭園が多く作られています。中でも多く作られたのが、池を作り、そのまわりに園路をめぐらして、築山・橋・島に見立てた岩などを配置した池泉四季回遊庭園です。それとは対照的に、枯山水は散策して楽しむ庭ではなく、広縁から、室内から、眺めるための庭です。余分なものはそぎおとされながら、世界、宇宙を感じさせる広がりがあります。
白砂に描かれる砂紋には、漣紋・うねり紋・片男波紋・青海波紋・市松紋などさまざまな種類があります。
直線が水面の穏やかな流れを表しているのに対し、うねりや渦巻き、波頭など、急流の川面や大海の荒波の表情を表現しています。石組は当時の思想や祈りを象徴しています。大小の石を使った石組で仙人が住むという蓬莱山のある理想郷を表現したり、3つの石を釈迦三尊や不動三尊に見立て、仏教の世界観を表現するなどの工夫が凝らされています。方丈の中から、縁側から、別の部屋から、円窓からと、見る場所によって違う眺めに見えるのも枯山水の特徴です。円は尊いものという意味があり、円窓で切り取られた風景は理想の世界でもあります。
枯山水のある寺で座禅体験
座禅を組むとともに、枯山水の庭園を鑑賞するというぜいたくな時間が過ごせる寺院をご紹介します。
臨済宗大徳寺頭塔大仙院
1509年に建立された大仙院は、大徳寺北派本庵として尊重されている名刹です。方丈南庭は白砂の中に2か所の砂盛を配したのみの簡潔な庭ですが、大海原を表現しています。大仙院書院前庭は開祖古岳宗亘が作ったもので、室町時代を代表する枯山水庭園といわれています。方丈にある「書院の間」の北から東にかけた狭い場所の中に、石組みによって蓬莱山から流れ落ちる滝が川となって海に流れ込む様子を表現したすぐれた庭です。植込まれた植木の姿が幽玄な趣を添えています。江戸時代後期の大仙院石庭の起こし絵図に基づいて1960年、現在の姿に復元されました。座禅会ではこの庭に向き合って、坐禅を組めます。
■住所:京都市北区紫野大徳寺町54-1
■アクセス:地下鉄北大路駅より市営バス10分大徳寺前下車すぐ
■座禅会:土曜座禅会
■開催日:毎週土日 17時〜18時(3月〜11月)16時30分〜17時30分(12月〜2月)
■予約・参加料:電話予約が必要/1000円
■お問い合わせ先:075-491-8346
■ホームページ:http://www.b-model.net/daisen-in/index.htm
臨済宗南禅寺派本山南禅寺
1291年、南禅寺は亀山法王の庇護の下、無石普門を開祖としで建立されました。京都五山や鎌倉五山よりもさらに上位、別格として位置付けられた由緒ある禅寺です。方丈庭園は小堀遠州作と伝えられる江戸時代初期の代表的枯山水庭園。東西に細長い地形に築地塀を巡らして樹木や苔が植えられており、手前側は白砂が敷き詰められた広い空間、左奥に大きな石組を配してあります。中でも横に寝かせた巨石が印象的です。俗に「虎の子渡し」の庭と呼ばれ、仏の悟りへの道を表しているとされています。小方丈庭園は別名「如心庭」。庭石が「心」字形に配置されていて、落ち着いた雰囲気の禅庭園となっています。
大方丈横の龍淵閣で行われる暁天座禅会のほか、第一日曜日の8時〜10時には南禅寺僧堂で胡禅会があります(075‐771‐3855に要確認。年会費2000円、当日会費200円)。一般観光客も気軽に宿泊できる宿坊「南禅会館」を利用すると便利です。方丈の拝観時間は8時40分〜17時(12月〜2月は16時30分)となっています。
■住所:京都府京都市左京区南禅寺福地町 龍淵閣
■アクセス:京都市営地下鉄蹴上駅下車徒歩10分
■座禅会:暁天座禅会
■開催日:毎月第2、第4日曜日(8月は休会 12月第4日曜、1月第2日曜は休会) 6時〜7時 (11月〜3月は6時30分から)
■予約・参加料:予約不要、参加料無料
■お問い合わせ先:075‐771‐0365
■URL:http://www.nanzen.net/index.html
臨済宗大徳寺頭塔大仙院
1509年に建立された大仙院は、大徳寺北派本庵として尊重されている名刹です。方丈南庭は白砂の中に2か所の砂盛を配したのみの簡潔な庭ですが、大海原を表現しています。大仙院書院前庭は開祖古岳宗亘が作ったもので、室町時代を代表する枯山水庭園といわれています。方丈にある「書院の間」の北から東にかけた狭い場所の中に、石組みによって蓬莱山から流れ落ちる滝が川となって海に流れ込む様子を表現したすぐれた庭です。植込まれた植木の姿が幽玄な趣を添えています。江戸時代後期の大仙院石庭の起こし絵図に基づいて1960年、現在の姿に復元されました。座禅会ではこの庭に向き合って、坐禅を組めます。
■住所:京都市北区紫野大徳寺町54-1
■アクセス:地下鉄北大路駅より市営バス10分大徳寺前下車すぐ
■座禅会:土曜座禅会
■開催日:毎週土日 17時〜18時(3月〜11月)16時30分〜17時30分(12月〜2月)
■予約・参加料:電話予約が必要/1000円
■お問い合わせ先:075-491-8346
■ホームページ:http://www.b-model.net/daisen-in/index.htm
臨済宗南禅寺派本山南禅寺
1291年、南禅寺は亀山法王の庇護の下、無石普門を開祖としで建立されました。京都五山や鎌倉五山よりもさらに上位、別格として位置付けられた由緒ある禅寺です。方丈庭園は小堀遠州作と伝えられる江戸時代初期の代表的枯山水庭園。東西に細長い地形に築地塀を巡らして樹木や苔が植えられており、手前側は白砂が敷き詰められた広い空間、左奥に大きな石組を配してあります。中でも横に寝かせた巨石が印象的です。俗に「虎の子渡し」の庭と呼ばれ、仏の悟りへの道を表しているとされています。小方丈庭園は別名「如心庭」。庭石が「心」字形に配置されていて、落ち着いた雰囲気の禅庭園となっています。
大方丈横の龍淵閣で行われる暁天座禅会のほか、第一日曜日の8時〜10時には南禅寺僧堂で胡禅会があります(075‐771‐3855に要確認。年会費2000円、当日会費200円)。一般観光客も気軽に宿泊できる宿坊「南禅会館」を利用すると便利です。方丈の拝観時間は8時40分〜17時(12月〜2月は16時30分)となっています。
■住所:京都府京都市左京区南禅寺福地町 龍淵閣
■アクセス:京都市営地下鉄蹴上駅下車徒歩10分
■座禅会:暁天座禅会
■開催日:毎月第2、第4日曜日(8月は休会 12月第4日曜、1月第2日曜は休会) 6時〜7時 (11月〜3月は6時30分から)
■予約・参加料:予約不要、参加料無料
■お問い合わせ先:075‐771‐0365
■URL:http://www.nanzen.net/index.html
絶対に訪れたい! 枯山水の庭園があるオススメの京都の寺院TOP5!!

『枯山水』とは、水をいっさい使わずに山水を表現している庭園のことです。
白砂の上には直線や曲線が描かれ、石が立っていたり横になったり……。
花や色を使っていないのに、華やかさを感じる不思議な庭園です。
お寺以外でもホテルの中庭や和食レストランの坪庭にあり、私たちの身近なところに枯山水があります。
しかし、そもそも枯山水はどうやって生まれたのかご存じですか?
そこで私たちを静寂へと導く枯山水の魅力や、オススメの京都の寺院をランキング形式でご紹介します!
そこで私たちを静寂へと導く枯山水の魅力や、オススメの京都の寺院をランキング形式でご紹介します!
ランキングの前に……なぜ、枯山水は生まれたのか?
枯山水はおもに、京都を中心とした禅宗寺院に多くあります。
枯山水の庭が造られるようになったのは、室町時代後期だと伝えられています。
室町時代は『北山文化』と『東山文化』が発展した時代です。 『北山文化』は、室町幕府第3代将軍・足利義満の造った金閣寺が代表格です。 新興の武家文化と伝統的な公家文化の融合した文化で、金閣寺の金閣は伝統的な寝殿造と禅宗寺院における禅宗様(寺院建築の様式のひとつ)のいい部分が合わさった造りになっています。 そして、『東山文化』は第8代将軍・義政が造った銀閣寺から発祥した文化です。 禅宗の精神の影響を受ける一方で、わび・さびが重んじられた文化で、銀閣寺も禅宗の影響を感じられる造りになっています。 ふたつの文化はあわせて、『室町文化』とよばれました。
そんな室町文化の中で枯山水はうまれました。 古来、日本の庭園は池を中心とした造りでした。池のほとりを歩いたり、船を浮かべて楽しむものだったのです。 それまであった一般的な建築様式が変化した中で、枯山水は新しくうまれた庭園でした。 『遊ぶ庭園』から、『ながめる庭園』へと変わっていったのです。 限られた敷地に水を用いらず、木と苔と石で表現できるように工夫されていった枯山水は、次第に寺院ごとに個性がうまれていきました。
室町時代は『北山文化』と『東山文化』が発展した時代です。 『北山文化』は、室町幕府第3代将軍・足利義満の造った金閣寺が代表格です。 新興の武家文化と伝統的な公家文化の融合した文化で、金閣寺の金閣は伝統的な寝殿造と禅宗寺院における禅宗様(寺院建築の様式のひとつ)のいい部分が合わさった造りになっています。 そして、『東山文化』は第8代将軍・義政が造った銀閣寺から発祥した文化です。 禅宗の精神の影響を受ける一方で、わび・さびが重んじられた文化で、銀閣寺も禅宗の影響を感じられる造りになっています。 ふたつの文化はあわせて、『室町文化』とよばれました。
そんな室町文化の中で枯山水はうまれました。 古来、日本の庭園は池を中心とした造りでした。池のほとりを歩いたり、船を浮かべて楽しむものだったのです。 それまであった一般的な建築様式が変化した中で、枯山水は新しくうまれた庭園でした。 『遊ぶ庭園』から、『ながめる庭園』へと変わっていったのです。 限られた敷地に水を用いらず、木と苔と石で表現できるように工夫されていった枯山水は、次第に寺院ごとに個性がうまれていきました。
オススメランキングをご紹介!!
○No.5! 高台寺圓徳院!!
高台寺は豊臣秀吉と妻・ねねの菩提寺として広く知られています。 塔頭寺院のひとつである圓徳院は、ねねが『高台院』として出家し、晩年の19年を過ごした場所です。
北庭には大きな岩があるのが特徴です。 まるで地面から生えているかのようで、息吹を感じ取れそうですよね。 北庭はもともと、秀吉が建てた伏見城の化粧御殿とその前庭を移築したものだと伝えられています。 そのときは枯山水の庭園ではなく、回遊式の庭だったのではないかと言われています。 この北庭は国の名勝にも指定されています。
また、南庭は白砂が広がっているのが特徴です。
高台寺は豊臣秀吉と妻・ねねの菩提寺として広く知られています。 塔頭寺院のひとつである圓徳院は、ねねが『高台院』として出家し、晩年の19年を過ごした場所です。
北庭には大きな岩があるのが特徴です。 まるで地面から生えているかのようで、息吹を感じ取れそうですよね。 北庭はもともと、秀吉が建てた伏見城の化粧御殿とその前庭を移築したものだと伝えられています。 そのときは枯山水の庭園ではなく、回遊式の庭だったのではないかと言われています。 この北庭は国の名勝にも指定されています。
また、南庭は白砂が広がっているのが特徴です。
北庭の力強さとは反対に、時間が止まったかのような静けさがあります。
北庭と南庭はどちらも紅葉の美しさは圧巻!
ねねが見ていた景色と変わらぬ美しさを、ぜひ堪能してみてください。
◇所在地
京都市東山区高台寺下河原町530
◇拝観料(高台寺と高台寺掌美術館)
・大人600円
・中高生250円
・小学生無料(ただし、父兄同伴)
※児童・小学生10名につき、1名以上の引率者をお願いします。
※大人団体(30名以上)500円
◇高台寺・高台寺掌美術館・圓徳院共通拝観券:900円
◇拝観時間
9:00〜17:30(17:00受付終了)
○No.4! 東福寺!!
東福寺は建長7年(1255年)に建てられたお寺で、19年もの歳月をかけて完成されました。 伽藍は現存最古のものだと言われています。 東福寺は本坊庭園はもちろんのこと、『龍吟庵』『光明院』『芬陀院』の塔頭寺院の庭園も有名です。 本坊庭園は2014年に国の名勝に指定されました。 広大な方丈の東西南北に庭が配されていて、このような庭園があるのは東福寺だけです。
東庭を表しているのは『北斗七星』で、円柱と白砂、苔と二重生垣によって表現されています。
◇所在地
京都市東山区高台寺下河原町530
◇拝観料(高台寺と高台寺掌美術館)
・大人600円
・中高生250円
・小学生無料(ただし、父兄同伴)
※児童・小学生10名につき、1名以上の引率者をお願いします。
※大人団体(30名以上)500円
◇高台寺・高台寺掌美術館・圓徳院共通拝観券:900円
◇拝観時間
9:00〜17:30(17:00受付終了)
○No.4! 東福寺!!
東福寺は建長7年(1255年)に建てられたお寺で、19年もの歳月をかけて完成されました。 伽藍は現存最古のものだと言われています。 東福寺は本坊庭園はもちろんのこと、『龍吟庵』『光明院』『芬陀院』の塔頭寺院の庭園も有名です。 本坊庭園は2014年に国の名勝に指定されました。 広大な方丈の東西南北に庭が配されていて、このような庭園があるのは東福寺だけです。
東庭を表しているのは『北斗七星』で、円柱と白砂、苔と二重生垣によって表現されています。
南庭は神仙思想を中心とした造りになっており、『蓬莱』『瀛州』『壺梁』『方丈』の四神仙島を石で表現しています。その周りには「八海」が砂紋で表わされています。
そして、五山が築山として表現されていて、広大です。
西庭は日本古来からある『市松模様』を、サツキの刈込と葛石で表現されています。
北庭は西庭より小さい市松模様の庭園が広がり、東北方向の谷に消えていく表現がなされています。
ひとつひとつの庭をみると、違う顔をみせています。
しかし、実は釈迦の出生から入滅までの8つの重要な段階を表す『釈迦八相成道』が表現されていることから、『八相の庭』と呼ばれています。
よく見てみると、ストーリー仕立ての構成になっているのです。
ぜひ訪れて、そのストーリーを実感してみてください!
◇所在地
京都市東山区本町15ー778
◇拝観時間
4〜10月末 9:00〜16:30(受付終了時間は16:00)
11〜12月初旬 8:30〜16:30(受付終了時間は16:00)
12月初旬〜3月末 9:00〜16:00(受付終了時間は15:30)
◇拝観料
通天橋・開山堂 大人400円(小中学生300円)
東福寺本坊庭園 大人400円(小中学生300円)
○No.3! 大徳寺大仙院!!
大徳寺は鎌倉時代末期に建てられ、大仙院は寺内にある塔頭寺院です。 永正6年(1509年)、大徳寺第76世住職の古岳宗亘によって創建されました。 方丈も庭も当時のままだといわれていて、500年も変わらぬ姿を私たちに見せてくれています。 このような庭園は大変貴重なものです。 また、千利休は生前からよく参拝していて、大仙院の庭を茶庭のヒントにしたと言われています。
ぜひ訪れて、そのストーリーを実感してみてください!
◇所在地
京都市東山区本町15ー778
◇拝観時間
4〜10月末 9:00〜16:30(受付終了時間は16:00)
11〜12月初旬 8:30〜16:30(受付終了時間は16:00)
12月初旬〜3月末 9:00〜16:00(受付終了時間は15:30)
◇拝観料
通天橋・開山堂 大人400円(小中学生300円)
東福寺本坊庭園 大人400円(小中学生300円)
○No.3! 大徳寺大仙院!!
大徳寺は鎌倉時代末期に建てられ、大仙院は寺内にある塔頭寺院です。 永正6年(1509年)、大徳寺第76世住職の古岳宗亘によって創建されました。 方丈も庭も当時のままだといわれていて、500年も変わらぬ姿を私たちに見せてくれています。 このような庭園は大変貴重なものです。 また、千利休は生前からよく参拝していて、大仙院の庭を茶庭のヒントにしたと言われています。
大仙院の庭は『蓬莱山』を起点としています。
蓬莱山は中国の神仙思想で不老不死の仙人が住んでいると言われています。
山からみて左側には滝を表す三段の石があります。
川を表した白砂が南下すると、ゆるやかな流れになり、『宝船(長船石)』が浮かんでいます。 宝船は蓬莱山の宝を運ぶ船のことです。
川を表した白砂が南下すると、ゆるやかな流れになり、『宝船(長船石)』が浮かんでいます。 宝船は蓬莱山の宝を運ぶ船のことです。
そして、南庭には『大海』が広がり、円錐形の砂盛が一対あるのが特徴です。庭は30坪あまりしかありませんが、仙境から海原まで表していて壮大です。
利休も愛した庭をぜひ、ご覧になってください。
◇所在地
京都市北区紫野大徳寺町54ー1
◇拝観時間
3〜11月 9:00〜17:00
12〜2月 9:00〜16:30
◇拝観料
大人(高校生以上)400円
小中学生270円
◇所在地
京都市北区紫野大徳寺町54ー1
◇拝観時間
3〜11月 9:00〜17:00
12〜2月 9:00〜16:30
◇拝観料
大人(高校生以上)400円
小中学生270円
○No.2! 建仁寺!!
京都五山のひとつである建仁寺は、建仁2年(1202年)に創建された、京都最古の禅宗寺院です。
建仁寺の方丈南庭は『大雄苑』とよばれています。
15個の石が配され、広がる白砂が特徴的です。
砂紋(砂に描かれた線)はうねったり、石組の周りを囲んでいます。
本当にそこに水が広がっているように感じます。
そして、本坊中庭にある『○△□乃庭』も必見です!

『○△□』とは、密教の六大思想のうちの水(○)、火(△)、地(□)のことで、左側にある書院には庭の語源となった『○△□』の掛け軸が飾られています。
○は木、△は庭の隅の形状、□は井戸で表されています。
また、本坊の中庭には『潮音庭』があります。
また、本坊の中庭には『潮音庭』があります。
こちらは大書院と小書院に囲まれ、四方向のどこから見ても眺められるのが特徴です。
『大雄苑』や『○△□乃庭』と違って苔や石があり、また雰囲気が変わります。
ゆるやかな白砂の流れや茂った苔の緑ををみていると、心がほっと落ち着きます。 ぜひ、訪れてみてください!
◇所在地
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
◇拝観料
大人500円 中高生300円
◇拝観時間
3〜10月末 10:00〜17:00(受付終了時間16:30)
11〜2月末 10:00〜16:30(受付終了時間16:00)
年末拝観休止 12月28日〜31日
○No.1! 龍安寺!!
やはり、枯山水の庭園といえば龍安寺でしょう!!
龍安寺は宝徳2年(1450年)に創建されました。
ユネスコの世界文化遺産にも登録され、外国人観光客がたくさん訪れています。
ゆるやかな白砂の流れや茂った苔の緑ををみていると、心がほっと落ち着きます。 ぜひ、訪れてみてください!
◇所在地
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
◇拝観料
大人500円 中高生300円
◇拝観時間
3〜10月末 10:00〜17:00(受付終了時間16:30)
11〜2月末 10:00〜16:30(受付終了時間16:00)
年末拝観休止 12月28日〜31日
○No.1! 龍安寺!!
やはり、枯山水の庭園といえば龍安寺でしょう!!
龍安寺は宝徳2年(1450年)に創建されました。
ユネスコの世界文化遺産にも登録され、外国人観光客がたくさん訪れています。
龍安寺の庭園は作者が不明だったり、石の配置の謎があったりと、訪れる人々を楽しませています。
配置の謎とは、庭園には大小15個の石が置かれていますが、どの角度から見ても1個の石が隠れて見えないようになっており、15個を数えられないという謎です。
訪れた人々は右へいったり、左へいったりして、石を数えています。
しかし、このような配置にした理由は、いまだに分かっていません。
また、この庭は『虎の子渡しの庭』や『七五三の庭』ともよばれています。 あるいは、中国の五岳や禅の五山を象徴している、『心』の字を配している、大海や雲海に浮かぶ島々や高峰を表している、などと言われており、いろんな解釈があります。 みる人によって受け止め方が違うため、あれやこれやと話しあうのもおもしろいかもしれません。
ぜひ、石の数を数えてみてくださいね!
◇所在地
京都市右京区龍安寺御陵下町13
◇拝観料
大人・高校生500円
小・中学生300円
◇拝観時間
3〜11月末 8:00〜17:00
12〜2月末 8:30〜16:30
いかがでしたか。
京都はとくに枯山水の庭園が多く、どの寺院を訪れてもみる人を圧倒させます。 枯山水は禅宗の影響を受けている中、日本人の細やかな配慮や思慮が織り込まれています。 そして、作者の主張を語る作品ではなく、みる人の感じ方で表情を変えていく……そんなアーティスティックが日本人のみならず、外国の人々をひきつける理由なのかもしれません。
時代が変わっても姿が変わらない枯山水。
ぜひ、京都へいった際には枯山水のある寺院へ訪れてみてください!
また、この庭は『虎の子渡しの庭』や『七五三の庭』ともよばれています。 あるいは、中国の五岳や禅の五山を象徴している、『心』の字を配している、大海や雲海に浮かぶ島々や高峰を表している、などと言われており、いろんな解釈があります。 みる人によって受け止め方が違うため、あれやこれやと話しあうのもおもしろいかもしれません。
ぜひ、石の数を数えてみてくださいね!
◇所在地
京都市右京区龍安寺御陵下町13
◇拝観料
大人・高校生500円
小・中学生300円
◇拝観時間
3〜11月末 8:00〜17:00
12〜2月末 8:30〜16:30
いかがでしたか。
京都はとくに枯山水の庭園が多く、どの寺院を訪れてもみる人を圧倒させます。 枯山水は禅宗の影響を受けている中、日本人の細やかな配慮や思慮が織り込まれています。 そして、作者の主張を語る作品ではなく、みる人の感じ方で表情を変えていく……そんなアーティスティックが日本人のみならず、外国の人々をひきつける理由なのかもしれません。
時代が変わっても姿が変わらない枯山水。
ぜひ、京都へいった際には枯山水のある寺院へ訪れてみてください!
座禅記事一覧はこちら
お寺での座禅体験で、静寂な空気に包まれてみる。
座禅の効果くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する
「あぐら」は室町時代までの正式な座り方だった!?座禅の姿勢「あぐら」と「結跏趺坐・半跏趺坐」似ているけど違う!
ビジネスマンにも人気!座禅朝晩の15分、座る時間が心と体を調える
こころとからだを見つめ、整える。座禅を体験するということ。
座禅の始まりは「座」り方から。正しい姿勢を知りましょう。
絶対に訪れたい! 枯山水の庭園があるオススメの京都の寺院TOP5!!

『枯山水』とは、水をいっさい使わずに山水を表現している庭園のことです。
白砂の上には直線や曲線が描かれ、石が立っていたり横になったり……。
花や色を使っていないのに、華やかさを感じる不思議な庭園です。
お寺以外でもホテルの中庭や和食レストランの坪庭にあり、私たちの身近なところに枯山水があります。
しかし、そもそも枯山水はどうやって生まれたのかご存じですか?
そこで私たちを静寂へと導く枯山水の魅力や、オススメの京都の寺院をランキング形式でご紹介します!
そこで私たちを静寂へと導く枯山水の魅力や、オススメの京都の寺院をランキング形式でご紹介します!
ランキングの前に……なぜ、枯山水は生まれたのか?
枯山水はおもに、京都を中心とした禅宗寺院に多くあります。
枯山水の庭がつくられるようになったのは、室町時代後期だと伝えられています。
室町時代は『北山文化』と『東山文化』が発展した時代です。 『北山文化』は、室町幕府第3代将軍・足利義満のつくった金閣寺が代表格です。 新興の武家文化と伝統的な公家文化の融合した文化で、金閣寺の金閣は伝統的な寝殿造と禅宗寺院における禅宗様(寺院建築の様式のひとつ)のいい部分が合わさった造りになっています。 そして、『東山文化』は第8代将軍・義政がつくった銀閣寺から発祥した文化です。 禅宗の精神の影響を受ける一方で、わび・さびが重んじられた文化で、銀閣寺も禅宗の影響を感じられる造りになっています。 ふたつの文化はあわせて、『室町文化』とよばれました。
そんな室町文化の中で枯山水はうまれました。 古来、日本の庭園は池を中心とした造りでした。池のほとりを歩いたり、船を浮かべて楽しむものだったのです。 それまであった一般的な建築様式が変化した中で、枯山水は新しくうまれた庭園でした。 『遊ぶ庭園』から、『ながめる庭園』へと変わっていったのです。 限られた敷地に水を用いらず、木と苔と石で表現できるように工夫されていった枯山水は、次第に寺院ごとに個性がうまれていきました。
室町時代は『北山文化』と『東山文化』が発展した時代です。 『北山文化』は、室町幕府第3代将軍・足利義満のつくった金閣寺が代表格です。 新興の武家文化と伝統的な公家文化の融合した文化で、金閣寺の金閣は伝統的な寝殿造と禅宗寺院における禅宗様(寺院建築の様式のひとつ)のいい部分が合わさった造りになっています。 そして、『東山文化』は第8代将軍・義政がつくった銀閣寺から発祥した文化です。 禅宗の精神の影響を受ける一方で、わび・さびが重んじられた文化で、銀閣寺も禅宗の影響を感じられる造りになっています。 ふたつの文化はあわせて、『室町文化』とよばれました。
そんな室町文化の中で枯山水はうまれました。 古来、日本の庭園は池を中心とした造りでした。池のほとりを歩いたり、船を浮かべて楽しむものだったのです。 それまであった一般的な建築様式が変化した中で、枯山水は新しくうまれた庭園でした。 『遊ぶ庭園』から、『ながめる庭園』へと変わっていったのです。 限られた敷地に水を用いらず、木と苔と石で表現できるように工夫されていった枯山水は、次第に寺院ごとに個性がうまれていきました。
オススメランキングをご紹介!!
○No.5! 高台寺圓徳院!!
高台寺は豊臣秀吉と妻・ねねの菩提寺として広く知られています。 塔頭寺院のひとつである圓徳院は、ねねが『高台院』として出家し、晩年の19年を過ごした場所です。
北庭には大きな岩があるのが特徴です。 まるで地面から生えているかのようで、息吹を感じ取れそうですよね。 北庭はもともと、秀吉が建てた伏見城の化粧御殿とその前庭を移築したものだと伝えられています。 そのときは枯山水の庭園ではなく、回遊式の庭だったのではないかといわれています。 この北庭は国の名勝にも指定されています。
また、南庭は白砂が広がっているのが特徴です。
高台寺は豊臣秀吉と妻・ねねの菩提寺として広く知られています。 塔頭寺院のひとつである圓徳院は、ねねが『高台院』として出家し、晩年の19年を過ごした場所です。
北庭には大きな岩があるのが特徴です。 まるで地面から生えているかのようで、息吹を感じ取れそうですよね。 北庭はもともと、秀吉が建てた伏見城の化粧御殿とその前庭を移築したものだと伝えられています。 そのときは枯山水の庭園ではなく、回遊式の庭だったのではないかといわれています。 この北庭は国の名勝にも指定されています。
また、南庭は白砂が広がっているのが特徴です。
北庭の力強さとは反対に、時間が止まったかのような静けさがあります。
北庭と南庭はどちらも紅葉の美しさは圧巻!
ねねが見ていた景色と変わらぬ美しさを、ぜひ堪能してみてください。
◇所在地
京都市東山区高台寺下河原町530
◇拝観料(高台寺と高台寺掌美術館)
・大人600円
・中高生250円
・小学生無料(ただし、父兄同伴)
※児童・小学生10名につき、1名以上の引率者をお願いします。
※大人団体(30名以上)500円
◇高台寺・高台寺掌美術館・圓徳院共通拝観券:900円
◇拝観時間
9:00〜17:30(17:00受付終了)
○No.4! 東福寺!!
東福寺は建長7年(1255年)に建てられたお寺で、19年もの歳月をかけて完成されました。 伽藍は現存最古のものだといわれています。 東福寺は本坊庭園はもちろんのこと、『龍吟庵』『光明院』『芬陀院』の塔頭寺院の庭園も有名です。 本坊庭園は2014年に国の名勝に指定されました。 広大な方丈の東西南北に庭が配されていて、このような庭園があるのは東福寺だけです。
東庭を表しているのは『北斗七星』で、円柱と白砂、苔と二重生垣によって表現されています。
◇所在地
京都市東山区高台寺下河原町530
◇拝観料(高台寺と高台寺掌美術館)
・大人600円
・中高生250円
・小学生無料(ただし、父兄同伴)
※児童・小学生10名につき、1名以上の引率者をお願いします。
※大人団体(30名以上)500円
◇高台寺・高台寺掌美術館・圓徳院共通拝観券:900円
◇拝観時間
9:00〜17:30(17:00受付終了)
○No.4! 東福寺!!
東福寺は建長7年(1255年)に建てられたお寺で、19年もの歳月をかけて完成されました。 伽藍は現存最古のものだといわれています。 東福寺は本坊庭園はもちろんのこと、『龍吟庵』『光明院』『芬陀院』の塔頭寺院の庭園も有名です。 本坊庭園は2014年に国の名勝に指定されました。 広大な方丈の東西南北に庭が配されていて、このような庭園があるのは東福寺だけです。
東庭を表しているのは『北斗七星』で、円柱と白砂、苔と二重生垣によって表現されています。
南庭は神仙思想を中心としたつくりになっており、『蓬莱』『瀛州』『壺梁』『方丈』の四神仙島を石で表現しています。その周りには「八海」が砂紋で表わされています。
そして、五山が築山として表現されていて、広大です。
西庭は日本古来からある『市松模様』を、サツキの刈込と葛石で表現されています。
北庭は西庭より小さい市松模様の庭園が広がり、東北方向の谷に消えていく表現がなされています。
ひとつひとつの庭をみると、違う顔をみせています。
しかし、実は釈迦の出生から入滅までの8つの重要な段階を表す『釈迦八相成道』が表現されていることから、『八相の庭』と呼ばれています。
よく見てみると、ストーリー仕立ての構成になっているのです。
ぜひ訪れて、そのストーリーを実感してみてください!
◇所在地
京都市東山区本町15ー778
◇拝観時間
4月〜10月末 9:00〜16:30(受付終了時間は16:00)
11月〜12月初旬 8:30〜16:30(受付終了時間は16:00)
12月初旬〜3月末 9:00〜16:00(受付終了時間は15:30)
◇拝観料
通天橋・開山堂 大人400円(小中学生300円)
東福寺本坊庭園 大人400円(小中学生300円)
○No.3! 大徳寺大仙院!!
大徳寺は鎌倉時代末期に建てられ、大仙院は寺内にある塔頭寺院です。 永正6年(1509年)、大徳寺第76世住職の古岳宗亘によって創建されました。 方丈も庭も当時のままだといわれていて、500年も変わらぬ姿を私たちに見せてくれています。 このような庭園は大変貴重なものです。 また、千利休は生前からよく参拝していて、大仙院の庭を茶庭のヒントにしたといいます。
ぜひ訪れて、そのストーリーを実感してみてください!
◇所在地
京都市東山区本町15ー778
◇拝観時間
4月〜10月末 9:00〜16:30(受付終了時間は16:00)
11月〜12月初旬 8:30〜16:30(受付終了時間は16:00)
12月初旬〜3月末 9:00〜16:00(受付終了時間は15:30)
◇拝観料
通天橋・開山堂 大人400円(小中学生300円)
東福寺本坊庭園 大人400円(小中学生300円)
○No.3! 大徳寺大仙院!!
大徳寺は鎌倉時代末期に建てられ、大仙院は寺内にある塔頭寺院です。 永正6年(1509年)、大徳寺第76世住職の古岳宗亘によって創建されました。 方丈も庭も当時のままだといわれていて、500年も変わらぬ姿を私たちに見せてくれています。 このような庭園は大変貴重なものです。 また、千利休は生前からよく参拝していて、大仙院の庭を茶庭のヒントにしたといいます。
大仙院の庭は『蓬莱山』を起点としています。
蓬莱山は中国の神仙思想で不老不死の仙人が住んでいるといわれています。
山からみて左側には滝を表す三段の石があります。
川を表した白砂が南下すると、ゆるやかな流れになり、『宝船(長船石)』が浮かんでいます。 宝船は蓬莱山の宝を運ぶ船のことです。
川を表した白砂が南下すると、ゆるやかな流れになり、『宝船(長船石)』が浮かんでいます。 宝船は蓬莱山の宝を運ぶ船のことです。
そして、南庭には『大海』が広がり、円錐形の砂盛が一対あるのが特徴です。庭は30坪あまりしかありませんが、仙境から海原まで表していて壮大です。
利休も愛した庭をぜひ、ご覧になってください。
◇所在地
京都市北区紫野大徳寺町54ー1
◇拝観時間
3月〜11月9:00〜17:00
12月〜2月9:00〜16:30
◇拝観料
大人(高校生以上)400円
小中学生270円
◇所在地
京都市北区紫野大徳寺町54ー1
◇拝観時間
3月〜11月9:00〜17:00
12月〜2月9:00〜16:30
◇拝観料
大人(高校生以上)400円
小中学生270円
絶対に訪れたい! 枯山水の庭園があるオススメの京都の寺院TOP5!!

○No.2! 建仁寺!!
京都五山のひとつである建仁寺は、建仁2年(1202年)に創建された、京都最古の禅宗寺院です。
建仁寺の方丈南庭は『大雄苑』とよばれています。 15個の石が配され、広がる白砂が特徴的です。 砂紋(砂に描かれた線)はうねったり、石組の周りを囲んでいます。 本当にそこに水が広がっているように感じます。
そして、本坊中庭にある『○△□乃庭』も必見です!
京都五山のひとつである建仁寺は、建仁2年(1202年)に創建された、京都最古の禅宗寺院です。
建仁寺の方丈南庭は『大雄苑』とよばれています。 15個の石が配され、広がる白砂が特徴的です。 砂紋(砂に描かれた線)はうねったり、石組の周りを囲んでいます。 本当にそこに水が広がっているように感じます。
そして、本坊中庭にある『○△□乃庭』も必見です!
『○△□』とは、密教の六大思想のうちの水(○)、火(△)、地(□)のことで、左側にある書院には庭の語源となった『○△□』の掛け軸が飾られています。
○は木、△は庭の隅の形状、□は井戸で表されています。
また、本坊の中庭には『潮音庭』があります。
また、本坊の中庭には『潮音庭』があります。
こちらは大書院と小書院に囲まれ、四方向のどこから見ても眺められるのが特徴です。
『大雄苑』や『○△□乃庭』と違って苔や石があり、また雰囲気が変わります。
ゆるやかな白砂の流れや茂った苔の緑ををみていると、心がほっと落ち着きます。 ぜひ、訪れてみてください!
◇所在地
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
◇拝観料
大人500円 中高生300円
◇拝観時間
3月〜10月末 10:00〜17:00(受付終了時間16:30)
11月〜2月末 10:00〜16:30(受付終了時間16:00)
年末拝観休止 12月28日〜12月31日
○No.1! 龍安寺!!
やはり、枯山水の庭園といえば龍安寺でしょう!!
龍安寺は宝徳2年(1450年)に創建されました。
ユネスコの世界文化遺産にも登録され、外国人観光客がたくさん訪れています。
ゆるやかな白砂の流れや茂った苔の緑ををみていると、心がほっと落ち着きます。 ぜひ、訪れてみてください!
◇所在地
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
◇拝観料
大人500円 中高生300円
◇拝観時間
3月〜10月末 10:00〜17:00(受付終了時間16:30)
11月〜2月末 10:00〜16:30(受付終了時間16:00)
年末拝観休止 12月28日〜12月31日
○No.1! 龍安寺!!
やはり、枯山水の庭園といえば龍安寺でしょう!!
龍安寺は宝徳2年(1450年)に創建されました。
ユネスコの世界文化遺産にも登録され、外国人観光客がたくさん訪れています。
龍安寺の庭園は作者が不明だったり、石の配置の謎があったりと、訪れる人々を楽しませています。
配置の謎とは、庭園には大小15個の石が置かれていますが、どの角度から見ても1個の石が隠れて見えないようになっており、15個を数えられないという謎です。
訪れた人々は右へいったり、左へいったりして、石を数えています。
しかし、このような配置にした理由は、いまだにわかっていません。
また、この庭は『虎の子渡しの庭』や『七五三の庭』ともよばれています。 あるいは、中国の五岳や禅の五山を象徴している、『心』の字を配している、大海や雲海に浮かぶ島々や高峰を表している、などといわれており、いろんな解釈があります。 みる人によって受け止め方が違うため、あれやこれやと話しあうのもおもしろいかもしれません。
ぜひ、石の数を数えてみてくださいね!
◇所在地
京都市右京区龍安寺御陵下町13
◇拝観料
大人・高校生500円
小・中学生300円
◇拝観時間
3月〜11月末 8:00〜17:00
12月〜2月末 8:30〜16:30
いかがでしたか。
京都はとくに枯山水の庭園が多く、どの寺院を訪れてもみる人を圧倒させます。 枯山水は禅宗の影響を受けている中、日本人の細やかな配慮や思慮が織り込まれています。 そして、作者の主張を語る作品ではなく、みる人の感じ方で表情を変えていく……そんなアーティスティックが日本人のみならず、外国の人々をひきつける理由なのかもしれません。
時代が変わっても姿が変わらない枯山水。
ぜひ、京都へいった際には枯山水のある寺院へ訪れてみてください!
また、この庭は『虎の子渡しの庭』や『七五三の庭』ともよばれています。 あるいは、中国の五岳や禅の五山を象徴している、『心』の字を配している、大海や雲海に浮かぶ島々や高峰を表している、などといわれており、いろんな解釈があります。 みる人によって受け止め方が違うため、あれやこれやと話しあうのもおもしろいかもしれません。
ぜひ、石の数を数えてみてくださいね!
◇所在地
京都市右京区龍安寺御陵下町13
◇拝観料
大人・高校生500円
小・中学生300円
◇拝観時間
3月〜11月末 8:00〜17:00
12月〜2月末 8:30〜16:30
いかがでしたか。
京都はとくに枯山水の庭園が多く、どの寺院を訪れてもみる人を圧倒させます。 枯山水は禅宗の影響を受けている中、日本人の細やかな配慮や思慮が織り込まれています。 そして、作者の主張を語る作品ではなく、みる人の感じ方で表情を変えていく……そんなアーティスティックが日本人のみならず、外国の人々をひきつける理由なのかもしれません。
時代が変わっても姿が変わらない枯山水。
ぜひ、京都へいった際には枯山水のある寺院へ訪れてみてください!






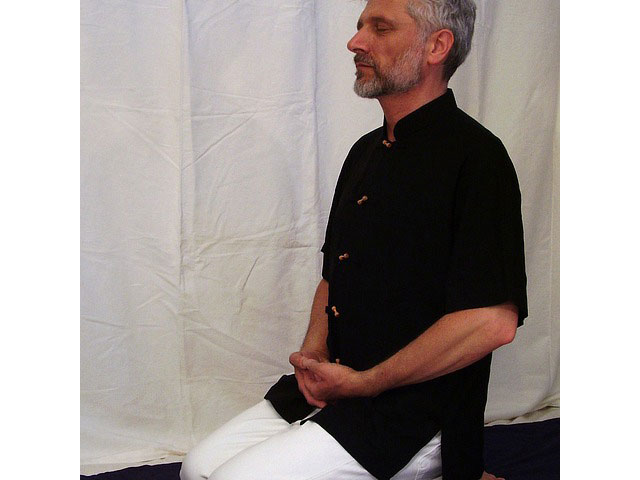


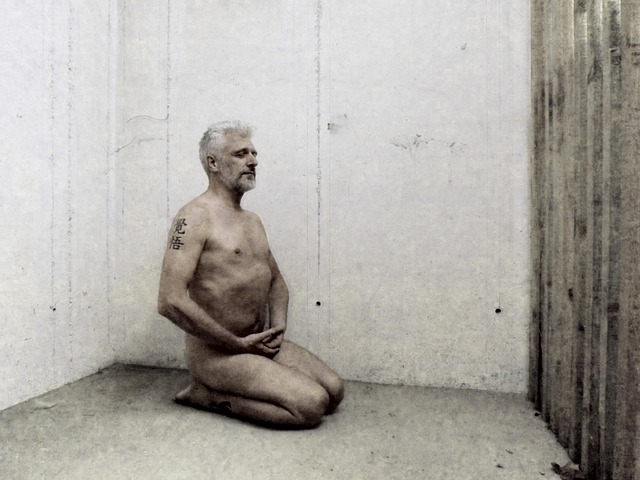














![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

