築城名人・加藤清正の傑作、熊本城と名古屋城
関連キーワード

1、難攻不落の名城、熊本城
熊本は中世ごろは隈本といいました。15世紀中ごろ、菊池氏の一族が茶臼山東端に千葉城、ついで西に隈本城を築きました。隈本城の跡地を現在は古城といっています。
16世紀末、築城術において突出した技量を持った戦国武将の加藤清正は隈本城に入ると茶臼山に新城建設を進め、地名も熊本城と改めました。
これは清正が秀吉の九州平定に従ったのち、肥後国を治めていた佐々成政の改易によって肥後国の北半分を与えられたことによっています。
なお、残りの半分には清正と仲が悪かった小西行長が配置されています。築城や治水など領地経営に清正は乗り出しますが、すぐに朝鮮出兵が行われ、清正が長期間領地を離れていたことが領地経営に影をおとすことになります。清正は築城や治水などのほかにも軍事面でも力を発揮しており、その優秀さゆえに領国が留守になるという事態をおこしてしまったのです。清正の死後、忠広があとをつぎますが、加藤氏は二代忠広で改易されてしまいます。これは清正のころからの負債が響いているともいわれています。
清正は農業や築城に力をいれましたが、それだけに出費も多く、百姓たちの負担も大きなものでした。清正はそれらの負債を解決する前に亡くなってしまったため、忠広に負担がまわってしまったのです。跡をついだとき、忠広はわずか11歳でした。そうして加藤氏が改易されたのち、細川氏が入り、明治に至りました。
縄張は梯廓式に渦廓式を加味して構想されています。地形上、西に弱点があるので東の最高地点に本丸を置き、廓内に東竹の丸・竹の丸・飯田丸・数寄屋丸を置きます。そして西に下って二の丸・三の丸と展開し、空堀で区画しました。その広さは98万㎡、公式の天守が2、櫓49、櫓門18、城門29を備えた豪壮雄大な平山城です。
別名は「銀杏城」です。これは清正が場内に銀杏の木を多く植えたことから出たものですが、この銀杏に関しては清正の逸話があります。「この木が天守の軒に届くころに、きっと大きな戦乱が起こるだろう」そう清正は予言したといいます。
その後、明治10年に起こった西南の役で熊本城は戦場と化します。
そのとき、あの銀杏の木は清正の予言通りに天守の軒に達していたといいます。西南の役では西郷隆盛率いる薩摩軍を相手に熊本城は50日あまりの籠城戦に耐え、難攻不落の城としての真価をいかんなく発揮しました。しかし、薩摩軍が総攻撃を仕掛ける3日前に原因不明の出火によって熊本城大天守と小天守など本丸中心部のほとんどが焼失しています。原因は城兵の失火とも、薩摩軍の密偵の放火ともいわれています。その際、宇土櫓などの一部は火災を免れ、現在は重要文化財として認定されています。
熊本城の特色は美しい石垣にあります。
本丸東方の石垣は特に高いですが、素晴らしいのは天守台のそれで、扇の勾配も美しく、清正勾配と呼ばれています。これは最初の勾配は緩やかで、上に行くほど急勾配となるもので「武者返しの石垣」として有名です。
16世紀末、築城術において突出した技量を持った戦国武将の加藤清正は隈本城に入ると茶臼山に新城建設を進め、地名も熊本城と改めました。
これは清正が秀吉の九州平定に従ったのち、肥後国を治めていた佐々成政の改易によって肥後国の北半分を与えられたことによっています。
なお、残りの半分には清正と仲が悪かった小西行長が配置されています。築城や治水など領地経営に清正は乗り出しますが、すぐに朝鮮出兵が行われ、清正が長期間領地を離れていたことが領地経営に影をおとすことになります。清正は築城や治水などのほかにも軍事面でも力を発揮しており、その優秀さゆえに領国が留守になるという事態をおこしてしまったのです。清正の死後、忠広があとをつぎますが、加藤氏は二代忠広で改易されてしまいます。これは清正のころからの負債が響いているともいわれています。
清正は農業や築城に力をいれましたが、それだけに出費も多く、百姓たちの負担も大きなものでした。清正はそれらの負債を解決する前に亡くなってしまったため、忠広に負担がまわってしまったのです。跡をついだとき、忠広はわずか11歳でした。そうして加藤氏が改易されたのち、細川氏が入り、明治に至りました。
縄張は梯廓式に渦廓式を加味して構想されています。地形上、西に弱点があるので東の最高地点に本丸を置き、廓内に東竹の丸・竹の丸・飯田丸・数寄屋丸を置きます。そして西に下って二の丸・三の丸と展開し、空堀で区画しました。その広さは98万㎡、公式の天守が2、櫓49、櫓門18、城門29を備えた豪壮雄大な平山城です。
別名は「銀杏城」です。これは清正が場内に銀杏の木を多く植えたことから出たものですが、この銀杏に関しては清正の逸話があります。「この木が天守の軒に届くころに、きっと大きな戦乱が起こるだろう」そう清正は予言したといいます。
その後、明治10年に起こった西南の役で熊本城は戦場と化します。
そのとき、あの銀杏の木は清正の予言通りに天守の軒に達していたといいます。西南の役では西郷隆盛率いる薩摩軍を相手に熊本城は50日あまりの籠城戦に耐え、難攻不落の城としての真価をいかんなく発揮しました。しかし、薩摩軍が総攻撃を仕掛ける3日前に原因不明の出火によって熊本城大天守と小天守など本丸中心部のほとんどが焼失しています。原因は城兵の失火とも、薩摩軍の密偵の放火ともいわれています。その際、宇土櫓などの一部は火災を免れ、現在は重要文化財として認定されています。
熊本城の特色は美しい石垣にあります。
本丸東方の石垣は特に高いですが、素晴らしいのは天守台のそれで、扇の勾配も美しく、清正勾配と呼ばれています。これは最初の勾配は緩やかで、上に行くほど急勾配となるもので「武者返しの石垣」として有名です。
2、熊本城の堅牢さ
城内のジグザグに折れ曲がった道を歩くと、両脇に高い壁を構成している石垣が視界の中に折り重なって先が見えにくくなっています。
攻め込んだ側からすると、さながら石の迷路のようでしょう。しかも石垣の角の向こうに城兵が潜んでいるかもしれないという恐怖を超えて進まないといけないため心理的にも攻めにくくなっています。二の丸跡の広場に立って遠目に熊本城の全貌を眺めると、茶臼山斜面いっぱいに石垣群が巨大な衝立を並べたように幾重にも重なって豪壮なこと限りありません。まさに鉄壁の大要塞であったことがわかります。
天守は事実上3つあります。大天守は五層に見えますが、三層六階、地下一階で高さ32メートル、二層四階地下一階の小天守との連結式、前期望楼型天守です。西にある宇土櫓も天守級で、三層四階、地下一階で最上階は望楼になっています。
軍事的配慮も細心です。天守や櫓には多くの狭間・石落としなどをそなえるほか、場内には120の井戸があり、庭には銀杏を植え、畳の芯には干瓢を入れるなど籠城の準備も考えられています。これは清正が朝鮮出兵の折に「泥水をすすり、死馬の肉を食らって戦う」という苦しい籠城を強いられた経験によるものです。
天守南面の下層の屋根を飾る千鳥破風と上層の屋根にある唐破風。それぞれに違った趣を持つ曲線の組み合わせに妙があります。また、屋根の棟端を飾る瓦は美観とともに雨の浸透を防ぐという実用性を持つものです。熊本城の棟端瓦には桔梗の家紋があしらわれています。
攻め込んだ側からすると、さながら石の迷路のようでしょう。しかも石垣の角の向こうに城兵が潜んでいるかもしれないという恐怖を超えて進まないといけないため心理的にも攻めにくくなっています。二の丸跡の広場に立って遠目に熊本城の全貌を眺めると、茶臼山斜面いっぱいに石垣群が巨大な衝立を並べたように幾重にも重なって豪壮なこと限りありません。まさに鉄壁の大要塞であったことがわかります。
天守は事実上3つあります。大天守は五層に見えますが、三層六階、地下一階で高さ32メートル、二層四階地下一階の小天守との連結式、前期望楼型天守です。西にある宇土櫓も天守級で、三層四階、地下一階で最上階は望楼になっています。
軍事的配慮も細心です。天守や櫓には多くの狭間・石落としなどをそなえるほか、場内には120の井戸があり、庭には銀杏を植え、畳の芯には干瓢を入れるなど籠城の準備も考えられています。これは清正が朝鮮出兵の折に「泥水をすすり、死馬の肉を食らって戦う」という苦しい籠城を強いられた経験によるものです。
天守南面の下層の屋根を飾る千鳥破風と上層の屋根にある唐破風。それぞれに違った趣を持つ曲線の組み合わせに妙があります。また、屋根の棟端を飾る瓦は美観とともに雨の浸透を防ぐという実用性を持つものです。熊本城の棟端瓦には桔梗の家紋があしらわれています。
3、天下の名城、名古屋城
尾張62万石の本拠、名古屋城の前身は戦国大名今川氏の那古屋城です。
徳川家康は1610年ごろから、この地に築城を開始しました。普請は、前田・池田・福島・黒田・加藤ら西国大名20家に命じた天下普請で、作事は幕府直轄でした。奉行には小堀遠州、大工頭に中井正清をあてて実施しています。この際、福島正則が労力と出費について愚痴をこぼしたところ、加藤清正から「では領国に戻って家康との戦をする準備をしろ」と言われ、黙ってしまったという有名な話があります。このころには家康に逆らうということは事実上できなくなっているということがわかるエピソードです。
城は面積が35ヘクタール、これは江戸城、大阪城につぐ規模でした。
縄張は梯廓式で、正方形の本丸を中心に、二の丸、御深井丸、西の丸を配していて、さらに外郭に三の丸を持っています。約20メートルの高さを持つ天守の石垣は加藤清正が担当しました。清正流三日月石垣と呼ばれ、熊本城と並んで、扇の勾配が美しいこと限りありません。
層塔型の天守は外観五層内部六階で高さは約36メートル、小天守を廊下橋でつなぐ連結式天守でした。外壁は総塗りごめで耐火構造とし、隠し狭間、石落とし、剣塀などの備えもあり、軍事的配慮も怠りませんでした。
本丸御殿も素晴らしく、書院造の豪華なもので二条城に匹敵するといわれました。二の丸御殿もつくられ、二の丸庭園は国の名勝に指定されています。
維新後も天守・櫓、それに本丸御殿も残り、面影も強く残っていましたが1945年の空襲でそのほとんどが焼失し、現在のものは復元されたものになっています。
徳川家康は1610年ごろから、この地に築城を開始しました。普請は、前田・池田・福島・黒田・加藤ら西国大名20家に命じた天下普請で、作事は幕府直轄でした。奉行には小堀遠州、大工頭に中井正清をあてて実施しています。この際、福島正則が労力と出費について愚痴をこぼしたところ、加藤清正から「では領国に戻って家康との戦をする準備をしろ」と言われ、黙ってしまったという有名な話があります。このころには家康に逆らうということは事実上できなくなっているということがわかるエピソードです。
城は面積が35ヘクタール、これは江戸城、大阪城につぐ規模でした。
縄張は梯廓式で、正方形の本丸を中心に、二の丸、御深井丸、西の丸を配していて、さらに外郭に三の丸を持っています。約20メートルの高さを持つ天守の石垣は加藤清正が担当しました。清正流三日月石垣と呼ばれ、熊本城と並んで、扇の勾配が美しいこと限りありません。
層塔型の天守は外観五層内部六階で高さは約36メートル、小天守を廊下橋でつなぐ連結式天守でした。外壁は総塗りごめで耐火構造とし、隠し狭間、石落とし、剣塀などの備えもあり、軍事的配慮も怠りませんでした。
本丸御殿も素晴らしく、書院造の豪華なもので二条城に匹敵するといわれました。二の丸御殿もつくられ、二の丸庭園は国の名勝に指定されています。
維新後も天守・櫓、それに本丸御殿も残り、面影も強く残っていましたが1945年の空襲でそのほとんどが焼失し、現在のものは復元されたものになっています。













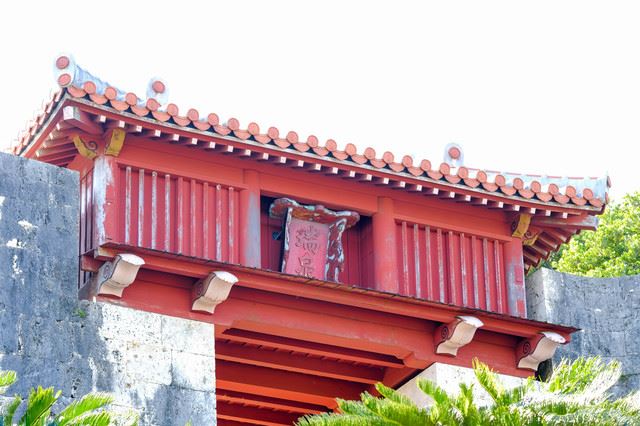






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

