国宝の山城、備中松山城
関連キーワード

1 備中松山城の築城まで
備中松山城は北から、大松山・天神の丸・小松山・前山の四つの峰からなる臥牛山中に築かれた山城です。そして、古い天守が現存している山城は、この備中松山城だけです。それゆえに日本三大山城の一つに数えられています。
もっとも、太平の世には山城は不要であり、使い勝手が悪く、近代の城はほとんどが平地での平城か、山城的な面を併せ持つ平山城です。それは戦いで敵に囲まれての籠城を前提とする意味がないためと、平野部でなければ街が発達せず、経済的な発展が見込めないということもあります。戦国時代には有用な山城も平和な時代では無用の長物となり、そのため数が少ないのです。
備中松山城の天守は築城当時のものです。そのころの天守が現存するのは合計で12しかないため、大変貴重なものです。ほとんどの城郭の天守は、明治維新後に取り壊されるか、第二次世界大戦の戦火で焼けてしまったからです。
臥牛山に城が築かれたのは鎌倉時代です。相模の豪族三浦氏の一族、秋庭三郎重信が備中国有漢郷の地頭として入国した際だといわれています。彼は大松山に最初の城を築きました。
その後、上野氏、庄氏、三村氏と変遷しましたが、戦国時代に城主となった三村元親により、大松山・小松山を含んだ城塞として整備されました。三村元親の父である家親は、備中国と備前国の一部を治めていました。さらに備前国・美作国への勢力拡大を企て、毛利氏と手を組み、これを後ろ立てとしました。
しかし謀略家である宇喜多直家により、1566年に暗殺されます。子である元親は直家への復讐と備前国制覇を企て、二万の兵をもってこれに挑みますが、わずか五千の兵力の直家に敗北します。これを「明善寺合戦」と呼びます。謀略家として恐れられた直家の一生で、戦を正攻法で勝利したのはこの一回限りでしたが、彼はこの戦功により独立性や発言力を増していきます。一方、敗北した元親は備中・備前での権勢が一時衰えるも、後の毛利氏の後押しで盛り返します。
しかしその後の1574年、毛利氏が宇喜多直家と結んだことにより、元親は毛利氏を離反し、織田信長と通じることになりました。毛利氏は小早川隆景の進言により、三村討伐を行います。毛利軍は守りを固めた備中松山城以外を残し、臥牛山中の他城をすべて攻略、籠城戦を強いられた元親は持久戦を展開するも敗北し、その自刃しました。
もっとも、太平の世には山城は不要であり、使い勝手が悪く、近代の城はほとんどが平地での平城か、山城的な面を併せ持つ平山城です。それは戦いで敵に囲まれての籠城を前提とする意味がないためと、平野部でなければ街が発達せず、経済的な発展が見込めないということもあります。戦国時代には有用な山城も平和な時代では無用の長物となり、そのため数が少ないのです。
備中松山城の天守は築城当時のものです。そのころの天守が現存するのは合計で12しかないため、大変貴重なものです。ほとんどの城郭の天守は、明治維新後に取り壊されるか、第二次世界大戦の戦火で焼けてしまったからです。
臥牛山に城が築かれたのは鎌倉時代です。相模の豪族三浦氏の一族、秋庭三郎重信が備中国有漢郷の地頭として入国した際だといわれています。彼は大松山に最初の城を築きました。
その後、上野氏、庄氏、三村氏と変遷しましたが、戦国時代に城主となった三村元親により、大松山・小松山を含んだ城塞として整備されました。三村元親の父である家親は、備中国と備前国の一部を治めていました。さらに備前国・美作国への勢力拡大を企て、毛利氏と手を組み、これを後ろ立てとしました。
しかし謀略家である宇喜多直家により、1566年に暗殺されます。子である元親は直家への復讐と備前国制覇を企て、二万の兵をもってこれに挑みますが、わずか五千の兵力の直家に敗北します。これを「明善寺合戦」と呼びます。謀略家として恐れられた直家の一生で、戦を正攻法で勝利したのはこの一回限りでしたが、彼はこの戦功により独立性や発言力を増していきます。一方、敗北した元親は備中・備前での権勢が一時衰えるも、後の毛利氏の後押しで盛り返します。
しかしその後の1574年、毛利氏が宇喜多直家と結んだことにより、元親は毛利氏を離反し、織田信長と通じることになりました。毛利氏は小早川隆景の進言により、三村討伐を行います。毛利軍は守りを固めた備中松山城以外を残し、臥牛山中の他城をすべて攻略、籠城戦を強いられた元親は持久戦を展開するも敗北し、その自刃しました。
2 江戸時代の松山城

その後は毛利氏の領有となった備中国ですが、江戸時代に入ると小堀氏が徳川幕府の代官として入城します。そして池田長幸が入りますが、二代・長常に嗣子がなく、池田氏は廃絶します。代わって備後福山藩主の水野勝成が城番となります。1642年に水谷勝隆が5万石で入封し、二代藩主の勝宗により天守を建造するなど大改修を行い、現在の松山城の姿となりました。
二層二階の複合式望楼型天守は小規模で、大坂や江戸といった巨城と比較してしまうと櫓のようでもありますが、山中に堂々と立つ姿はなかなかに威厳があり美しい。また本来は防衛拠点とされた中世の山城であったため、直角に曲がった石段や、天守へは渡櫓から入らなければならない構造といった、実戦的な姿を現在に伝える貴重な城郭です。そのため、山麓に藩の執務を行う御根小屋という御殿が構えられた。これにより、中世期の様式美と近世式の人工美を兼ね備えた城郭となっていて、周囲の自然と同時に、松山城の歴史の変遷をうかがうことができます。
なお、戦国初期には山城を詰めの城とし、城主の居館をその麓において政務を執るというのが典型的なパターンであったが、またその古い形式に落ち着いたことになる。
その後、水谷氏三代にして嗣子がなかったため廃絶となり、次に忠臣蔵で有名な赤穂藩主・浅野長矩が受け取り、「大石内蔵助」として有名な家老の大石良雄が城主となります。次いで、安藤氏、石川氏と入り、最後に5万石で板倉氏が入り、明治の世まで八代続きました。
江戸期に入っても大名が次々と代わったのにも、直接治めるべき備中国が関ヶ原の合戦時に分割統治されていたという背景を考えるとわかる。小藩が多数分立し、備中国は旗本の知行地として利用されていたのです。さらに太平の世となった江戸時代に守備型要塞の山城は不要であったのでしょう。
二層二階の複合式望楼型天守は小規模で、大坂や江戸といった巨城と比較してしまうと櫓のようでもありますが、山中に堂々と立つ姿はなかなかに威厳があり美しい。また本来は防衛拠点とされた中世の山城であったため、直角に曲がった石段や、天守へは渡櫓から入らなければならない構造といった、実戦的な姿を現在に伝える貴重な城郭です。そのため、山麓に藩の執務を行う御根小屋という御殿が構えられた。これにより、中世期の様式美と近世式の人工美を兼ね備えた城郭となっていて、周囲の自然と同時に、松山城の歴史の変遷をうかがうことができます。
なお、戦国初期には山城を詰めの城とし、城主の居館をその麓において政務を執るというのが典型的なパターンであったが、またその古い形式に落ち着いたことになる。
その後、水谷氏三代にして嗣子がなかったため廃絶となり、次に忠臣蔵で有名な赤穂藩主・浅野長矩が受け取り、「大石内蔵助」として有名な家老の大石良雄が城主となります。次いで、安藤氏、石川氏と入り、最後に5万石で板倉氏が入り、明治の世まで八代続きました。
江戸期に入っても大名が次々と代わったのにも、直接治めるべき備中国が関ヶ原の合戦時に分割統治されていたという背景を考えるとわかる。小藩が多数分立し、備中国は旗本の知行地として利用されていたのです。さらに太平の世となった江戸時代に守備型要塞の山城は不要であったのでしょう。
3 近年の松山城

幕末に戊辰戦争が勃発すると、幕府側の松山藩は朝敵とされ、岡山藩などの周辺の大名に討伐の命令が下されました。当時、幕府側について官軍と戦っていた藩主、板倉勝静でしたが、執政を預かっていた儒者で陽明学者の山田方谷は勝静に従って官軍と戦うよりも松山の領民を救うことを決断し、1868年2月11日、無血開城しました。その後、1873年には新政府より廃城令が公布され、御根小屋は取り壊されました。
こうして備中松山城は放置され、1941年に国宝指定を受けるまで山上の建造物は荒廃していたといいます。現在は重要文化財として指定され、近年の戦国時代への人気から観光客も多く、賑わいを見せています。
こうして備中松山城は放置され、1941年に国宝指定を受けるまで山上の建造物は荒廃していたといいます。現在は重要文化財として指定され、近年の戦国時代への人気から観光客も多く、賑わいを見せています。












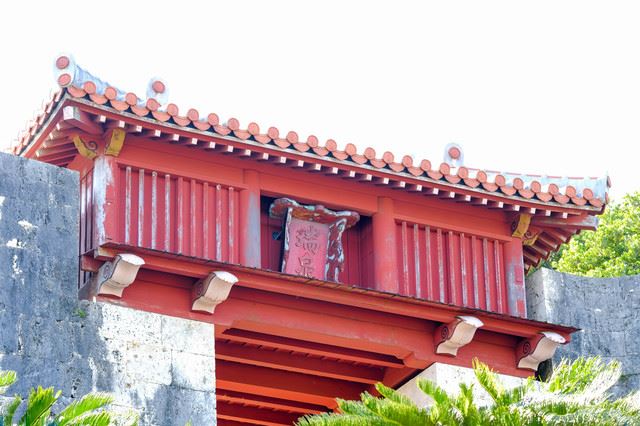







![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

