武家から厚遇を受けた【臨済宗】誰もが知っている「あのお寺」も「このお寺」も臨済宗だった!
関連キーワード
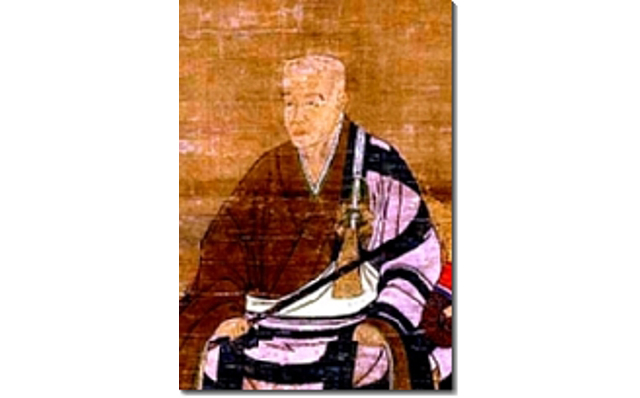
出典:https://ja.wikipedia.org/|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E8%8F%B4%E6%A0%84%E8%A5%BF#/media/File:Eisai.jpg
禅宗の1つである臨済宗。
歴史の教科書などで名前を見たり聞いたりしたのではないでしょうか。 しかし、いつから始まり、どんな教えをしているのか知っていますか? 実は臨済宗のお寺は他の宗教よりも数は少ないものの、誰もが知っている”あの”お寺も”この”お寺も臨済宗なのです。 今回はその歴史と教えから、実は身近にある臨済宗の魅力をご紹介します!
歴史の教科書などで名前を見たり聞いたりしたのではないでしょうか。 しかし、いつから始まり、どんな教えをしているのか知っていますか? 実は臨済宗のお寺は他の宗教よりも数は少ないものの、誰もが知っている”あの”お寺も”この”お寺も臨済宗なのです。 今回はその歴史と教えから、実は身近にある臨済宗の魅力をご紹介します!
栄西の生い立ちと臨済宗の歴史とは?
臨済宗の開祖・明庵栄西(みょうあんえいさい)は頭のてっぺんが平らで、角張った形が特徴的なお坊さんです。元々、臨済宗は中国から始まりましたが、日本に広めたのがこの栄西でした。
栄西は1141年、岡山県岡山市にある吉備津神社の神職・賀陽(かや)氏の子供として生まれました。
神職の息子とは驚きです!
そして、14歳の時、比叡山で受戒(仏門に入る者が仏の定めた戒律を受けること)し、密教を学びました。 1168年には宋(現在の中国)に半年間入り、1187年にも宋へ出向きました。
そこで「臨済宗黄龍派」の禅を継ぎ、帰国しました。
九州に着いた栄西は禅寺を建てるために努め、布教のために京都へ入ろうとしましたが、比叡山から圧力を受け、禅宗停止の宣旨が下されてしまったのです。 禅宗はすでに日本で普及していた他の仏教宗派を否定して、新興宗教として勢力を拡大している、と思われてしまったのです。 迫害を受けた栄西は九州に戻って、禅寺を建てることに力を注ぎました。 翌年には、現在の福岡県・博多市に日本で初めての本格的な禅寺・安国山聖福寺を建てました。そして、天台宗の開祖・最澄が教えた伝統的な禅に帰ること、また、禅は仏法復興に重要であることを主張したのです。
既存勢力とも調和をはかり、布教に努めましたが、限界を感じた栄西は幕府のある鎌倉に出向きました。 そこで初代将軍・源頼朝の妻の北条政子から厚く迎えられ、政子は栄西のために現在の鎌倉市内に寿福寺を建てました。栄西は天台密教の秘法を会得した祈祷僧として、政子やその息子・頼家から手厚いおもてなしを受けたのです。
頼家も栄西のために、現在の京都市に建仁寺を建て、京都で初めての禅院となりました。 建仁寺は当初、禅・止観(天台)・真言の兼修道場でした。そして、栄西は東大寺の勧進職にも就任し、旧仏教との関係を友好的なものにしていったのです。 頼家以降も朝廷や幕府から厚遇され続けてきた臨済宗は、次第に発展していくこととなりました。
その後、14の宗派(妙心寺派、南禅寺派、建長寺派、東福寺派、円覚寺派、大徳寺派、方広寺派、永源寺派、天龍寺派、相国寺派、建仁寺派、向嶽寺派、佛通寺派、国泰寺派)に分かれて行きました。
主に釈迦如来をご本尊としていて、建長寺は地蔵菩薩、永源寺は世継観世音菩薩をご本尊としています。
そして、臨済宗は禅と公案によって悟りを開くことを教えています。
公案とは、師匠から弟子へ禅問答をして弟子は座禅をしてその答えを出すという、臨済宗独特の修行法です。これはただ座るだけではなく、問答により積極的に禅を行うことで修行僧が自己に本来備わっている本性を見極めることを促すのです。これを「看(かん)話(な)禅(ぜん)」と言います。
自分の中にある仏性の存在に出会い、本性とはすでに一緒なんだと体験し、会得することがこの看話禅の最も重要な目的なのです。
栄西は1141年、岡山県岡山市にある吉備津神社の神職・賀陽(かや)氏の子供として生まれました。
神職の息子とは驚きです!
そして、14歳の時、比叡山で受戒(仏門に入る者が仏の定めた戒律を受けること)し、密教を学びました。 1168年には宋(現在の中国)に半年間入り、1187年にも宋へ出向きました。
そこで「臨済宗黄龍派」の禅を継ぎ、帰国しました。
九州に着いた栄西は禅寺を建てるために努め、布教のために京都へ入ろうとしましたが、比叡山から圧力を受け、禅宗停止の宣旨が下されてしまったのです。 禅宗はすでに日本で普及していた他の仏教宗派を否定して、新興宗教として勢力を拡大している、と思われてしまったのです。 迫害を受けた栄西は九州に戻って、禅寺を建てることに力を注ぎました。 翌年には、現在の福岡県・博多市に日本で初めての本格的な禅寺・安国山聖福寺を建てました。そして、天台宗の開祖・最澄が教えた伝統的な禅に帰ること、また、禅は仏法復興に重要であることを主張したのです。
既存勢力とも調和をはかり、布教に努めましたが、限界を感じた栄西は幕府のある鎌倉に出向きました。 そこで初代将軍・源頼朝の妻の北条政子から厚く迎えられ、政子は栄西のために現在の鎌倉市内に寿福寺を建てました。栄西は天台密教の秘法を会得した祈祷僧として、政子やその息子・頼家から手厚いおもてなしを受けたのです。
頼家も栄西のために、現在の京都市に建仁寺を建て、京都で初めての禅院となりました。 建仁寺は当初、禅・止観(天台)・真言の兼修道場でした。そして、栄西は東大寺の勧進職にも就任し、旧仏教との関係を友好的なものにしていったのです。 頼家以降も朝廷や幕府から厚遇され続けてきた臨済宗は、次第に発展していくこととなりました。
その後、14の宗派(妙心寺派、南禅寺派、建長寺派、東福寺派、円覚寺派、大徳寺派、方広寺派、永源寺派、天龍寺派、相国寺派、建仁寺派、向嶽寺派、佛通寺派、国泰寺派)に分かれて行きました。
主に釈迦如来をご本尊としていて、建長寺は地蔵菩薩、永源寺は世継観世音菩薩をご本尊としています。
そして、臨済宗は禅と公案によって悟りを開くことを教えています。
公案とは、師匠から弟子へ禅問答をして弟子は座禅をしてその答えを出すという、臨済宗独特の修行法です。これはただ座るだけではなく、問答により積極的に禅を行うことで修行僧が自己に本来備わっている本性を見極めることを促すのです。これを「看(かん)話(な)禅(ぜん)」と言います。
自分の中にある仏性の存在に出会い、本性とはすでに一緒なんだと体験し、会得することがこの看話禅の最も重要な目的なのです。
金閣寺も龍安寺も臨済宗!!
金色の美しいお寺・鹿苑寺(通称・金閣寺)は修学旅行や遠足で訪れたことがある人もいるのではないでしょうか。
実は金閣寺は臨済宗なのです! 宗派は相国寺派で、室町幕府第3将軍・足利義満によって開かれました。 そして、その金閣寺を模して、第8代将軍・足利義政が建てた慈照寺(通称・銀閣寺)も臨済宗です。
また、臨済宗の寺院の多くには庭園が枯山水の様式で造営されています。
枯山水は水を使わず、石や砂などで禅の思想を表現しているのです。 中でも、京都市にある龍安寺(妙心寺派)の方丈庭園が有名です。 庭にある石が15個並べられているのですが、なぜかどの角度から見ても1個の石が隠れてしまい、14個しか数えられないような造りになっているのです。 みなさんも参詣したときには、ぜひ数えてみてくださいね。
実は金閣寺は臨済宗なのです! 宗派は相国寺派で、室町幕府第3将軍・足利義満によって開かれました。 そして、その金閣寺を模して、第8代将軍・足利義政が建てた慈照寺(通称・銀閣寺)も臨済宗です。
また、臨済宗の寺院の多くには庭園が枯山水の様式で造営されています。
枯山水は水を使わず、石や砂などで禅の思想を表現しているのです。 中でも、京都市にある龍安寺(妙心寺派)の方丈庭園が有名です。 庭にある石が15個並べられているのですが、なぜかどの角度から見ても1個の石が隠れてしまい、14個しか数えられないような造りになっているのです。 みなさんも参詣したときには、ぜひ数えてみてくださいね。
日本の茶祖! 栄西はお茶の再興に貢献!!
現在では、お茶を飲むことは生活の中にあり、当たり前になっています。
実は、栄西はお茶が身体にいいものなんだと、その効能を説いて世間に広めた第一人者なのです。
それまでも喫茶の文化はありましたが、貴族などの一部上流階級だけのものでした。
栄西は宋から日本に戻る時、茶の種を持って帰って栽培しました。
布教とともにお茶の普及にも努めたと言われています。 禅宗には茶の湯の原型である茶礼など、お茶についての儀式がたくさんあります。 座禅の時には、眠気覚ましの効能があるお茶はもってこいで、修場には欠かせないものでした。
それから栄西は、「喫茶養生記」というお茶の専門書を書き、一般にも広めていきました。
お酒が大好きだったという鎌倉幕府三代将軍・源実朝にもお茶とこの本を献上したという記録もあります。 私たちがいつでも、どこでもお茶がいただけるのは栄西のおかげなのですね。
いかがでしたか。
禅宗の1つである臨済宗は武家に親しまれながら、庶民にもお茶とともに広まっていったのがお分かりいただけたでしょうか。 そして、実は金閣寺や龍安寺も臨済宗で、私たちの身近にある宗教だったのです。 京都に行った時にはぜひ参詣して、臨済宗を肌で感じてみてくださいね。
■各派のご本山
○正法山妙心寺
〒616‐8035
京都市右京区花園妙心寺町64
○瑞龍山南禅寺
〒606‐8435
京都市左京区南禅寺福地町
○巨福山建長寺
〒247‐8525
神奈川県鎌倉市山ノ内8
○慧日山東福寺
〒605‐0981
京都市東山区本町15丁目
○瑞鹿山円覚寺
〒247‐8503
神奈川県鎌倉市山ノ内409
○龍宝山大徳寺
〒603‐8231
京都市北区紫野大徳寺町53
○深奥山方広寺
〒431‐2224
静岡県浜松市引佐町奥山1557‐1
○瑞石山永源寺
〒527‐0212
滋賀県東近江市永源寺高野41
○霊亀山天龍寺
〒616‐8385
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
○万年山相国寺
〒602‐0898
京都市上京区相国寺門前町701
○東山建仁寺
〒605‐0811
京都市東山区小松町584
○塩山向嶽寺
〒404‐0042
山梨県塩山市上於曽2026
○御許山佛通山
〒729‐0471
広島県三原市高坂町許山22
○摩頂山国泰寺
〒933‐0133
富山県高岡市太田184
栄西は宋から日本に戻る時、茶の種を持って帰って栽培しました。
布教とともにお茶の普及にも努めたと言われています。 禅宗には茶の湯の原型である茶礼など、お茶についての儀式がたくさんあります。 座禅の時には、眠気覚ましの効能があるお茶はもってこいで、修場には欠かせないものでした。
それから栄西は、「喫茶養生記」というお茶の専門書を書き、一般にも広めていきました。
お酒が大好きだったという鎌倉幕府三代将軍・源実朝にもお茶とこの本を献上したという記録もあります。 私たちがいつでも、どこでもお茶がいただけるのは栄西のおかげなのですね。
いかがでしたか。
禅宗の1つである臨済宗は武家に親しまれながら、庶民にもお茶とともに広まっていったのがお分かりいただけたでしょうか。 そして、実は金閣寺や龍安寺も臨済宗で、私たちの身近にある宗教だったのです。 京都に行った時にはぜひ参詣して、臨済宗を肌で感じてみてくださいね。
■各派のご本山
○正法山妙心寺
〒616‐8035
京都市右京区花園妙心寺町64
○瑞龍山南禅寺
〒606‐8435
京都市左京区南禅寺福地町
○巨福山建長寺
〒247‐8525
神奈川県鎌倉市山ノ内8
○慧日山東福寺
〒605‐0981
京都市東山区本町15丁目
○瑞鹿山円覚寺
〒247‐8503
神奈川県鎌倉市山ノ内409
○龍宝山大徳寺
〒603‐8231
京都市北区紫野大徳寺町53
○深奥山方広寺
〒431‐2224
静岡県浜松市引佐町奥山1557‐1
○瑞石山永源寺
〒527‐0212
滋賀県東近江市永源寺高野41
○霊亀山天龍寺
〒616‐8385
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
○万年山相国寺
〒602‐0898
京都市上京区相国寺門前町701
○東山建仁寺
〒605‐0811
京都市東山区小松町584
○塩山向嶽寺
〒404‐0042
山梨県塩山市上於曽2026
○御許山佛通山
〒729‐0471
広島県三原市高坂町許山22
○摩頂山国泰寺
〒933‐0133
富山県高岡市太田184























![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

