【意外な共通点!?】吉田兼好とマックス・ウェーバー「兼好のお金談義」"
関連キーワード
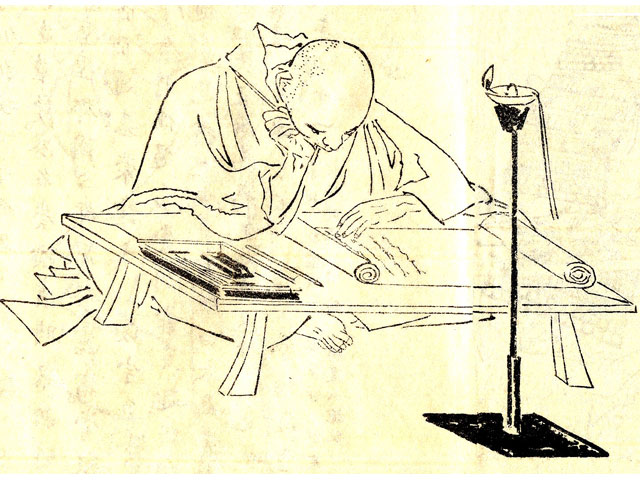
吉田兼好の『徒然草』は、多種多様な話題を自由自在に語ることで有名です。他愛のない日々の出来事をのびのびと書き流したと思ったら、次のページでは仏教思想についての洞察が披露され、時には筆が走り過ぎ、章段間で矛盾することを書くことも珍しくありません。全244段の自由奔放で色彩豊かな随筆は、江戸時代以降の人々の心をつかみ、『枕草子』や『方丈記』と並ぶ日本三大随筆の一つとして、その名を不朽のものとしました。
『徒然草』が書かれたのは、鎌倉時代も終わりが見えてきたのは14世紀のはじめ。鎌倉時代は、日本に貨幣経済が本格的に浸透し始めた時代であるといわれています。鎌倉時代の終盤を生きた吉田兼好も、お金とは無縁ではありませんでした。『徒然草』にもお金に関して兼好が意見を述べている部分もあります。そういった部分のなかでも最も注目を集めてきた章段が「ある大黒長者」の話に取材した217段です。217段に披瀝されている「お金観」について、19~20世紀ドイツの社会学者マックス・ウェーバー(1864-1920)が有名な『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のなかで述べた「資本主義の精神」と比較しながら紹介していきます。
(『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の引用は、大塚久雄訳 岩波文庫 1989年改訳 に依りました。)
『徒然草』が書かれたのは、鎌倉時代も終わりが見えてきたのは14世紀のはじめ。鎌倉時代は、日本に貨幣経済が本格的に浸透し始めた時代であるといわれています。鎌倉時代の終盤を生きた吉田兼好も、お金とは無縁ではありませんでした。『徒然草』にもお金に関して兼好が意見を述べている部分もあります。そういった部分のなかでも最も注目を集めてきた章段が「ある大黒長者」の話に取材した217段です。217段に披瀝されている「お金観」について、19~20世紀ドイツの社会学者マックス・ウェーバー(1864-1920)が有名な『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のなかで述べた「資本主義の精神」と比較しながら紹介していきます。
(『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の引用は、大塚久雄訳 岩波文庫 1989年改訳 に依りました。)
1.『徒然草』の時代とお金
『徒然草』の書かれた鎌時代、お金は生活に欠かせないものとなりました。とはいえ、鎌倉時代になってはじめてお金が日本史の舞台に登場したわけではありません。鎌倉時代以前にも和同開珎や皇朝十二銭といった貨幣が存在し、711年の蓄銭叙位令など、貨幣経済を定着させる試みがなされました。しかし、貨幣の使用の多くは都に集中し、貨幣に対する信頼が社会全体に浸透したとはいい難く、貨幣経済を定着させるには至りませんでした。
ではなぜ鎌倉時代になってようやく貨幣経済が浸透したのでしょうか。要因の一つに農業技術・農業生産性の進歩が挙げられます。農業技術が進歩するにともないエゴマといった商品作物が生産されるようになると、三斎市といった市場が登場しました。宋銭の輸入も一つの要因です。それまでの貨幣の場合、流通量がそれほど多くなく、悪銭が跋扈するなどして貨幣への信頼が下がることが往々にしてあり、そのことが貨幣経済の定着のひとつの妨げになっていました。しかし、平安時代の末期から宋銭が大量に流入すると、貨幣に対する信頼も公家や武家から次第に民衆に広がり、貨幣経済が定着していきました。
貨幣経済が定着すると社会も変化しました。農業では年貢として米などの現物の代わりに宋銭を納める代銭納が現れ、金融業も盛んとなり、為替も登場します。市場の発達にあわせては、商品の輸送、委託販売をおこなう問丸も登場します。
吉田兼好もまた、貨幣経済の世の中に揉まれて生きる一人でした。吉田兼好は、当時和歌四天王とよばれた頓阿にとある一首を送ります。
夜もすずし 寝覚めのかりほ 手まくらも 真袖の秋に 隔て無き風
一見、秋の寝覚めの涼しさを詠んだ普通の和歌に見えますが、からくりが隠されています。この歌には「沓冠」(くつかぶり)という技法が盛り込まれているのです。どういうことかというと、句ごとの頭文字と、最後の文字をたどると意味のある言葉が浮かび上がってくるのです。先ほどの歌をひらがな書きで見てみます。
よもすずし ねざめのかりほ たまくらも まそでのあきに へだてなきかぜ
頭文字をたどると、「よねたまへ」、すなわち「米給え」(米をくれ)というメッセージが浮かび上がります。一方、逆から同じことをすると、「ぜにもほし」、すなわち「銭も欲し」(金も欲しい)というメッセージが浮かび上がります。この歌のメッセージから、吉田兼好も生活にお金が必要だったことがわかります。ちなみに、この歌を贈られた頓阿は、和歌の達人だけあって兼好の遊び心を見抜き、次のように返しています。
夜も憂し ねたく我が背子 果ては来ず なほざりにだに しばし訪ひませ
兼好よ、うちに来ないか、というのが表の意味。しかし、先ほどと同じように頭文字に注目すると、「よねはなし、せにずこし」、すなわち、「米は無いよ、お金ならちょっと」というメッセージが浮かび上がります。兼好と頓阿の洒落た文通でした。
ではなぜ鎌倉時代になってようやく貨幣経済が浸透したのでしょうか。要因の一つに農業技術・農業生産性の進歩が挙げられます。農業技術が進歩するにともないエゴマといった商品作物が生産されるようになると、三斎市といった市場が登場しました。宋銭の輸入も一つの要因です。それまでの貨幣の場合、流通量がそれほど多くなく、悪銭が跋扈するなどして貨幣への信頼が下がることが往々にしてあり、そのことが貨幣経済の定着のひとつの妨げになっていました。しかし、平安時代の末期から宋銭が大量に流入すると、貨幣に対する信頼も公家や武家から次第に民衆に広がり、貨幣経済が定着していきました。
貨幣経済が定着すると社会も変化しました。農業では年貢として米などの現物の代わりに宋銭を納める代銭納が現れ、金融業も盛んとなり、為替も登場します。市場の発達にあわせては、商品の輸送、委託販売をおこなう問丸も登場します。
吉田兼好もまた、貨幣経済の世の中に揉まれて生きる一人でした。吉田兼好は、当時和歌四天王とよばれた頓阿にとある一首を送ります。
夜もすずし 寝覚めのかりほ 手まくらも 真袖の秋に 隔て無き風
一見、秋の寝覚めの涼しさを詠んだ普通の和歌に見えますが、からくりが隠されています。この歌には「沓冠」(くつかぶり)という技法が盛り込まれているのです。どういうことかというと、句ごとの頭文字と、最後の文字をたどると意味のある言葉が浮かび上がってくるのです。先ほどの歌をひらがな書きで見てみます。
よもすずし ねざめのかりほ たまくらも まそでのあきに へだてなきかぜ
頭文字をたどると、「よねたまへ」、すなわち「米給え」(米をくれ)というメッセージが浮かび上がります。一方、逆から同じことをすると、「ぜにもほし」、すなわち「銭も欲し」(金も欲しい)というメッセージが浮かび上がります。この歌のメッセージから、吉田兼好も生活にお金が必要だったことがわかります。ちなみに、この歌を贈られた頓阿は、和歌の達人だけあって兼好の遊び心を見抜き、次のように返しています。
夜も憂し ねたく我が背子 果ては来ず なほざりにだに しばし訪ひませ
兼好よ、うちに来ないか、というのが表の意味。しかし、先ほどと同じように頭文字に注目すると、「よねはなし、せにずこし」、すなわち、「米は無いよ、お金ならちょっと」というメッセージが浮かび上がります。兼好と頓阿の洒落た文通でした。
2.『徒然草』第217段「ある大黒長者のいわく」
兼好のお金に対する考え方が現れた章段が第217段です。この段では、兼好が「ある大黒長者」(お金持ち)の語ったお金哲学を紹介し、「俺はそうは思わん」と反対する、という構成になっています。「ある大黒長者」の話はだいたい以下のようなもの。
ある大黒長者:
「人間の生きがいは財産を築くことだ。財産を築くコツは心構えにある。その心構えとは、
1. 人間いつまでも生きられるのだと思うこと、そして無常観などは持たないこと。
2. 欲望を抑えること。欲望には限りがないが、財産には限りがある。際限のない欲望は悪と心得て、ささいなことにもお金を使ってはならない。
3. お金を神や主君と心得て大切にすること。くれぐれも、お金を家来のように自由に使えるものだと思ってはならない。
4. 恥ずかしい目にあっても怒ったり、恨んだりしない。
5. 正直で約束を守ること。
これらの心構えを持てば、あたかも火が乾いているものに就き、水が低い方に流れていくように(自然と)お金が貯まるだろう。お金が貯まれば欲望を満たさなくても心はつだって愉しいものだ。」
欲望をおさえ、お金を使わないようにする、こういった大黒長者の考えに対し、兼好は大反対。兼好の言い分は以下の通り。
兼好:
「そもそも人間は欲望を成し遂げようとして財産を求める。お金が大事なのは、それが欲望を満たすたづき・手段となるからだ。欲望があっても我慢し、お金があっても使わないのは、まったく貧乏人に等しい。大黒長者の教えは、むしろ世間的な欲望を捨て、貧乏を託ってはならない、と言っているように聞こえる。こう考えると、貧乏と金持ちの区別なぞあったものではない。悟りは迷いに等しい。大欲は無欲に似ている。」
最後は筆が走ったのか、仏教的な教訓めいたことを述べている兼好ですが、彼の意見は、「使わないなら、お金があってもしょうがない」というもの。
兼好の言い分は普通の考えに思われますし、実際、兼好がわざわざ大黒長者の話を『徒然草』に載せているわけですから、大黒長者のお金観は一風変わったものとして提示されているように思えます。しかし、この大黒長者のお金観に似たような話が別の本にも出てきます。その本とは、『徒然草』とは似ても似つかぬドイツの社会学者マックス・ウェーバーによる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』です。
ある大黒長者:
「人間の生きがいは財産を築くことだ。財産を築くコツは心構えにある。その心構えとは、
1. 人間いつまでも生きられるのだと思うこと、そして無常観などは持たないこと。
2. 欲望を抑えること。欲望には限りがないが、財産には限りがある。際限のない欲望は悪と心得て、ささいなことにもお金を使ってはならない。
3. お金を神や主君と心得て大切にすること。くれぐれも、お金を家来のように自由に使えるものだと思ってはならない。
4. 恥ずかしい目にあっても怒ったり、恨んだりしない。
5. 正直で約束を守ること。
これらの心構えを持てば、あたかも火が乾いているものに就き、水が低い方に流れていくように(自然と)お金が貯まるだろう。お金が貯まれば欲望を満たさなくても心はつだって愉しいものだ。」
欲望をおさえ、お金を使わないようにする、こういった大黒長者の考えに対し、兼好は大反対。兼好の言い分は以下の通り。
兼好:
「そもそも人間は欲望を成し遂げようとして財産を求める。お金が大事なのは、それが欲望を満たすたづき・手段となるからだ。欲望があっても我慢し、お金があっても使わないのは、まったく貧乏人に等しい。大黒長者の教えは、むしろ世間的な欲望を捨て、貧乏を託ってはならない、と言っているように聞こえる。こう考えると、貧乏と金持ちの区別なぞあったものではない。悟りは迷いに等しい。大欲は無欲に似ている。」
最後は筆が走ったのか、仏教的な教訓めいたことを述べている兼好ですが、彼の意見は、「使わないなら、お金があってもしょうがない」というもの。
兼好の言い分は普通の考えに思われますし、実際、兼好がわざわざ大黒長者の話を『徒然草』に載せているわけですから、大黒長者のお金観は一風変わったものとして提示されているように思えます。しかし、この大黒長者のお金観に似たような話が別の本にも出てきます。その本とは、『徒然草』とは似ても似つかぬドイツの社会学者マックス・ウェーバーによる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』です。
3.マックス・ウェーバーの「資本主義の精神」
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、禁欲的という言葉に代表されるプロテスタントの生活倫理と「資本主義の精神」との関連を扱った論考です。この論考の画期的な点は、およそ営利欲からは程遠い「プロテスタンティズムの倫理」が、営利欲に結びつけられがちな「資本主義」の精神の成立に関与した、という一見逆説的な指摘をしたことにあります。
「資本主義の精神」とは何か、その精神の一つの表現としてウェーバーは、「時は金なり」に代表されるベンジャミン・フランクリンのお金観を例示します。「時は金なり」とは、時間を労働による対価で換算する考えです。たとえば、1時間映画を見たとしましょう。この1時間のコストは、チケット代1000円だけではなく、その時間働いていた場合に得られた賃金、たとえば1000円、を機会費用として勘定した2000円となります。「時は金なり」のほかにも、「信用は金なり」、「貨幣は繁殖する」などの言葉にフランクリンの考えは代表されます。ウェーバーは、フランクリンのお金観には「自己の資本を増加させることを自己目的と考えるのが各人の義務だという思想」(p.43)があり、「営利は人生の目的と考えられ、人間が物質的生活の要求を満たすための手段とは考えられていない」(p.48)と指摘します。
このフランクリンの考えに現れる「資本主義の精神」の形成に貢献したのが「プロテスタンティズムの倫理」だった、とウェーバーは主張するのです。お金の増殖を自己目的とするような「資本主義の精神」と聞くと、その形成には旺盛な金銭欲が必要だ、と考えがちですが、ウェーバーは「貨幣を渇望する「衝動」の強弱といったものに資本主義とそれ以前の差異があるわけではない。」(p.54)と否定します。では、いったいなにが「資本主義の精神」の形成に貢献したのか。ウェーバーによれば、それは新しい「倫理」、具体的にはプロテスタントにみられる「世俗的禁欲」および「天職義務」(Berufspflicht )でした。
「資本主義の精神」とは何か、その精神の一つの表現としてウェーバーは、「時は金なり」に代表されるベンジャミン・フランクリンのお金観を例示します。「時は金なり」とは、時間を労働による対価で換算する考えです。たとえば、1時間映画を見たとしましょう。この1時間のコストは、チケット代1000円だけではなく、その時間働いていた場合に得られた賃金、たとえば1000円、を機会費用として勘定した2000円となります。「時は金なり」のほかにも、「信用は金なり」、「貨幣は繁殖する」などの言葉にフランクリンの考えは代表されます。ウェーバーは、フランクリンのお金観には「自己の資本を増加させることを自己目的と考えるのが各人の義務だという思想」(p.43)があり、「営利は人生の目的と考えられ、人間が物質的生活の要求を満たすための手段とは考えられていない」(p.48)と指摘します。
このフランクリンの考えに現れる「資本主義の精神」の形成に貢献したのが「プロテスタンティズムの倫理」だった、とウェーバーは主張するのです。お金の増殖を自己目的とするような「資本主義の精神」と聞くと、その形成には旺盛な金銭欲が必要だ、と考えがちですが、ウェーバーは「貨幣を渇望する「衝動」の強弱といったものに資本主義とそれ以前の差異があるわけではない。」(p.54)と否定します。では、いったいなにが「資本主義の精神」の形成に貢献したのか。ウェーバーによれば、それは新しい「倫理」、具体的にはプロテスタントにみられる「世俗的禁欲」および「天職義務」(Berufspflicht )でした。
4.「プロテスタンティズムの倫理」と「資本主義の精神」
一見すると貨幣欲を思わせる「資本主義の精神」が、禁欲的な「プロテスタンティズムの倫理」とどう関連するのでしょうか。
ウェーバーは、「プロテスタンティズムの倫理」の大きな一画を占める思想として、先に挙げた「天職義務」を挙げます。「天職義務」とは、世俗において自己の職業に専心務めることが神の使命にかなうのだ、という思想です。その天職義務の背景となったのがカルヴィニズムに見られる「予定説」でした。予定説とは神の救済を受ける者とそうでないものが、神によって「あらかじめ」決められている、という考えを言います。予定説の立場では、現世におけるいかなる信心・努力も、神による「予定」を変えることはできません。神の定めを人間の行いによって変えられると考えることは不遜であり、不可能だとされたのです。この客観的な、それゆえ仮借なき予定説の支配下に置かれた信者たちに残された道は、「自分が救われているか、否か」を確かめることでした。この歴史的展開のなかで、「善行は、救いをうるための手段としてはどこまでも無力なものだが、…選びを見分ける印しとしては必要不可欠なもの」(p.185)という認識が生まれてきます。そして、救いの確信に至るための「善行」として、神の召命(Beruf)によって定められた「天職」に励む、という思想が生まれました。これが「天職義務」です。天職義務によれば、労働は神の栄誉を確認するためになされ、したがって労働は富への手段であることをやめ、自己目的化します。また、天職の考えは、世俗において労働することが神の御心にかなう、という考えを内包しますから、それまでの修道院での「祈れ、かつ働け」といった世俗を離れた禁欲生活は、世俗化の道をたどります。こうした「世俗内禁欲」は、自己目的化した労働を合理化し、富やそれによる快楽のための労働を否定します。
このように、「世俗的禁欲」、「天職義務」を基礎とする「プロテスタンティズムの倫理」は、労働を自己目的化および合理化し、富は付随的に集積するものの、欲望を満たす手段としては否定されます。こうした「プロテスタンティズムの倫理」はやがて世俗化し、フランクリンに見られるような営利を自己目的とするような「資本主義の精神」へと至るのです。
ウェーバーは、「プロテスタンティズムの倫理」の大きな一画を占める思想として、先に挙げた「天職義務」を挙げます。「天職義務」とは、世俗において自己の職業に専心務めることが神の使命にかなうのだ、という思想です。その天職義務の背景となったのがカルヴィニズムに見られる「予定説」でした。予定説とは神の救済を受ける者とそうでないものが、神によって「あらかじめ」決められている、という考えを言います。予定説の立場では、現世におけるいかなる信心・努力も、神による「予定」を変えることはできません。神の定めを人間の行いによって変えられると考えることは不遜であり、不可能だとされたのです。この客観的な、それゆえ仮借なき予定説の支配下に置かれた信者たちに残された道は、「自分が救われているか、否か」を確かめることでした。この歴史的展開のなかで、「善行は、救いをうるための手段としてはどこまでも無力なものだが、…選びを見分ける印しとしては必要不可欠なもの」(p.185)という認識が生まれてきます。そして、救いの確信に至るための「善行」として、神の召命(Beruf)によって定められた「天職」に励む、という思想が生まれました。これが「天職義務」です。天職義務によれば、労働は神の栄誉を確認するためになされ、したがって労働は富への手段であることをやめ、自己目的化します。また、天職の考えは、世俗において労働することが神の御心にかなう、という考えを内包しますから、それまでの修道院での「祈れ、かつ働け」といった世俗を離れた禁欲生活は、世俗化の道をたどります。こうした「世俗内禁欲」は、自己目的化した労働を合理化し、富やそれによる快楽のための労働を否定します。
このように、「世俗的禁欲」、「天職義務」を基礎とする「プロテスタンティズムの倫理」は、労働を自己目的化および合理化し、富は付随的に集積するものの、欲望を満たす手段としては否定されます。こうした「プロテスタンティズムの倫理」はやがて世俗化し、フランクリンに見られるような営利を自己目的とするような「資本主義の精神」へと至るのです。
5. 兼好と大黒長者、ふたたび。
長々とウェーバーの説を述べてきましたが、『徒然草』第217段との関係はもうおわかりだろうと思います。つまり、大黒長者の資本獲得を自己目的とした禁欲的なお金観には、「資本主義の精神」の端緒が見られるのです。もちろん、大黒長者のお金観に西洋の宗教的背景もなければ、日本の近代的資本主義に貢献したというわけでもありません。しかし、時代も場所もまったく異なる著作と思わぬ形でつながりをもつこと、その普遍性こそ『徒然草』に古典作品に値する深みを与えているのです。
兼好にしてみれば、すさびごととして書いた『徒然草』が、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という長~い題名のドイツの論文と比べられるとはゆめゆめ思ってはいなかったでしょうが。
兼好にしてみれば、すさびごととして書いた『徒然草』が、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という長~い題名のドイツの論文と比べられるとはゆめゆめ思ってはいなかったでしょうが。























![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

