浅井長政と三人の娘~天下人に残った浅井の系譜~
関連キーワード
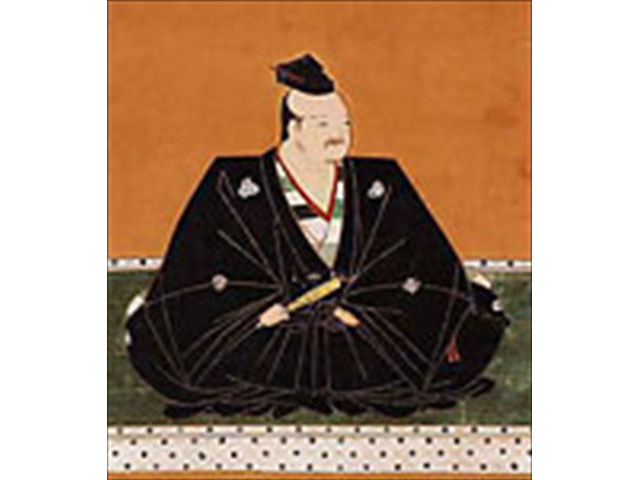
北近江の戦国大名として勇名を馳せた浅井長政ですが、信長の妹・市を妻にしながら信長を裏切り、滅亡した武将として取り上げられることが多い人物です。しかし、この長政の家系から二人の天下人が生まれているのです。今日は、浅井家の系譜について、お伝えします。
北近江の戦国大名 浅井長政
もともと近江国は、京極氏や六角氏といった守護大名が力をもっている地域でした。浅井氏も長政の祖父の亮政の代に下剋上を成し遂げ北近江を領地化したものの、父・久政の代には六角氏に敗れ、臣従していました。
しかし、長政15歳の時に浅井氏は六角氏と戦いました。野良田合戦と言われる戦いで寡兵の浅井氏は、長政の奮戦で六角氏を撃破し、再び独立を成し遂げました。この時、長政の器量を認めた家臣たちは、久政を隠居させ、若い長政を領主に押し立てたのです。戦国大名・浅井家の復権でした。
しかし、長政15歳の時に浅井氏は六角氏と戦いました。野良田合戦と言われる戦いで寡兵の浅井氏は、長政の奮戦で六角氏を撃破し、再び独立を成し遂げました。この時、長政の器量を認めた家臣たちは、久政を隠居させ、若い長政を領主に押し立てたのです。戦国大名・浅井家の復権でした。
信長との同盟
新興勢力で勢いのある長政に、信長が接近してきました。美濃の完全攻略と京都への道を確保したい信長にとって、長政の支援がどうしても必要だったのです。この時、信長は妹の市を長政に娶らせ、同盟を結びました。長政は美貌の妻を深く愛し、この同盟関係はゆるぎないものになるかに思えました。
長政の裏切り
しかし、浅井と織田の同盟は、信長と朝倉義景との対立によって破たんします。朝倉家との闘う場合、浅井家にも伝えるという約定を信長が反故にしたのが原因でした。浅井家は朝倉家と同盟関係にあり、浅井家には親朝倉派の武将が多かったので、通知すれば作戦が朝倉家に筒抜けになる惧れがあったのです。長政も結局は家臣たちを抑えきることができず、信長に反旗を翻したのです。
以後、金ヶ崎の退き口、姉川の合戦、信長包囲網などで長政と信長は対立していきます。
以後、金ヶ崎の退き口、姉川の合戦、信長包囲網などで長政と信長は対立していきます。
浅井家滅亡
しかし、信長は強敵に囲まれながらも凌ぎきり、攻勢に出ます。朝倉家を滅亡させた後、天正元(1573)年、小谷城に攻め寄せた信長は、長政に降伏を勧告しますが、長政は拒否して抗戦を続けます、結局、勢いに乗る信長が小谷城を陥落させ、長政は自害しました。
この時、市は織田家に復帰します。嫡男の万福丸は捉えられ処刑されますが、娘三人は織田家の庇護を受けて成長することになりました。この長政の三人の娘・茶々、初、江だったのです。
この時、市は織田家に復帰します。嫡男の万福丸は捉えられ処刑されますが、娘三人は織田家の庇護を受けて成長することになりました。この長政の三人の娘・茶々、初、江だったのです。
長政の三人の娘
市は、長政死後誰にも嫁がずに暮らしていました。しかし、天正10(1582)年に起きた本能寺の変で信長が死ぬと、市は柴田勝家の許に嫁ぐことになりました。勝家は、市と娘たちをとても大事にしたと言われています。
ところが、その勝家と羽柴秀吉が信長の後継者争いをすることになってしまいます。
天正11(1583)年、勝家と秀吉は近江の賤ケ岳で激突しました。この戦いで敗れた勝家は越前・北ノ庄城で市とともに自刃して果てました。この時に三人の娘は再び助けられました。
ところが、その勝家と羽柴秀吉が信長の後継者争いをすることになってしまいます。
天正11(1583)年、勝家と秀吉は近江の賤ケ岳で激突しました。この戦いで敗れた勝家は越前・北ノ庄城で市とともに自刃して果てました。この時に三人の娘は再び助けられました。
三人娘の運命
この後、三人娘は秀吉の許で庇護を受けることになります。しかし、この生活は三人とってどれほど苦しかったでしょうか。秀吉は、小谷城攻城戦で武勲をあげており、父・長政の仇ともいえる存在でした。そして、賤ケ岳では義父・勝家だけでなく、母・市までも自害に追い込んだ正真正銘の親の仇でした。
しかし、長女の茶々にはさらに過酷な運命が待っていました。その仇である秀吉の側室として迎えられることになるのです。内心はどうであろうと、天下人の意向に逆らえません。茶々は秀吉の側室となり、後に秀吉の子・秀頼を生むことになるのです。
一方、次女の初は、名門・京極家の京極高次に嫁ぎます。京極家はかつての浅井氏の主筋にあたる家柄でした。初にとって高次は従兄にあたる存在でした。この二人の間には子ができませんでした。また、三女の江は二度の婚姻を経て、三度目に徳川秀忠の継室として徳川家に輿入れします。天下を巡って争う因縁にある大名家にそれぞれが嫁いでいったのです。
しかし、長女の茶々にはさらに過酷な運命が待っていました。その仇である秀吉の側室として迎えられることになるのです。内心はどうであろうと、天下人の意向に逆らえません。茶々は秀吉の側室となり、後に秀吉の子・秀頼を生むことになるのです。
一方、次女の初は、名門・京極家の京極高次に嫁ぎます。京極家はかつての浅井氏の主筋にあたる家柄でした。初にとって高次は従兄にあたる存在でした。この二人の間には子ができませんでした。また、三女の江は二度の婚姻を経て、三度目に徳川秀忠の継室として徳川家に輿入れします。天下を巡って争う因縁にある大名家にそれぞれが嫁いでいったのです。
天下を巡る争いが引き裂いた姉妹の仲
豊臣家に臣従した徳川家康でしたが、秀吉死後、天下への野望を露わにします。慶長5(1600)年の関ケ原の戦いで、大きな敵対勢力であった石田三成などの勢力を滅ぼした家康は、慶長14(1614)年の大坂冬の陣、慶長15(1615)年の大坂夏の陣で、豊臣家を滅ぼしました。茶々は秀頼とともに大阪城で自害して果てました。一方の、徳川家に嫁いだ江は、嫡男の家光を産みました。しかし、内心はどうだったのでしょうか。ともに苦労を分かち合ってきた姉の死を悲しんでいたのに違いありません。
生き残った江は、姉の初とともに京都の養源院で淀と秀頼の菩提を弔う法要を行っています。また、火災で養源院が焼失した際には、秀忠に掛け合い、すぐに再建させています。
この養源院こそ、実は長政と市の菩提を弔うために淀が秀吉に作ってもらった寺でした。
三姉妹は時代の波に翻弄され、敵味方に分かれてしまいました。そして、それぞれの家で嫡男を産んだことで、浅井の血は天下人の系譜の中に残ったのです。 しかし、三姉妹にとってそうして運命は幸せだったとは言えないのではないでしょうか。
父母が眠る養源院こそ、三姉妹がかつての小谷城で過ごした日々に帰れる唯一の空間であったのかも知れません。
生き残った江は、姉の初とともに京都の養源院で淀と秀頼の菩提を弔う法要を行っています。また、火災で養源院が焼失した際には、秀忠に掛け合い、すぐに再建させています。
この養源院こそ、実は長政と市の菩提を弔うために淀が秀吉に作ってもらった寺でした。
三姉妹は時代の波に翻弄され、敵味方に分かれてしまいました。そして、それぞれの家で嫡男を産んだことで、浅井の血は天下人の系譜の中に残ったのです。 しかし、三姉妹にとってそうして運命は幸せだったとは言えないのではないでしょうか。
父母が眠る養源院こそ、三姉妹がかつての小谷城で過ごした日々に帰れる唯一の空間であったのかも知れません。
浅井長政 父・久政より家督を奪う

まだ長政の父である久政が当主であったころの浅井家は、南近江の六角家の支配下にある一国人に過ぎませんでした。
かつては北近江の守護であった京極家の一家臣に過ぎなかった祖父・亮政が、主家に対して下克上を成し遂げ独立し世間から注目されたのとは対照的にです。
そのため長政も、六角家の当主である六角義賢から一字をもらって「賢政」と名乗らされただけではなく、六角家の重臣とはいえ家臣に過ぎない平井定武の娘を正室に迎えねばなりませんでした。
このように六角家に臣従したかのような父・久政の政事を浅井家に仕えている家臣たちは苦々しく見ていました。
それは長政も同じで、永禄2年(1559年)、家臣たちの思惑に乗る形で父・久政に叛旗を翻しました。
久政は隠居に追い込まれ、長政も六角家との手切れを表明し、名前を「賢政」から「長政」に。正室となっていた平井定武の娘とは離縁し定武の元へ送り返しました。
それらと平行して六角家方の国人衆にも調略の手を延ばし、近々起こるであろう対六角家との戦いに備えました。
こうして六角家との戦は避けられないものになっていったのです。
かつては北近江の守護であった京極家の一家臣に過ぎなかった祖父・亮政が、主家に対して下克上を成し遂げ独立し世間から注目されたのとは対照的にです。
そのため長政も、六角家の当主である六角義賢から一字をもらって「賢政」と名乗らされただけではなく、六角家の重臣とはいえ家臣に過ぎない平井定武の娘を正室に迎えねばなりませんでした。
このように六角家に臣従したかのような父・久政の政事を浅井家に仕えている家臣たちは苦々しく見ていました。
それは長政も同じで、永禄2年(1559年)、家臣たちの思惑に乗る形で父・久政に叛旗を翻しました。
久政は隠居に追い込まれ、長政も六角家との手切れを表明し、名前を「賢政」から「長政」に。正室となっていた平井定武の娘とは離縁し定武の元へ送り返しました。
それらと平行して六角家方の国人衆にも調略の手を延ばし、近々起こるであろう対六角家との戦いに備えました。
こうして六角家との戦は避けられないものになっていったのです。
浅井長政の初陣 野良田の戦い
そして永禄3年(1560年)には愛知郡の有力国人であった肥田城主の高野備前守を寝返らせることに成功します。
その裏切りに対して、今は隠居の身となっていた六角義賢は激怒し肥田城に対して軍を率いて押し寄せ、世にも珍しい水攻めを行いますが失敗してしまいました。
そうこうしているうちに長政も援軍を率いて到着し、両軍は宇曾川を挟んで対峙します。
六角軍の兵力は総勢2万5000。対する浅井軍は1万1000と兵力には倍以上の差がありました。
さらに六角軍には先鋒に蒲生定秀と永原重興を配置し、第2陣には楢崎壱岐守に田中治部大輔らを配置するなど、六角軍の勝利は誰が見てもゆるがないものになっていました。
両軍の火蓋が切って落とされると倍以上の兵力を有する六角軍が有利に戦を進めました。
しかしそこで六角軍は油断し長政に対して隙を見せてしまいます。
もちろん長政がそこを見過ごすはずがありません。
すわ反撃ぞと、長政が押し返し、ここが正念場と新手を斬り込ませるなど徹底的に六角軍に攻め入りました。
六角軍は防ぎきれず、居城である観音寺城に撤退し、戦も気がつけば劣勢だった浅井軍の勝利に終わっていました。
「江濃記」によると、この戦の死者は、六角軍920人に対し、浅井軍は400人と伝わっており、戦の行われた地名からこの戦は、後世「野良田の戦い」と呼ばれ長政の初陣として一躍有名になりました。
この勝利により、長く臣従させられていた六角家よりの独立を果たし、長政は北近江の小谷城を根城に勢力を拡大することになるのです。
その裏切りに対して、今は隠居の身となっていた六角義賢は激怒し肥田城に対して軍を率いて押し寄せ、世にも珍しい水攻めを行いますが失敗してしまいました。
そうこうしているうちに長政も援軍を率いて到着し、両軍は宇曾川を挟んで対峙します。
六角軍の兵力は総勢2万5000。対する浅井軍は1万1000と兵力には倍以上の差がありました。
さらに六角軍には先鋒に蒲生定秀と永原重興を配置し、第2陣には楢崎壱岐守に田中治部大輔らを配置するなど、六角軍の勝利は誰が見てもゆるがないものになっていました。
両軍の火蓋が切って落とされると倍以上の兵力を有する六角軍が有利に戦を進めました。
しかしそこで六角軍は油断し長政に対して隙を見せてしまいます。
もちろん長政がそこを見過ごすはずがありません。
すわ反撃ぞと、長政が押し返し、ここが正念場と新手を斬り込ませるなど徹底的に六角軍に攻め入りました。
六角軍は防ぎきれず、居城である観音寺城に撤退し、戦も気がつけば劣勢だった浅井軍の勝利に終わっていました。
「江濃記」によると、この戦の死者は、六角軍920人に対し、浅井軍は400人と伝わっており、戦の行われた地名からこの戦は、後世「野良田の戦い」と呼ばれ長政の初陣として一躍有名になりました。
この勝利により、長く臣従させられていた六角家よりの独立を果たし、長政は北近江の小谷城を根城に勢力を拡大することになるのです。
織田信長との同盟 そして裏切り

織田信長と同盟を結び、その妹である市の方を正室に迎えたことにより、東側からの圧力が無くなった長政はさらに一歩強国への道を踏み出していました。
永禄11年(1568年)9月には、足利義昭を将軍に据えるため信長が京に上洛することになり、それに協力して上洛を阻む旧主・六角家の駆逐にも成功しました。
信長の元ではありましたが、時代の立役者として脚光を浴びることに対してまんざらでもない長政。
しかし長政には一つの懸念がありました。
それは祖父・亮政の代から続く越前朝倉家との同盟です。
亮政が京極家から下克上する際に全面的に協力してくれたのがこの朝倉家であり、この同盟は今も固く守られていました。
しかし、浅井家の同盟者である織田家と盟友朝倉家は仲が悪く、朝倉家と事を構えない事を条件に同盟した長政でしたが雲行きは怪しくなっていました。
そして元亀元年(1570年)、とうとうその時が来てしまったのです。
足利義昭の上洛を成功させた信長よりの上洛命令に朝倉家が従わなかったために、信長は家康と共に長政に無断で朝倉家への侵攻を開始したのです。
浅井家の願いはいとも簡単に破られてしまったのです。
こうなれば古くからの恩に報いるか、愛する妻の兄に味方するか…。
悩んだ長政の出した答えは、越前に侵攻した信長を朝倉家と共同で挟み撃ちにする。つまりは義兄を捨て、朝倉家の味方をしたのです。
「浅井長政 離反」の報を初め信長は信じようとはしませんでした。
しかし次から次にもたらされる長政離反の報に信長も越前からの撤退を決断し、浅井・朝倉連合の追撃を逃れて命からがら京の都に帰りつくのです。
信長が京に戻った時は供回りが10人ほどしかなく、凄惨な撤退戦は後世「金ヶ崎の退き口」と呼ばれるようになりました。
永禄11年(1568年)9月には、足利義昭を将軍に据えるため信長が京に上洛することになり、それに協力して上洛を阻む旧主・六角家の駆逐にも成功しました。
信長の元ではありましたが、時代の立役者として脚光を浴びることに対してまんざらでもない長政。
しかし長政には一つの懸念がありました。
それは祖父・亮政の代から続く越前朝倉家との同盟です。
亮政が京極家から下克上する際に全面的に協力してくれたのがこの朝倉家であり、この同盟は今も固く守られていました。
しかし、浅井家の同盟者である織田家と盟友朝倉家は仲が悪く、朝倉家と事を構えない事を条件に同盟した長政でしたが雲行きは怪しくなっていました。
そして元亀元年(1570年)、とうとうその時が来てしまったのです。
足利義昭の上洛を成功させた信長よりの上洛命令に朝倉家が従わなかったために、信長は家康と共に長政に無断で朝倉家への侵攻を開始したのです。
浅井家の願いはいとも簡単に破られてしまったのです。
こうなれば古くからの恩に報いるか、愛する妻の兄に味方するか…。
悩んだ長政の出した答えは、越前に侵攻した信長を朝倉家と共同で挟み撃ちにする。つまりは義兄を捨て、朝倉家の味方をしたのです。
「浅井長政 離反」の報を初め信長は信じようとはしませんでした。
しかし次から次にもたらされる長政離反の報に信長も越前からの撤退を決断し、浅井・朝倉連合の追撃を逃れて命からがら京の都に帰りつくのです。
信長が京に戻った時は供回りが10人ほどしかなく、凄惨な撤退戦は後世「金ヶ崎の退き口」と呼ばれるようになりました。
義兄・織田信長との激突 姉川の戦い

朝倉軍と共に信長を追撃した長政でしたが、信長は京を抜け無事に本拠地の岐阜城に辿り着くことに成功していました。
一息ついた信長は諸将を集めて、裏切った長政の小谷城を攻略せんと報復戦を開始しました。
義兄と戦う宿命は避けられないとして、長政と5000の兵は朝倉家からの援軍8000と共に姉川を前に二手に分かれて布陣しました。
信長にも家康が援軍として駆けつけ、浅井軍には織田軍が。朝倉軍には家康率いる徳川軍が当たることになりました。
大軍を率いる信長に対して長政の5000は余りにも頼りなく見えました。
しかしそこで目を見張る活躍を見せたのが、先陣を務める家臣・磯野員昌の戦いぶりでした。
織田軍を次々と破り、信長の本陣の間近まで攻め入り、信長も陣を捨てる覚悟をしたといいます。
あと少しで信長を討てるかも知れぬ!
そう確信した矢先に別の箇所で綻びができてしまいました。
朝倉軍より寡兵な徳川軍が、浅井・朝倉両軍の陣が伸びきっていることに気付き、家臣の榊原康政に命じて側面を攻めさせたのです。
徳川軍の攻撃に朝倉軍は壊走。それを見た浅井軍が優勢だったにも関わらず負けたと思い込み次々と戦線を離脱し、戦は織田・徳川連合の勝利に終わりました。
この戦で長政は生き残ったものの、遠藤直経を始め主だった武将が討死し急速に弱体化していくのです。
後世では「姉川の戦い」として知られるこの戦も、布陣した土地に鑑み、浅井家では「野村合戦」と呼ばれたのでした。
一息ついた信長は諸将を集めて、裏切った長政の小谷城を攻略せんと報復戦を開始しました。
義兄と戦う宿命は避けられないとして、長政と5000の兵は朝倉家からの援軍8000と共に姉川を前に二手に分かれて布陣しました。
信長にも家康が援軍として駆けつけ、浅井軍には織田軍が。朝倉軍には家康率いる徳川軍が当たることになりました。
大軍を率いる信長に対して長政の5000は余りにも頼りなく見えました。
しかしそこで目を見張る活躍を見せたのが、先陣を務める家臣・磯野員昌の戦いぶりでした。
織田軍を次々と破り、信長の本陣の間近まで攻め入り、信長も陣を捨てる覚悟をしたといいます。
あと少しで信長を討てるかも知れぬ!
そう確信した矢先に別の箇所で綻びができてしまいました。
朝倉軍より寡兵な徳川軍が、浅井・朝倉両軍の陣が伸びきっていることに気付き、家臣の榊原康政に命じて側面を攻めさせたのです。
徳川軍の攻撃に朝倉軍は壊走。それを見た浅井軍が優勢だったにも関わらず負けたと思い込み次々と戦線を離脱し、戦は織田・徳川連合の勝利に終わりました。
この戦で長政は生き残ったものの、遠藤直経を始め主だった武将が討死し急速に弱体化していくのです。
後世では「姉川の戦い」として知られるこの戦も、布陣した土地に鑑み、浅井家では「野村合戦」と呼ばれたのでした。






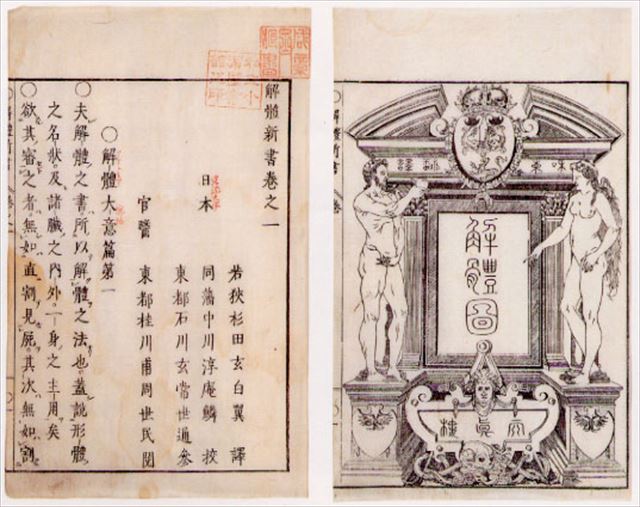
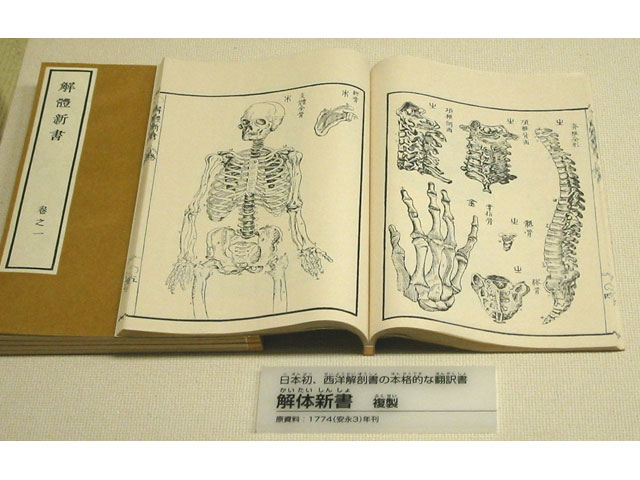















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

