津軽為信、石田三成の血筋を残した「仁義」に厚い津軽の戦国武将とは
関連キーワード

陸奥の津軽の地を領有し、弘前城を築いた戦国武将・津軽為信。元々は、南部家の一族であったものの、本家に対し独立を画策します。そのきっかけになったのは、本家の南部家の家督争いでした。
南部家13代当主春継が急死し、その跡継ぎの座を南部家一族である石川信直と九戸実親が争います。為信は、実親側に立って必死に応援しました。しかし、結果として石川家の信直が南部家の跡取りに決定します。この後継争いで、為信と信直に間に溝ができました。以後、為信排除に躍起になる信直に対し、為信は津軽領の独立を画策します。津軽家と南部家は以後、不倶戴天の敵として果てしない抗争を繰り広げていくのです。
南部家13代当主春継が急死し、その跡継ぎの座を南部家一族である石川信直と九戸実親が争います。為信は、実親側に立って必死に応援しました。しかし、結果として石川家の信直が南部家の跡取りに決定します。この後継争いで、為信と信直に間に溝ができました。以後、為信排除に躍起になる信直に対し、為信は津軽領の独立を画策します。津軽家と南部家は以後、不倶戴天の敵として果てしない抗争を繰り広げていくのです。
孤立した津軽為信
天正13(1585)年、最上義光からの情報で、天下の情勢は豊臣秀吉が中心になっているという情勢を知ると、為信は秀吉と気脈を通じようとします。この年、自ら上洛するため鰺ヶ沢から海路、京を目指しましたが、嵐のために松前沖まで流されて断念。
その後も陸路によって毎年、上洛を目指しますが、周辺の敵対勢力が妨害し、上洛はならなかったのです。秀吉に上洛し謁見しなければ、服属とは見做されない状況だったため為信は焦ります。
天正17(1589)年、為信はようやく家臣を上洛させることに成功しました。この時の、取次窓口になったのが石田三成だったのです。
この時、為信は危機に陥っていました。為信の仇敵・南部信直が、為信を秀吉の惣無事令に反する敵であると前田利家を通じて秀吉に訴えていたのです。この訴えに対し、津軽家を守ったのが三成だったのです。以後、為信は三成と秀吉に恩義を感じます。
その後も陸路によって毎年、上洛を目指しますが、周辺の敵対勢力が妨害し、上洛はならなかったのです。秀吉に上洛し謁見しなければ、服属とは見做されない状況だったため為信は焦ります。
天正17(1589)年、為信はようやく家臣を上洛させることに成功しました。この時の、取次窓口になったのが石田三成だったのです。
この時、為信は危機に陥っていました。為信の仇敵・南部信直が、為信を秀吉の惣無事令に反する敵であると前田利家を通じて秀吉に訴えていたのです。この訴えに対し、津軽家を守ったのが三成だったのです。以後、為信は三成と秀吉に恩義を感じます。
為信の義
天正19(1591)年、為信の盟友だった九戸政実(実親の兄)が、南部家並びに豊臣政権に対し、叛旗を翻しました。世に言う「九戸政実の乱」です。この乱には、鎮圧側として為信も加わりました。しかし、政実は、為信とともに南部信直に対抗した人物でした。九戸勢5000に対し、鎮圧軍6万。政実にとっては勝ち目のない戦でした。為信は、せめて血筋だけでも繋げてやりたいと考え、無断で九戸家の3歳の男子を家臣の懐に抱かせ、秋田に逃がしました。発覚したら取り潰し覚悟の上での処置です。こうして、九戸家の血筋は残り、弘前藩3代藩主・信義の代に家臣に取り立て、九戸家を再興させたのです。
為信の義 再び
秀吉死後、三成は有力大名である徳川家康と対立し、関ケ原の合戦が勃発しました。
関ヶ原の決戦は、家康の西軍切り崩し工作が功を奏し、たった一日で決着がついてしまいました。三成は再起を図って逃走を続けましたが、潜伏中についに捉えられ、処刑されてしまいます。
その後、三成の居城であった佐和山城が家康方の軍勢に攻められ、三成の父・正継や三成の妻・皎月院(うた)など多くの石田家一族が自害したと言われています。
三成には子供が三男三女がありました。敗れた石田家の血筋ですから、後世の憂いを断つためにこの子供たちは殺されても不思議はありません。
しかし、嫡男の重家は、三成が敗れたという報がもたらされると、すぐに出家し、京都の妙心寺に匿われました。
この時、重家を助けたのは豪商・角倉了以の従兄弟で妙心寺住職だった伯蒲慧稜でした。しかも、慧稜は隠すことなく、堂々と京都所司代に重家の助命嘆願を行い、重家が仏門に入ることを条件に許されたのです。仏門に入るということは、一般的には政治に一切関わらないことを意味しました。また、妻帯できないので、子孫が残る惧れもなくなるのです。過去にも仏門に入ることで命を許された例もあり、重家もその一例であったと言えるでしょう。ただ、それでは、他の子どもたちはどうだったでしょうか。ここでも三成の恩義に為信が応えたのです。
三成と親交があり、秀吉の小姓として傍に仕えた津軽信建は、二人を密かに陸奥に連れて帰ります。この行動は、独断であったと言われます。為信は、戸惑いながらも長男の判断を咎めませんでした。重成は杉山源吾と名を変えて、津軽家に守られます。
そして、杉山家は代々、津軽家の重臣として仕えることになったのです。政実の時と同様、三成の子を無断で匿ったら、取り潰される可能性があります。
それを承知で為信は次男・重成と三女辰姫を津軽の地で匿ったのです。
三成と親交があり、秀吉の小姓として傍に仕えた津軽信建は、二人を密かに陸奥に連れて帰ります。この行動は、独断であったと言われます。
それだけでなく、辰姫は自分たちを助けてくれた信建の弟・信枚の妻に迎えられました。
関ヶ原の決戦は、家康の西軍切り崩し工作が功を奏し、たった一日で決着がついてしまいました。三成は再起を図って逃走を続けましたが、潜伏中についに捉えられ、処刑されてしまいます。
その後、三成の居城であった佐和山城が家康方の軍勢に攻められ、三成の父・正継や三成の妻・皎月院(うた)など多くの石田家一族が自害したと言われています。
三成には子供が三男三女がありました。敗れた石田家の血筋ですから、後世の憂いを断つためにこの子供たちは殺されても不思議はありません。
しかし、嫡男の重家は、三成が敗れたという報がもたらされると、すぐに出家し、京都の妙心寺に匿われました。
この時、重家を助けたのは豪商・角倉了以の従兄弟で妙心寺住職だった伯蒲慧稜でした。しかも、慧稜は隠すことなく、堂々と京都所司代に重家の助命嘆願を行い、重家が仏門に入ることを条件に許されたのです。仏門に入るということは、一般的には政治に一切関わらないことを意味しました。また、妻帯できないので、子孫が残る惧れもなくなるのです。過去にも仏門に入ることで命を許された例もあり、重家もその一例であったと言えるでしょう。ただ、それでは、他の子どもたちはどうだったでしょうか。ここでも三成の恩義に為信が応えたのです。
三成と親交があり、秀吉の小姓として傍に仕えた津軽信建は、二人を密かに陸奥に連れて帰ります。この行動は、独断であったと言われます。為信は、戸惑いながらも長男の判断を咎めませんでした。重成は杉山源吾と名を変えて、津軽家に守られます。
そして、杉山家は代々、津軽家の重臣として仕えることになったのです。政実の時と同様、三成の子を無断で匿ったら、取り潰される可能性があります。
それを承知で為信は次男・重成と三女辰姫を津軽の地で匿ったのです。
三成と親交があり、秀吉の小姓として傍に仕えた津軽信建は、二人を密かに陸奥に連れて帰ります。この行動は、独断であったと言われます。
それだけでなく、辰姫は自分たちを助けてくれた信建の弟・信枚の妻に迎えられました。
信建の死によって、信枚は陸奥国弘前藩2代目藩主になり、辰姫は藩主の妻になったのです。信枚と辰姫の仲は睦まじく、二人の間に生まれた長男・信義は3代目藩主になりました。
為信は、領国独立のために汚い手も使っており、毀誉褒貶の激しい人物です。しかし、自分を助けてくれた相手には、危険を顧みずに助ける温情も兼ね備えていた人物でした。
この為信の仁のおかげで、九戸家・石田家の血筋は現在まで残ることができたのです。
為信は、領国独立のために汚い手も使っており、毀誉褒貶の激しい人物です。しかし、自分を助けてくれた相手には、危険を顧みずに助ける温情も兼ね備えていた人物でした。
この為信の仁のおかげで、九戸家・石田家の血筋は現在まで残ることができたのです。






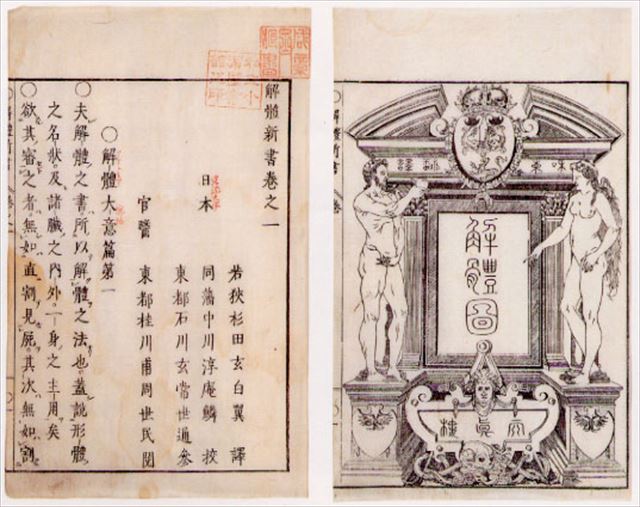
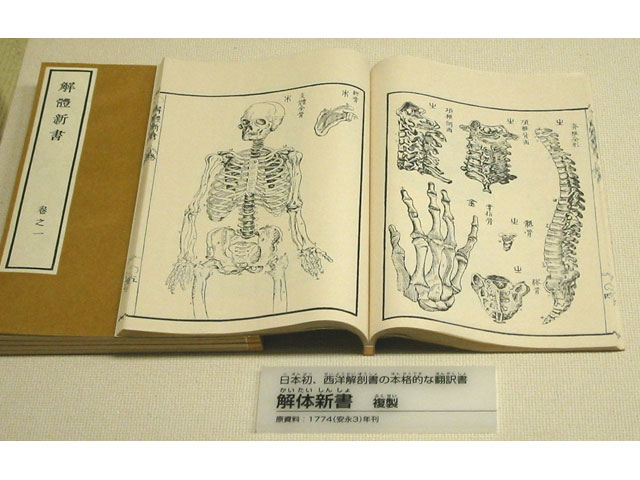















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

