北条政子と静御前、あなたはどっち派?
関連キーワード
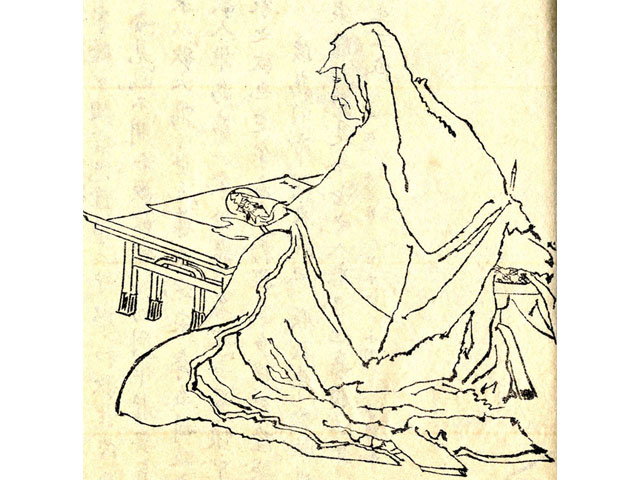
北条政子が静御前をかばった鶴岡八幡宮の名シーンに何を思う?
北条政子といえば源氏を統率し、鎌倉幕府の守り神的存在となった、棟梁・源頼朝の妻です。そのイメージから、女性的な魅力よりは、鎌倉幕府の屋台骨的ゴッドマザーとして「なんだか厄介そうな女性だな」と思われがちではないでしょうか。
「源氏の女」の中でも、男心をくすぐる柔和な女性的イメージとして、北条政子よりも男性的に恋人にしたいステータスが高く人気があるのは、静御前ではないでしょうか? 鶴岡八幡宮、敵陣のど真ん中とも言える舞台の上で彼女が舞ったのは、自分をこんな目にあわせた不甲斐ない恋人への恨み節どころか、愛し合った日々を切々と綴った歌でした。 「しづやしづ」 の歌の冒頭にあるこの言葉、もしかしたら義経が「しづや」と呼びかける優しい声を回想していたのかもしれません。 男からしたらたまらないいじらしさではないでしょうか? しかし、忘れてはならないのは、この晴れ舞台をセッティングし、源家の勘気から静御前をかばった女性こそ、北条政子だということです。 義経がどこへ向かって逃亡しているのか黙秘しているにもかかわらず、鶴岡八幡宮に頼朝が参詣するという晴れの場で、義経への愛情と「昔を今になすよしもがな」という現政権批判をしてのけた静御前の肝の太さも相当なものですが、激怒した頼朝に向かって「私も彼女の立場なら、あれくらいやりましたよ」と夫への愛情と自分たちの非情さを一度に表現してのけた北条政子は、とても現代的な知性を持つ女性に思えます。 男にとって都合のいい女、女にとってカッコイイと思える女。源氏のを彩るふたりのの女性の人柄をたどってみましょう。
「源氏の女」の中でも、男心をくすぐる柔和な女性的イメージとして、北条政子よりも男性的に恋人にしたいステータスが高く人気があるのは、静御前ではないでしょうか? 鶴岡八幡宮、敵陣のど真ん中とも言える舞台の上で彼女が舞ったのは、自分をこんな目にあわせた不甲斐ない恋人への恨み節どころか、愛し合った日々を切々と綴った歌でした。 「しづやしづ」 の歌の冒頭にあるこの言葉、もしかしたら義経が「しづや」と呼びかける優しい声を回想していたのかもしれません。 男からしたらたまらないいじらしさではないでしょうか? しかし、忘れてはならないのは、この晴れ舞台をセッティングし、源家の勘気から静御前をかばった女性こそ、北条政子だということです。 義経がどこへ向かって逃亡しているのか黙秘しているにもかかわらず、鶴岡八幡宮に頼朝が参詣するという晴れの場で、義経への愛情と「昔を今になすよしもがな」という現政権批判をしてのけた静御前の肝の太さも相当なものですが、激怒した頼朝に向かって「私も彼女の立場なら、あれくらいやりましたよ」と夫への愛情と自分たちの非情さを一度に表現してのけた北条政子は、とても現代的な知性を持つ女性に思えます。 男にとって都合のいい女、女にとってカッコイイと思える女。源氏のを彩るふたりのの女性の人柄をたどってみましょう。
頼朝の妻と義経の妻、ふたりの格の違いは?
武家にとっては神仏のごとき存在として崇められている源氏の血筋。その棟梁といったら、都で己の安泰ばかりを気にして民の不遇を見殺しにする公家に対抗する旗印として、何よりも大切にしなければいけない存在です。
その妻もまた、誰もが認める高貴な血筋が求められるかと思いきや、彼女たちの出自はそうではありませんでした。
まず、源家の棟梁・源頼朝の妻である北条政子は、田舎の地方豪族の娘でした。
平清盛の政敵であった義朝が「平治の乱」にて敗北し、無念の内に殺害された後、逃亡していた頼朝は捕らえられ、殺されるところを減刑されて島流しとなった場所が、伊豆の蛭ヶ小島でした。
源氏の棟梁の血を引く跡取り息子を世間の目から忘れさせる場所として選ばれた蛭ヶ小島近辺は、もちろん平氏の勢力が強い場所です。その地を収める豪族であった北条家もまた、平氏の流れをくむ一族でした。
頼朝の監視役として選ばれたのが、伊豆に住まう東国武者をまとめあげていた北条時政で、その娘が政子なのです。
つまり政子は、平氏とゆかりある地方豪族の娘にすぎません。
一方、頼朝の弟・義経の恋人であった静御前とは、どういう立場の人だったのでしょう?
静御前といえば、当代一の呼び声も高い白拍子でした。公家や有力者の邸宅に出入りして、その場の応じた歌や舞を、時に即興で舞う女芸人は、美貌や舞の見事さだけではなく、機転と知性、品性が重要であったことは言うまでもありません。
頼朝も義経も、家柄や親のステータスで恋人を選んだわけではないところが、やはり兄弟だと言えます。
その妻もまた、誰もが認める高貴な血筋が求められるかと思いきや、彼女たちの出自はそうではありませんでした。
まず、源家の棟梁・源頼朝の妻である北条政子は、田舎の地方豪族の娘でした。
平清盛の政敵であった義朝が「平治の乱」にて敗北し、無念の内に殺害された後、逃亡していた頼朝は捕らえられ、殺されるところを減刑されて島流しとなった場所が、伊豆の蛭ヶ小島でした。
源氏の棟梁の血を引く跡取り息子を世間の目から忘れさせる場所として選ばれた蛭ヶ小島近辺は、もちろん平氏の勢力が強い場所です。その地を収める豪族であった北条家もまた、平氏の流れをくむ一族でした。
頼朝の監視役として選ばれたのが、伊豆に住まう東国武者をまとめあげていた北条時政で、その娘が政子なのです。
つまり政子は、平氏とゆかりある地方豪族の娘にすぎません。
一方、頼朝の弟・義経の恋人であった静御前とは、どういう立場の人だったのでしょう?
静御前といえば、当代一の呼び声も高い白拍子でした。公家や有力者の邸宅に出入りして、その場の応じた歌や舞を、時に即興で舞う女芸人は、美貌や舞の見事さだけではなく、機転と知性、品性が重要であったことは言うまでもありません。
頼朝も義経も、家柄や親のステータスで恋人を選んだわけではないところが、やはり兄弟だと言えます。
北条政子の恋した頼朝とは
頼朝が流された当時の蛭ヶ小島、および伊豆は、富士山噴火(貞観大噴火)の傷跡もまだ生々しい、溶岩がゴロゴロと転がっている状態だったことでしょう。その土地の豪族という荒々しい環境で育った北条政子にとって、京とは遠いおとぎの国であり、そこからやってきた源頼朝という14歳の男子は、北条の男子と同じ男性とは思えない雅やかさに包まれた、キラキラしたスーパースターに見えたに違いありません。
ちょっとした物腰や話し言葉に京のハイソサエティな品格が感じ取れる頼朝は、「罪人のくせにすかしやがって」と北条家の男性からは嫌われるタイプだったかもしれませんが、田舎の少女の心を一瞬で奪う貴種でした。
こともあろうに敵の捕虜に恋してしまった北条家の総領娘の目を覚まそうと、別の縁談を取り決めた父・時政でしたが、「障害があるほど恋は燃え上がる」の言葉のまま、政子は雨のふりそぼる夜道を駆け抜け、頼朝と駆け落ちしたそうです。
鶴岡八幡宮で頼朝を諭した「私もそうしますよ」という言葉に、嘘はなかったのです。
ちょっとした物腰や話し言葉に京のハイソサエティな品格が感じ取れる頼朝は、「罪人のくせにすかしやがって」と北条家の男性からは嫌われるタイプだったかもしれませんが、田舎の少女の心を一瞬で奪う貴種でした。
こともあろうに敵の捕虜に恋してしまった北条家の総領娘の目を覚まそうと、別の縁談を取り決めた父・時政でしたが、「障害があるほど恋は燃え上がる」の言葉のまま、政子は雨のふりそぼる夜道を駆け抜け、頼朝と駆け落ちしたそうです。
鶴岡八幡宮で頼朝を諭した「私もそうしますよ」という言葉に、嘘はなかったのです。
北条政子の実家はどんな感じだった?
自ら開墾した土地を武力で守る武士勢力のひとつであった、伊豆を本拠地とした北条氏は、時の権力者・平氏の一派として、東国武者をまとめ上げる存在でした。その惣領姫が、主人の敵勢力の総領息子である頼朝の妻となることは、端的に言えば裏切り行為となります。
23歳で頼朝の監視役の命を受けた時政でしたが、娘の想いの深さを感じ、腹を括ってこの夫婦を保護しました。そして20年後、力をしっかり蓄えた北条家は、頼朝の手足となって平家を打ち滅ぼしたのです。
23歳で頼朝の監視役の命を受けた時政でしたが、娘の想いの深さを感じ、腹を括ってこの夫婦を保護しました。そして20年後、力をしっかり蓄えた北条家は、頼朝の手足となって平家を打ち滅ぼしたのです。
北条政子と静御前、芯は似ていた女性たち
北条政子の運命の恋は、源平の逆転劇を招き、その後はるか江戸時代まで続く武士の世の礎となりました。
それほどの恋の炎を燃え上がらせた北条政子だからこそ、義弟の妻・静御前の名誉や命を守ろうと幾度も夫・頼朝に口添えをしたのでしょう。
情の深さと視野の広さ、それが、頼朝亡き後の鎌倉幕府を支えたゴットマザーの源だったのかもしれません。
それほどの恋の炎を燃え上がらせた北条政子だからこそ、義弟の妻・静御前の名誉や命を守ろうと幾度も夫・頼朝に口添えをしたのでしょう。
情の深さと視野の広さ、それが、頼朝亡き後の鎌倉幕府を支えたゴットマザーの源だったのかもしれません。
実は頼朝よりも坂東武者の気質を知るのが北条政子
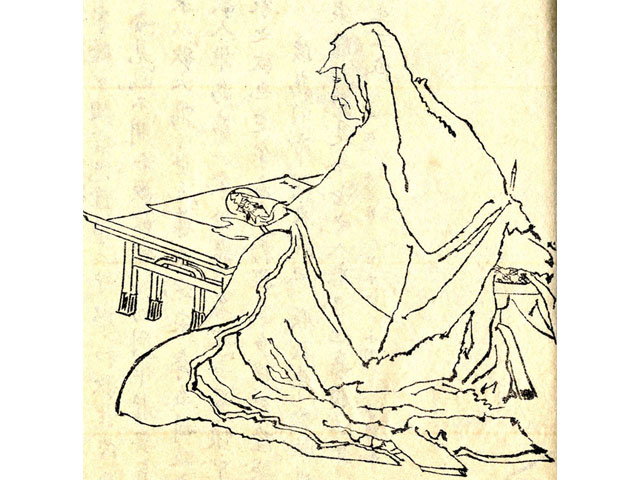
「平家にあらずんば人にあらず」という栄耀栄華を極めた平家一族を西の果てまで追い詰め、壇ノ浦の波間に沈めた源頼朝率いる源氏一族、その華麗なる逆襲から勝利へとたどる軌跡は、いつの時代の人々も魅了されてしまいます。
源氏の棟梁・源頼朝の妻が尼将軍・北条政子ですが、歴史をつぶさに見てみると、どうやら「北条政子の夫が、源頼朝」と言っても過言ではないほどの活躍を見せた、魅力的な女傑だったようです。
源頼朝は、血筋は源氏の直系の御曹司という申し分のないものながら、平清盛に捕縛され、歴史の敗者として、後は静かなエンディングを待つばかりの存在でした。
時は平家の世。平家に逆らうようなそぶりを少しでも見せようものなら、すぐさま頼朝と同じ憂き目にあう情勢でした。
もし、北条政子が源頼朝という厄介な存在に恋することがなければ、勇猛なる坂東武者が頼朝のために立ち上がり、その配下になることもなかったことでしょう。
伊豆の北条率いる坂東武者にとって、源頼朝は牢人に過ぎず、少年頼朝にとってもまた、気性の荒く腕っぷしの強い坂東武者とどう付き合えばいいのか見当もつかなかったに違いなく、その両者の間を固い絆で結びつけた存在が、北条の姫・政子でした。
源氏の棟梁・源頼朝の妻が尼将軍・北条政子ですが、歴史をつぶさに見てみると、どうやら「北条政子の夫が、源頼朝」と言っても過言ではないほどの活躍を見せた、魅力的な女傑だったようです。
源頼朝は、血筋は源氏の直系の御曹司という申し分のないものながら、平清盛に捕縛され、歴史の敗者として、後は静かなエンディングを待つばかりの存在でした。
時は平家の世。平家に逆らうようなそぶりを少しでも見せようものなら、すぐさま頼朝と同じ憂き目にあう情勢でした。
もし、北条政子が源頼朝という厄介な存在に恋することがなければ、勇猛なる坂東武者が頼朝のために立ち上がり、その配下になることもなかったことでしょう。
伊豆の北条率いる坂東武者にとって、源頼朝は牢人に過ぎず、少年頼朝にとってもまた、気性の荒く腕っぷしの強い坂東武者とどう付き合えばいいのか見当もつかなかったに違いなく、その両者の間を固い絆で結びつけた存在が、北条の姫・政子でした。
北条政子は生まれながらの姫将軍
源氏の棟梁に恋した政子の数奇な運命は、愛する夫と死別した後から、急激に荒れ出します。政権を無事に長子・頼家に引き継いだはずが、2代目としての気負いが目を曇らせたのか、北条家や古参の家臣から権力を吸い上げ、将軍への中央集権を性急に行ったのです。
御家人たちからの不穏な空気を感じた北条政子は、腹を痛めて産んだ実の息子に加担することなく、頼家を政権から外し、次子・実朝を3代目に据える決断を下しました。 並みの母親なら、我が子可愛さが優先されそうなものですが、北条政子は違いました。
夫・頼朝とともに、戦乱に翻弄される時代を泳ぎ、政権維持の難しさを実地で学んできた女傑だからこそ、鎌倉幕府という平和は源家単独でもたらしたものではなく、それを支えた御家人の信頼こそが重要であると、為政者としての俯瞰の視点を持っていたのです。
その姿勢は、実の父・北条時政が起こした謀反に対しても、凛と貫かれました。
北条政子自身が愛情深いからこそ、権力者の肉親愛が政権にとって時に害悪となること、そして頼朝が義経にとった「政治家としての審判」の裏の哀しさを深く理解していたことも、政子が息子二人や父親に行った行動から察することができます。
御家人たちからの不穏な空気を感じた北条政子は、腹を痛めて産んだ実の息子に加担することなく、頼家を政権から外し、次子・実朝を3代目に据える決断を下しました。 並みの母親なら、我が子可愛さが優先されそうなものですが、北条政子は違いました。
夫・頼朝とともに、戦乱に翻弄される時代を泳ぎ、政権維持の難しさを実地で学んできた女傑だからこそ、鎌倉幕府という平和は源家単独でもたらしたものではなく、それを支えた御家人の信頼こそが重要であると、為政者としての俯瞰の視点を持っていたのです。
その姿勢は、実の父・北条時政が起こした謀反に対しても、凛と貫かれました。
北条政子自身が愛情深いからこそ、権力者の肉親愛が政権にとって時に害悪となること、そして頼朝が義経にとった「政治家としての審判」の裏の哀しさを深く理解していたことも、政子が息子二人や父親に行った行動から察することができます。
朝廷vs幕府!御家人たちの心を打った政子のスピーチ
なぜ、源頼朝や自分たち北条家、そして坂東武者やその他の御家人は、武家だというのに政治を朝廷に任せることが出来なくなったのか。
北条政子が「最期の詞」と呼ばれるスピーチを御家人たち相手に行ったのは、「承久の乱」においてでした。
それは、夫・頼朝、坂東武者たち、都にいる公家の勝手な振る舞いに憤る人々が「より良い安全な世の中を作ろう」という思いで戦い、犠牲の上に勝ち取った御家人のための幕府が、政子の息子二人の死によって後継者がいなくなり、都の後鳥羽上皇によって倒幕されようとしていた時でした。
朝廷と幕府、どちらに着くか迷っていた御家人たちを、政子の邸宅に集め、彼女がスピーチした内容とは、朝廷に刃向かう恐ろしさよりも勝る、朝廷にこの政権を返上したらこの先どうなるか、という未来予想図だったのではないでしょうか?
肉親が次々に殺される乱世を生き、自分自身もまたいつ殺されるかもわからない人質として20年間、伊豆で日々を過ごした頼朝だからこそ、御家人の権利を保証し、彼らを守護する幕府を作れたことを忘れ、いっときの恐怖で全てを手放すことの愚かさと、果たして幕府を倒そうとしている朝廷に正当な理由はあるのか、という内容だったという政子のスピーチ。
それは、頼朝以前の時代をつぶさに知る、時代の生き証人・北条政子だからこそできた名演説だったのです。
北条政子が「最期の詞」と呼ばれるスピーチを御家人たち相手に行ったのは、「承久の乱」においてでした。
それは、夫・頼朝、坂東武者たち、都にいる公家の勝手な振る舞いに憤る人々が「より良い安全な世の中を作ろう」という思いで戦い、犠牲の上に勝ち取った御家人のための幕府が、政子の息子二人の死によって後継者がいなくなり、都の後鳥羽上皇によって倒幕されようとしていた時でした。
朝廷と幕府、どちらに着くか迷っていた御家人たちを、政子の邸宅に集め、彼女がスピーチした内容とは、朝廷に刃向かう恐ろしさよりも勝る、朝廷にこの政権を返上したらこの先どうなるか、という未来予想図だったのではないでしょうか?
肉親が次々に殺される乱世を生き、自分自身もまたいつ殺されるかもわからない人質として20年間、伊豆で日々を過ごした頼朝だからこそ、御家人の権利を保証し、彼らを守護する幕府を作れたことを忘れ、いっときの恐怖で全てを手放すことの愚かさと、果たして幕府を倒そうとしている朝廷に正当な理由はあるのか、という内容だったという政子のスピーチ。
それは、頼朝以前の時代をつぶさに知る、時代の生き証人・北条政子だからこそできた名演説だったのです。
伊豆山神社に燃え上がる政子の情熱
生まれながらの坂東武者の姫将軍にして、源頼朝のかたわらで政権の名スタッフとして生き、新たな社会の枠組みをプランニングする参謀となり、御家人たちのゴットマザーとして尊敬を集めた北条政子の若き頃は、その胸に燃え上がらせた恋の炎で北条一族を平家の裏切り者にしてしまったという、恋する乙女そのものでした。
伊豆に流罪にされた源頼朝と北条政子が密会を重ね、恋を育んでいた伊豆山神社は、現在でも「恋愛のパワースポット」として男女問わず大人気です。
北条政子の凛々しさ、一途さ、誠実さに恋してしまったら、足を運ぶことをおすすめします。
◆伊豆山神社
住所 静岡県熱海市伊豆山上野地708 番地1
URL http://izusanjinjya.jp/
伊豆に流罪にされた源頼朝と北条政子が密会を重ね、恋を育んでいた伊豆山神社は、現在でも「恋愛のパワースポット」として男女問わず大人気です。
北条政子の凛々しさ、一途さ、誠実さに恋してしまったら、足を運ぶことをおすすめします。
◆伊豆山神社
住所 静岡県熱海市伊豆山上野地708 番地1
URL http://izusanjinjya.jp/
現代女性の理想とする女性像、北条政子
現代女性の多くがそうであるように、「誰々の妻」というポジションのみでその人物像を探ろうとするとわからなくなるのが、女性を探る上で難しいところです。
北条政子の実家の力なくしては、源頼朝は荒ぶる坂東武者を配下にすることなど無理でしたでしょうし、彼女に愛情がなければ源頼朝を最期まで支えることができなかったことでしょう。
そして彼女自身に知恵とキャリア、政治家としてのセンスがなければ、承久の乱以前に何度となく幕府はあっけなく滅びる危機的状況がありました。
一筋縄ではいかない男性を心酔させる女性リーダーの理想像が、北条政子の生き方を探る上で見えてくるのではないでしょうか。
北条政子の実家の力なくしては、源頼朝は荒ぶる坂東武者を配下にすることなど無理でしたでしょうし、彼女に愛情がなければ源頼朝を最期まで支えることができなかったことでしょう。
そして彼女自身に知恵とキャリア、政治家としてのセンスがなければ、承久の乱以前に何度となく幕府はあっけなく滅びる危機的状況がありました。
一筋縄ではいかない男性を心酔させる女性リーダーの理想像が、北条政子の生き方を探る上で見えてくるのではないでしょうか。
北条政子 最愛の夫・源頼朝の死

源氏の棟梁である源頼朝が平家打倒の功労者である弟・源義経を奥州藤原氏とともに平泉で滅ぼしてから早3年。
建久3年(1192年)には征夷大将軍に任じられ、相模国の鎌倉にて幕府を開いた頼朝は全国の武家の棟梁として君臨していました。
北条政子も頼朝の正室として、頼朝の浮気を水面下で阻止しつつも跡取りに恵まれるなど、比較的うまく事が運んでいました。
しかし建久10年(1199年)、落馬が元で頼朝が急死すると政子の目の前は真っ暗になってしまいます。
2年前には大事な娘・大姫を亡くし、今愛する頼朝を亡くしたことで、自分もここで最後だと思った政子。
後を追いたい自分を抑えたのは、まだ幼い跡取りである頼家や成立して間もない鎌倉幕府の存在でした。
政子は決意し、出家して頼家を補佐する道を選びました。
そんな政子を人々は「尼御台」と呼ぶようになるのです。
建久3年(1192年)には征夷大将軍に任じられ、相模国の鎌倉にて幕府を開いた頼朝は全国の武家の棟梁として君臨していました。
北条政子も頼朝の正室として、頼朝の浮気を水面下で阻止しつつも跡取りに恵まれるなど、比較的うまく事が運んでいました。
しかし建久10年(1199年)、落馬が元で頼朝が急死すると政子の目の前は真っ暗になってしまいます。
2年前には大事な娘・大姫を亡くし、今愛する頼朝を亡くしたことで、自分もここで最後だと思った政子。
後を追いたい自分を抑えたのは、まだ幼い跡取りである頼家や成立して間もない鎌倉幕府の存在でした。
政子は決意し、出家して頼家を補佐する道を選びました。
そんな政子を人々は「尼御台」と呼ぶようになるのです。
2代目・源頼家の暴走
跡を継いだ頼家の評判は決して芳しくありませんでした。
蹴鞠や遊興に耽るならまだしも、有力御家人の妾を奪うなど家来である御家人たちの我慢は限界に達していました。
さらに頼家は、舅である比企能員(ひきよしかず)を重用し、政子の実家である北条家に対して追討令を発します。
しかしタイミング悪く、それを障子越しに聞いてしまった政子は、もはやこれまでと実家の父・北条時政に告げると間を置かずして能員を謀殺。
その勢いでもって政子の名の元、比企氏を滅ぼすと後ろ盾の無くなった頼家を庇うものは誰もなく、頼家は隠居させられてしまいました。
そして失意のまま元久元年(1204年)に亡くなってしまうのです。
蹴鞠や遊興に耽るならまだしも、有力御家人の妾を奪うなど家来である御家人たちの我慢は限界に達していました。
さらに頼家は、舅である比企能員(ひきよしかず)を重用し、政子の実家である北条家に対して追討令を発します。
しかしタイミング悪く、それを障子越しに聞いてしまった政子は、もはやこれまでと実家の父・北条時政に告げると間を置かずして能員を謀殺。
その勢いでもって政子の名の元、比企氏を滅ぼすと後ろ盾の無くなった頼家を庇うものは誰もなく、頼家は隠居させられてしまいました。
そして失意のまま元久元年(1204年)に亡くなってしまうのです。
3代目・源実朝の誕生と父・時政の裏切り
頼家に代わって3代目の征夷大将軍に就任したのは、政子のもう一人の息子で頼家の実弟である源実朝でした。
実朝は兄・頼家と違って専横に走らず、教養に富み、どこか亡き父・頼朝を思わせるようなところがありました。
この子ならば安泰だと政子も思ったことでしょう。
後顧の憂いを断つために先代・頼家の子供たちを全員出家させて寺にいれ、さらに将軍を補佐する「執権」職を設け、その役を実父・北条時政に依頼しました。
ですがその時政がまさかの裏切りを犯すことになるのです。
時政には後妻がいました。
その名は「牧の方」といい、美貌のみならず謀略を好むところもあり、今度はその矛先をあろうことか時政の甥にもあたる源実朝に向けたのです。
権勢欲の強い牧の方の考えはこうでした。
時政との間にできた娘が嫁いでいる有力な御家人・平賀朝雅を将軍にすれば天下人の母として幕府に君臨できる!…と。
もちろん時政も賛同し、事を起こそうとしたその時、二人の前に立ちふさがる者がおりました。
その者の名は北条義時。
政子の弟であり、時政の息子です。
義時は政子に協力をお願いされ、義時も非があるのは時政の方と力を貸したのでした。
陰謀は見事防がれ、平賀朝雅は討たれ、時政と牧の方の二人は出家させられてしまい伊豆に追放され、二度と表舞台に出てくることはありませんでした。
そして功のあった義時が時政に代わって執権職を引き継いだのです。
実朝は兄・頼家と違って専横に走らず、教養に富み、どこか亡き父・頼朝を思わせるようなところがありました。
この子ならば安泰だと政子も思ったことでしょう。
後顧の憂いを断つために先代・頼家の子供たちを全員出家させて寺にいれ、さらに将軍を補佐する「執権」職を設け、その役を実父・北条時政に依頼しました。
ですがその時政がまさかの裏切りを犯すことになるのです。
時政には後妻がいました。
その名は「牧の方」といい、美貌のみならず謀略を好むところもあり、今度はその矛先をあろうことか時政の甥にもあたる源実朝に向けたのです。
権勢欲の強い牧の方の考えはこうでした。
時政との間にできた娘が嫁いでいる有力な御家人・平賀朝雅を将軍にすれば天下人の母として幕府に君臨できる!…と。
もちろん時政も賛同し、事を起こそうとしたその時、二人の前に立ちふさがる者がおりました。
その者の名は北条義時。
政子の弟であり、時政の息子です。
義時は政子に協力をお願いされ、義時も非があるのは時政の方と力を貸したのでした。
陰謀は見事防がれ、平賀朝雅は討たれ、時政と牧の方の二人は出家させられてしまい伊豆に追放され、二度と表舞台に出てくることはありませんでした。
そして功のあった義時が時政に代わって執権職を引き継いだのです。
3代目・源実朝の暗殺

「牧氏事件」と呼ばれた乗っ取り未遂事件から時は経って建保6年(1218年)。
病がちな実朝でしたが、教養に富んだその人柄は朝廷より大変気に入られ、さらに官位が高まるとともに実朝の朝廷への忠誠心が高まっていました。
これが朝廷の懐柔策であり、実朝と御家人達との間に溝を広げようとしていることが見え透けている義時や政子が実朝に訴えても実朝は耳を貸しません。
そんな中、鶴岡八幡宮に詣でた実朝は、鶴岡八幡宮の別当である「公暁」なる人物と出会います。
何を隠そうこの公暁こそが、亡き兄・頼家の忘れ形見でした。
本来なら自分が将軍になるはずだったのに自分は寺の坊主で叔父が将軍になっている。なぜ自分ではないのか…。
気付いたら実朝は倒れ、周りは赤く染まっていました。
そして自分の手には赤く染まった一本の脇差。
その直後、公暁は討ち取られ、実朝に駆け寄ったものの実朝はすでに事切れていました。
それを知った政子は頼朝を亡くした時のことを思い出しました。
実朝が亡くなったことで子供たちを全て失ってしまった政子は、孤独を感じながらも幕府のためにまだ死ぬわけにはいかなかったのです。
病がちな実朝でしたが、教養に富んだその人柄は朝廷より大変気に入られ、さらに官位が高まるとともに実朝の朝廷への忠誠心が高まっていました。
これが朝廷の懐柔策であり、実朝と御家人達との間に溝を広げようとしていることが見え透けている義時や政子が実朝に訴えても実朝は耳を貸しません。
そんな中、鶴岡八幡宮に詣でた実朝は、鶴岡八幡宮の別当である「公暁」なる人物と出会います。
何を隠そうこの公暁こそが、亡き兄・頼家の忘れ形見でした。
本来なら自分が将軍になるはずだったのに自分は寺の坊主で叔父が将軍になっている。なぜ自分ではないのか…。
気付いたら実朝は倒れ、周りは赤く染まっていました。
そして自分の手には赤く染まった一本の脇差。
その直後、公暁は討ち取られ、実朝に駆け寄ったものの実朝はすでに事切れていました。
それを知った政子は頼朝を亡くした時のことを思い出しました。
実朝が亡くなったことで子供たちを全て失ってしまった政子は、孤独を感じながらも幕府のためにまだ死ぬわけにはいかなかったのです。
尼将軍・北条政子

政子は実朝に代わって藤原摂関家より、まだ幼い藤原頼経を将軍に迎え、自身は後見役として幕府に関わりました。
しかしそんな幕府の存続を苦々しく見ていたのが、天皇を退いた後も絶大な権力を握る「後鳥羽上皇」でした。
そしてとうとう挙兵に踏み切ったのです。
鎌倉追討の院宣を受け取った全国の御家人たちは恐怖しました。
力の衰えた朝廷といえど、万古の時代より日本の頂点に君臨する朝廷の意向を無視できず迷いに迷いました。
しかしそこに政子は喝を入れました。
「故右大将(頼朝)の恩は山よりも高く、海よりも深い。逆臣の讒言により不義の綸旨が下された。秀康、胤義(上皇の近臣)を討って、三代将軍の遺跡を全うせよ。ただし、院に参じたい者は直ちに申し出て参じるがよい。」
「承久記」ではこのように演説を行ったとあります。
これを聞いた御家人たちの意思は一つになり、朝廷軍に攻めかかりました。
その数19万騎。
院宣に恐れをなして何もして来れないと油断していた朝廷軍は大混乱に陥り各地で連戦連敗。
京を占領した幕府軍は朝廷軍の降伏を受け入れ、後鳥羽上皇は隠岐島に流罪となりました。
「承久の乱」と呼ばれたこの戦を制した北条政子は「尼将軍」と呼ばれ、幕府に無くてはならない人になっていました。
鎌倉幕府の存続を見守った政子は嘉禄元年(1225年)、病により69歳の生涯を終えたのです。
しかしそんな幕府の存続を苦々しく見ていたのが、天皇を退いた後も絶大な権力を握る「後鳥羽上皇」でした。
そしてとうとう挙兵に踏み切ったのです。
鎌倉追討の院宣を受け取った全国の御家人たちは恐怖しました。
力の衰えた朝廷といえど、万古の時代より日本の頂点に君臨する朝廷の意向を無視できず迷いに迷いました。
しかしそこに政子は喝を入れました。
「故右大将(頼朝)の恩は山よりも高く、海よりも深い。逆臣の讒言により不義の綸旨が下された。秀康、胤義(上皇の近臣)を討って、三代将軍の遺跡を全うせよ。ただし、院に参じたい者は直ちに申し出て参じるがよい。」
「承久記」ではこのように演説を行ったとあります。
これを聞いた御家人たちの意思は一つになり、朝廷軍に攻めかかりました。
その数19万騎。
院宣に恐れをなして何もして来れないと油断していた朝廷軍は大混乱に陥り各地で連戦連敗。
京を占領した幕府軍は朝廷軍の降伏を受け入れ、後鳥羽上皇は隠岐島に流罪となりました。
「承久の乱」と呼ばれたこの戦を制した北条政子は「尼将軍」と呼ばれ、幕府に無くてはならない人になっていました。
鎌倉幕府の存続を見守った政子は嘉禄元年(1225年)、病により69歳の生涯を終えたのです。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

