大義名分
関連キーワード

もともとは「臣下として守らなくてはいけない節度、道義など」を示しました。最近では意味合いが変わってきて「何か行動を起こす、相手に対して干渉するときに、その正当性を主張する根拠」となってきています。
由来
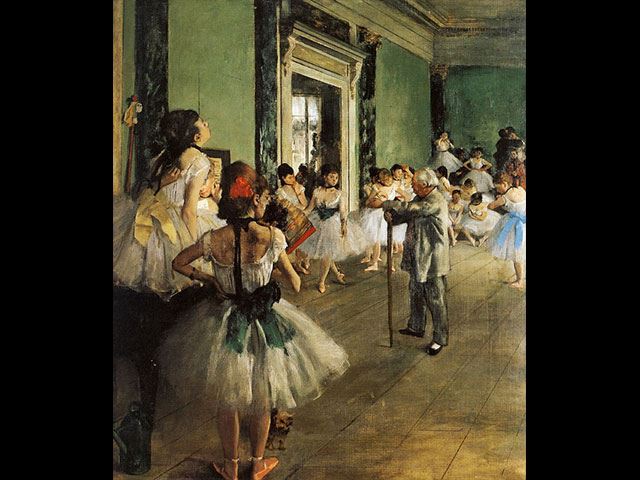
中国において「大義」とは君主(仕える主人)に対する臣下の忠誠が、人が守らなくてはいけない道義の中でも重要とされていました。
それと同じくして親子の情愛も重要視されましたが、これらの関係を「名」としたのです。そしてそれぞれが負うべき責任や役割を「分」として、それぞれの関係性を把握・理解したうえで倫理的価値判断を行うものを「大義」としたのです。その儒教的思想の根本は孔子によってまとめられたものであり、そののち北宋の司馬光の「資治通鑑」に継承され、そのはじめに「君主が社会の秩序を維持していくためには名分を尊重しなければならない」と記されました。
そして南宋の朱熹(朱子)が「資治通鑑綱目」を記しましたが、そこでも道徳的行為の重要さを説いています。しかしそこではどちらかというとその価値判断の基準をそれぞれの個人の内面においていたために「名分」という形式的な肩書を重要視はしていませんでした。そのために「大義名分」という言葉の根本的な趣旨は中国で生まれたものの、熟語としては発生しなかったのです。
それが江戸時代の日本に朱子学が推奨され、5代将軍綱吉のころからは公の学問として普及していきました。
そこでは「大義」や「名分」についても中国の思想として学ばれて育っていきました。そして幕末を迎えます。そのころは日本国内は開国論や尊王論、攘夷論など様々な思想が入り乱れていました。そして自分たちの思想を正当化し、相手を攻撃するために「大義名分」を用いるようになっていったのです。
日本に侵入してくる外国を「敵」としてとらえ、力で追い払うという考え方と、進んでいる文化や技術を取り入れるためにむしろ外国を招き入れるべきとする開国派、さらに頼りにならない幕府をつぶして天皇中心の世の中を作ろうとする尊王派などが争うなかで、どれだけ自分たちの思想が理論的に優れているか、正しいかを主張するために「大義名分」を掲げたのです。
それと同じくして親子の情愛も重要視されましたが、これらの関係を「名」としたのです。そしてそれぞれが負うべき責任や役割を「分」として、それぞれの関係性を把握・理解したうえで倫理的価値判断を行うものを「大義」としたのです。その儒教的思想の根本は孔子によってまとめられたものであり、そののち北宋の司馬光の「資治通鑑」に継承され、そのはじめに「君主が社会の秩序を維持していくためには名分を尊重しなければならない」と記されました。
そして南宋の朱熹(朱子)が「資治通鑑綱目」を記しましたが、そこでも道徳的行為の重要さを説いています。しかしそこではどちらかというとその価値判断の基準をそれぞれの個人の内面においていたために「名分」という形式的な肩書を重要視はしていませんでした。そのために「大義名分」という言葉の根本的な趣旨は中国で生まれたものの、熟語としては発生しなかったのです。
それが江戸時代の日本に朱子学が推奨され、5代将軍綱吉のころからは公の学問として普及していきました。
そこでは「大義」や「名分」についても中国の思想として学ばれて育っていきました。そして幕末を迎えます。そのころは日本国内は開国論や尊王論、攘夷論など様々な思想が入り乱れていました。そして自分たちの思想を正当化し、相手を攻撃するために「大義名分」を用いるようになっていったのです。
日本に侵入してくる外国を「敵」としてとらえ、力で追い払うという考え方と、進んでいる文化や技術を取り入れるためにむしろ外国を招き入れるべきとする開国派、さらに頼りにならない幕府をつぶして天皇中心の世の中を作ろうとする尊王派などが争うなかで、どれだけ自分たちの思想が理論的に優れているか、正しいかを主張するために「大義名分」を掲げたのです。
意味の変遷
こうして「大義名分」は時代と国によって少しずつ使われる意味合いを変えていきました。
もともとは君臣や親子の守るべき節度や道義についての言葉であったものが、自分の政治的思想を主張するための言葉となり、さらに現代では政治的思想も関係なく、個人の行動や言い分が正当であるということの根拠というような意味合いで使われることが多くなってきています。
もともとは君臣や親子の守るべき節度や道義についての言葉であったものが、自分の政治的思想を主張するための言葉となり、さらに現代では政治的思想も関係なく、個人の行動や言い分が正当であるということの根拠というような意味合いで使われることが多くなってきています。





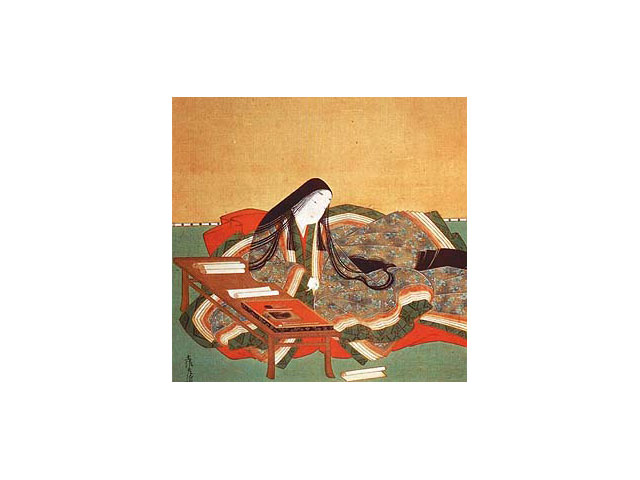














![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

