「分かる―!」と女性読者に共感の嵐!?枕草子で楽しむ【清少納言】の世界観
関連キーワード

『春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。』
この有名な書き出しで始まる「枕草子」。作者は平安時代の女官【清少納言】です。同時期に作られた源氏物語の作者・紫式部と並び称される、平安朝のきっての才女であった清少納言は、けっして恵まれた人生を送った女性ではありませんでした。
けれど、この枕草子には、ユーモアやウイット、朗らかさ、ちょっとの意地悪と優しい目線があり、作者の清少納言の世界観がよく分かる非常に面白いエッセイとして読むことができます。今回はそんな枕草子から、清少納言の美醜論、男性の好みなどがよく分かる部分を独断と偏見で抜粋し、現代語訳しています。
有名な「春はあけぼの―」の一段目しか知らないなんてもったいない!思わず「あるある!」「分かるー!」と共感すること間違いなしです。
この有名な書き出しで始まる「枕草子」。作者は平安時代の女官【清少納言】です。同時期に作られた源氏物語の作者・紫式部と並び称される、平安朝のきっての才女であった清少納言は、けっして恵まれた人生を送った女性ではありませんでした。
けれど、この枕草子には、ユーモアやウイット、朗らかさ、ちょっとの意地悪と優しい目線があり、作者の清少納言の世界観がよく分かる非常に面白いエッセイとして読むことができます。今回はそんな枕草子から、清少納言の美醜論、男性の好みなどがよく分かる部分を独断と偏見で抜粋し、現代語訳しています。
有名な「春はあけぼの―」の一段目しか知らないなんてもったいない!思わず「あるある!」「分かるー!」と共感すること間違いなしです。
清少納言の好き嫌い

・上品なもの
薄紫に白がさねの汗衫(かざみ・童女の上着)。雁の卵。削った氷に甘葛(あまづら)の蜜をかけて新しい金の椀にいれたもの。水晶の数珠。藤の花。梅の花に雪が降りかかった様子、とても可愛らしい小さな子供が、莓などを食べている姿も(42段)
・にくらしいもの
忙しい時に限ってやってきて、長話をする客人。大したことのない人ならば「またあとで」といえるけれども、さすがに目上に人だとそうもいかないので、とても憎たらしい。 中略
人のことを羨むくせに、自分のことは泣き言ばかり、人のうわさ話が好きで、ささいな事も詳しく知りたがって、何でも聞きたいような顔をして、内緒にしてると恨んで文句を言い、また少しくらい聞きかじったようなことを、まるで自分が最初から知っていたかのように、他人に得意げに語っているのも、とても憎たらしいもの(28段)
・忍びたるところ
人目を忍んで逢引するのは、夏が一番趣がある。とても短い夏の夜がもう明けてしまったので、ひと晩中、全然眠らないで過ごした。昼間のように開け放したままで夜を過ごしたので、庭を涼し気に見渡せる。夜は明けてしまったけれど、やはりまだ少し話足りなく感じお互いに受け答えしているうちに、座っている真上を鳥が高い声で鳴きながら飛んでいくのは、まるで誰かに見られている様な気持ちがして、面白いものだ(69段)
薄紫に白がさねの汗衫(かざみ・童女の上着)。雁の卵。削った氷に甘葛(あまづら)の蜜をかけて新しい金の椀にいれたもの。水晶の数珠。藤の花。梅の花に雪が降りかかった様子、とても可愛らしい小さな子供が、莓などを食べている姿も(42段)
・にくらしいもの
忙しい時に限ってやってきて、長話をする客人。大したことのない人ならば「またあとで」といえるけれども、さすがに目上に人だとそうもいかないので、とても憎たらしい。 中略
人のことを羨むくせに、自分のことは泣き言ばかり、人のうわさ話が好きで、ささいな事も詳しく知りたがって、何でも聞きたいような顔をして、内緒にしてると恨んで文句を言い、また少しくらい聞きかじったようなことを、まるで自分が最初から知っていたかのように、他人に得意げに語っているのも、とても憎たらしいもの(28段)
・忍びたるところ
人目を忍んで逢引するのは、夏が一番趣がある。とても短い夏の夜がもう明けてしまったので、ひと晩中、全然眠らないで過ごした。昼間のように開け放したままで夜を過ごしたので、庭を涼し気に見渡せる。夜は明けてしまったけれど、やはりまだ少し話足りなく感じお互いに受け答えしているうちに、座っている真上を鳥が高い声で鳴きながら飛んでいくのは、まるで誰かに見られている様な気持ちがして、面白いものだ(69段)
やっぱりイケメンがいい!
・お説法をするお坊さんの顔は、良い方がだんぜんいい。
お坊さんの顔に見とれて見つめているからこそ、その仏法のありがたみも分かるということ。
よそ見していると聞いたことをすぐ忘れてしまうので、顔の悪いお坊さんのお説法を聞くと、説法をちゃんと聞かないという罪を犯してしまうような気がするのだ。本当はこんなことは書かないで置くべきなのだろうが。私がもう少し年が若かったら、こんな罪を犯しそうなことでも平気で書いたと思う。でも年を重ねてしまった今では、ちゃんとお説法を聞かないのは仏法に背く感じで恐ろしいのだ(33段)
・雑色、隋身は痩せぎみで、ほっそりしている人がいい。
身分の高い男性も、やはり若いうちは細身の方が良い。とても太っている男はいつも眠たそうに見えるからあまり良くない(53段)
お坊さんの顔に見とれて見つめているからこそ、その仏法のありがたみも分かるということ。
よそ見していると聞いたことをすぐ忘れてしまうので、顔の悪いお坊さんのお説法を聞くと、説法をちゃんと聞かないという罪を犯してしまうような気がするのだ。本当はこんなことは書かないで置くべきなのだろうが。私がもう少し年が若かったら、こんな罪を犯しそうなことでも平気で書いたと思う。でも年を重ねてしまった今では、ちゃんとお説法を聞かないのは仏法に背く感じで恐ろしいのだ(33段)
・雑色、隋身は痩せぎみで、ほっそりしている人がいい。
身分の高い男性も、やはり若いうちは細身の方が良い。とても太っている男はいつも眠たそうに見えるからあまり良くない(53段)
あるある!シリーズ

・しゃくにさわるもの(もどかしいもの)
誰かに出す文でも、人の歌に対する返歌でも、その歌を書いて使いに持たせてしまったあとで、文字を1つ2つ書き直したくなった時
急ぎの着物を縫っていて、うまく縫うことができた!と思ったのに、針を抜いたら玉止めをしていなくて、糸が全部抜けてしまった時。また、裏返しで縫ってしまったのに気付いた時もとってもしゃくにさわる(95段)
・情けないもの
当人が聞いたらとても恥ずかしく思われるような悪口を、周りに遠慮もなく言っている時。
必ず来ると思っていた男性を一晩中待って、明け方に近くになって少しつかれて寝入ってしまって、鳥が近くでカァカァと鳴くので、空を見上げたらもう昼になってしまっていた・・・とても情けない(97段)
・残念なもの
五節、御仏名に、風情のある雪が降らずに、雨が長々と降った時。晴れやかな節会などに、さけようのない宮中の物忌がぶつかってしまった時。ずっと前から準備をして今か今かと待っていたイベントが、支障があって急に中止になってしまった時。会いたかったり、見せたいものがあって呼んだのに、その人が来てくれないのはとても残念だ(98段)
・見苦しいもの
中略
さて早朝は、早く起きてくる方がスッキリしていて見苦しくない。夏、昼寝から覚めた寝起きの様子は、高貴な人であればまだ少しはマシだろうが、醜い容貌では、脂ぎって、目が腫れて、わるくすれば頬が寝跡がついてしまっている場合もあるだろう。男女がそんな醜いよう図でお互いに顔を見合わせた時などは、もう、生きている甲斐がないじゃない!とまで思ってしまう。(109段)
・かっこうつかないもの
中略
人の奥さんが、くだらない嫉妬などをして家を出ていなくなったのを、必ず夫がパニックになってで探し回るに違いないと思っていたのに、期待はずれにもそういう風にはならずに、憎たらしく平気な顔で過ごしているので、そんなにいつまでも外に出かけているわけにもいかず、自分から家に帰って来た時。(125段)
誰かに出す文でも、人の歌に対する返歌でも、その歌を書いて使いに持たせてしまったあとで、文字を1つ2つ書き直したくなった時
急ぎの着物を縫っていて、うまく縫うことができた!と思ったのに、針を抜いたら玉止めをしていなくて、糸が全部抜けてしまった時。また、裏返しで縫ってしまったのに気付いた時もとってもしゃくにさわる(95段)
・情けないもの
当人が聞いたらとても恥ずかしく思われるような悪口を、周りに遠慮もなく言っている時。
必ず来ると思っていた男性を一晩中待って、明け方に近くになって少しつかれて寝入ってしまって、鳥が近くでカァカァと鳴くので、空を見上げたらもう昼になってしまっていた・・・とても情けない(97段)
・残念なもの
五節、御仏名に、風情のある雪が降らずに、雨が長々と降った時。晴れやかな節会などに、さけようのない宮中の物忌がぶつかってしまった時。ずっと前から準備をして今か今かと待っていたイベントが、支障があって急に中止になってしまった時。会いたかったり、見せたいものがあって呼んだのに、その人が来てくれないのはとても残念だ(98段)
・見苦しいもの
中略
さて早朝は、早く起きてくる方がスッキリしていて見苦しくない。夏、昼寝から覚めた寝起きの様子は、高貴な人であればまだ少しはマシだろうが、醜い容貌では、脂ぎって、目が腫れて、わるくすれば頬が寝跡がついてしまっている場合もあるだろう。男女がそんな醜いよう図でお互いに顔を見合わせた時などは、もう、生きている甲斐がないじゃない!とまで思ってしまう。(109段)
・かっこうつかないもの
中略
人の奥さんが、くだらない嫉妬などをして家を出ていなくなったのを、必ず夫がパニックになってで探し回るに違いないと思っていたのに、期待はずれにもそういう風にはならずに、憎たらしく平気な顔で過ごしているので、そんなにいつまでも外に出かけているわけにもいかず、自分から家に帰って来た時。(125段)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
どれもこれも短いものの、おもわずクスッと笑ってしまうものやなるほど確かに、と納得してしまうような段がありました。
なによりも1000年も前に生きた女性と、現代の私たちとの間で共感できるものがあるとは驚きです。枕草子がこれまで読み継がれてきた理由が分かる気がします。
興味を持たれた方はぜひ本屋さんで手に取ってみてくださいね!
どれもこれも短いものの、おもわずクスッと笑ってしまうものやなるほど確かに、と納得してしまうような段がありました。
なによりも1000年も前に生きた女性と、現代の私たちとの間で共感できるものがあるとは驚きです。枕草子がこれまで読み継がれてきた理由が分かる気がします。
興味を持たれた方はぜひ本屋さんで手に取ってみてくださいね!







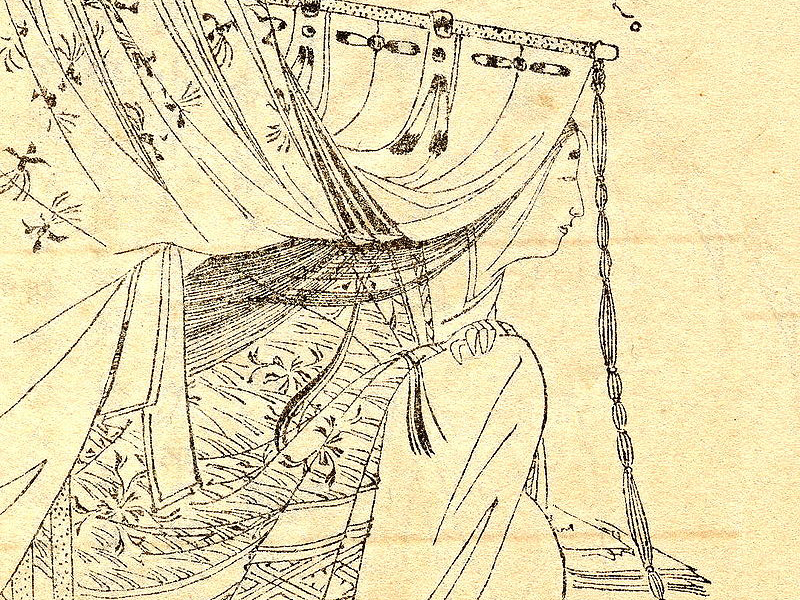














![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

