その率直さ、見習いたい!?朝廷権力を掌握した藤原道長
関連キーワード
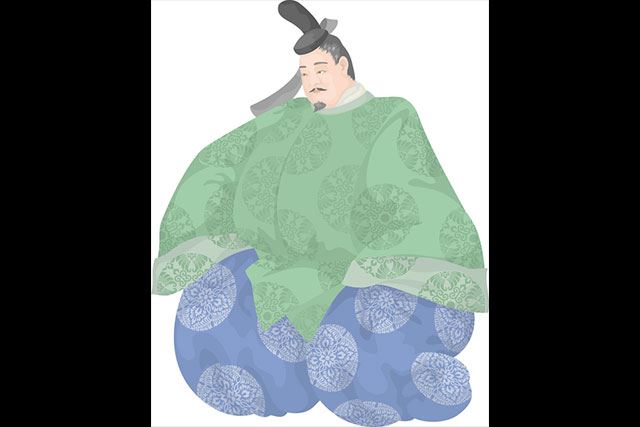
『この世をば我が世とぞおもう 望月のかけたることもなしをおもへば』
(この世は私のためにあるようなものだ、満月のように満たされていて、どこも欠けたところがない)
いかがでしょうか、この率直さ。
この歌は平安中期の貴族・藤原道長が、公卿たち前で詠んだ歌です。朝廷内の熾烈な権力競争を勝ち抜き、この世の春を謳歌した道長の気持ちが率直に、声高々と詠まれています。
歌を受けた中納言・藤原実資は返歌を断り、そこにいる皆で一堂に和す(何度も!)ことにしたと言います。確かに、この歌に返歌を求められても困りますよね。追従する以外の方法はありません。
(この世は私のためにあるようなものだ、満月のように満たされていて、どこも欠けたところがない)
いかがでしょうか、この率直さ。
この歌は平安中期の貴族・藤原道長が、公卿たち前で詠んだ歌です。朝廷内の熾烈な権力競争を勝ち抜き、この世の春を謳歌した道長の気持ちが率直に、声高々と詠まれています。
歌を受けた中納言・藤原実資は返歌を断り、そこにいる皆で一堂に和す(何度も!)ことにしたと言います。確かに、この歌に返歌を求められても困りますよね。追従する以外の方法はありません。
道長の栄華と女流文学の流行

平安時代、藤原氏が政治を牛耳った、いわゆる摂関政治が行われていた頃、摂政である父・藤原兼家の5男として生まれた藤原道長は、実は出世の期待が持てないポジションにいました。ところが、兄たちが病没するとにわかに摂政職への出世の道が見えてきたのです。
最強のライバルであった甥の藤原伊周は、法皇に弓引く罪で太宰権帥に配流されて失脚しました。権力争いを勝利した道長は、なんと娘をそれぞれ三人の天皇のに嫁がせ、(のちに天皇となる)男の子を生ませることに成功しました。摂関政治下においては天皇の外祖父となることが必須。こうして権力の全てを手に入れた藤原道長は、朝廷での栄華を極めました。
そんな道長に目をかけられたのが紫式部や和泉式部といった女流文学者たちです。紫式部は言わずと知れた源氏物語の作者であり、和泉式部は優れた歌人でもあります。二人とも道長の娘で一条天皇の中宮である彰子に仕えていました。まだまだ紙なども高級な時代、権力者の庇護があってこそ、たくさんの物語を書くことができたのですね。
最強のライバルであった甥の藤原伊周は、法皇に弓引く罪で太宰権帥に配流されて失脚しました。権力争いを勝利した道長は、なんと娘をそれぞれ三人の天皇のに嫁がせ、(のちに天皇となる)男の子を生ませることに成功しました。摂関政治下においては天皇の外祖父となることが必須。こうして権力の全てを手に入れた藤原道長は、朝廷での栄華を極めました。
そんな道長に目をかけられたのが紫式部や和泉式部といった女流文学者たちです。紫式部は言わずと知れた源氏物語の作者であり、和泉式部は優れた歌人でもあります。二人とも道長の娘で一条天皇の中宮である彰子に仕えていました。まだまだ紙なども高級な時代、権力者の庇護があってこそ、たくさんの物語を書くことができたのですね。
栄華のあとは没落がセオリー。でも・・・?

歴史上の人物を見てみると、栄華を極めた人物はのちに零落し寂しい晩年を送るのがセオリーですが、強運の持ち主である道長は違いました。
晩年は深く仏教に帰依し出家しますが、出家してもなお権力は続き、法成寺を建立する際は多くの資財と人力を投入、公卿や僧・民衆に対しても役の負担を命じました。
病気がち(糖尿病とも)であった道長は、臨終の際には自ら建立した法成寺・阿弥陀堂の中で、釈迦の涅槃スタイルと同じように横たわり、阿弥陀如来の手と自分の手を糸で結びました。僧侶たちの読経が響く中、自分も念仏を唱え往生を願いながら、亡くなったと言います。
医療もなく苦痛のあった最期だったでしょうが、当時として考え得る最高の亡くなり方です。藤原道長は最後まで権力の中にいたのですね。
晩年は深く仏教に帰依し出家しますが、出家してもなお権力は続き、法成寺を建立する際は多くの資財と人力を投入、公卿や僧・民衆に対しても役の負担を命じました。
病気がち(糖尿病とも)であった道長は、臨終の際には自ら建立した法成寺・阿弥陀堂の中で、釈迦の涅槃スタイルと同じように横たわり、阿弥陀如来の手と自分の手を糸で結びました。僧侶たちの読経が響く中、自分も念仏を唱え往生を願いながら、亡くなったと言います。
医療もなく苦痛のあった最期だったでしょうが、当時として考え得る最高の亡くなり方です。藤原道長は最後まで権力の中にいたのですね。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

