台湾茶の種類と味わいとは、茶器もご紹介
関連キーワード

近年関心を集めている台湾茶。種類が多く、専用の茶器を使う台湾茶には、日本茶や紅茶とはまた違った奥深さがあります。
今回は代表的な台湾茶や茶器についてご紹介します。
今回は代表的な台湾茶や茶器についてご紹介します。
台湾茶とは

台湾茶とは、台湾で生産された茶葉を発酵・製造したお茶のことです。
1800年頃に中国茶の苗木が台湾に伝えられた後、台湾の環境や気候に合った独自の製法が発達しました。台湾茶は種類が多く、特にウーロン茶のバラエティーが豊富です。
ウーロン茶は不発酵の緑茶と全発酵の紅茶の中間にある半発酵茶で、発酵の度合いによって味や香りが違うため、さまざまなお茶があるのです。
1800年頃に中国茶の苗木が台湾に伝えられた後、台湾の環境や気候に合った独自の製法が発達しました。台湾茶は種類が多く、特にウーロン茶のバラエティーが豊富です。
ウーロン茶は不発酵の緑茶と全発酵の紅茶の中間にある半発酵茶で、発酵の度合いによって味や香りが違うため、さまざまなお茶があるのです。
台湾四大銘茶

種類の豊富な台湾茶の中でも特に有名なのが、台湾四大銘茶です。それぞれの特徴をご紹介します。
東方美人茶(トウホウビジンチャ)
元はといえば、害虫のウンカに吸われた茶葉で試しにお茶を作ってみたところ、はちみつのような甘味と香りが加わっていたという、偶然の産物のようなお茶です。発酵度は高めで、紅茶に近い風味があります。
凍頂烏龍茶(トウチョウウーロンチャ)
温暖な凍頂山という山脈でとれた茶葉を使用したお茶です。他の烏龍茶より発酵度が低いため、お茶の色は淡い金色。花のような香りと爽やかな風味が特徴です。
木柵鉄観音茶(モクサクテッカンノンチャ)
発酵・焙煎共に強めで、日本のほうじ茶に似た香ばしさが感じられます。ドライフルーツのような香りがあり、口に含むと甘い余韻が残ります。
文山包種茶(ブンザンホウシュチャ)
発酵度が低く、緑茶に似た清々しい味わいです。渋みもなく、飲みやすいお茶といえるでしょう。薄い黄緑色で、ほのかに花のような香りがします。
東方美人茶(トウホウビジンチャ)
元はといえば、害虫のウンカに吸われた茶葉で試しにお茶を作ってみたところ、はちみつのような甘味と香りが加わっていたという、偶然の産物のようなお茶です。発酵度は高めで、紅茶に近い風味があります。
凍頂烏龍茶(トウチョウウーロンチャ)
温暖な凍頂山という山脈でとれた茶葉を使用したお茶です。他の烏龍茶より発酵度が低いため、お茶の色は淡い金色。花のような香りと爽やかな風味が特徴です。
木柵鉄観音茶(モクサクテッカンノンチャ)
発酵・焙煎共に強めで、日本のほうじ茶に似た香ばしさが感じられます。ドライフルーツのような香りがあり、口に含むと甘い余韻が残ります。
文山包種茶(ブンザンホウシュチャ)
発酵度が低く、緑茶に似た清々しい味わいです。渋みもなく、飲みやすいお茶といえるでしょう。薄い黄緑色で、ほのかに花のような香りがします。
台湾茶の茶器

台湾茶を淹れるための専用茶器は「工夫茶器」と呼ばれます。小さな茶壺を使い、茶葉の香りを引き出します。いろいろな道具がありますが、一般的によく使われるものをご紹介します。
茶壺(ちゃふう)
日本のものより小さめの急須
茶海(ちゃかい)
お茶の濃さを均一にするため、茶壺から一旦移す器
茶杯(ちゃはい)
お茶をいただくための小ぶりの器
聞香杯(もんこうはい)
お茶の香りを楽しむための器
茶盤(ちゃばん)
茶器を載せるトレイで、お茶を淹れるお湯や不要なお茶を捨てる役割も
これらの茶器がなくても台湾茶は淹れられますが、専用のものがあると雰囲気も楽しめそうです。日本の急須や湯呑みと似た茶壺や茶杯から試してみると良いかもしれません。
茶壺(ちゃふう)
日本のものより小さめの急須
茶海(ちゃかい)
お茶の濃さを均一にするため、茶壺から一旦移す器
茶杯(ちゃはい)
お茶をいただくための小ぶりの器
聞香杯(もんこうはい)
お茶の香りを楽しむための器
茶盤(ちゃばん)
茶器を載せるトレイで、お茶を淹れるお湯や不要なお茶を捨てる役割も
これらの茶器がなくても台湾茶は淹れられますが、専用のものがあると雰囲気も楽しめそうです。日本の急須や湯呑みと似た茶壺や茶杯から試してみると良いかもしれません。
まとめ

多くの種類がある台湾茶は味わいもさまざま。できれば専用の茶器を使って、好みのお茶を丁寧に淹れ、特別な時間を過ごしてみたいですね。





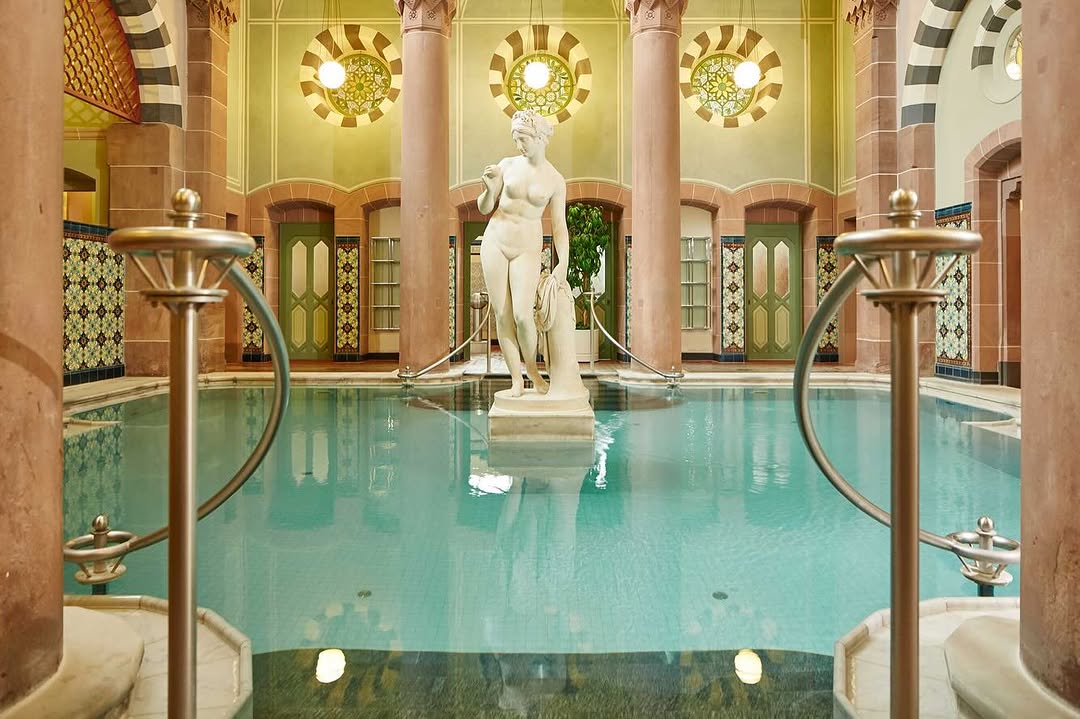















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

