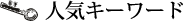武士であり詩人。 そして僧となった西行の人物像
関連キーワード

武士にして詩人、やがては出家僧として各地を放浪とした西行。
西行の生き方は古来多くの人々を魅了し、『西行物語』や『西行桜』、辻邦生の『西行花伝』など、数多くの西行をテーマとした小説・評論が生み出されました。西行はとりわけ短歌の名手とも知られ、勅撰集『新古今和歌集』には最多の94首が入選しているほか、彼の『山家集』は優れた私家集として、藤原俊成や定家らの歌集と並び、六家集のひとつに数えられています。
ときに、浮き世を突き放した歌を詠み、またあるときには、桜や月へのおさえきれない愛着が吐露されている、こういった定家や俊成といった宮廷の貴族達とは異なった、親しみやすさこそが西行の人気の秘密でしょうか。西行の魅力は和歌だけではありません。北面の武士として、周囲の評価も高かったにもかかわらず、突然の出家を遂げます。いったいなぜ出家したのか、西行以外にその理由を知る者はいません。こうしたユニークでミステリアスな西行の生き様も、後世の人々を惹きつけてやまない理由もひとつといえましょう。
西行が残した和歌は彼の謎めいた人生について何を語るのでしょうか。和歌と生き様、この二つを辿りながら、西行の魅力の一端を紹介します。
西行の生き方は古来多くの人々を魅了し、『西行物語』や『西行桜』、辻邦生の『西行花伝』など、数多くの西行をテーマとした小説・評論が生み出されました。西行はとりわけ短歌の名手とも知られ、勅撰集『新古今和歌集』には最多の94首が入選しているほか、彼の『山家集』は優れた私家集として、藤原俊成や定家らの歌集と並び、六家集のひとつに数えられています。
ときに、浮き世を突き放した歌を詠み、またあるときには、桜や月へのおさえきれない愛着が吐露されている、こういった定家や俊成といった宮廷の貴族達とは異なった、親しみやすさこそが西行の人気の秘密でしょうか。西行の魅力は和歌だけではありません。北面の武士として、周囲の評価も高かったにもかかわらず、突然の出家を遂げます。いったいなぜ出家したのか、西行以外にその理由を知る者はいません。こうしたユニークでミステリアスな西行の生き様も、後世の人々を惹きつけてやまない理由もひとつといえましょう。
西行が残した和歌は彼の謎めいた人生について何を語るのでしょうか。和歌と生き様、この二つを辿りながら、西行の魅力の一端を紹介します。
北面の武士 佐藤義清
佐藤義清(のりきよ)、のちの西行が生まれたのは1118年。平将門の乱で武功をあげた藤原秀郷を先祖にもつ左衛門尉佐藤康清を父として生まれました。母は源清経の娘。この西行の母方の祖父にあたる源清経は、風流人として知られ、蹴鞠の名手であったと伝えられています。父方に藤原秀郷をもち、母方に風流人源清経をもつ、こうした血が西行の二面性になにか関係があるのかもしれません。
さて、佐藤義清が生を受けた1118年という時代は、表向きには鳥羽天皇が天下を知ろしめしていましたが、陰では白河上皇が院政を行っていました。このような状況にあった宮廷において佐藤義清は、若くして鳥羽院の北面の武士の地位をつかみます。
北面の武士とは、上皇の行在所である院の北側の部屋に侍り院の身辺警護にあたる役職で、皇族の側近として当然ながら重要な地位でした。
北面の武士に選ばれたのですから、いかに義清が蹴鞠や詩歌管弦に卓越した才能を見せ、宮廷での覚えも高かったのか、ということは推して知るべしでしょう。
一例を挙げれば、後白河院の『梁塵秘抄口伝集』には義清が今様の達人であったとの記述がみえます。
さて、佐藤義清が生を受けた1118年という時代は、表向きには鳥羽天皇が天下を知ろしめしていましたが、陰では白河上皇が院政を行っていました。このような状況にあった宮廷において佐藤義清は、若くして鳥羽院の北面の武士の地位をつかみます。
北面の武士とは、上皇の行在所である院の北側の部屋に侍り院の身辺警護にあたる役職で、皇族の側近として当然ながら重要な地位でした。
北面の武士に選ばれたのですから、いかに義清が蹴鞠や詩歌管弦に卓越した才能を見せ、宮廷での覚えも高かったのか、ということは推して知るべしでしょう。
一例を挙げれば、後白河院の『梁塵秘抄口伝集』には義清が今様の達人であったとの記述がみえます。
突然の出家
1140年、佐藤義清23歳のときに、妻子も地位も捨てて突然出家します。
この義清の出家は幼い娘を振り切って出家するシーンとして、のちに『西行物語』に印象的に描かれることになりますが、当時の宮廷にとってもこの出家は衝撃だったらしく、出家の二年後に書かれた藤原頼長の日記『台記』の記事に、当時の反応が次のように言及されています。
「(西行は)重代の勇士なるを以て法皇に仕たり。俗時より心を仏道に入れ、家富み年若く、心愁ひなきも、遂に以て遁世せり。人これを嘆美せるなり。」
出家の原因としては当時も現在も変わらず不可解で、ある高貴な女性(鳥羽上皇の中宮待賢門院ともいわれる)との失恋が原因だとか、友人の急死に人生の無常を悟ったから、道心が強くなったから、など様々な説が挙げられています。西行は出家についても短歌を詠んでいて、
「世を捨つる人はまことに捨つるかは 捨てぬ人をぞ捨つるとはいふ」
(出家遁世した人は本当に世を捨てたと言えるのだろうか。出家遁世しない人こそ本当ではないか。)
「世の中を捨てて捨て得ぬ心地して 都離れぬ我が身なりけり」
(世を捨てたようで捨てられない気持ちがして 都を離れられないわたしであることだ。)
という、出家を満足に喜べない屈折した思いも、素直に述べているのが面白いところです。
この義清の出家は幼い娘を振り切って出家するシーンとして、のちに『西行物語』に印象的に描かれることになりますが、当時の宮廷にとってもこの出家は衝撃だったらしく、出家の二年後に書かれた藤原頼長の日記『台記』の記事に、当時の反応が次のように言及されています。
「(西行は)重代の勇士なるを以て法皇に仕たり。俗時より心を仏道に入れ、家富み年若く、心愁ひなきも、遂に以て遁世せり。人これを嘆美せるなり。」
出家の原因としては当時も現在も変わらず不可解で、ある高貴な女性(鳥羽上皇の中宮待賢門院ともいわれる)との失恋が原因だとか、友人の急死に人生の無常を悟ったから、道心が強くなったから、など様々な説が挙げられています。西行は出家についても短歌を詠んでいて、
「世を捨つる人はまことに捨つるかは 捨てぬ人をぞ捨つるとはいふ」
(出家遁世した人は本当に世を捨てたと言えるのだろうか。出家遁世しない人こそ本当ではないか。)
「世の中を捨てて捨て得ぬ心地して 都離れぬ我が身なりけり」
(世を捨てたようで捨てられない気持ちがして 都を離れられないわたしであることだ。)
という、出家を満足に喜べない屈折した思いも、素直に述べているのが面白いところです。
出家後の放浪
義清は出家して西行と名を改め、全国を放浪します。
『山家集』には、その当時の西行の気持ちを歌った一首がおさめられています。
「鈴鹿山うき世をよそにふり捨てて いかになりゆくわが身なるらん」
(鈴鹿山で、つらい世を捨てたはいいが、わたしはこれからどうなっていくのだろうか。)
出家をした後しばらくは京都の周辺をさすらっていた西行ですが、27歳のときに、東北地方への旅に出ます。これは旅する歌人として著名だった能因法師の足跡をたどったものでした。西行は能因法師の訪れた白河の関や松島、衣川といった歌の名所(歌枕)を訪れ、歌を詠んでいます。
東北の旅路から帰ってきてしばらくすると、今度は高野山に向かい、以後30年ほどを高野山で過ごすこととなります。
西行が入山中の1164年、保元の乱の結果、讃岐へ流されていた崇徳上皇が亡くなります。その4年後、西行は讃岐への旅に出ます。上田秋成の『雨月物語』のうちの一編「白峰」は、このときの西行の遍歴がもととなっています。
讃岐の旅から高野山に戻り、やがて伊勢に移住した西行でしたが、70歳近くになった1186年、再び奥州へ向かいます。
このときの旅路に詠まれた短歌が残っています。
「年長けてまた越ゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山」
(年をとってまた中山道をこえるとは、はたして思っただろうか。命あってのかとだなあ。)
奥州から帰ってきた西行は、伊勢から河内国(現在の大阪府)の弘川寺に草庵を結び、晩年を過ごすこととなります。
『山家集』には、その当時の西行の気持ちを歌った一首がおさめられています。
「鈴鹿山うき世をよそにふり捨てて いかになりゆくわが身なるらん」
(鈴鹿山で、つらい世を捨てたはいいが、わたしはこれからどうなっていくのだろうか。)
出家をした後しばらくは京都の周辺をさすらっていた西行ですが、27歳のときに、東北地方への旅に出ます。これは旅する歌人として著名だった能因法師の足跡をたどったものでした。西行は能因法師の訪れた白河の関や松島、衣川といった歌の名所(歌枕)を訪れ、歌を詠んでいます。
東北の旅路から帰ってきてしばらくすると、今度は高野山に向かい、以後30年ほどを高野山で過ごすこととなります。
西行が入山中の1164年、保元の乱の結果、讃岐へ流されていた崇徳上皇が亡くなります。その4年後、西行は讃岐への旅に出ます。上田秋成の『雨月物語』のうちの一編「白峰」は、このときの西行の遍歴がもととなっています。
讃岐の旅から高野山に戻り、やがて伊勢に移住した西行でしたが、70歳近くになった1186年、再び奥州へ向かいます。
このときの旅路に詠まれた短歌が残っています。
「年長けてまた越ゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山」
(年をとってまた中山道をこえるとは、はたして思っただろうか。命あってのかとだなあ。)
奥州から帰ってきた西行は、伊勢から河内国(現在の大阪府)の弘川寺に草庵を結び、晩年を過ごすこととなります。
西行の死
西行は1190年(建久元年)、河内国弘川寺において73歳という長命を全うしました。
弘川寺には西行の墳墓があり、春になると、西行が愛した桜の花びらが舞い散る風景を見ることができます。
西行の有名な歌として、
「願はくは花の下にて春死なむ その如月の望月のころ」
(叶うならば、花(桜)のしたで春に死にたい。2月の満月ごろに。)
が知られていますが、これは西行の辞世の句ではないものの、西行の桜に対する愛着と死に対する姿勢が素直に詠まれています。
「その如月の望月のころ」とは、旧暦の2月15日、つまり釈迦の入滅の日でもあり、遁世人としての西行の一面も見逃せません。
西行はこの歌に詠み込んだ思いに違わず、2月16日に没し、のちに桜の名所となる弘川寺で眠ることとなったのです。
弘川寺には西行の墳墓があり、春になると、西行が愛した桜の花びらが舞い散る風景を見ることができます。
西行の有名な歌として、
「願はくは花の下にて春死なむ その如月の望月のころ」
(叶うならば、花(桜)のしたで春に死にたい。2月の満月ごろに。)
が知られていますが、これは西行の辞世の句ではないものの、西行の桜に対する愛着と死に対する姿勢が素直に詠まれています。
「その如月の望月のころ」とは、旧暦の2月15日、つまり釈迦の入滅の日でもあり、遁世人としての西行の一面も見逃せません。
西行はこの歌に詠み込んだ思いに違わず、2月16日に没し、のちに桜の名所となる弘川寺で眠ることとなったのです。

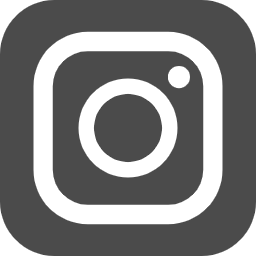
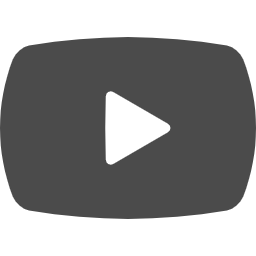

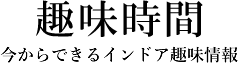





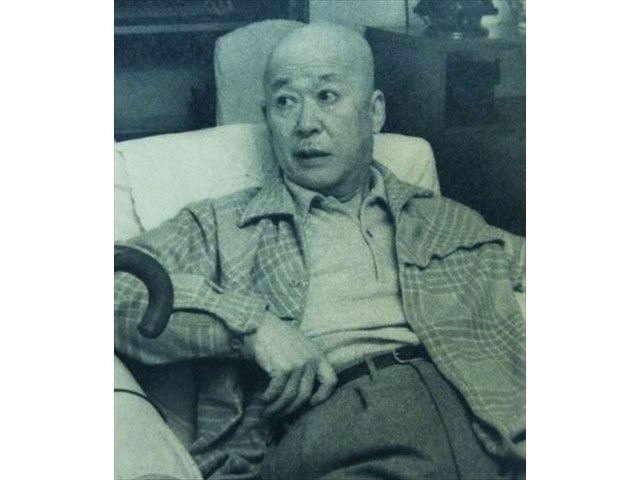











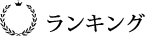

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)