豊臣秀吉の初居城、長浜城と浅井氏の居城、小谷城
関連キーワード

1 長浜城
長浜と呼ばれる場所はもともとは今浜と称していました。最初に城が築かれたのは1336年のことで、京極高氏の手によるものでした。これが今浜城で、今浜氏が入っていました。
天正元年(1573年)8月、北近江の大名浅井氏を小谷城で滅ぼした織田信長は、戦功のあった羽柴藤吉郎秀吉に浅井長政の旧領北近江三郡(伊香・東浅井・坂田)12万石を与えました。城もまた長政の元々の居城があてがわれましたが、これをもって低い身分で織田家に随身した秀吉はついに一国一城の主となったわけです。ちなみにこれまでの木下姓を羽柴姓にかえたのは、その年の7月のことでした。武運を願う意味あいが強かったようです。
当時の勢いにのる秀吉が感じたことは当然、北近江の将来性であったと思われます。領主の真価が問われるだけに居城としての小谷城についてはかなり価値判断をしたようです。そして秀吉は要害の小谷城を捨て、今浜の地に築城を望んだのです。
琵琶湖沿岸の今浜は、北陸と畿内を結ぶ水陸交通の要衝として、また鉄砲生産地国友村の管理、さらには湖北の一向一揆の対応にも都合の良い土地でした。こうした戦略的要衝の築城工事にあたって、秀吉は懸命に知恵を絞りました。
工事が始まったのは1574年6月からです。当時の秀吉は城普請について、出家・侍・奉公人・商人に限らず、鍬、鋤、もっこを持ち、人足としてでることを命じている。もし応じなかった場合は成敗するという、厳しい人足徴収令でした。
精力的に城造りが行われる一方、城下町の建設もあわせてすすめられました。小谷城の城下町を強制的に今浜に移した秀吉は、近隣から商人を招き、年貢の面で優遇している。人集めの段階から町の年貢や諸役を免除するなど急速に町づくりを行ったのです。当時、秀吉は38歳の働き盛りでした。
天正元年(1573年)8月、北近江の大名浅井氏を小谷城で滅ぼした織田信長は、戦功のあった羽柴藤吉郎秀吉に浅井長政の旧領北近江三郡(伊香・東浅井・坂田)12万石を与えました。城もまた長政の元々の居城があてがわれましたが、これをもって低い身分で織田家に随身した秀吉はついに一国一城の主となったわけです。ちなみにこれまでの木下姓を羽柴姓にかえたのは、その年の7月のことでした。武運を願う意味あいが強かったようです。
当時の勢いにのる秀吉が感じたことは当然、北近江の将来性であったと思われます。領主の真価が問われるだけに居城としての小谷城についてはかなり価値判断をしたようです。そして秀吉は要害の小谷城を捨て、今浜の地に築城を望んだのです。
琵琶湖沿岸の今浜は、北陸と畿内を結ぶ水陸交通の要衝として、また鉄砲生産地国友村の管理、さらには湖北の一向一揆の対応にも都合の良い土地でした。こうした戦略的要衝の築城工事にあたって、秀吉は懸命に知恵を絞りました。
工事が始まったのは1574年6月からです。当時の秀吉は城普請について、出家・侍・奉公人・商人に限らず、鍬、鋤、もっこを持ち、人足としてでることを命じている。もし応じなかった場合は成敗するという、厳しい人足徴収令でした。
精力的に城造りが行われる一方、城下町の建設もあわせてすすめられました。小谷城の城下町を強制的に今浜に移した秀吉は、近隣から商人を招き、年貢の面で優遇している。人集めの段階から町の年貢や諸役を免除するなど急速に町づくりを行ったのです。当時、秀吉は38歳の働き盛りでした。
この秀吉が今浜の地名を長浜に改めて面目を一新したために、軍事・経済的に重要な戦略的価値をもつようになりました。
長浜城を足がかりにした秀吉は、信長の武将として各地に出陣しますが、翌年の越前一向一揆攻めには大活躍をみせ、12月には、晴れがましく筑前守に任ぜられました。秀吉が長浜城を本拠としたのは、大坂に移るまでの約10年間です。
信長が1582年6月に本能寺で倒れてのち、尾張清洲城で行われた会議で、秀吉は山城・丹波両国を得て、秀吉の旧領北近江三郡と勝家の旧領越前は柴田勝家のものになりました。このため長浜には勝家の甥の柴田勝豊が入り、秀吉は山城山崎に築城しています。その年の冬、5万の兵を率いて出陣した秀吉は長浜城を攻めて勝豊を降伏させました。
勝家と秀吉が雌雄を決すべく翌年には賤ヶ岳の戦いが起こります。それに先立つ緒戦の大岩山で柴田軍に敗れたことを知った秀吉は、大垣から急遽軍を近江の木の本に移動させましたが、このとき長浜城下の町人などは秀吉のために奔走したと伝えられています。秀吉が善政をしいていたことがうかがえます。
現在、長浜八幡宮の春祭りに催される「曳山祭り」は秀吉が城主のときに側室松の丸が男子をもうけたのを祝って町人たちに砂金を贈りました。これを基金にして山車を造ったのがはじまりといわれています。
いま城跡は豊公園として市民の憩いの場になり、南呉服町には秀吉を祭神とした豊国神社があります。秀吉の遺徳を偲んだ町民が建立したとされています。
長浜城を足がかりにした秀吉は、信長の武将として各地に出陣しますが、翌年の越前一向一揆攻めには大活躍をみせ、12月には、晴れがましく筑前守に任ぜられました。秀吉が長浜城を本拠としたのは、大坂に移るまでの約10年間です。
信長が1582年6月に本能寺で倒れてのち、尾張清洲城で行われた会議で、秀吉は山城・丹波両国を得て、秀吉の旧領北近江三郡と勝家の旧領越前は柴田勝家のものになりました。このため長浜には勝家の甥の柴田勝豊が入り、秀吉は山城山崎に築城しています。その年の冬、5万の兵を率いて出陣した秀吉は長浜城を攻めて勝豊を降伏させました。
勝家と秀吉が雌雄を決すべく翌年には賤ヶ岳の戦いが起こります。それに先立つ緒戦の大岩山で柴田軍に敗れたことを知った秀吉は、大垣から急遽軍を近江の木の本に移動させましたが、このとき長浜城下の町人などは秀吉のために奔走したと伝えられています。秀吉が善政をしいていたことがうかがえます。
現在、長浜八幡宮の春祭りに催される「曳山祭り」は秀吉が城主のときに側室松の丸が男子をもうけたのを祝って町人たちに砂金を贈りました。これを基金にして山車を造ったのがはじまりといわれています。
いま城跡は豊公園として市民の憩いの場になり、南呉服町には秀吉を祭神とした豊国神社があります。秀吉の遺徳を偲んだ町民が建立したとされています。
2 小谷城
かつての小谷城は標高299mの小谷山に築かれていました。築城をみたのは1516年ですが、確証はありません。しかし、浅井亮政の手によるもので、浅井氏三代の本拠地でした。
小谷城は伊吹山地の西側に位置し、丁野山・山脇山・虎御前山・雲雀山などを含む上、西と南には湖北平野がひらける要衝にありました。しかも南には距離をおいて中山道、西には近く北陸街道が横たわっていて、これらは軍事的動脈の役割を果たしていました。
要衝にあった小谷城は、本丸・中の丸・京極丸・山王丸などの本城域と、標高495mの大嶽とに分かれていました。後者は大嶽城とも称され、のち対信長戦のときに来援にかけつけた朝倉氏のために造られたといいます。また、本城のまわりには金吾丸・月所丸・福寿丸などの支城が点々と尾根にたたずみ、浅井氏の居館は清水谷の奥に設けられていました。とにかくその城域は広く、面積は93万㎡にも及びます。
また、尾根筋には堀切を配して空堀を設けるなど敵の侵攻を防ぐ工夫がされており、尾根筋の崖とあわせて極めて高い防御力を備えています。
もともとは浅井亮政は京極氏の被官でしたが、1523年、京極氏に生じた長子と次男の相続争いのとき、長子の高広に味方して当主高清を尾張に追い払い、次男高慶を沈黙させました。その後も側近などの争いは陰湿に続きましたが、やがて亮政は巧妙に実権を握りました。
越前の朝倉家と友好関係を保ち、当時北近江に散在していた一向宗との関係も円滑だったようです。
浅井家の基礎を築いた亮政が小谷城で没したのは1542年の正月でした。跡を子の久政、さらに長政が継いで行きますが、この長政の室が織田信長の妹のお市の方でした。このころの信長はすでに美濃を平定していて天下統一の野望をひめた「天下布武」の印判状を発給していました。
のちに浅井・朝倉氏は信長と敵対することになります。1570年には信長・徳川連合軍を相手に浅井・朝倉連合軍は姉川で戦い、大敗を喫して総崩れとなりました。その後、長政は小谷城を根城に朝倉義景、あるいは北近江十ヶ寺を中心とした一向一揆衆とともに、反信長戦に出陣しましたが、いずれも敗北しました。
のちに足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼした信長は1573年8月、総力を挙げて小谷城攻略にかかりました。このときも朝倉義景が長政救援に出陣してきたため、やむなく信長は主力を朝倉攻めにむけてこれを破り、勢いに乗じて越前に攻め込み、義景を自害させました。これが8月20日のことで、28日には孤立無援の久政・長政親子は信長軍を支える術がなく、小谷城で自害しています。このとき、長政の室お市の方と三人の娘(茶々・初・江)は長政の配慮で信長のもとに送り届けられました。一方、ひそかに城を脱出した嫡男の万福丸は余呉方面に潜伏しましたが、のちに発見されて処刑されました。
小谷城には羽柴秀吉が入りましたが、のちに廃城とされ、北近江の拠点は長浜へと移っていきます。
小谷城は伊吹山地の西側に位置し、丁野山・山脇山・虎御前山・雲雀山などを含む上、西と南には湖北平野がひらける要衝にありました。しかも南には距離をおいて中山道、西には近く北陸街道が横たわっていて、これらは軍事的動脈の役割を果たしていました。
要衝にあった小谷城は、本丸・中の丸・京極丸・山王丸などの本城域と、標高495mの大嶽とに分かれていました。後者は大嶽城とも称され、のち対信長戦のときに来援にかけつけた朝倉氏のために造られたといいます。また、本城のまわりには金吾丸・月所丸・福寿丸などの支城が点々と尾根にたたずみ、浅井氏の居館は清水谷の奥に設けられていました。とにかくその城域は広く、面積は93万㎡にも及びます。
また、尾根筋には堀切を配して空堀を設けるなど敵の侵攻を防ぐ工夫がされており、尾根筋の崖とあわせて極めて高い防御力を備えています。
もともとは浅井亮政は京極氏の被官でしたが、1523年、京極氏に生じた長子と次男の相続争いのとき、長子の高広に味方して当主高清を尾張に追い払い、次男高慶を沈黙させました。その後も側近などの争いは陰湿に続きましたが、やがて亮政は巧妙に実権を握りました。
越前の朝倉家と友好関係を保ち、当時北近江に散在していた一向宗との関係も円滑だったようです。
浅井家の基礎を築いた亮政が小谷城で没したのは1542年の正月でした。跡を子の久政、さらに長政が継いで行きますが、この長政の室が織田信長の妹のお市の方でした。このころの信長はすでに美濃を平定していて天下統一の野望をひめた「天下布武」の印判状を発給していました。
のちに浅井・朝倉氏は信長と敵対することになります。1570年には信長・徳川連合軍を相手に浅井・朝倉連合軍は姉川で戦い、大敗を喫して総崩れとなりました。その後、長政は小谷城を根城に朝倉義景、あるいは北近江十ヶ寺を中心とした一向一揆衆とともに、反信長戦に出陣しましたが、いずれも敗北しました。
のちに足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼした信長は1573年8月、総力を挙げて小谷城攻略にかかりました。このときも朝倉義景が長政救援に出陣してきたため、やむなく信長は主力を朝倉攻めにむけてこれを破り、勢いに乗じて越前に攻め込み、義景を自害させました。これが8月20日のことで、28日には孤立無援の久政・長政親子は信長軍を支える術がなく、小谷城で自害しています。このとき、長政の室お市の方と三人の娘(茶々・初・江)は長政の配慮で信長のもとに送り届けられました。一方、ひそかに城を脱出した嫡男の万福丸は余呉方面に潜伏しましたが、のちに発見されて処刑されました。
小谷城には羽柴秀吉が入りましたが、のちに廃城とされ、北近江の拠点は長浜へと移っていきます。





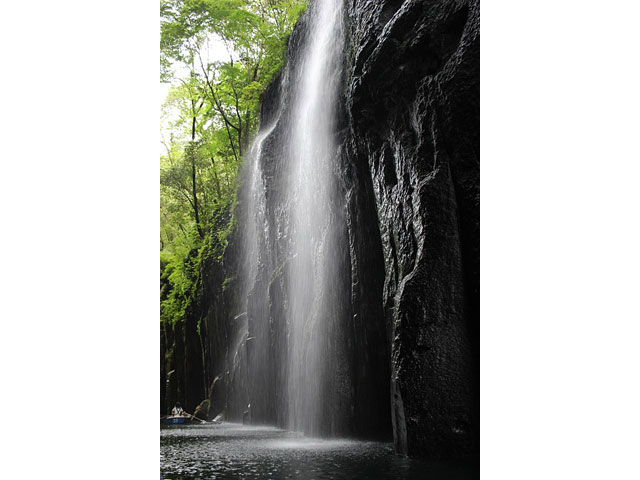









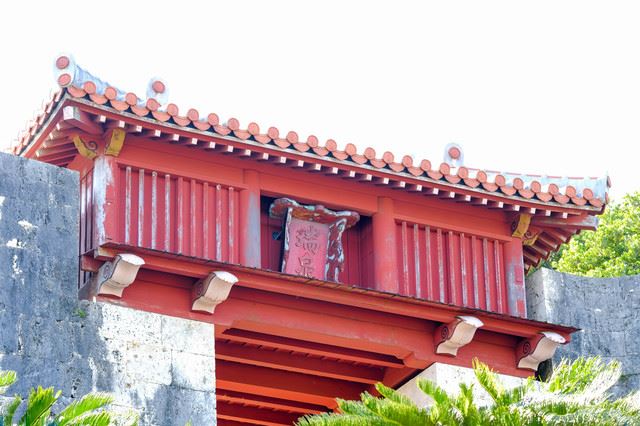






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

