意外に身近!?実は仏教用語だった言葉達・日常語と化した言葉編
関連キーワード

本を読んだり、インターネットを見たり、時には誰かと会話をしたり。人は言葉を使います。何気なく使っている言葉が1000年も前の若者言葉が発祥だった、ということもあります。意外な起源を持つ場合があるのをご存知でしょうか?
【しゃもじ】
平安時代に女房たちが使っていた言葉が元。当時は語尾に「~もじ」と付けるのが流行っており、それが浸透して今も使われているわけです。
【ごきぶり】
御器かぶりが語源(一説)。御器とは食器で、かぶりは「かじる」と言う意味。「食器をかじる虫」と言う意味があります。
このように、今尚使われる言葉には古く、そして面白い語源があるわけです。仏教由来の言葉もいくつも存在します。
【しゃもじ】
平安時代に女房たちが使っていた言葉が元。当時は語尾に「~もじ」と付けるのが流行っており、それが浸透して今も使われているわけです。
【ごきぶり】
御器かぶりが語源(一説)。御器とは食器で、かぶりは「かじる」と言う意味。「食器をかじる虫」と言う意味があります。
このように、今尚使われる言葉には古く、そして面白い語源があるわけです。仏教由来の言葉もいくつも存在します。
意外な仏教由来の言葉
【絶対】
意味としては「必ず」と同じような意味で使われたり、他の何者にも制限を受けることのないことを意味しますね。仏教では「絶待」と書き「ぜつだい」と読みます。意味は善と悪、美や醜といったあらゆる対比、観念を超越した立場、状態のこと。
【皮肉】
これは仏の道の表面を撫でただけで、真髄まで達していないという意味です。禅宗の祖、達磨大使は弟子たちが何をどう悟ったのかを聞き出し、あまり深く悟っていなかった弟子たちに対し「お前は皮を手に入れたに過ぎない」「肉を手に入れたに過ぎない」と言ったとされます。
【退屈】
暇という意味でつかわれますが、本来の意味は修行に耐え切れずに逃げ出してしまうこと。それほどに、悟りを目指す仏道の修行は厳しい物なのです。
【機嫌】
元の字は譏嫌。「譏」は「そしる」、つまり悪口を言うという意味。譏嫌の意味は「人が嫌がること」です。現在では「機嫌いいねえ」など、「今の気持ち」として使われていますね。字が変わったのは、「機」という文字に心の状態などの意味がある為です。それを自分の心で探ることから、「機嫌」と書くようになりました。
【迷惑】
これも実は仏教用語。迷い、惑うの文字通り、「仏道が分かりませんです」「俺ちゃんと理解しているのかなあ」という状態を表す言葉でした。
【うろうろ】
うろうろするという言葉、実は感じがありました。それは有漏。漏(ろ)は煩悩のことです。つまり、有漏とは煩悩に悩まされた人物という意味です。意味もなく歩き回る人や様子を「うろうろする」と表現するのは、煩悩に翻弄されている様の表現でしょうね。
【とにかく】
漢字では「兎に角」と書きます。「いつの間にか」とか「その話はいったん置いといて」と言う意味で時に使いますね。「とにかく、話を聞け」といった具合に。しかし何故兎(ウサギ)と角?本来の意味は「あり得ない、もしくは間違った物の見方或いは執着などを「兎角」と呼んでいました。「ウサギに角が生えて、亀の毛がフサフサになるようなもの」ということらしいです。フサフサの亀は縁起良さそうですね。この「縁起」も、仏教から生まれた言葉です。しかし、意味は変わっていました。
【工夫】
問答という言葉があります。これは禅宗から生まれた言葉で、師匠と弟子が仏道についてあれやこれやと議論することを言いますが、工夫は問答から更に先を言った段階です。「師匠はああ仰ったが、つまりどういうことだ?ああかな?こうかな?」と座禅を組みながら考えること。これが工夫の語源で、正確には工夫弁道(くふうべんどう)といいます。
【虚仮】
「コケにされた!」と相手を舐めきったり馬鹿にしたりする時に使いますね。元々「虚仮」とは言っていることと心が一致しないこと、真実とは違うことを意味します。虚仮脅しという言葉も、こちらから来ているようです。
意味としては「必ず」と同じような意味で使われたり、他の何者にも制限を受けることのないことを意味しますね。仏教では「絶待」と書き「ぜつだい」と読みます。意味は善と悪、美や醜といったあらゆる対比、観念を超越した立場、状態のこと。
【皮肉】
これは仏の道の表面を撫でただけで、真髄まで達していないという意味です。禅宗の祖、達磨大使は弟子たちが何をどう悟ったのかを聞き出し、あまり深く悟っていなかった弟子たちに対し「お前は皮を手に入れたに過ぎない」「肉を手に入れたに過ぎない」と言ったとされます。
【退屈】
暇という意味でつかわれますが、本来の意味は修行に耐え切れずに逃げ出してしまうこと。それほどに、悟りを目指す仏道の修行は厳しい物なのです。
【機嫌】
元の字は譏嫌。「譏」は「そしる」、つまり悪口を言うという意味。譏嫌の意味は「人が嫌がること」です。現在では「機嫌いいねえ」など、「今の気持ち」として使われていますね。字が変わったのは、「機」という文字に心の状態などの意味がある為です。それを自分の心で探ることから、「機嫌」と書くようになりました。
【迷惑】
これも実は仏教用語。迷い、惑うの文字通り、「仏道が分かりませんです」「俺ちゃんと理解しているのかなあ」という状態を表す言葉でした。
【うろうろ】
うろうろするという言葉、実は感じがありました。それは有漏。漏(ろ)は煩悩のことです。つまり、有漏とは煩悩に悩まされた人物という意味です。意味もなく歩き回る人や様子を「うろうろする」と表現するのは、煩悩に翻弄されている様の表現でしょうね。
【とにかく】
漢字では「兎に角」と書きます。「いつの間にか」とか「その話はいったん置いといて」と言う意味で時に使いますね。「とにかく、話を聞け」といった具合に。しかし何故兎(ウサギ)と角?本来の意味は「あり得ない、もしくは間違った物の見方或いは執着などを「兎角」と呼んでいました。「ウサギに角が生えて、亀の毛がフサフサになるようなもの」ということらしいです。フサフサの亀は縁起良さそうですね。この「縁起」も、仏教から生まれた言葉です。しかし、意味は変わっていました。
【工夫】
問答という言葉があります。これは禅宗から生まれた言葉で、師匠と弟子が仏道についてあれやこれやと議論することを言いますが、工夫は問答から更に先を言った段階です。「師匠はああ仰ったが、つまりどういうことだ?ああかな?こうかな?」と座禅を組みながら考えること。これが工夫の語源で、正確には工夫弁道(くふうべんどう)といいます。
【虚仮】
「コケにされた!」と相手を舐めきったり馬鹿にしたりする時に使いますね。元々「虚仮」とは言っていることと心が一致しないこと、真実とは違うことを意味します。虚仮脅しという言葉も、こちらから来ているようです。
お釈迦様絡みだった言葉

【出世】
「あなた、早く出世してくださいよ」「これで俺も出世街道をばく進だ!」と、社会的地位が上がる意味合いで使われる「出世」も仏教由来です。お釈迦様が説法の為現世に現れること、または出家することを差します。
【縁起】
「縁起が良い」とか普通に使うこの言葉、実は略語です。正式名称は因縁生起(いんねんしょうき)。「この世の物は、全て原因があり、縁があって色々なことが起こるのだよ。皆、何かしらの縁で繋がっているの」というお釈迦様のありがたいお言葉なのです。
【方便】
サンスクリット名はウパーヤ。目的、つまり悟りに至るまでの方法、道が元の意味です。お釈迦様は色々な弟子などに色々な方法、つまり方便を使って諭したわけですね。本来の方便は『法華経』の中にある『法華七喩』に記されています。色々な方法を使っていたのが、いつからか嘘をついてでも!との意味になってしまいました。
「あなた、早く出世してくださいよ」「これで俺も出世街道をばく進だ!」と、社会的地位が上がる意味合いで使われる「出世」も仏教由来です。お釈迦様が説法の為現世に現れること、または出家することを差します。
【縁起】
「縁起が良い」とか普通に使うこの言葉、実は略語です。正式名称は因縁生起(いんねんしょうき)。「この世の物は、全て原因があり、縁があって色々なことが起こるのだよ。皆、何かしらの縁で繋がっているの」というお釈迦様のありがたいお言葉なのです。
【方便】
サンスクリット名はウパーヤ。目的、つまり悟りに至るまでの方法、道が元の意味です。お釈迦様は色々な弟子などに色々な方法、つまり方便を使って諭したわけですね。本来の方便は『法華経』の中にある『法華七喩』に記されています。色々な方法を使っていたのが、いつからか嘘をついてでも!との意味になってしまいました。
悟り関係だった言葉

【大丈夫】
丈夫というのは健康もしくはちょっとやそっとじゃ壊れない者や状態を示しますが、「美丈夫」というように、成人男性などを指すこともあります。そんな丈夫、実は仏教用語でした。それ即ち、仏の称号の一つであり、いわば菩薩の別名「調御丈夫」。更に「大」をつけた「大丈夫」も仏教用語。意味は同じですので、混乱しなくても大丈夫です。
【無頓着】
「気にしない」が現在の大体の意味。仏教には三毒という言葉があります。悟りの妨げ、害となる心の動きです。そのうちの一つが貪(とん)。またの名を頓着。無頓着とは元々、何の欲も持たないという意味でした。欲がないから気にもならない、ということでしょうか。
【世間】
「いいか、社会人新入生。世間という物はだなあ!」と現代では人間の世界に限って使われる世間も仏教由来でした。人間だけでなく、あらゆる生物による生きる営み、生の移り変わりを意味します。全ての生き物の世間(衆生世間)、その住処も世間(国土世間)、精神や肉体の世間(五陰世間)と、三つの世間が存在。出世剣という言葉もありますが、こちらは生滅の変化を越えた悟りの域を指します。スケール感はすぼまりましたが、人間の世界という意味ではちゃんと残っているでしょう。
【面目】
禅宗の言葉で、真理、真髄を表します。現在では「面目が立たない」と言ったように、世間体を気にするような意味合いで使われますが、面、つまり顔と目を重要な器官として認識。仏教の心理もまた同じように重要であり、尊いとの考えのようです。
【成仏】
「迷わず成仏して!」と、極楽往生やあの世へ行くイメージのあるこの言葉。仏教では文字通り仏と成る意味を持ちます。「仏さんになる」との言葉自体、主に刑事ドラマなどの影響で死を連想しますが、本来の意味は悟りを開くことです。
【玄関】
建物の出入り口ですね。「そんな大仰なものだったの!?」そうです。元はサンスクリット語のジャーナを訳した言葉。意味は禅です。座禅を組む、あの禅ですね。禅那(ぜんな)という当て字がありましたが、意味と照らし合わせて「玄」の字を使うようになりました。禅の目的は、心を静かに落ち着かせ、あらゆる迷い、煩悩から解き放たれて真理を悟ること。「関」は関所を意味します。つまるところ、「悟る為に通る関所」でした。当初は禅寺にしかなかったようですが、「何かいい感じ」と皆玄関を付けるようになり、今に至ります。
丈夫というのは健康もしくはちょっとやそっとじゃ壊れない者や状態を示しますが、「美丈夫」というように、成人男性などを指すこともあります。そんな丈夫、実は仏教用語でした。それ即ち、仏の称号の一つであり、いわば菩薩の別名「調御丈夫」。更に「大」をつけた「大丈夫」も仏教用語。意味は同じですので、混乱しなくても大丈夫です。
【無頓着】
「気にしない」が現在の大体の意味。仏教には三毒という言葉があります。悟りの妨げ、害となる心の動きです。そのうちの一つが貪(とん)。またの名を頓着。無頓着とは元々、何の欲も持たないという意味でした。欲がないから気にもならない、ということでしょうか。
【世間】
「いいか、社会人新入生。世間という物はだなあ!」と現代では人間の世界に限って使われる世間も仏教由来でした。人間だけでなく、あらゆる生物による生きる営み、生の移り変わりを意味します。全ての生き物の世間(衆生世間)、その住処も世間(国土世間)、精神や肉体の世間(五陰世間)と、三つの世間が存在。出世剣という言葉もありますが、こちらは生滅の変化を越えた悟りの域を指します。スケール感はすぼまりましたが、人間の世界という意味ではちゃんと残っているでしょう。
【面目】
禅宗の言葉で、真理、真髄を表します。現在では「面目が立たない」と言ったように、世間体を気にするような意味合いで使われますが、面、つまり顔と目を重要な器官として認識。仏教の心理もまた同じように重要であり、尊いとの考えのようです。
【成仏】
「迷わず成仏して!」と、極楽往生やあの世へ行くイメージのあるこの言葉。仏教では文字通り仏と成る意味を持ちます。「仏さんになる」との言葉自体、主に刑事ドラマなどの影響で死を連想しますが、本来の意味は悟りを開くことです。
【玄関】
建物の出入り口ですね。「そんな大仰なものだったの!?」そうです。元はサンスクリット語のジャーナを訳した言葉。意味は禅です。座禅を組む、あの禅ですね。禅那(ぜんな)という当て字がありましたが、意味と照らし合わせて「玄」の字を使うようになりました。禅の目的は、心を静かに落ち着かせ、あらゆる迷い、煩悩から解き放たれて真理を悟ること。「関」は関所を意味します。つまるところ、「悟る為に通る関所」でした。当初は禅寺にしかなかったようですが、「何かいい感じ」と皆玄関を付けるようになり、今に至ります。
まとめ
意外な言葉に意外な意味があったものです。関係性も面白いですね。
日常生活だけでなく、食べ物やことわざなど、仏教生まれの言葉はまだまだあります。
日常生活だけでなく、食べ物やことわざなど、仏教生まれの言葉はまだまだあります。
意外に身近!?実は仏教用語だった言葉達・食べ物、ことわざその他諸々編

仏教生まれの意外な言葉特集、今度はことわざ等で、いかに仏の世界が言葉として広まっているかをご紹介します。
日常では使わないけど仏教由来の言葉
【浄瑠璃】
人形浄瑠璃などで知られる、三味線の音色に乗せて物語を語る日本伝統芸能の一つ。現代で言えばある意味でラップのようなものです。仏教では、東方にある薬師如来の土地、浄瑠璃浄土を示します。何故そんな尊い場所が芸能の一つになったのか?元は『浄瑠璃物語』という作品のタイトルで、それを三味線等で語ったのが、現在伝わる浄瑠璃とされています。内容は、浄瑠璃姫と牛若丸が仏門についての問答をするという、ちょっと変わったラブストーリーのようです。この浄瑠璃姫の正体は薬師如来。この物語が大ヒットした為、三味線のリズムで語る芸能を浄瑠璃と呼ぶようになりました。
【般若】
「鬼のお面がどうしたって?」そちらではありません。元々般若とは智慧を意味し、大乗仏教に置ける菩薩の修行(六波羅蜜)の最終段階ともされています。サンスクリット語ではプラジュニャーですが、初期仏典を記したパーリ語のパンニャーを漢字にした物です。響きはかわいいですね。
人形浄瑠璃などで知られる、三味線の音色に乗せて物語を語る日本伝統芸能の一つ。現代で言えばある意味でラップのようなものです。仏教では、東方にある薬師如来の土地、浄瑠璃浄土を示します。何故そんな尊い場所が芸能の一つになったのか?元は『浄瑠璃物語』という作品のタイトルで、それを三味線等で語ったのが、現在伝わる浄瑠璃とされています。内容は、浄瑠璃姫と牛若丸が仏門についての問答をするという、ちょっと変わったラブストーリーのようです。この浄瑠璃姫の正体は薬師如来。この物語が大ヒットした為、三味線のリズムで語る芸能を浄瑠璃と呼ぶようになりました。
【般若】
「鬼のお面がどうしたって?」そちらではありません。元々般若とは智慧を意味し、大乗仏教に置ける菩薩の修行(六波羅蜜)の最終段階ともされています。サンスクリット語ではプラジュニャーですが、初期仏典を記したパーリ語のパンニャーを漢字にした物です。響きはかわいいですね。
食べ物だって仏教関係
【しゃり】
お釈迦様の遺骨のことを仏舎利と言いますが、お米を壮呼ぶようになったのは何故か?信者たちが「私にもください!」と殺到した為、細かく分けられたためです。
【インゲン豆】
隠元という僧侶が日本に持ち込んだのが始まりです。隠元和尚は日本ではなく明のご出身。63歳の時、日本に呼ばれました。そこでインゲン豆と呼ばれることになる豆を精進料理として出したのが名前の由来です。
【カルピス】
仏教はジュースにも絡んでいました。カルピスの語源は、仏の教えの真髄を示すサルピスマンダとカルシウムを合わせた言葉。サルピスマンダも元々は最上級の美味を持った乳製品で、仏教では「醍醐味」という言葉に訳されています。
【がんもどき】
宗派によりますが、肉食禁止は仏僧の掟の一つ。でも食べたい。そこで生まれたのが味を似せた「肉もどき」「魚もどき」です。がんもどきとは、鳥の鴈の味時似せた料理が元なのですね。他にも昆布を斬って入れたら何だか鴈が飛んでいるように見えた、丸(がん)という鶏肉を使った料理に似ていたとの説があります。
【羊羹】
羹(あつもの)というのは、煮凝りのスープ。ここでは羊の煮凝りスープとなります。しかし、お坊さんが食べちゃダメなのは(ダメということはありませんが)先にも述べた通り。ぷるんぷるんした煮凝りなので、固めたお菓子になったというわけです。他に、元々は肉料理だけど、お坊さんがお菓子に発展させた料理として、饅頭があります。こちらも肉まんのような形態が普通でしたが、せめてもと餡子を入れたのが始まり。
お釈迦様の遺骨のことを仏舎利と言いますが、お米を壮呼ぶようになったのは何故か?信者たちが「私にもください!」と殺到した為、細かく分けられたためです。
【インゲン豆】
隠元という僧侶が日本に持ち込んだのが始まりです。隠元和尚は日本ではなく明のご出身。63歳の時、日本に呼ばれました。そこでインゲン豆と呼ばれることになる豆を精進料理として出したのが名前の由来です。
【カルピス】
仏教はジュースにも絡んでいました。カルピスの語源は、仏の教えの真髄を示すサルピスマンダとカルシウムを合わせた言葉。サルピスマンダも元々は最上級の美味を持った乳製品で、仏教では「醍醐味」という言葉に訳されています。
【がんもどき】
宗派によりますが、肉食禁止は仏僧の掟の一つ。でも食べたい。そこで生まれたのが味を似せた「肉もどき」「魚もどき」です。がんもどきとは、鳥の鴈の味時似せた料理が元なのですね。他にも昆布を斬って入れたら何だか鴈が飛んでいるように見えた、丸(がん)という鶏肉を使った料理に似ていたとの説があります。
【羊羹】
羹(あつもの)というのは、煮凝りのスープ。ここでは羊の煮凝りスープとなります。しかし、お坊さんが食べちゃダメなのは(ダメということはありませんが)先にも述べた通り。ぷるんぷるんした煮凝りなので、固めたお菓子になったというわけです。他に、元々は肉料理だけど、お坊さんがお菓子に発展させた料理として、饅頭があります。こちらも肉まんのような形態が普通でしたが、せめてもと餡子を入れたのが始まり。
動植物だって仏教関係

【閻魔コオロギ】
閻魔様のような怖い顔、ということでこの名前がついたそうです。何をどうしたら虫に閻魔様の姿を見い出せるのか少々疑問ですが、死者の量刑を決めることで有名な閻魔様のような眼光を感じることは感じます。でも声は美しいそうですよ。
【精霊バッタ】
見られる時期がお盆なので、この名前がつきました。精霊流しの船と似た姿をしているのも、名前の由来の一因となっています。オスで5センチ、メスで10センチほど。大体が葉っぱの中にいるような虫を見て「ああ、ご先祖様」と思いを馳せるとは、昔の人は目がいい上に想像力が豊かだったのですね。
【マッコウクジラ】
クジラの腸にできる通称「龍涎香」。病気の巣ですが、人間にとっては「あらいい匂い」と評判で、高値で取引されることも多々あります。マッコウクジラの出す龍涎香は抹香(まっこう)と呼ばれるお香に似た臭いを発するとか。抹香の使い道は、ご焼香や体を清めることなど。マッコウクジラのお腹の色が抹香に似ているとの説もあります。
【菩提樹】
「ああ、お釈迦様が悟りを開いた、あの木ね」とあまり仏教に詳しくない人でも何となく分かるかもしれませんが、この木は実在します。菩提というのは悟りのこと。お釈迦様が悟りを開いたため、菩提樹と呼ばれるようになりました。
【曼珠沙華】
天に咲き、悪いカルマから離れることができるとされる花です。彼岸花として知られる花で、美しいのですが、有毒。
【仏の坐】
何がどう仏教絡みなのかと言えば、仏が座る蓮華座に似ているので、この名前がつきました。春の七草の一つとされますが、実際には違う草です。なので食べないようにしましょう。
閻魔様のような怖い顔、ということでこの名前がついたそうです。何をどうしたら虫に閻魔様の姿を見い出せるのか少々疑問ですが、死者の量刑を決めることで有名な閻魔様のような眼光を感じることは感じます。でも声は美しいそうですよ。
【精霊バッタ】
見られる時期がお盆なので、この名前がつきました。精霊流しの船と似た姿をしているのも、名前の由来の一因となっています。オスで5センチ、メスで10センチほど。大体が葉っぱの中にいるような虫を見て「ああ、ご先祖様」と思いを馳せるとは、昔の人は目がいい上に想像力が豊かだったのですね。
【マッコウクジラ】
クジラの腸にできる通称「龍涎香」。病気の巣ですが、人間にとっては「あらいい匂い」と評判で、高値で取引されることも多々あります。マッコウクジラの出す龍涎香は抹香(まっこう)と呼ばれるお香に似た臭いを発するとか。抹香の使い道は、ご焼香や体を清めることなど。マッコウクジラのお腹の色が抹香に似ているとの説もあります。
【菩提樹】
「ああ、お釈迦様が悟りを開いた、あの木ね」とあまり仏教に詳しくない人でも何となく分かるかもしれませんが、この木は実在します。菩提というのは悟りのこと。お釈迦様が悟りを開いたため、菩提樹と呼ばれるようになりました。
【曼珠沙華】
天に咲き、悪いカルマから離れることができるとされる花です。彼岸花として知られる花で、美しいのですが、有毒。
【仏の坐】
何がどう仏教絡みなのかと言えば、仏が座る蓮華座に似ているので、この名前がつきました。春の七草の一つとされますが、実際には違う草です。なので食べないようにしましょう。
ことわざだって仏教関係

【果報は寝て待て】
意味は「焦らずに、好機を待つ」。人は迷いがちです。どの道を選んでも、「間違いだったのではないか」と不安になることもあるでしょう。しかし、そんなウジウジ迷って考えたって仕方ありません。「これだ!」と思った道を突き進むしかないのです。「何もしないで寝てろ」という意味ではなく、「ある程度の準備をしていれば、いつか時期がやってくる」と言った意味合いのようですね。
【釈迦に説法】
その道のプロ、或いはそれに通ずる人にエッヘンと講釈を垂れる滑稽な様を現すことわざ。三ツ星フランス料理のシェフに「フレンチとはねえ」と語るような物です。真相を知った時は恥ずかしいことこの上ないでしょう。
【栴檀は双葉より芳し】
優れた人は幼い頃からその片鱗があった、という意味。栴檀とは仏像の材料としてよく使用される木です。元々香木ですが、目が出た時から、妙なる芳香を放つとされます。
意味は「焦らずに、好機を待つ」。人は迷いがちです。どの道を選んでも、「間違いだったのではないか」と不安になることもあるでしょう。しかし、そんなウジウジ迷って考えたって仕方ありません。「これだ!」と思った道を突き進むしかないのです。「何もしないで寝てろ」という意味ではなく、「ある程度の準備をしていれば、いつか時期がやってくる」と言った意味合いのようですね。
【釈迦に説法】
その道のプロ、或いはそれに通ずる人にエッヘンと講釈を垂れる滑稽な様を現すことわざ。三ツ星フランス料理のシェフに「フレンチとはねえ」と語るような物です。真相を知った時は恥ずかしいことこの上ないでしょう。
【栴檀は双葉より芳し】
優れた人は幼い頃からその片鱗があった、という意味。栴檀とは仏像の材料としてよく使用される木です。元々香木ですが、目が出た時から、妙なる芳香を放つとされます。
慣用句だって仏教関係
【足を洗う】
「足を洗ってカタギで生きるよ!」と、悪事を止める時に使われますね。由来はインド時代まで遡ります。当時の修行僧は裸足で生活し、托鉢などの為に歩いていました。寺に帰れば足を洗って、反省会をしたり、お釈迦様の説法を聞くこともあったようです。修行僧からすると托鉢する町は煩悩や迷いの多い世界であり、寺は悟りを得た世界という想いもあったかもしれません。つまり、そんな煩悩や迷いを洗い流すという意味です。
【魔が差す】
不意に万引きなどの悪事を行った時「魔が差した」と人はいいます。これは元々、お釈迦様が悟りを開く寸前に現れた悪魔が関係していました。心に差す魔の正体は、あらゆる煩悩。欲望や疑いや恐怖などでした。そんな魔に負けないよう、清らかな、とまではいかないまでも強い心を持ちましょう。
【図に乗る】
調子に乗るという意味ですね。これは歌のような節つきのお経にある節の調子が変わることを「図」と呼び、うまく切り替えができた時に「お、図に乗れたねえ」などとったのが始まりだそうです。
【滅相もない】
「あってはならない」「とんでもない」。そんな意味ですが、仏教における無常に関する言葉でした。生まれて、成長して、やがては老いて死ぬ。この四段階を生相、往相、異相、滅相と分けた、最後の一つであり、「滅んじゃうのね」と言う哀愁のある言葉なのです。
【冥利に尽きる】
「男冥利に尽きるね」と多大な恩恵に感謝するこの言葉。「冥利」とは、前世の善行により、今の幸福になっていることを表します。冥利が尽きないよう、徳を積みましょう。
「足を洗ってカタギで生きるよ!」と、悪事を止める時に使われますね。由来はインド時代まで遡ります。当時の修行僧は裸足で生活し、托鉢などの為に歩いていました。寺に帰れば足を洗って、反省会をしたり、お釈迦様の説法を聞くこともあったようです。修行僧からすると托鉢する町は煩悩や迷いの多い世界であり、寺は悟りを得た世界という想いもあったかもしれません。つまり、そんな煩悩や迷いを洗い流すという意味です。
【魔が差す】
不意に万引きなどの悪事を行った時「魔が差した」と人はいいます。これは元々、お釈迦様が悟りを開く寸前に現れた悪魔が関係していました。心に差す魔の正体は、あらゆる煩悩。欲望や疑いや恐怖などでした。そんな魔に負けないよう、清らかな、とまではいかないまでも強い心を持ちましょう。
【図に乗る】
調子に乗るという意味ですね。これは歌のような節つきのお経にある節の調子が変わることを「図」と呼び、うまく切り替えができた時に「お、図に乗れたねえ」などとったのが始まりだそうです。
【滅相もない】
「あってはならない」「とんでもない」。そんな意味ですが、仏教における無常に関する言葉でした。生まれて、成長して、やがては老いて死ぬ。この四段階を生相、往相、異相、滅相と分けた、最後の一つであり、「滅んじゃうのね」と言う哀愁のある言葉なのです。
【冥利に尽きる】
「男冥利に尽きるね」と多大な恩恵に感謝するこの言葉。「冥利」とは、前世の善行により、今の幸福になっていることを表します。冥利が尽きないよう、徳を積みましょう。
まとめ
食べ物にもことわざにも慣用句にも。仏の世界は無宗教とされる現代日本にも息づいていることが分かりますね。








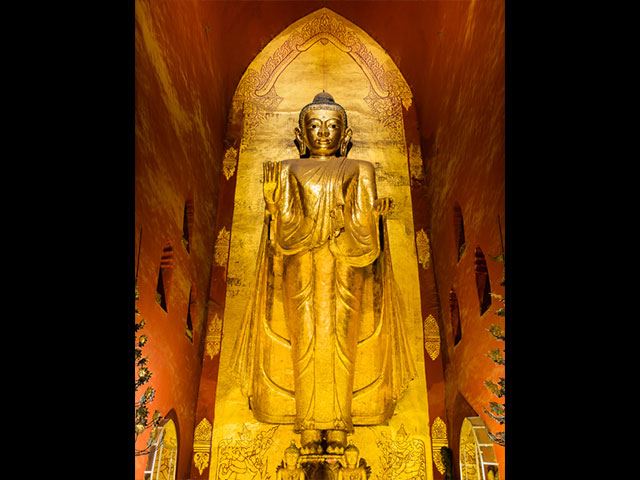













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

