独立不羈で悟りへ向かう
関連キーワード

仏教の最終目的は悟りを得ることです。
しかし、これがなかなかどうして難しいのは先人の例を見れば明らか。
そんな中、独立不羈(どくりつふき)の精神で悟りを得た人々がいました。
しかし、これがなかなかどうして難しいのは先人の例を見れば明らか。
そんな中、独立不羈(どくりつふき)の精神で悟りを得た人々がいました。
独立不羈の意味、類語、用例など
【意味】
誰に言われるでもなく、自分自身の意思、力、判断に基づいて行動をすること。何ものにも縛られず、自由にすることを言います。
【類語】
独立独歩など。
【用例】
「彼は独立不羈の精神で会社を立ち上げた」
誰に言われるでもなく、自分自身の意思、力、判断に基づいて行動をすること。何ものにも縛られず、自由にすることを言います。
【類語】
独立独歩など。
【用例】
「彼は独立不羈の精神で会社を立ち上げた」
お釈迦様が出家に至った精神でもある
お釈迦様も独立不羈の精神で出家しました。
元々はインド小国の王子で、何不自由な意を得に描いたような暮らしをしていたのです。
物理的には。「何で病気になる?何で老いる?何で死ぬ?」贅沢な宴も一時の気晴らしでしかありませんでした。王族、貴族に生まれたって、どうせ死ぬ。何のために生きるんだ?若きゴータマ・シッダールタ(出家前の名前)は悩みに悩んだ末、ちょっと気晴らしをしようと馬を走らせます。
しかし、東の門には老人がいました。「も、いいや」とその日は城に帰り、別の日、今度は南の門から出ようとしますが今度は病人、その次には、西の門に死人がいたのです。
「もう嫌だあ」と思いながらも馬に乗り、最後に残った木田の門から出ようとすると、修行僧と出会います。
それはもう立派な僧侶で、まぶしさを感じたシッダールタは「出家しよう!」と思い立ったのです。
実際に出家に至るのはもう少し先になりますが、恵まれると言うにはあまりに贅沢を享受できる王子の地位も財産も家族でさえも全てを捨てたのは苦しみから抜け出すためでした。
父王が催す見せかけの快楽ではない真の幸福を見つける為、覚悟の上の行動です。
その後、苦行僧に混じっていましたがこれに意味を見い出せず、断食修行中にもらった乳粥で元気を得て、菩提樹の下で悟りを得ました。
元々はインド小国の王子で、何不自由な意を得に描いたような暮らしをしていたのです。
物理的には。「何で病気になる?何で老いる?何で死ぬ?」贅沢な宴も一時の気晴らしでしかありませんでした。王族、貴族に生まれたって、どうせ死ぬ。何のために生きるんだ?若きゴータマ・シッダールタ(出家前の名前)は悩みに悩んだ末、ちょっと気晴らしをしようと馬を走らせます。
しかし、東の門には老人がいました。「も、いいや」とその日は城に帰り、別の日、今度は南の門から出ようとしますが今度は病人、その次には、西の門に死人がいたのです。
「もう嫌だあ」と思いながらも馬に乗り、最後に残った木田の門から出ようとすると、修行僧と出会います。
それはもう立派な僧侶で、まぶしさを感じたシッダールタは「出家しよう!」と思い立ったのです。
実際に出家に至るのはもう少し先になりますが、恵まれると言うにはあまりに贅沢を享受できる王子の地位も財産も家族でさえも全てを捨てたのは苦しみから抜け出すためでした。
父王が催す見せかけの快楽ではない真の幸福を見つける為、覚悟の上の行動です。
その後、苦行僧に混じっていましたがこれに意味を見い出せず、断食修行中にもらった乳粥で元気を得て、菩提樹の下で悟りを得ました。
学のない慧能を見い出した弘忍
慧能と言うのは達磨大師の後継者に当たります。と言っても直弟子ではありません。というか、正式に僧侶になったのは悟りを得たずっと後でした。
この人は中国でも南方の出身なのですが、幼い頃から貧しく、働きに出ていたのでロクに勉強をしたことがないため字も知りません。それでも禅宗の寺へ行き、達磨大師から続く禅宗の五代目の後継者、弘忍和尚に密かに見い出されました。
とはいえ、出身地の関係で、弟子入りさせると皆がいい顔をしないため、弘忍和尚は敢えて下働きをさせ、後を継がせないように見せかけます。
慧能が悟ったことを知るとこっそり呼び出し、後継者の印となる衣を与え、「時が来るまで身を隠せ」と言い、夜が明ける前に逃がしたのです。「こいつなら、字を読ませなくても悟れる」と言う目論見もあったようですね。
この人は中国でも南方の出身なのですが、幼い頃から貧しく、働きに出ていたのでロクに勉強をしたことがないため字も知りません。それでも禅宗の寺へ行き、達磨大師から続く禅宗の五代目の後継者、弘忍和尚に密かに見い出されました。
とはいえ、出身地の関係で、弟子入りさせると皆がいい顔をしないため、弘忍和尚は敢えて下働きをさせ、後を継がせないように見せかけます。
慧能が悟ったことを知るとこっそり呼び出し、後継者の印となる衣を与え、「時が来るまで身を隠せ」と言い、夜が明ける前に逃がしたのです。「こいつなら、字を読ませなくても悟れる」と言う目論見もあったようですね。
破戒僧だった一休さん

とんち物語で知られる一休さんこと一休宗純、どのような人物かと言えば破戒僧です。
肉は食べるし結婚はするし、お酒だって飲んでいました。
読経をするでもなく、正月には首から髑髏を下げて「ご用心~」と言いながら歩き回ったり、立派な太刀を腰に下げて尺八を噴きながら歩いたなどの奇行に走ったとされます。
しかし不思議と皆一休さんに惹かれていました。
というのも、奇行の数々は皆、当時の見せかけだけの仏教界やお上に対する風刺であり、一休さん自身は若い頃に悟りを得ていたのです。
立派な太刀は実は飾りだけで中身は木刀。「着飾って見かけだけ立派にして威張るなよ」と言う意味になります。
肉は食べるし結婚はするし、お酒だって飲んでいました。
読経をするでもなく、正月には首から髑髏を下げて「ご用心~」と言いながら歩き回ったり、立派な太刀を腰に下げて尺八を噴きながら歩いたなどの奇行に走ったとされます。
しかし不思議と皆一休さんに惹かれていました。
というのも、奇行の数々は皆、当時の見せかけだけの仏教界やお上に対する風刺であり、一休さん自身は若い頃に悟りを得ていたのです。
立派な太刀は実は飾りだけで中身は木刀。「着飾って見かけだけ立派にして威張るなよ」と言う意味になります。
まとめ
僧侶の中にはとんでもないような伝説を持つ人もいます。
悟り方は実に様々なのです。しかし共通しているのは、皆自分の意思を持って行動したことです。仏教、どう卿などに通じる福沢諭吉氏もまた独立不羈を勧めています。戒律の多いように見える仏教ですが、悟りを得れば楽になるのです。
重要なのは、余計な束縛から解き放たれることに他なりません。
悟り方は実に様々なのです。しかし共通しているのは、皆自分の意思を持って行動したことです。仏教、どう卿などに通じる福沢諭吉氏もまた独立不羈を勧めています。戒律の多いように見える仏教ですが、悟りを得れば楽になるのです。
重要なのは、余計な束縛から解き放たれることに他なりません。







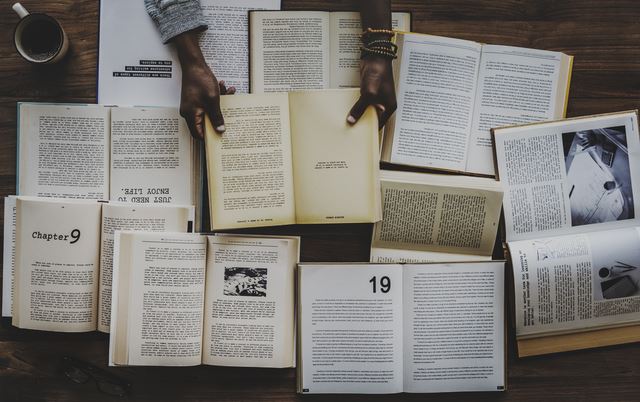














![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

