餅は餅屋の意味・使い方
関連キーワード

意味
何事でもそれぞれの道の専門家に任せるのが一番良いということ。
上手な素人でもやはり専門家には勝てないということのたとえ。
上手な素人でもやはり専門家には勝てないということのたとえ。
由来
いくつか説はありますが、江戸時代ごろの「貸つき屋」「貸餅屋」が元であるとされています。昔は年末になると各家庭で杵と臼を使って餅をついていました。
しかし「師走」と呼ばれるほど年末はどの家庭も忙しいものです。そのために注文をすると杵と臼と材料を持って専門の人たちが出張餅つきをしてくれる制度があったのです。これが「貸つき屋」「貸餅屋」と呼ばれるものです。やはり素人が行うよりも圧倒的に速く綺麗に餅をついていたようで、しかも丸餅や角餅など希望したように仕上げてくれるというものでした。こうして専門家に依頼するのが一番だとなったとされるものです。
もう一つの説はやはり江戸時代の「滑稽太閤記」に記されている部分で、「餅は餅やがよし、指し合いのことは此方にまかせよ」から来たとされているものです。こちらも結局は「やはりよく知っている専門家に任せるのが良い」という意味合いですので、結果的には同じなのかもしれません。
また、同様の表現は英語でもあり、
There is a mystery in the meanest trade.
(どんなつまらない仕事にも秘訣がある)
となっています。これはささいなことに関してもコツがあって、専門家はそれを知っているという意味になります。
しかし「師走」と呼ばれるほど年末はどの家庭も忙しいものです。そのために注文をすると杵と臼と材料を持って専門の人たちが出張餅つきをしてくれる制度があったのです。これが「貸つき屋」「貸餅屋」と呼ばれるものです。やはり素人が行うよりも圧倒的に速く綺麗に餅をついていたようで、しかも丸餅や角餅など希望したように仕上げてくれるというものでした。こうして専門家に依頼するのが一番だとなったとされるものです。
もう一つの説はやはり江戸時代の「滑稽太閤記」に記されている部分で、「餅は餅やがよし、指し合いのことは此方にまかせよ」から来たとされているものです。こちらも結局は「やはりよく知っている専門家に任せるのが良い」という意味合いですので、結果的には同じなのかもしれません。
また、同様の表現は英語でもあり、
There is a mystery in the meanest trade.
(どんなつまらない仕事にも秘訣がある)
となっています。これはささいなことに関してもコツがあって、専門家はそれを知っているという意味になります。
意味の変遷

現在は職業選択の自由もあり、書物やインターネット、テレビなどの媒体から素人でもできるということが圧倒的に増えています。しかし江戸時代のころは職業選択の自由はなく、基本的には親の職業が子の職業となっていました。そのために専門家はとことん専門家でその家に伝わる技術や道具もあったのです。それだけに現在よりも専門色が強く、素人ではかなわないということが多くあったのでしょう。
現在、そういった先祖から伝わる専門家の家庭というのは減ってきてはいるでしょうが、やはり何事も専門家の方が上手に行うことができるという考え方は変わっていないようです。特に素人が自分ができると思ってやってみて失敗すると「専門家に任せておけばよかった」と後悔することが多く、そんなときに「餅は餅屋」が使われています。
現在、そういった先祖から伝わる専門家の家庭というのは減ってきてはいるでしょうが、やはり何事も専門家の方が上手に行うことができるという考え方は変わっていないようです。特に素人が自分ができると思ってやってみて失敗すると「専門家に任せておけばよかった」と後悔することが多く、そんなときに「餅は餅屋」が使われています。
使用法、使用例
「自分で水道管を修理したんだが大失敗だ。余計にひどくなった気がするよ。」
「餅は餅屋って言うだろう。やっぱり専門家に任せないと」
「餅は餅屋って言うだろう。やっぱり専門家に任せないと」
似た意味のことわざ
「蛇の道は蛇」「仏の沙汰は僧が知る」「馬は馬方」など専門家に任せるのが良いという意味のものが多数あります。





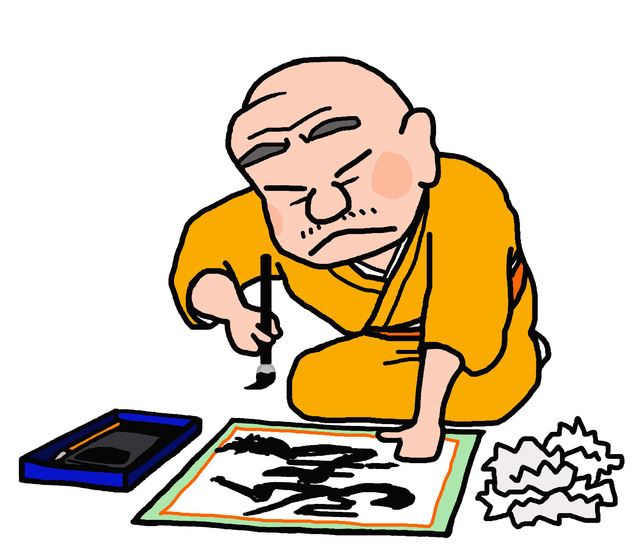
















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

