弘法も筆の誤りの意味・使い方
関連キーワード
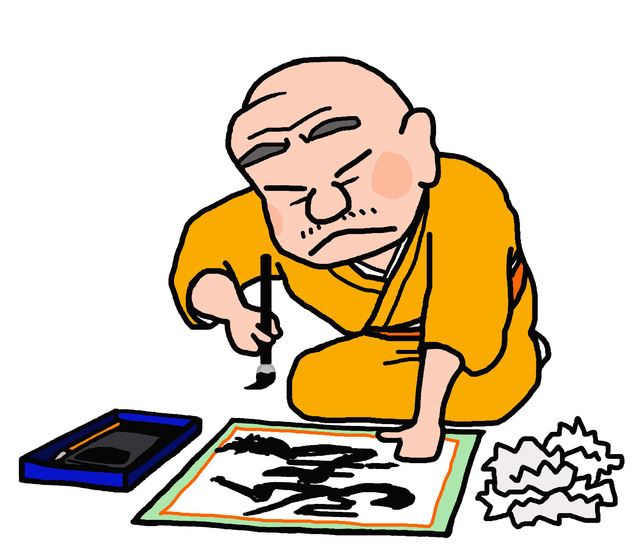
どんな名人や達人でも失敗することもあるというたとえ。
由来
もともとは平安時代の書の大家として知られる弘法大師でも時には書き誤りをすることがあるという故事から発生したことわざです。弘法大師とは真言宗の開祖である空海のことで、嵯峨天皇、橘逸勢と共に「三筆」と呼ばれた書の達人でした。
ある時、京の都にある応天門に掲げる額を書くように弘法大師は命令を受けます。彼は見事に「応天門」という字を書いたのですが、「応」の上の点を打つのを忘れてしまったのです。額はそのまま門の上に飾られてしまいました。人々は「あの弘法大師でも書き間違いをすることがあるのか」と驚いたといいます。
ここまでの話でことわざの意味としては成立しているのですが、この話には後日談があり、それが「今昔物語」に記されています。
「応天門の額打ちつけて後これを見るに、初めに字の点、すでに落ち失せたり。驚きて筆を投げて点を付けつ。もろもろの人これを見て、手を打ちてこれを感ず」
とあります。つまり弘法大師は額を一度下ろさせることなく、筆を額に向かって投げつけて足りなかった点を打ったのです。それを見た人々は拍手喝采して褒め称えたと書かれています。
ことわざでは「名人の失敗」が強調されていますが、この「見事な後始末」に関しては書かれていません。
ある時、京の都にある応天門に掲げる額を書くように弘法大師は命令を受けます。彼は見事に「応天門」という字を書いたのですが、「応」の上の点を打つのを忘れてしまったのです。額はそのまま門の上に飾られてしまいました。人々は「あの弘法大師でも書き間違いをすることがあるのか」と驚いたといいます。
ここまでの話でことわざの意味としては成立しているのですが、この話には後日談があり、それが「今昔物語」に記されています。
「応天門の額打ちつけて後これを見るに、初めに字の点、すでに落ち失せたり。驚きて筆を投げて点を付けつ。もろもろの人これを見て、手を打ちてこれを感ず」
とあります。つまり弘法大師は額を一度下ろさせることなく、筆を額に向かって投げつけて足りなかった点を打ったのです。それを見た人々は拍手喝采して褒め称えたと書かれています。
ことわざでは「名人の失敗」が強調されていますが、この「見事な後始末」に関しては書かれていません。
意味の変遷

現在でも基本的には「名人でも失敗することがある」という意味で使用されます。たまに「名人でも失敗することがあるのだから、名人ほど才能のない自分が失敗したって仕方ない」と失敗したことに対する言い訳に使われることもあります。
また、弘法大師と筆に関することわざは他にもあり、「弘法は筆を選ばず」というようなことわざもあります。ただしこれに関しては歴史的には間違えているとされています。弘法大師は人一倍使用する道具や筆を選んで使用したとされているのです。こちらのことわざに関しては使用する際に注意したほうが良いでしょう。
また、弘法大師と筆に関することわざは他にもあり、「弘法は筆を選ばず」というようなことわざもあります。ただしこれに関しては歴史的には間違えているとされています。弘法大師は人一倍使用する道具や筆を選んで使用したとされているのです。こちらのことわざに関しては使用する際に注意したほうが良いでしょう。
使用法、使用例
「聞いたか、あの将棋の名人が二歩を指して負けたらしいぞ」
「弘法も筆の誤りだな。名人ほどそういった基本的なミスをするものさ」
「弘法も筆の誤りだな。名人ほどそういった基本的なミスをするものさ」
類似した意味のことわざ
このことわざには類似した意味のことわざが非常に多くあります。
有名なところでは「河童の川流れ」「猿も木から落ちる」の二つでしょうか。
他にも「巧者の手から水が漏る」「釈迦にも経の読み違い」「天狗の飛び損ない」など多数あり、そのどれもが「上手な者(名人や達人)でも失敗することがある」という意味を含んでいます。
有名なところでは「河童の川流れ」「猿も木から落ちる」の二つでしょうか。
他にも「巧者の手から水が漏る」「釈迦にも経の読み違い」「天狗の飛び損ない」など多数あり、そのどれもが「上手な者(名人や達人)でも失敗することがある」という意味を含んでいます。






















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

