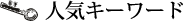織田信長 時代に異と覇を唱えた男のまぶしさを追う
関連キーワード

織田信長といえば、いくら歴史に興味が無い人でも、名前を知らない人はいないのではないでしょうか。
今では、歴史上の人物の域を超えて、ドラマや映画にゲーム、果てはパロディーと下手な芸能人やタレントより、よほどマルチに活躍しているように見えます。
巷での信長像といえば、「時代の革命者」であり、「泣かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」という句があるくらい残虐で、最後は天下統一を目前にして、本能寺の変で明智光秀に殺された人といった印象が強いように見えます。
確かにそういった一面もあるにはあるのですが、調べれば調べるほど、信長も一人の人間だったのであり、いろんな顔を見せてくれます。
今回はそんな信長の生き方を、その時々の時勢や感情を交えながら紹介していきたいと思います。
今では、歴史上の人物の域を超えて、ドラマや映画にゲーム、果てはパロディーと下手な芸能人やタレントより、よほどマルチに活躍しているように見えます。
巷での信長像といえば、「時代の革命者」であり、「泣かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」という句があるくらい残虐で、最後は天下統一を目前にして、本能寺の変で明智光秀に殺された人といった印象が強いように見えます。
確かにそういった一面もあるにはあるのですが、調べれば調べるほど、信長も一人の人間だったのであり、いろんな顔を見せてくれます。
今回はそんな信長の生き方を、その時々の時勢や感情を交えながら紹介していきたいと思います。
織田信長とは

織田信長は、天文3年(1534年)5月12日に、尾張国(愛知県西部)勝幡城で、織田信秀の三男として誕生しました。
幼名は「吉法師」であり、後に、「織田三郎信長」となります。
上に腹違いの兄、信広と秀俊がいますが、信長の生母である「土田御前」が信秀の正室であったために、三男でありながら嫡男とされました。
幼い時の信長は、町のヤンキーのボス的な位置付けで、周りの者からは「尾張の大うつけ」と陰口を叩かれていました。
その反面、新しい物への感心も強く、身分に関係なく町の若者と行動を共にしていたことから、庶民からは案外人気がありました。
また、面倒見もいいことから、当時三河国(愛知県東部)から、織田家への人質として来ていた、幼い竹千代(後の徳川家康)とも仲良くなり、後の織田・徳川連合締結に繋がっています。
そんな信長も天文15年(1546年)、古渡城にて元服し、「織田上総介信長」と周囲から呼ばれるようになります。
天文17年(1548年)には、織田家と対立していた美濃(岐阜県南部)の支配者である斉藤道山に気に入られ、娘の帰蝶(濃姫)を嫁に迎えました。
無事に嫁を迎えることができた信長ですが、天文20年(1551年)、父である信秀が亡くなったことから、「織田弾正忠家」の家督を継ぐことになります。
尾張守護代の中の、三家老の一家に過ぎなかった「織田弾正忠家」でしたが、弟・信行の謀反に遭いながらもそれを跳ね返し、謀略と金の力でもって下克上を果たし尾張を統一しました。
統一直後の尾張を、駿河(静岡県東部)の大大名である今川義元が、上洛のため尾張に侵攻しますが、一世一代の奇襲作戦にて義元の御首を上げ、侵攻を阻止することに成功し、一気に名を天下に広めました。
美濃の斎藤家の内紛に介入して美濃を併呑し、信長を頼ってきた足利義昭を奉じて上洛も果たしています。
畿内を押さえた信長は勢いに乗り、義昭が信長と袂を分かつ覚悟で、他大名と連携して苦しめた「信長包囲網」も各個撃破で潰され、気が付けば単独で信長を倒せる勢力はどこにもいなくなっていました。
天正10年(1582年)には戦国最強と呼ばれた武田騎馬軍団を擁する武田家も滅ぼされ、各方面でも有利に戦を進め、天下統一も目前というところで、部下である明智光秀の謀反に遭い、同年6月2日に、京の本能寺にて49歳の生涯を閉じるのです。
幼名は「吉法師」であり、後に、「織田三郎信長」となります。
上に腹違いの兄、信広と秀俊がいますが、信長の生母である「土田御前」が信秀の正室であったために、三男でありながら嫡男とされました。
幼い時の信長は、町のヤンキーのボス的な位置付けで、周りの者からは「尾張の大うつけ」と陰口を叩かれていました。
その反面、新しい物への感心も強く、身分に関係なく町の若者と行動を共にしていたことから、庶民からは案外人気がありました。
また、面倒見もいいことから、当時三河国(愛知県東部)から、織田家への人質として来ていた、幼い竹千代(後の徳川家康)とも仲良くなり、後の織田・徳川連合締結に繋がっています。
そんな信長も天文15年(1546年)、古渡城にて元服し、「織田上総介信長」と周囲から呼ばれるようになります。
天文17年(1548年)には、織田家と対立していた美濃(岐阜県南部)の支配者である斉藤道山に気に入られ、娘の帰蝶(濃姫)を嫁に迎えました。
無事に嫁を迎えることができた信長ですが、天文20年(1551年)、父である信秀が亡くなったことから、「織田弾正忠家」の家督を継ぐことになります。
尾張守護代の中の、三家老の一家に過ぎなかった「織田弾正忠家」でしたが、弟・信行の謀反に遭いながらもそれを跳ね返し、謀略と金の力でもって下克上を果たし尾張を統一しました。
統一直後の尾張を、駿河(静岡県東部)の大大名である今川義元が、上洛のため尾張に侵攻しますが、一世一代の奇襲作戦にて義元の御首を上げ、侵攻を阻止することに成功し、一気に名を天下に広めました。
美濃の斎藤家の内紛に介入して美濃を併呑し、信長を頼ってきた足利義昭を奉じて上洛も果たしています。
畿内を押さえた信長は勢いに乗り、義昭が信長と袂を分かつ覚悟で、他大名と連携して苦しめた「信長包囲網」も各個撃破で潰され、気が付けば単独で信長を倒せる勢力はどこにもいなくなっていました。
天正10年(1582年)には戦国最強と呼ばれた武田騎馬軍団を擁する武田家も滅ぼされ、各方面でも有利に戦を進め、天下統一も目前というところで、部下である明智光秀の謀反に遭い、同年6月2日に、京の本能寺にて49歳の生涯を閉じるのです。
正室・濃姫の謎

信長には、何人か側室がいましたが、正室に位置づけられているのが、「美濃のマムシ」こと斎藤道三の娘である濃姫です。
別名は帰蝶とも鷺山殿とも呼ばれており、天文4年(1535年)生まれで、信長より1つ年下であり、本能寺で信長を討った明智光秀の従兄妹でもあったようです。
天文17年(1548年)には、織田家と対立していた美濃(岐阜県南部)の支配者である斉藤道山に気に入られ、娘である濃姫を正室に迎えました。
濃姫も「美濃のマムシ」と呼ばれた戦国の梟雄・斉藤道山の娘だけあって肝が据わっており、信長との初夜の際に信長を暗殺しようとして失敗し、逆にお互いの絆が深まったという話も伝わっています。
しかし、道三が嫡子である斎藤義龍に「長良川の戦い」で討たれた後、濃姫の名前は歴史からぱったりと姿を消してしまいます。
信長の嫡男・信忠は、側室の吉乃との子であり、濃姫との間に子供ができたとは伝わっていないからかも知れませんが定かではありません。
濃姫の享年も分からないことから、信長に離縁された説や、はたまた本能寺で信長と共に光秀を迎え撃って討死したとも、たくさんの説が流れていますが、逆に何も分からないからこそ、後世の想像が膨らむのでしょう。
別名は帰蝶とも鷺山殿とも呼ばれており、天文4年(1535年)生まれで、信長より1つ年下であり、本能寺で信長を討った明智光秀の従兄妹でもあったようです。
天文17年(1548年)には、織田家と対立していた美濃(岐阜県南部)の支配者である斉藤道山に気に入られ、娘である濃姫を正室に迎えました。
濃姫も「美濃のマムシ」と呼ばれた戦国の梟雄・斉藤道山の娘だけあって肝が据わっており、信長との初夜の際に信長を暗殺しようとして失敗し、逆にお互いの絆が深まったという話も伝わっています。
しかし、道三が嫡子である斎藤義龍に「長良川の戦い」で討たれた後、濃姫の名前は歴史からぱったりと姿を消してしまいます。
信長の嫡男・信忠は、側室の吉乃との子であり、濃姫との間に子供ができたとは伝わっていないからかも知れませんが定かではありません。
濃姫の享年も分からないことから、信長に離縁された説や、はたまた本能寺で信長と共に光秀を迎え撃って討死したとも、たくさんの説が流れていますが、逆に何も分からないからこそ、後世の想像が膨らむのでしょう。
信長の側室
信長には正室・濃姫の他に側室と呼ばれる妻たちもたくさんおりました。その中でも有名な側室を紹介します。
吉乃(生駒氏の娘)
吉乃は濃姫と違い、嫡男・信忠の母親であるからか、生没がしっかりと伝わっています。
享禄元年(1528年)の生まれで、信長よりも年上だったようです。信長の側室になる前には別の男性と結婚していましたが、夫が戦死して実家に戻っていたところを信長に気に入られ側室となりました。
信長との子供は、信忠の他に、信雄、徳姫(家康の嫡男・信康の正室)と、どれも歴史的に有名な子供達ですが産後の肥立ちが悪く、永禄9年(1566年)5月31日に亡くなったようです。
享禄元年(1528年)の生まれで、信長よりも年上だったようです。信長の側室になる前には別の男性と結婚していましたが、夫が戦死して実家に戻っていたところを信長に気に入られ側室となりました。
信長との子供は、信忠の他に、信雄、徳姫(家康の嫡男・信康の正室)と、どれも歴史的に有名な子供達ですが産後の肥立ちが悪く、永禄9年(1566年)5月31日に亡くなったようです。
坂氏の娘
この夫人は名前は分かっていませんが、信長の三男・信孝の生母として有名です。
吉乃の子である信雄より信孝の方が20日ほど早く生まれたそうですが、吉乃の方が側室としての序列が上位だったため、信孝が三男にされたという話があります。
信孝に随伴していたようですが、信長亡き後の天正10年(1582年)12月、信孝が秀吉に攻められ降伏した際に、信孝の娘と共に秀吉の人質となりました。
ですが天正11年(1583年)4月、再度信孝が秀吉を裏切った際に、秀吉によって磔刑にされてしまいました。
吉乃の子である信雄より信孝の方が20日ほど早く生まれたそうですが、吉乃の方が側室としての序列が上位だったため、信孝が三男にされたという話があります。
信孝に随伴していたようですが、信長亡き後の天正10年(1582年)12月、信孝が秀吉に攻められ降伏した際に、信孝の娘と共に秀吉の人質となりました。
ですが天正11年(1583年)4月、再度信孝が秀吉を裏切った際に、秀吉によって磔刑にされてしまいました。
お鍋の方(興雲院)
この夫人は、信長が討たれた後に、秀吉の正室である北政所(おね)に仕えたことで名を知られています。
お鍋の方も初めは別の男性に嫁いでいましたが、嫁ぎ先が敵に攻められて前夫が討死した後に、信長の側室になったようです。
子供は前夫との間に2人と、信長との間に信高、信吉、於振を設けており、晩年は、豊臣秀頼と北政所の庇護によって過ごし、慶長17年(1612年)6月に亡くなったようです。
お鍋の方も初めは別の男性に嫁いでいましたが、嫁ぎ先が敵に攻められて前夫が討死した後に、信長の側室になったようです。
子供は前夫との間に2人と、信長との間に信高、信吉、於振を設けており、晩年は、豊臣秀頼と北政所の庇護によって過ごし、慶長17年(1612年)6月に亡くなったようです。
養観院
この夫人は秀吉の養子に出した信長の四男・羽柴秀勝の生母です。他に、蒲生氏郷の正室となった相応院の母とも言われています。
生没年は不明ですが、天正13年(1585年)12月に秀勝が亡くなった後に出家して信長と秀勝の菩提を弔ったと伝えられています。
生没年は不明ですが、天正13年(1585年)12月に秀勝が亡くなった後に出家して信長と秀勝の菩提を弔ったと伝えられています。
信長の子供たち

信長にも子供はたくさんいましたが、その中でも特に有名な子供たちを紹介します。
嫡男・織田信忠
信忠は、弘治元年(1555年)に信長の嫡男として、吉乃との間に生まれました。嫡男だったため正室・濃姫の養子にされたとも伝わっています。幼名は「奇妙丸」でした。
信長の後継者であり、信長の代理として長く戦陣にあり、優れた統率力や政治力を持った、後継者として相応しい人物でした。
天正10年(1582年)に武田家を滅亡させた甲州征伐でも総大将を務め、高遠城攻略戦では怯む味方に代わり、自ら陣頭に立って塀をよじ登って下知するなどの勇猛さを見せる一方で、婚約者だった信玄の六女・松姫の消息を追うなど、純粋な心も持ち合わせていました。
そんな貴公子・信忠も本能寺の変で信長が討たれた時には、同じく京にいましたが、宿所が違ったために生き残り、信長の仇の光秀を討つため残存兵力でもって光秀に挑むも多勢に無勢。
光秀軍に押し返され、最後は二条城に籠城し、仇を討つことなく自刃して果てるのです。
信長の後継者であり、信長の代理として長く戦陣にあり、優れた統率力や政治力を持った、後継者として相応しい人物でした。
天正10年(1582年)に武田家を滅亡させた甲州征伐でも総大将を務め、高遠城攻略戦では怯む味方に代わり、自ら陣頭に立って塀をよじ登って下知するなどの勇猛さを見せる一方で、婚約者だった信玄の六女・松姫の消息を追うなど、純粋な心も持ち合わせていました。
そんな貴公子・信忠も本能寺の変で信長が討たれた時には、同じく京にいましたが、宿所が違ったために生き残り、信長の仇の光秀を討つため残存兵力でもって光秀に挑むも多勢に無勢。
光秀軍に押し返され、最後は二条城に籠城し、仇を討つことなく自刃して果てるのです。
次男・織田信雄(北畠信雄)
信雄は、永禄元年(1558年)に信長と吉乃との間に生まれました。幼名は信雄の頭が茶道具の茶筅に似ていることから「茶筅」と名付けられたそうです。
信長の伊勢攻略時に、伊勢の国司である北畠具房の養子として北畠家へ入り、時間を追って北畠家の乗っ取りに成功しました。
信長亡き後は、秀吉の力を借りて、三男・信孝を攻め滅ぼすも秀吉と仲違いし、徳川家康と組んで秀吉と戦いますが単独講和に踏み切り、秀吉と和睦したのち改易され流罪となってしまいました。
その後は、秀吉に許され大坂城で秀吉、秀頼と二代に渡って仕えますが、大坂冬の陣の直前に徳川方に寝返り、戦後家康から5万石を与えられ、寛永7年(1630年)4月30日に京で73年の生涯を閉じました。
織田家中では無能の扱いを受け、信長から絶縁すると脅されたほどでしたが、織田家を明治維新まで残した功績は大きい人物と考えられています。
信長の伊勢攻略時に、伊勢の国司である北畠具房の養子として北畠家へ入り、時間を追って北畠家の乗っ取りに成功しました。
信長亡き後は、秀吉の力を借りて、三男・信孝を攻め滅ぼすも秀吉と仲違いし、徳川家康と組んで秀吉と戦いますが単独講和に踏み切り、秀吉と和睦したのち改易され流罪となってしまいました。
その後は、秀吉に許され大坂城で秀吉、秀頼と二代に渡って仕えますが、大坂冬の陣の直前に徳川方に寝返り、戦後家康から5万石を与えられ、寛永7年(1630年)4月30日に京で73年の生涯を閉じました。
織田家中では無能の扱いを受け、信長から絶縁すると脅されたほどでしたが、織田家を明治維新まで残した功績は大きい人物と考えられています。
三男・織田信孝(神戸信孝)
信孝は永禄元年(1558年)に信長と坂氏との間に生まれました。
信雄より20日ほど早く生まれ本来は次男になる予定でしたが、側室の序列で逆にされたとの話が伝わっています。幼名は「三七」でした。
信長の伊勢攻略戦の際に、伊勢北部の北畠家に信雄が養子に入ると、今度は信孝を伊勢南部の神戸家に養子として送り込み、神戸家を乗っ取らせました。
信長死亡時には四国征伐軍の総大将となっていましたが、信長討死の報に兵の逃亡が止まず、兵力が激減したところに大軍を率いた秀吉が到着し、連合して光秀を討つもその後の主導権は秀吉に奪われてしまいました。
織田家の宿老・柴田勝家と組んで秀吉に対抗しますが、勝家が越前北ノ庄城で滅ぼされると秀吉と組んだ次男・信雄に攻められ降伏。護送中に自害を命じられ天正11年(1583年)4月に自刃しました。
信孝が詠んだ辞世の句として、「むかしより 主をうつみの 野間なれば むくいを待てや 羽柴ちくぜん」という恨みのこもった壮絶な句が残されています。
信雄より20日ほど早く生まれ本来は次男になる予定でしたが、側室の序列で逆にされたとの話が伝わっています。幼名は「三七」でした。
信長の伊勢攻略戦の際に、伊勢北部の北畠家に信雄が養子に入ると、今度は信孝を伊勢南部の神戸家に養子として送り込み、神戸家を乗っ取らせました。
信長死亡時には四国征伐軍の総大将となっていましたが、信長討死の報に兵の逃亡が止まず、兵力が激減したところに大軍を率いた秀吉が到着し、連合して光秀を討つもその後の主導権は秀吉に奪われてしまいました。
織田家の宿老・柴田勝家と組んで秀吉に対抗しますが、勝家が越前北ノ庄城で滅ぼされると秀吉と組んだ次男・信雄に攻められ降伏。護送中に自害を命じられ天正11年(1583年)4月に自刃しました。
信孝が詠んだ辞世の句として、「むかしより 主をうつみの 野間なれば むくいを待てや 羽柴ちくぜん」という恨みのこもった壮絶な句が残されています。
信長の四男・羽柴秀勝
秀勝は永禄11年(1568年)に信長と養観院との間に誕生し「於次丸」と呼ばれました。
天正4年(1576年)10月に、秀吉が側室との間に産んだ石松丸を亡くした際に信長に願い出て、於次丸を養子として預かり、羽柴秀勝と名を改めさせました。
本能寺の変の後、秀勝は信長の四男という立場から、秀勝を喪主に立てつつ、秀吉が信長の葬儀を執り行い、内外に後継者である旨をアピールすることに成功しました。
秀吉の代行もこなすなど、そつなく優秀だった秀勝も病には勝てず、天正13年(1585年)12月、居城の丹波亀山城にて18歳の若さで病死したのです。
天正4年(1576年)10月に、秀吉が側室との間に産んだ石松丸を亡くした際に信長に願い出て、於次丸を養子として預かり、羽柴秀勝と名を改めさせました。
本能寺の変の後、秀勝は信長の四男という立場から、秀勝を喪主に立てつつ、秀吉が信長の葬儀を執り行い、内外に後継者である旨をアピールすることに成功しました。
秀吉の代行もこなすなど、そつなく優秀だった秀勝も病には勝てず、天正13年(1585年)12月、居城の丹波亀山城にて18歳の若さで病死したのです。
信長の長女・徳姫(五徳)
徳姫は永禄2年(1559年)に信長と吉乃との間に誕生しました。
永禄10年(1567年)に家康の嫡男である松平信康の元に嫁ぎ、2人の娘を産みましたが、いつまでも嫡子の誕生する様子が無いことを心配した信康の母である築山殿が、信康に側室を娶らせたことで徳姫との関係が悪化してしまいました。
このことに不満を持った徳姫は、父である信長に対して、築山殿や信康が武田に通じているなどの内容を盛り込んだ訴状を信長に送りました。
それを信じた信長は、築山殿と信康を成敗するよう家康に命じ、天正7年(1579年)、二人は自害させられてしまいました。
その後二人の娘を家康に預けて実家に戻り、晩年は京で過ごし、寛永13年(1636年)に死去したと伝わっています。
永禄10年(1567年)に家康の嫡男である松平信康の元に嫁ぎ、2人の娘を産みましたが、いつまでも嫡子の誕生する様子が無いことを心配した信康の母である築山殿が、信康に側室を娶らせたことで徳姫との関係が悪化してしまいました。
このことに不満を持った徳姫は、父である信長に対して、築山殿や信康が武田に通じているなどの内容を盛り込んだ訴状を信長に送りました。
それを信じた信長は、築山殿と信康を成敗するよう家康に命じ、天正7年(1579年)、二人は自害させられてしまいました。
その後二人の娘を家康に預けて実家に戻り、晩年は京で過ごし、寛永13年(1636年)に死去したと伝わっています。
信長の居城
信長は生まれた土地にこだわることなく領国支配に最適な土地があれば迷わずに本拠地を遷しました。
この土地に縛られない考え方も信長の強みの一つで、新しい考え方の持ち主であることがこのことからも窺えます。
ここでは信長が本拠地として定めた城を解説していきたいと思います。
この土地に縛られない考え方も信長の強みの一つで、新しい考え方の持ち主であることがこのことからも窺えます。
ここでは信長が本拠地として定めた城を解説していきたいと思います。
清洲城(1555年~1563年)

清須城ともいいます。場所は愛知県の清須市にあり、応永12年(1405年)に斯波義重に築城され、代々尾張守護代を務めた織田大和守家の居城となっていました。
弘治元年(1555年)に尾張守護の斯波義統を弑逆した織田大和守信友を討ち、清洲城を奪取した信長は、那古野城から清洲城に本拠を遷し、約8年に渡り本拠地としました。
今川義元を討った際もこの城に籠城するか討って出るかで意見が分かれたり、家康と同盟を結んだ城が清洲城であったことから、家康との同盟は「清洲同盟」と呼ばれています。
永禄6年(1563年)に美濃の斎藤龍興との戦に備えるため、本拠を清洲城から小牧山城に遷しました。
この後も清洲城は重要拠点として歴史に何度も登場しますが、江戸時代に名古屋城が完成すると清洲城はその役目を終えることになりました。
弘治元年(1555年)に尾張守護の斯波義統を弑逆した織田大和守信友を討ち、清洲城を奪取した信長は、那古野城から清洲城に本拠を遷し、約8年に渡り本拠地としました。
今川義元を討った際もこの城に籠城するか討って出るかで意見が分かれたり、家康と同盟を結んだ城が清洲城であったことから、家康との同盟は「清洲同盟」と呼ばれています。
永禄6年(1563年)に美濃の斎藤龍興との戦に備えるため、本拠を清洲城から小牧山城に遷しました。
この後も清洲城は重要拠点として歴史に何度も登場しますが、江戸時代に名古屋城が完成すると清洲城はその役目を終えることになりました。
小牧山城(1563年~1567年)

現在の愛知県小牧市にあり、初めは寺院があったそうですが、信長の小牧山城築城に際し移設されたと伝わっています。
美濃を獲るためには恰好な場所でしたが、清洲城からの移転に反対する者も少なくなく、信長は一計を案じました。
それは、もっと遠くの地に本拠地を移転するといっておきながら、皆の反対が出尽くしたころに改めて小牧山城に移す。と言ったもので、実行したところ反対意見が止んだそうです。
人間心理を巧みについた作戦でしたが、居城としたのはわずか4年であり、信長が美濃を制して岐阜城に本城を遷した永禄10年(1567年)に廃城となりました。
その後の登場は、天正12年(1584年)に秀吉と家康・信雄連合が戦った「小牧・長久手の戦い」で、その際に家康の本陣が小牧山に置かれ、城跡が有効活用されています。
美濃を獲るためには恰好な場所でしたが、清洲城からの移転に反対する者も少なくなく、信長は一計を案じました。
それは、もっと遠くの地に本拠地を移転するといっておきながら、皆の反対が出尽くしたころに改めて小牧山城に移す。と言ったもので、実行したところ反対意見が止んだそうです。
人間心理を巧みについた作戦でしたが、居城としたのはわずか4年であり、信長が美濃を制して岐阜城に本城を遷した永禄10年(1567年)に廃城となりました。
その後の登場は、天正12年(1584年)に秀吉と家康・信雄連合が戦った「小牧・長久手の戦い」で、その際に家康の本陣が小牧山に置かれ、城跡が有効活用されています。
岐阜城(1567年~1576年)

岐阜城は岐阜県の県庁所在地である岐阜市にあります。
岐阜城の前身は古く、建仁元年(1201年)に二階堂行政により稲葉山に砦が築かれたのが始まりでしたが、一度砦は破却されます。
それを15世紀中頃に砦跡を美濃守護代・斎藤利永が修復して居城としました。
そして大永5年(1525年)、斎藤氏の家臣だった長井氏が謀反を起こして稲葉山城を攻撃し、城を奪取して長井氏改め斎藤氏の代々の居城となりました。
そんな難攻不落の稲葉山城も、龍興が信長に敗れると龍興は逃亡し、稲葉山城を手に入れた信長は、小牧山から本拠を遷し、名を「岐阜城」と改めました。
岐阜とは、周の文王が岐山によって天下を平定したという、古代中国の故事に習った信長によって命名されました。
岐阜の名前は、信長の天下統一の意思表示の表れであり、「天下布武」もこの頃から使い始めたといわれています。
岐阜城は天正4年(1576年)に嫡男・信忠に織田家の家督と共に譲り、自身は近江の安土城へと本拠地を遷しました。
信長亡き後も、岐阜城は重要拠点であり続けましたが、慶長6年(1601年)、事実上の天下人となった徳川家康によって岐阜城は廃城とされました。
岐阜城の前身は古く、建仁元年(1201年)に二階堂行政により稲葉山に砦が築かれたのが始まりでしたが、一度砦は破却されます。
それを15世紀中頃に砦跡を美濃守護代・斎藤利永が修復して居城としました。
そして大永5年(1525年)、斎藤氏の家臣だった長井氏が謀反を起こして稲葉山城を攻撃し、城を奪取して長井氏改め斎藤氏の代々の居城となりました。
そんな難攻不落の稲葉山城も、龍興が信長に敗れると龍興は逃亡し、稲葉山城を手に入れた信長は、小牧山から本拠を遷し、名を「岐阜城」と改めました。
岐阜とは、周の文王が岐山によって天下を平定したという、古代中国の故事に習った信長によって命名されました。
岐阜の名前は、信長の天下統一の意思表示の表れであり、「天下布武」もこの頃から使い始めたといわれています。
岐阜城は天正4年(1576年)に嫡男・信忠に織田家の家督と共に譲り、自身は近江の安土城へと本拠地を遷しました。
信長亡き後も、岐阜城は重要拠点であり続けましたが、慶長6年(1601年)、事実上の天下人となった徳川家康によって岐阜城は廃城とされました。
安土城(1576年~1582年)

安土城は滋賀県の近江八幡市安土町にあり、琵琶湖東岸の安土山に築かれました。
元々は六角氏の本拠地である観音寺城の支城があった場所でしたが、信長の築いたその城は、五層七重の絢爛豪華な城で、天主の中は吹き抜けになっており、夜はライトアップまでしていたなど、凄いスペックを誇っていました。
その代わり、防御面には乏しく、どちらかといえば戦のためというよりも、政治、経済の中心地としての位置付けの方が高かったようです。
そんな安土城も、光秀が謀反を起こして信長を討った後、山崎の地で秀吉に敗れた際に、安土城を押さえていた、光秀の娘婿である明智秀満が撤退すると、天主が全焼してしまい、安土城からは天主が無くなってしまいました。
それでも二の丸を中心に安土城は存在していましたが、秀吉の養子である豊臣秀次が、近隣に近江八幡城を築城することになり、天正13年(1585年)に廃城とされました。
元々は六角氏の本拠地である観音寺城の支城があった場所でしたが、信長の築いたその城は、五層七重の絢爛豪華な城で、天主の中は吹き抜けになっており、夜はライトアップまでしていたなど、凄いスペックを誇っていました。
その代わり、防御面には乏しく、どちらかといえば戦のためというよりも、政治、経済の中心地としての位置付けの方が高かったようです。
そんな安土城も、光秀が謀反を起こして信長を討った後、山崎の地で秀吉に敗れた際に、安土城を押さえていた、光秀の娘婿である明智秀満が撤退すると、天主が全焼してしまい、安土城からは天主が無くなってしまいました。
それでも二の丸を中心に安土城は存在していましたが、秀吉の養子である豊臣秀次が、近隣に近江八幡城を築城することになり、天正13年(1585年)に廃城とされました。
信長の性格
信長を一言で表した俳句に「鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」というものがあります。
確かに信長には大量虐殺者のイメージが付き纏い、弟殺しまでしていますが、実は自分から裏切ったことは一度もなかったということを知っている人はどれほどいるでしょうか?
また、身内をすごく大事にし、身内を殺されたりした場合の報復にはすさまじいものがありましたが、信長の行動は全てが結果であり、そこに至るまでのプロセスが存在します。
ここでは残虐さが目立つ信長が、なぜそうしなければならなかったのかを見て行きたいと思います。
確かに信長には大量虐殺者のイメージが付き纏い、弟殺しまでしていますが、実は自分から裏切ったことは一度もなかったということを知っている人はどれほどいるでしょうか?
また、身内をすごく大事にし、身内を殺されたりした場合の報復にはすさまじいものがありましたが、信長の行動は全てが結果であり、そこに至るまでのプロセスが存在します。
ここでは残虐さが目立つ信長が、なぜそうしなければならなかったのかを見て行きたいと思います。
弟・信行との家督争い
生母である土田御前は信長を疎んじており、貴公子然とした弟の信行を溺愛していました。
柴田勝家を始め、多くの重臣たちも信行を次期当主にと推す者は多く、家中での信長の人気は高くありませんでした。
弘治2年(1556年)4月には、信長の正室・濃姫の父である斎藤道三が、嫡子の斎藤義龍と争い、信長も道三を助けるために援軍を率いるも、道三は長良川の戦いにて敗死し、信長もかろうじて戦場を離脱して尾張に戻ってきました。
そんな信長の器量を疑った、重臣・林秀貞、柴田勝家らは、信長を廃嫡し、聡明との誉れ高い信長の弟である信行を当主に据えようと画策し始めました。
道三も討死したことで、信長へ美濃からの援軍も無いと知っている信行軍はとうとう挙兵し、稲生の戦いにて信長軍と激突しますが、信行軍は返り討ちにあってしまいました。
信行は籠城し、信長と対峙しますが信長に降伏し、兄の信広も便乗して信長に謀反を企てますが事前に発覚したため、信長に侘びを入れ許されました。
しかしそんな信長の温情に対して、信行は再度信長に謀反を企てることで応えてしまいました。
二度目は無しと、信長もやむなく信行を清洲城に誘い出して殺害に及び、家督争いに決着が着いたのです。
柴田勝家を始め、多くの重臣たちも信行を次期当主にと推す者は多く、家中での信長の人気は高くありませんでした。
弘治2年(1556年)4月には、信長の正室・濃姫の父である斎藤道三が、嫡子の斎藤義龍と争い、信長も道三を助けるために援軍を率いるも、道三は長良川の戦いにて敗死し、信長もかろうじて戦場を離脱して尾張に戻ってきました。
そんな信長の器量を疑った、重臣・林秀貞、柴田勝家らは、信長を廃嫡し、聡明との誉れ高い信長の弟である信行を当主に据えようと画策し始めました。
道三も討死したことで、信長へ美濃からの援軍も無いと知っている信行軍はとうとう挙兵し、稲生の戦いにて信長軍と激突しますが、信行軍は返り討ちにあってしまいました。
信行は籠城し、信長と対峙しますが信長に降伏し、兄の信広も便乗して信長に謀反を企てますが事前に発覚したため、信長に侘びを入れ許されました。
しかしそんな信長の温情に対して、信行は再度信長に謀反を企てることで応えてしまいました。
二度目は無しと、信長もやむなく信行を清洲城に誘い出して殺害に及び、家督争いに決着が着いたのです。
比叡山焼き討ち
将軍・足利義昭に信長包囲網を敷かれた信長は苦戦し、義昭に調停を依頼することで窮地を脱した信長は、各個撃破せんと攻略に勤しんでいましたが、膠着状態から抜け出せずにいました。
それには比叡山も一枚噛んでいました。比叡山の主は現天皇である正親町天皇の弟であり、京の隣の大津に総本山を置き、その中には仇敵である浅井・朝倉軍も匿っており、信長にとっては膠着状態を抜け出すために、どうしても攻略しなければならない要衝でした。
浅井・朝倉軍の追放を願い出るももちろん却下され、比叡山を焼き尽くして全滅させるしかないという信長に対し、味方の中からも反対が相次ぎます。
比叡山は天台宗の聖地であり、信仰心の篤い者も多い中でその聖地を焼き払うなど、その業の深さに耐えられる者は決して多くはなかったのです。
しかし、手をこまねいていれば滅ぶのは自分の方。ならばと比叡山を包囲して僧侶、僧兵から女子供もまで山上に押し上げ、元亀2年(1571年)9月12日、総攻撃を開始し悉く虐殺して火をかけ、比叡山は一夜にして灰燼に帰してまいました。
比叡山全域が無人の荒野となってしまったことで、戦略価値の無くなった比叡山を寄り代にできなくなった浅井・朝倉連合は領国に戻るしかなくなり、各個撃破を待つだけとなってしまいました。
比叡山の焼き討ちは包囲網を崩すことには多大な貢献をしましたが、その苛烈な処断は世間での信長の悪評をさらに広め、家臣の心にはちょっとした翳りを残すことになってしまったのです。
それには比叡山も一枚噛んでいました。比叡山の主は現天皇である正親町天皇の弟であり、京の隣の大津に総本山を置き、その中には仇敵である浅井・朝倉軍も匿っており、信長にとっては膠着状態を抜け出すために、どうしても攻略しなければならない要衝でした。
浅井・朝倉軍の追放を願い出るももちろん却下され、比叡山を焼き尽くして全滅させるしかないという信長に対し、味方の中からも反対が相次ぎます。
比叡山は天台宗の聖地であり、信仰心の篤い者も多い中でその聖地を焼き払うなど、その業の深さに耐えられる者は決して多くはなかったのです。
しかし、手をこまねいていれば滅ぶのは自分の方。ならばと比叡山を包囲して僧侶、僧兵から女子供もまで山上に押し上げ、元亀2年(1571年)9月12日、総攻撃を開始し悉く虐殺して火をかけ、比叡山は一夜にして灰燼に帰してまいました。
比叡山全域が無人の荒野となってしまったことで、戦略価値の無くなった比叡山を寄り代にできなくなった浅井・朝倉連合は領国に戻るしかなくなり、各個撃破を待つだけとなってしまいました。
比叡山の焼き討ちは包囲網を崩すことには多大な貢献をしましたが、その苛烈な処断は世間での信長の悪評をさらに広め、家臣の心にはちょっとした翳りを残すことになってしまったのです。
長島一向一揆
浅井・朝倉連合を滅ぼした信長でしたが、石山本願寺の暗躍で一向一揆が静まる様子がありませんでした。
元亀元年(1570年)には一揆勢に追い詰められた弟・織田信興が籠城戦の末に自害に追い込まれています。
ここに至り信長は一向一揆の完全鎮圧に乗り出します。まず手始めに伊勢長島の一向一揆の鎮圧に向かいました。
初戦は有利に進んでいましたが、ある程度鎮圧して帰国しようとしたところ、一揆勢がまさかの逆襲を仕掛け、織田軍を追撃してきました。
不意を突かれつつも何とか美濃の大垣まで撤退することができた信長でしたが、代わりに異母兄の織田信広や弟の織田秀成が討死してしまいました。
それから1年後の天正2年(1574年)7月、復讐を誓った信長は、今度こそ伊勢長島の一向一揆を鎮圧するために、数万の大軍にて伊勢に侵攻し長島城を包囲。
一揆勢は降伏しましたが、信長は許さずに鉄砲で皆殺しにしてしまいました。
長島城が陥落し、残る二つの城に対しても火攻めを行い、城内の者たちもろとも焼き殺し、力ずくで平定されたのでした。
もちろん石山本願寺への報復も忘れず、石山本願寺のある河内国(大坂府東部)周辺を攻略し、一時的な和睦を取り付けたのです。
元亀元年(1570年)には一揆勢に追い詰められた弟・織田信興が籠城戦の末に自害に追い込まれています。
ここに至り信長は一向一揆の完全鎮圧に乗り出します。まず手始めに伊勢長島の一向一揆の鎮圧に向かいました。
初戦は有利に進んでいましたが、ある程度鎮圧して帰国しようとしたところ、一揆勢がまさかの逆襲を仕掛け、織田軍を追撃してきました。
不意を突かれつつも何とか美濃の大垣まで撤退することができた信長でしたが、代わりに異母兄の織田信広や弟の織田秀成が討死してしまいました。
それから1年後の天正2年(1574年)7月、復讐を誓った信長は、今度こそ伊勢長島の一向一揆を鎮圧するために、数万の大軍にて伊勢に侵攻し長島城を包囲。
一揆勢は降伏しましたが、信長は許さずに鉄砲で皆殺しにしてしまいました。
長島城が陥落し、残る二つの城に対しても火攻めを行い、城内の者たちもろとも焼き殺し、力ずくで平定されたのでした。
もちろん石山本願寺への報復も忘れず、石山本願寺のある河内国(大坂府東部)周辺を攻略し、一時的な和睦を取り付けたのです。
信長の優しさ
何ごとも合理的で冷たいイメージの付き纏う信長ですが、動けないものを保護しようとしたり、人の忠義に感動したりする人情家な部分も信長にはありました。
また自分の間違いは素直に認めることができるのも信長の魅力の一つでもあります。
ここではそんな信長の珍しい義理人情ものを紹介したいと思います。
また自分の間違いは素直に認めることができるのも信長の魅力の一つでもあります。
ここではそんな信長の珍しい義理人情ものを紹介したいと思います。
爺・平手政秀の諫言
信長は幼少時、「尾張の大うつけ」と呼ばれ、母の土田御前や家臣たちから厄介者の扱いを受けていました。
ですがそんな状況下でも、信長の守役である平手政秀だけは、信長のうつけぶりが擬態であると信じて諫言を続けていました。
そんな中、天文20年(1551年)、父・信秀が亡くなったことから、「織田弾正忠家」の家督を継ぐことになりました。
葬式の際、信長が信秀の霊前に抹香を投げつけたという逸話もあり、信長の大うつけぶりが国を超えて広がる元にもなりました。
事ここに至って政秀は、信長の目を覚ます最後の仕上げとして、自ら自害して果てることで信長を諫めました。
信長は目を覚ましました。
そしてそんな自分を信じて叱り続けてくれた爺を弔うために、政秀寺を建立して爺に応えると共に、その英邁さを世間に披露することになるのです。
ですがそんな状況下でも、信長の守役である平手政秀だけは、信長のうつけぶりが擬態であると信じて諫言を続けていました。
そんな中、天文20年(1551年)、父・信秀が亡くなったことから、「織田弾正忠家」の家督を継ぐことになりました。
葬式の際、信長が信秀の霊前に抹香を投げつけたという逸話もあり、信長の大うつけぶりが国を超えて広がる元にもなりました。
事ここに至って政秀は、信長の目を覚ます最後の仕上げとして、自ら自害して果てることで信長を諫めました。
信長は目を覚ましました。
そしてそんな自分を信じて叱り続けてくれた爺を弔うために、政秀寺を建立して爺に応えると共に、その英邁さを世間に披露することになるのです。
山中の猿
美濃と近江の国境近くの山中というところで「山中の猿」と呼ばれる、体に障害を抱えた男が街道沿いで乞食をしていました。
信長も移動中にたびたび目撃しており、大変気にかけていました。
そしてとうとう信長は見て見ぬふりができなくなり、山中集落の人々を集めると木綿20反を山中の猿に与えました。
そして人々には、この木綿を金に換えて、この者に小屋を建ててやってくれと訴えました。
さらにこの者が飢えないように、毎年食べ物を施してくれれば自分はとても嬉しいとも。
それを聞いた猿は元より、その場にいた人々も信長の優しさに涙したといいます。
信長も移動中にたびたび目撃しており、大変気にかけていました。
そしてとうとう信長は見て見ぬふりができなくなり、山中集落の人々を集めると木綿20反を山中の猿に与えました。
そして人々には、この木綿を金に換えて、この者に小屋を建ててやってくれと訴えました。
さらにこの者が飢えないように、毎年食べ物を施してくれれば自分はとても嬉しいとも。
それを聞いた猿は元より、その場にいた人々も信長の優しさに涙したといいます。
竹中半兵衛の隠し事
秀吉軍の与力として播磨に従軍していた摂津守護・荒木村重は、信長への不信から、居城である有岡城に戻り謀反を起こしました。
報せを受けた信長は、明智光秀や黒田官兵衛を説得の使者として有岡城に派遣しますが、村重が説得に応じる気配はありません。官兵衛に関しては逆に捕らえられ土牢に幽閉されてしまいました。
いつまでも有岡城から帰ってこない官兵衛を信長は疑い、秀吉が人質として預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸(後の長政)を殺せと命じました。
それから約1年後、落城した有岡城には村重や家臣達の親族や、村重が預かっていた人質に、土牢に幽閉された瀕死の官兵衛の姿もありました。
それを知った信長は、官兵衛の息子を殺させたと思い込んでおり、官兵衛に合わせる顔がないと、深く後悔するしかありませんでした。
しかし官兵衛を信じていた竹中半兵衛は、独断で松寿丸を殺さずに信長に隠し通していました。
それを知った信長は大変喜び、命令違反を咎めるどころか不問にし、半兵衛に謝意を示したのでした。
報せを受けた信長は、明智光秀や黒田官兵衛を説得の使者として有岡城に派遣しますが、村重が説得に応じる気配はありません。官兵衛に関しては逆に捕らえられ土牢に幽閉されてしまいました。
いつまでも有岡城から帰ってこない官兵衛を信長は疑い、秀吉が人質として預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸(後の長政)を殺せと命じました。
それから約1年後、落城した有岡城には村重や家臣達の親族や、村重が預かっていた人質に、土牢に幽閉された瀕死の官兵衛の姿もありました。
それを知った信長は、官兵衛の息子を殺させたと思い込んでおり、官兵衛に合わせる顔がないと、深く後悔するしかありませんでした。
しかし官兵衛を信じていた竹中半兵衛は、独断で松寿丸を殺さずに信長に隠し通していました。
それを知った信長は大変喜び、命令違反を咎めるどころか不問にし、半兵衛に謝意を示したのでした。
信長の名言

信長も歴史上の偉人だけあり、数々の名言を残しています。
その中から数点、解説を交えて紹介していきたいと思います。
「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て滅せぬ者のあるべきか」
これは信長が好んで舞ったといわれる幸若舞の演目の一つである「敦盛」の一節です。
今川義元に攻め込まれた際に、信長が清洲城にて敦盛を一差し舞って覚悟を決めたと言われています。
ここからの信長は素早く、瞬く間に義元の首を上げたのは余りに有名です。
信長の享年が49歳だったこともあり、信長の生き様はまさしく、この「敦盛」のようであったと思えてなりません。
「人を用ふるの者は能否を択ぶべし、何ぞ新古を論ぜん」
人を用いる者は才能の有無で選ぶべきで、奉公年数の長さで論ずべきではない。という意味です。
信長は常々この言葉を発していたと言われており、家臣に対しての考え方が一言で分かります。
才能があれば極貧の百姓出身の秀吉や、城を追われ諸国を流浪したこともある明智光秀であっても軍団長に任命しました。
逆に古くから織田家に仕えている林秀貞や佐久間信盛など、働きが悪かった家臣は追放するなどの厳しい一面も見せています。
この当時、家柄や年功序列よりも才覚を重視した信長は大変珍しく、織田家には綺羅星のごとく人材が集まったのです。
「是非に及ばず」
信長公記でも取り上げられており、信長のセリフの中では一番有名なのではないでしょうか。
信長が本能寺で謀反に遭った際、側近の森蘭丸に誰の謀反かを問いかけたところ、蘭丸は「紫に桔梗の紋 明智光秀の軍勢と見受けられます。」と答え、それを聞いた信長の一言。
是非に及ばず。は「仕方がない」、「やむを得ない」という意味であり、光秀に攻められたのなら、自分が生き長らえる見込みは万に一つもないことを悟ったからこその、信長の名言だったと考えられます。
光秀を評価していたのは誰よりも信長だったからこそ、この一言に全てがこもっている様に思えてなりません。
普段なら一目散に逃亡を図る信長も、この時ばかりは逃げるのを諦め、ひたすら明智勢を弓で射続けた信長の覚悟を感じます。
その中から数点、解説を交えて紹介していきたいと思います。
「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て滅せぬ者のあるべきか」
これは信長が好んで舞ったといわれる幸若舞の演目の一つである「敦盛」の一節です。
今川義元に攻め込まれた際に、信長が清洲城にて敦盛を一差し舞って覚悟を決めたと言われています。
ここからの信長は素早く、瞬く間に義元の首を上げたのは余りに有名です。
信長の享年が49歳だったこともあり、信長の生き様はまさしく、この「敦盛」のようであったと思えてなりません。
「人を用ふるの者は能否を択ぶべし、何ぞ新古を論ぜん」
人を用いる者は才能の有無で選ぶべきで、奉公年数の長さで論ずべきではない。という意味です。
信長は常々この言葉を発していたと言われており、家臣に対しての考え方が一言で分かります。
才能があれば極貧の百姓出身の秀吉や、城を追われ諸国を流浪したこともある明智光秀であっても軍団長に任命しました。
逆に古くから織田家に仕えている林秀貞や佐久間信盛など、働きが悪かった家臣は追放するなどの厳しい一面も見せています。
この当時、家柄や年功序列よりも才覚を重視した信長は大変珍しく、織田家には綺羅星のごとく人材が集まったのです。
「是非に及ばず」
信長公記でも取り上げられており、信長のセリフの中では一番有名なのではないでしょうか。
信長が本能寺で謀反に遭った際、側近の森蘭丸に誰の謀反かを問いかけたところ、蘭丸は「紫に桔梗の紋 明智光秀の軍勢と見受けられます。」と答え、それを聞いた信長の一言。
是非に及ばず。は「仕方がない」、「やむを得ない」という意味であり、光秀に攻められたのなら、自分が生き長らえる見込みは万に一つもないことを悟ったからこその、信長の名言だったと考えられます。
光秀を評価していたのは誰よりも信長だったからこそ、この一言に全てがこもっている様に思えてなりません。
普段なら一目散に逃亡を図る信長も、この時ばかりは逃げるのを諦め、ひたすら明智勢を弓で射続けた信長の覚悟を感じます。
信長の合戦
信長は49年の生涯の間に数々の戦を行ってきました。
基本、信長の戦闘スタイルは敵より多い兵力を集め、圧倒的優位に立って敵を殲滅するスタイルですが、もちろんそこまで都合良くは行かず、その中には仕方なく戦わざるを得なかった戦もありました。
ここでは信長が行った合戦を何点かピックアップして紹介したいと思います。
基本、信長の戦闘スタイルは敵より多い兵力を集め、圧倒的優位に立って敵を殲滅するスタイルですが、もちろんそこまで都合良くは行かず、その中には仕方なく戦わざるを得なかった戦もありました。
ここでは信長が行った合戦を何点かピックアップして紹介したいと思います。
桶狭間の戦い

信長が仕方なく戦うしかなかった戦の一つがこの桶狭間の戦いです。
尾張を統一した信長でしたが、豊かな尾張国は他国からも狙われていました。
駿河(静岡県東部)の太守である今川義元もその一人であり、上洛のために尾張を版図に加えようと画策していました。
義元は「東海一の弓取り」とも呼ばれ、駿河、遠江(静岡県西部)、三河の三国を支配する大大名でもありました。
たくさんの家臣を抱え、その中にはかつて、織田家に人質として来ていた竹千代の姿もありました。現在は、「松平元康」と名乗り、義元の養女を娶った娘婿でもあります。
そんな義元が、永禄3年(1560年)5月、とうとう上洛のために2万5000の大軍にて、尾張に侵攻を開始しました。
尾張を統一したばかりの信長はまだ支配も確立しておらず、用意できる兵力は3000にも及びませんでした。
今川軍は松平元康を先陣にどんどん尾張を攻略していきます。
まともに正面からぶつかれば織田軍は一瞬で吹き飛んでしまいます。
籠城を進言する家中に対し信長は決断。「敦盛」を一差し舞った後、城を飛び出しそのまま熱田神宮へ参拝し勝利祈願すると全軍を従えて、義元の本陣のある田楽狭間に真一文字に突き進みました。
田楽狭間にて休息中の義元の軍はバラバラに陣を張っており、義元の本陣には300余りの兵しかいませんでした。
そこに目を着けた信長は、雨風を味方に義元の本陣に近づき2000の兵にて強襲。
元々十分の一だった兵力は、義元の本陣だけに狙いを定めたこの一瞬のみ兵力が十倍近くという逆転現象が発生し、直前まで織田軍の接近に気付けなかった今川軍は大混乱に陥りました。
義元も多勢に無勢。信長の馬廻である服部小平太、毛利新助に討ち取られ、今川軍は総崩れとなって本国である駿河に撤退して行きました。
こうして名門の今川家は急速に力を失い、急死に一生を得た信長の名声が天下に轟くことになるのです。
尾張を統一した信長でしたが、豊かな尾張国は他国からも狙われていました。
駿河(静岡県東部)の太守である今川義元もその一人であり、上洛のために尾張を版図に加えようと画策していました。
義元は「東海一の弓取り」とも呼ばれ、駿河、遠江(静岡県西部)、三河の三国を支配する大大名でもありました。
たくさんの家臣を抱え、その中にはかつて、織田家に人質として来ていた竹千代の姿もありました。現在は、「松平元康」と名乗り、義元の養女を娶った娘婿でもあります。
そんな義元が、永禄3年(1560年)5月、とうとう上洛のために2万5000の大軍にて、尾張に侵攻を開始しました。
尾張を統一したばかりの信長はまだ支配も確立しておらず、用意できる兵力は3000にも及びませんでした。
今川軍は松平元康を先陣にどんどん尾張を攻略していきます。
まともに正面からぶつかれば織田軍は一瞬で吹き飛んでしまいます。
籠城を進言する家中に対し信長は決断。「敦盛」を一差し舞った後、城を飛び出しそのまま熱田神宮へ参拝し勝利祈願すると全軍を従えて、義元の本陣のある田楽狭間に真一文字に突き進みました。
田楽狭間にて休息中の義元の軍はバラバラに陣を張っており、義元の本陣には300余りの兵しかいませんでした。
そこに目を着けた信長は、雨風を味方に義元の本陣に近づき2000の兵にて強襲。
元々十分の一だった兵力は、義元の本陣だけに狙いを定めたこの一瞬のみ兵力が十倍近くという逆転現象が発生し、直前まで織田軍の接近に気付けなかった今川軍は大混乱に陥りました。
義元も多勢に無勢。信長の馬廻である服部小平太、毛利新助に討ち取られ、今川軍は総崩れとなって本国である駿河に撤退して行きました。
こうして名門の今川家は急速に力を失い、急死に一生を得た信長の名声が天下に轟くことになるのです。
金ヶ崎の退き口
畿内を平定した信長は将軍・足利義昭を擁していることを理由に越前の朝倉義景に上洛するよう迫りますが、義景は上洛しないどころか返事すら返さない始末。
義景がいつまでも上洛要請に応えないことを理由に元亀元年(1570年)4月、盟友の徳川家康と共に越前侵攻を開始しました。
侵攻は順調に進み、越前の玄関口でもある敦賀の金ヶ崎城を陥落させることに成功しました。
ところが、ここで思わぬ情報が飛び込んできます。
それは、「浅井長政、離反」というもの。
これはすなわち、浅井家が朝倉家に味方したことを意味し、同時に退路を失ったことも意味していました。
元々、浅井家と朝倉家は同盟関係にあり、朝倉家と織田家の仲が悪いことから、浅井家中では織田家との婚姻が反対されていたのを長政が押し通した形となっていました。
次から次へと「浅井長政、離反」の報に接するも、初め信長はその報を信じようとはしませんでした。
しかしふと、朝倉攻めの直前、長政に嫁いだ妹のお市の方から、不思議な袋に入った小豆を贈られたことを思い出してしまいました。
その袋はなぜか両端の口が紐で縛られていたのです。普通なら片方だけで充分なはずなのに…です。
信長はハッとしました。両端の口の縛りに合点がいったのです。
つまり、両端は朝倉と浅井、そして中の小豆は…。
信長はすぐさま朝倉攻めを中止し撤退を決断。家臣で智謀の誉れ高い木下藤吉郎秀吉と明智光秀に殿軍を任せ引き上げました。
それをみた朝倉軍も黙ってはいません。すぐさま追撃をかけ殿軍を次々と削って行きます。もちろん殿軍も覚悟の上ですし、信長も後ろを振り返る余裕はありません。
なにせ朝倉領を抜けても今度は敵地となった浅井家の北近江を抜かなければならないからです。
織田軍は解散し、散り散りになって京に落ち延びました。信長の供回りもわずか10人あまりしか残っておらず、生きていられたのが不思議なほどでした。
この撤退戦は後世「金ヶ崎の退き口」と呼ばれ、戦国時代でも最も有名な撤退戦として語り継がれるのです。
義景がいつまでも上洛要請に応えないことを理由に元亀元年(1570年)4月、盟友の徳川家康と共に越前侵攻を開始しました。
侵攻は順調に進み、越前の玄関口でもある敦賀の金ヶ崎城を陥落させることに成功しました。
ところが、ここで思わぬ情報が飛び込んできます。
それは、「浅井長政、離反」というもの。
これはすなわち、浅井家が朝倉家に味方したことを意味し、同時に退路を失ったことも意味していました。
元々、浅井家と朝倉家は同盟関係にあり、朝倉家と織田家の仲が悪いことから、浅井家中では織田家との婚姻が反対されていたのを長政が押し通した形となっていました。
次から次へと「浅井長政、離反」の報に接するも、初め信長はその報を信じようとはしませんでした。
しかしふと、朝倉攻めの直前、長政に嫁いだ妹のお市の方から、不思議な袋に入った小豆を贈られたことを思い出してしまいました。
その袋はなぜか両端の口が紐で縛られていたのです。普通なら片方だけで充分なはずなのに…です。
信長はハッとしました。両端の口の縛りに合点がいったのです。
つまり、両端は朝倉と浅井、そして中の小豆は…。
信長はすぐさま朝倉攻めを中止し撤退を決断。家臣で智謀の誉れ高い木下藤吉郎秀吉と明智光秀に殿軍を任せ引き上げました。
それをみた朝倉軍も黙ってはいません。すぐさま追撃をかけ殿軍を次々と削って行きます。もちろん殿軍も覚悟の上ですし、信長も後ろを振り返る余裕はありません。
なにせ朝倉領を抜けても今度は敵地となった浅井家の北近江を抜かなければならないからです。
織田軍は解散し、散り散りになって京に落ち延びました。信長の供回りもわずか10人あまりしか残っておらず、生きていられたのが不思議なほどでした。
この撤退戦は後世「金ヶ崎の退き口」と呼ばれ、戦国時代でも最も有名な撤退戦として語り継がれるのです。
姉川の戦い
越前から命からがら逃げ戻った信長を討たんと浅井・朝倉連合は、南近江の六角家と信長を挟み撃ちにしようとしますが、信長はそれを避け、本国の岐阜城へ撤退することに成功しました。
信長の挟み撃ちに失敗した六角軍がまず撃破され、その足で長政の居城・小谷城の南に姉川を隔てて立地する横山城を包囲しました。
家康も三河から駆けつけた一方、浅井軍も朝倉家からの援軍と合流し、姉川を挟んで織田軍の前面に浅井軍が。そして朝倉軍の前に徳川軍が対峙する形が出来上がりました。
そして元亀元年(1570年)6月28日午前6時、両軍は激突しました。
始め織田軍は浅井軍の先鋒である磯野員昌(かずまさ)にやり込められ、圧倒的に兵力では織田軍が有利だったにも関わらず次々と陣を破られ、信長の本陣の間近まで攻め込まれました。
絶対窮地の織田軍でしたが、もう一方では朝倉軍より寡兵な家康が、浅井・朝倉連合の陣が伸びきっていることに気付き、家臣の榊原康政に命じて側面を攻めさせたことにより戦況は好転。
朝倉軍が壊走すると、それを見た浅井軍が優勢だったにも関わらず負けたと思い込み次々と逃亡し、織田・徳川連合の勝利に終わりました。
浅井・朝倉連合の敗走を知った横山城も織田軍に降伏し、小谷城は王手を掛けられた状態になったのです。
信長の挟み撃ちに失敗した六角軍がまず撃破され、その足で長政の居城・小谷城の南に姉川を隔てて立地する横山城を包囲しました。
家康も三河から駆けつけた一方、浅井軍も朝倉家からの援軍と合流し、姉川を挟んで織田軍の前面に浅井軍が。そして朝倉軍の前に徳川軍が対峙する形が出来上がりました。
そして元亀元年(1570年)6月28日午前6時、両軍は激突しました。
始め織田軍は浅井軍の先鋒である磯野員昌(かずまさ)にやり込められ、圧倒的に兵力では織田軍が有利だったにも関わらず次々と陣を破られ、信長の本陣の間近まで攻め込まれました。
絶対窮地の織田軍でしたが、もう一方では朝倉軍より寡兵な家康が、浅井・朝倉連合の陣が伸びきっていることに気付き、家臣の榊原康政に命じて側面を攻めさせたことにより戦況は好転。
朝倉軍が壊走すると、それを見た浅井軍が優勢だったにも関わらず負けたと思い込み次々と逃亡し、織田・徳川連合の勝利に終わりました。
浅井・朝倉連合の敗走を知った横山城も織田軍に降伏し、小谷城は王手を掛けられた状態になったのです。
長篠の戦い

信玄亡き後の武田家では四男・勝頼が跡目を継いでいました。
勝頼は偉大なる父を超えるために再三隣国への侵攻を繰り返して領土の拡大に邁進しており、次の目標を武田家から徳川家に寝返った奥平貞昌の居城である長篠城に定めました。
1万5000の大軍に攻められた貞昌も寡兵ながら善戦し、長篠城は何とか持ち堪えるも落城は時間の問題でした。
家康よりの援軍要請を受けた信長は、武田の倍の3万の軍勢でもって、家康の8000の兵と共に長篠城に急行しました。
設楽原に陣を敷いた織田・徳川連合は、ここに馬防柵を張り巡らせ、堅固な野戦陣地を構築し、そこに持ち込んでいた大量の鉄砲を配置し、武田軍を待ち伏せました。
武田軍も、徳川軍に退路を断たれてしまいどうすることもできず、離脱するには織田・徳川連合軍が構築した馬防柵を突破するしかありませんでした。
信玄以来の重臣たちは無謀な突撃に反対しますが、勝頼はこれを強行し、突撃を敢行。
そして馬防柵からは鉄砲が騎馬隊目がけて間断なく撃ち掛けられ、山県昌景初め信玄以来の重臣達は悉く討死し、勝頼はほぼ全ての兵力をこの戦で失ってしまったのです。
勝頼は偉大なる父を超えるために再三隣国への侵攻を繰り返して領土の拡大に邁進しており、次の目標を武田家から徳川家に寝返った奥平貞昌の居城である長篠城に定めました。
1万5000の大軍に攻められた貞昌も寡兵ながら善戦し、長篠城は何とか持ち堪えるも落城は時間の問題でした。
家康よりの援軍要請を受けた信長は、武田の倍の3万の軍勢でもって、家康の8000の兵と共に長篠城に急行しました。
設楽原に陣を敷いた織田・徳川連合は、ここに馬防柵を張り巡らせ、堅固な野戦陣地を構築し、そこに持ち込んでいた大量の鉄砲を配置し、武田軍を待ち伏せました。
武田軍も、徳川軍に退路を断たれてしまいどうすることもできず、離脱するには織田・徳川連合軍が構築した馬防柵を突破するしかありませんでした。
信玄以来の重臣たちは無謀な突撃に反対しますが、勝頼はこれを強行し、突撃を敢行。
そして馬防柵からは鉄砲が騎馬隊目がけて間断なく撃ち掛けられ、山県昌景初め信玄以来の重臣達は悉く討死し、勝頼はほぼ全ての兵力をこの戦で失ってしまったのです。
本能寺の変

合戦ではないのでしょうが、信長最後の戦いが行われたのが、京にある本能寺です。
天正10年(1582年)6月、3ヶ月前には武田家を滅亡させ、関東方面軍の滝川一益、同盟者・徳川家康らが旧武田領の戦後処理に勤しんでいました。
北陸では柴田勝家率いる北陸方面軍が、上杉謙信亡き後の家督争いで疲弊した上杉を、越中(富山県全域)魚津城まで追い詰め、三男・信孝は、丹羽長秀を副将に長宗我部家の支配する四国に攻めかかる準備をしていました。
そして、羽柴秀吉率いる中国方面軍は、備中高松城にて、毛利方の忠臣・清水宗治を水攻めにして、城を湖の中に孤立させ落城寸前まで追い込み、毛利家の領国の備中(岡山県西南部)も間もなく支配下に治めんというところまで来ていました。
しかし、毛利領は広大で、とても秀吉軍だけで攻略するのは厳しいと感じていた秀吉は、信長に対して援軍の派遣を要請します。
そこで信長が選んだのが明智光秀の率いる畿内平定軍でした。畿内も今や、丹波(京都府中央部及び兵庫県東部)の波多野一族が滅び、光秀の手が空いていたことから白羽の矢が立ったのです。
しかし内心光秀は援軍が嫌でなりませんでした。それはつまり、光秀軍は実質、秀吉軍の麾下に置かれることに他ならなかったからです。
また、光秀の所領である近江坂本、丹波を召し上げ、代わりに攻略した後の出雲(島根県東部)・石見(同西部)の二カ国を安堵すると通達されます。
それは実質の減俸に他なりませんでした。現在、光秀の石高が40万石近くあるのに対し、一旦召し上げられた挙句、切り取り次第で与えられる出雲・石見は二カ国合わせても30万石にすらなりませんでした。
そんな渋る光秀に対し、信長は再度厳命し、光秀は居城の坂本城に戻り戦支度を始めました。戦支度を整えながら光秀は丹波亀山城に移動を開始。
その頃、信長は100名ほどの供回りと共に京の本能寺に宿所を移していました。
6月1日には本能寺に公家・僧侶衆を招き茶会を催しています。茶会から宴会へと移行し疲れた信長は床に入りました。
同じ日、光秀も信長の前で閲兵式を行うという名目を付け、1万3000の兵にて丹波亀山城を出陣しました。
まず初めに、明智秀満や斎藤利三など重臣達を集めて、信長への謀反を切り出しました。
重臣達は黙っていましたが、光秀の決断が変わらないことを察し、何より光秀の恩に報いるため、快く従うことを誓いました。
次は兵士たちの説得です。一つ間違えば軍の解散を招くだけではなく、信長に謀反を知られることにもなりかねません。
本能寺まであとわずかの場所である桂川に到達すると、兵に戦支度をさせ、引けぬ状況に追い込んだ後で光秀は真の敵の名を明かします。
兵はあまりの恐れ多さに驚愕しますが、光秀により戦支度させられてしまった以上は賊軍のそしりを免れず、連帯責任で信長を討つしかなくなり、逆に士気は高まりました。
そして光秀は声高に号令を発しました。
「敵は本能寺にあり」
天正10年(1582年)6月2日未明、明智軍1万3000は本能寺を包囲。
騒ぎに目を覚ました信長は鬨の声が聞こえてきたことから、近くにいた近習の森蘭丸に誰の仕業かと訪ねました。
そこで蘭丸は答えました。
紫に桔梗の紋。明智光秀の軍勢と見受けられます。との返答に対して信長は、「是非に及ばず」と答え覚悟を決め、次から次へと明智勢を弓で射抜いていきます。弓の弦が切れると今度は槍を片手に雑兵を蹴散らしていきました。
近習たちはそんな信長を守りながら奮戦しますが数が圧倒的に違うため、次から次へと討ち減らされていきます。
森兄弟も討たれ、万策尽きた信長は燃え盛る本能寺の中に姿を消し、本能寺は灰燼の中に帰しました。
近くの妙覚寺に滞在していた信忠は、光秀の謀反を知ると、京都所司代の村井貞勝らと共に信長の救援に向かおうとしますがこちらも多勢に無勢。
二条城に籠城すると皇太子や公家衆を逃がしたのち、光秀に攻められ自刃しました。
変後、光秀は本能寺の焼け跡の中から信長の首を探しますが、とうとう発見することができず、万が一の生存の不安がしこりとなって胸に残ることになってしまいました。
そして、賊軍として畿内を固めることのできないまま秀吉軍の来襲を許し、わずか11日後の6月13日に秀吉に京の郊外の山崎で決戦を挑んで破れ、小栗栖(おぐるす)の地にて落ち武者狩りに遭いその最期を終えました。
信長の仇を討った秀吉は織田家の後継者戦争を勝ち残り、信長の意思を継いで天下を統一することになるのです。
天正10年(1582年)6月、3ヶ月前には武田家を滅亡させ、関東方面軍の滝川一益、同盟者・徳川家康らが旧武田領の戦後処理に勤しんでいました。
北陸では柴田勝家率いる北陸方面軍が、上杉謙信亡き後の家督争いで疲弊した上杉を、越中(富山県全域)魚津城まで追い詰め、三男・信孝は、丹羽長秀を副将に長宗我部家の支配する四国に攻めかかる準備をしていました。
そして、羽柴秀吉率いる中国方面軍は、備中高松城にて、毛利方の忠臣・清水宗治を水攻めにして、城を湖の中に孤立させ落城寸前まで追い込み、毛利家の領国の備中(岡山県西南部)も間もなく支配下に治めんというところまで来ていました。
しかし、毛利領は広大で、とても秀吉軍だけで攻略するのは厳しいと感じていた秀吉は、信長に対して援軍の派遣を要請します。
そこで信長が選んだのが明智光秀の率いる畿内平定軍でした。畿内も今や、丹波(京都府中央部及び兵庫県東部)の波多野一族が滅び、光秀の手が空いていたことから白羽の矢が立ったのです。
しかし内心光秀は援軍が嫌でなりませんでした。それはつまり、光秀軍は実質、秀吉軍の麾下に置かれることに他ならなかったからです。
また、光秀の所領である近江坂本、丹波を召し上げ、代わりに攻略した後の出雲(島根県東部)・石見(同西部)の二カ国を安堵すると通達されます。
それは実質の減俸に他なりませんでした。現在、光秀の石高が40万石近くあるのに対し、一旦召し上げられた挙句、切り取り次第で与えられる出雲・石見は二カ国合わせても30万石にすらなりませんでした。
そんな渋る光秀に対し、信長は再度厳命し、光秀は居城の坂本城に戻り戦支度を始めました。戦支度を整えながら光秀は丹波亀山城に移動を開始。
その頃、信長は100名ほどの供回りと共に京の本能寺に宿所を移していました。
6月1日には本能寺に公家・僧侶衆を招き茶会を催しています。茶会から宴会へと移行し疲れた信長は床に入りました。
同じ日、光秀も信長の前で閲兵式を行うという名目を付け、1万3000の兵にて丹波亀山城を出陣しました。
まず初めに、明智秀満や斎藤利三など重臣達を集めて、信長への謀反を切り出しました。
重臣達は黙っていましたが、光秀の決断が変わらないことを察し、何より光秀の恩に報いるため、快く従うことを誓いました。
次は兵士たちの説得です。一つ間違えば軍の解散を招くだけではなく、信長に謀反を知られることにもなりかねません。
本能寺まであとわずかの場所である桂川に到達すると、兵に戦支度をさせ、引けぬ状況に追い込んだ後で光秀は真の敵の名を明かします。
兵はあまりの恐れ多さに驚愕しますが、光秀により戦支度させられてしまった以上は賊軍のそしりを免れず、連帯責任で信長を討つしかなくなり、逆に士気は高まりました。
そして光秀は声高に号令を発しました。
「敵は本能寺にあり」
天正10年(1582年)6月2日未明、明智軍1万3000は本能寺を包囲。
騒ぎに目を覚ました信長は鬨の声が聞こえてきたことから、近くにいた近習の森蘭丸に誰の仕業かと訪ねました。
そこで蘭丸は答えました。
紫に桔梗の紋。明智光秀の軍勢と見受けられます。との返答に対して信長は、「是非に及ばず」と答え覚悟を決め、次から次へと明智勢を弓で射抜いていきます。弓の弦が切れると今度は槍を片手に雑兵を蹴散らしていきました。
近習たちはそんな信長を守りながら奮戦しますが数が圧倒的に違うため、次から次へと討ち減らされていきます。
森兄弟も討たれ、万策尽きた信長は燃え盛る本能寺の中に姿を消し、本能寺は灰燼の中に帰しました。
近くの妙覚寺に滞在していた信忠は、光秀の謀反を知ると、京都所司代の村井貞勝らと共に信長の救援に向かおうとしますがこちらも多勢に無勢。
二条城に籠城すると皇太子や公家衆を逃がしたのち、光秀に攻められ自刃しました。
変後、光秀は本能寺の焼け跡の中から信長の首を探しますが、とうとう発見することができず、万が一の生存の不安がしこりとなって胸に残ることになってしまいました。
そして、賊軍として畿内を固めることのできないまま秀吉軍の来襲を許し、わずか11日後の6月13日に秀吉に京の郊外の山崎で決戦を挑んで破れ、小栗栖(おぐるす)の地にて落ち武者狩りに遭いその最期を終えました。
信長の仇を討った秀吉は織田家の後継者戦争を勝ち残り、信長の意思を継いで天下を統一することになるのです。
信長の強さの真髄
信長亡き後に天下を取った豊臣秀吉は、大坂城に諸侯を集めた際にこういう謎掛けをしました。
それは、「1万の兵を率いた蒲生殿(氏郷)と5000の兵を率いた亡き信長様が戦ったらどちらが勝つか」というもの。
蒲生氏郷といえば信長の娘婿であり、戦上手で知られ、今は奥羽(東北全域)の抑えとして、会津に92万石で封じられている大大名です。
諸侯は恐れ多いながらも、そんな蒲生氏郷が相手ならば半分の兵力しかない信長はさすがに勝てないだろうと、大半の諸侯は蒲生氏郷の勝ちを予想しました。
しかし秀吉の答えは違いました。秀吉は半分の兵力の信長が勝つと断言したのです。
氏郷に比べ信長の戦い方は、敵よりも多い兵を用意して、敵よりも優位に立って戦うやり方であり、真正面から戦う信長が強いとは考えられていませんでした。
実際信長が相手より劣勢で戦ったのは桶狭間での戦いなどごく少数しかありません。
そんな信長が勝つと断言した秀吉に対して、諸侯は亡き主君に対する忠義を褒め称えましたが、秀吉はそうではないと諸侯を抑えました。
秀吉はこういいました。
勇猛な蒲生殿のことだ。もし1万のうち半数の兵が討ち取られればその中に必ずや蒲生殿の首があろう。
しかし信長様は勝てない戦をする人ではない。もし5000のうち4900の首が獲られたとしてもその中に信長様の首はあるまい。
そして、何度も戦を挑み、最後は必ずや蒲生殿に勝つと断言したのです。
その返答に諸侯はただただ納得するだけだったといいます。
秀吉も言っていたように信長は必ず相手よりも優位な立ち位置に着いてから戦を始めていました。逆に相手より不利ならば戦を始めることはありませんでした。
それでも戦わなければならない時は、最小限に被害を留めつつも逃げるを恥とせず、果ては土下座して和睦を請うことも厭いませんでした。
そして必ず最後には勝つ。信長の戦いには武士の誉れなど関係ない、実利だけを伴った必勝のプロセスがあったのです。
それは、「1万の兵を率いた蒲生殿(氏郷)と5000の兵を率いた亡き信長様が戦ったらどちらが勝つか」というもの。
蒲生氏郷といえば信長の娘婿であり、戦上手で知られ、今は奥羽(東北全域)の抑えとして、会津に92万石で封じられている大大名です。
諸侯は恐れ多いながらも、そんな蒲生氏郷が相手ならば半分の兵力しかない信長はさすがに勝てないだろうと、大半の諸侯は蒲生氏郷の勝ちを予想しました。
しかし秀吉の答えは違いました。秀吉は半分の兵力の信長が勝つと断言したのです。
氏郷に比べ信長の戦い方は、敵よりも多い兵を用意して、敵よりも優位に立って戦うやり方であり、真正面から戦う信長が強いとは考えられていませんでした。
実際信長が相手より劣勢で戦ったのは桶狭間での戦いなどごく少数しかありません。
そんな信長が勝つと断言した秀吉に対して、諸侯は亡き主君に対する忠義を褒め称えましたが、秀吉はそうではないと諸侯を抑えました。
秀吉はこういいました。
勇猛な蒲生殿のことだ。もし1万のうち半数の兵が討ち取られればその中に必ずや蒲生殿の首があろう。
しかし信長様は勝てない戦をする人ではない。もし5000のうち4900の首が獲られたとしてもその中に信長様の首はあるまい。
そして、何度も戦を挑み、最後は必ずや蒲生殿に勝つと断言したのです。
その返答に諸侯はただただ納得するだけだったといいます。
秀吉も言っていたように信長は必ず相手よりも優位な立ち位置に着いてから戦を始めていました。逆に相手より不利ならば戦を始めることはありませんでした。
それでも戦わなければならない時は、最小限に被害を留めつつも逃げるを恥とせず、果ては土下座して和睦を請うことも厭いませんでした。
そして必ず最後には勝つ。信長の戦いには武士の誉れなど関係ない、実利だけを伴った必勝のプロセスがあったのです。

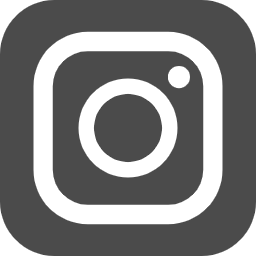
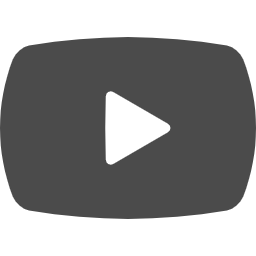

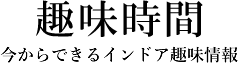

















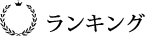

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)