ローズマリーの剪定のコツ。きれいに樹形をととのえよう。
関連キーワード

ローズマリーは香りが強く、常緑なので、料理に使う分などをちょっぴり収穫する場合は、一年中収穫することができます。
ローズマリーには虫もあまり寄り付かないので、安心して無農薬で栽培できる点も魅力です。
ローズマリーは紫色の小さな花も楽しめる、見た目も爽やかな育てやすいハーブですが、剪定をしないとボサボサになって扱いにくくなってしまいます。
おしゃれな樹形を保ってローズマリーを長く栽培していくために、剪定のコツをご紹介していきましょう。
ローズマリーには虫もあまり寄り付かないので、安心して無農薬で栽培できる点も魅力です。
ローズマリーは紫色の小さな花も楽しめる、見た目も爽やかな育てやすいハーブですが、剪定をしないとボサボサになって扱いにくくなってしまいます。
おしゃれな樹形を保ってローズマリーを長く栽培していくために、剪定のコツをご紹介していきましょう。
ローズマリーの強剪定は花のない時期が適期

ローズマリーの開花期間は11~5月ですが、一度に桜のように満開になるのではなく、小さな紫色の花がポツポツと咲き続けます。
ローズマリーの剪定の適期は花後になる6月と、花の咲く前の9~10月で、大きな枝をバッサリ切るのはこの頃が適しています。
枝をちょいちょい切って収穫するのは剪定と違って通年できますが、真夏や真冬は木が弱っているので収穫は控えめに行いましょう。
小さな枝先を切り落とすと、そこから脇芽が出てくるので、こんもりさせたいときは枝先を時々剪定する必要があります。
ローズマリーの剪定の適期は花後になる6月と、花の咲く前の9~10月で、大きな枝をバッサリ切るのはこの頃が適しています。
枝をちょいちょい切って収穫するのは剪定と違って通年できますが、真夏や真冬は木が弱っているので収穫は控えめに行いましょう。
小さな枝先を切り落とすと、そこから脇芽が出てくるので、こんもりさせたいときは枝先を時々剪定する必要があります。
伸ばす枝の先には必ず緑の葉っぱを残して
ローズマリーの枝同士が絡み合ってしまい、一つの枝をまるごと切り落としてしまうときは、枝の付け根から切り落とします。
これから育てていきたい枝を少し切りそろえる場合は、枝に緑の葉っぱが残っている状態で切り落とします。
緑の葉っぱがなくなるところまで剪定してしまうと、その枝からは次に新しい緑の葉っぱは出て来ません。
切った枝を大きく伸ばしたいときは、必ず緑の葉っぱが残っている位置で剪定します。
これから育てていきたい枝を少し切りそろえる場合は、枝に緑の葉っぱが残っている状態で切り落とします。
緑の葉っぱがなくなるところまで剪定してしまうと、その枝からは次に新しい緑の葉っぱは出て来ません。
切った枝を大きく伸ばしたいときは、必ず緑の葉っぱが残っている位置で剪定します。
混み枝はいつでも剪定してスッキリさせて

葉がたくさん出過ぎて、ローズマリーがワシャワシャしてしまって、株全体が蒸れてしまっているときは、剪定の適期でなくても適宜剪定してすっきりさせる必要があります。
夏に枝がたくさん出てきて混み合っていると、特に蒸れがひどくなってしまうので、盛夏になる前に、必ず一度は混み枝をすっきりさせる剪定するようにしましょう。
ローズマリーの枝が地面についてしまうと、そこから根を伸ばして根付いてしまい、上へ上へと成長していく力が別の方向へ進んでしまうので、地面につくような下の方の枝を優先的に切り落とします。
ローズマリーは生育が旺盛なので、いつの間にやら枝が伸び過ぎ、地面についていることがよくあります。
地面に枝がつくことがないように、下の方の枝の伸び具合には日頃から気をつけるようにしましょう。
下の方の地面につくような枝を剪定したら、株全体に風通しが良くなるように、混み枝も落としていきます。
地面からローズマリーの枝までの間に、十分に空間が空いている状態になって、空気が抜けるように形を整えていきます。
どの枝を切ったからと言って、大きく枯れ込む心配はないので、全体に軽くなるように枝数を減らしていきましょう。
夏に枝がたくさん出てきて混み合っていると、特に蒸れがひどくなってしまうので、盛夏になる前に、必ず一度は混み枝をすっきりさせる剪定するようにしましょう。
ローズマリーの枝が地面についてしまうと、そこから根を伸ばして根付いてしまい、上へ上へと成長していく力が別の方向へ進んでしまうので、地面につくような下の方の枝を優先的に切り落とします。
ローズマリーは生育が旺盛なので、いつの間にやら枝が伸び過ぎ、地面についていることがよくあります。
地面に枝がつくことがないように、下の方の枝の伸び具合には日頃から気をつけるようにしましょう。
下の方の地面につくような枝を剪定したら、株全体に風通しが良くなるように、混み枝も落としていきます。
地面からローズマリーの枝までの間に、十分に空間が空いている状態になって、空気が抜けるように形を整えていきます。
どの枝を切ったからと言って、大きく枯れ込む心配はないので、全体に軽くなるように枝数を減らしていきましょう。
木立性のローズマリーの剪定のポイント
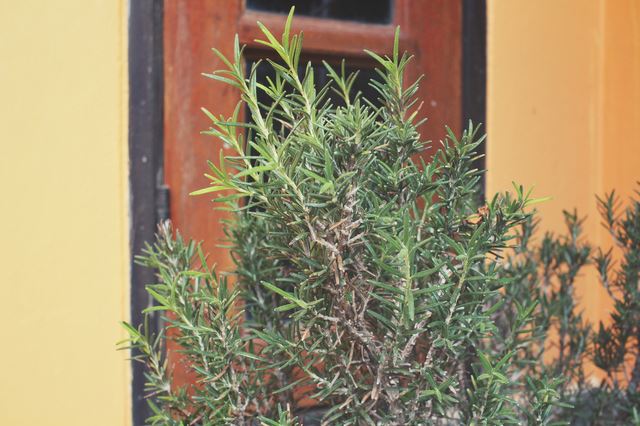
木立性のローズマリーを剪定する場合、枝数全体を減らす場合は、枝の途中でなく付け根から切り落とすようにしましょう。
大きくなったローズマリーの上の方の枝が曲がってきたときは、伸びすぎて横に倒れたような枝をバッサリ好きなところから切り落として、まっすぐに伸びるように形を整えます。
木立性のローズマリーでも土に枝がつくと根が出てどんどん広がるので、枝が土に触れないようにして、枝の下から空気が入るように剪定します。
下の方の枝はできるだけ落としておくようにします。
大きくなったローズマリーの上の方の枝が曲がってきたときは、伸びすぎて横に倒れたような枝をバッサリ好きなところから切り落として、まっすぐに伸びるように形を整えます。
木立性のローズマリーでも土に枝がつくと根が出てどんどん広がるので、枝が土に触れないようにして、枝の下から空気が入るように剪定します。
下の方の枝はできるだけ落としておくようにします。
匍匐性・半匍匐性のローズマリーの剪定のポイント

匍匐性・半匍匐性のローズマリーは、横へ横へとどんどん伸びていくので、放置していると下の方の枝周りが蒸れて枯れ込んでしまいます。
枯れ込んでしまった枝は復活してこないので、付け根から切り落として全体を軽くします。
これから伸ばす枝は緑の葉っぱのある位置で切り落としますが、残した枝でも、下の方の混み枝は、風通しを良くするのにじゃまになるので、根本から切り落とします。
全体的に下の方を重点的にすっきりさせると、空気が通るようになって、株の状態を良くすることができます。
枯れ込んでしまった枝は復活してこないので、付け根から切り落として全体を軽くします。
これから伸ばす枝は緑の葉っぱのある位置で切り落としますが、残した枝でも、下の方の混み枝は、風通しを良くするのにじゃまになるので、根本から切り落とします。
全体的に下の方を重点的にすっきりさせると、空気が通るようになって、株の状態を良くすることができます。
スタイリッシュな樹形に剪定するには

ローズマリーの下の方に枝がない状態で、上の方にだけ葉っぱが茂る、葉のない茎が長く伸びる「スタンダード仕立て」にするときは、立木性のローズマリーの中から、特に下の方の枝数が少ないものを選んで、下の方の枝を切り落としながら育てていきます。
上の方の枝はちょうど長さが揃うように伸びすぎた分だけ剪定しながら育てます。
葉っぱが円などを描くような「トピアリー仕立て」にするときは、匍匐性のローズマリーを選んで、左右の長い枝2本だけを残して中央の枝を剪定し、残した枝を上で交差させ、枝の交わっているところを針金などで固定して形を整えていきます。
匍匐性のローズマリーの細い枝は柔らかいので、簡単に形作れます。
ローズマリーは剪定に強いので、思い切った形に剪定することができます。
小さく枝先を切っているとどんどん大きくなるので、大きくしたいときは緑の葉を残して枝先で剪定し、小さくまとめておきたいときは枝の付け根で剪定しておきましょう。
監修:きなりのすもも
16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、
ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、
一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。
上の方の枝はちょうど長さが揃うように伸びすぎた分だけ剪定しながら育てます。
葉っぱが円などを描くような「トピアリー仕立て」にするときは、匍匐性のローズマリーを選んで、左右の長い枝2本だけを残して中央の枝を剪定し、残した枝を上で交差させ、枝の交わっているところを針金などで固定して形を整えていきます。
匍匐性のローズマリーの細い枝は柔らかいので、簡単に形作れます。
ローズマリーは剪定に強いので、思い切った形に剪定することができます。
小さく枝先を切っているとどんどん大きくなるので、大きくしたいときは緑の葉を残して枝先で剪定し、小さくまとめておきたいときは枝の付け根で剪定しておきましょう。
監修:きなりのすもも
16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、
ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、
一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。
























![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

