加賀友禅の歴史は500年前から! 有名な加賀友禅の特徴とは
関連キーワード

加賀友禅の起源はおよそ500年前、加賀の国の染め技法であった”梅染”に遡ります。
17世紀の中頃には、いわゆる加賀御国染と呼ばれる兼房染や色絵、色絵紋の技法が確立されました。加賀友禅の始祖、その名の由縁となる宮崎友禅斎の登場により、加賀友禅は大きな発展期を迎えます。友禅斎は江戸中期に京都から金沢の御用紺屋棟取・太郎田屋に身を寄せ、御国染の意匠の改善や友禅糊の完成など輝かしい加賀友禅の基礎をうちたてました。
17世紀の中頃には、いわゆる加賀御国染と呼ばれる兼房染や色絵、色絵紋の技法が確立されました。加賀友禅の始祖、その名の由縁となる宮崎友禅斎の登場により、加賀友禅は大きな発展期を迎えます。友禅斎は江戸中期に京都から金沢の御用紺屋棟取・太郎田屋に身を寄せ、御国染の意匠の改善や友禅糊の完成など輝かしい加賀友禅の基礎をうちたてました。

加賀友禅の特色は、写実的な草花模様を中心とした絵画調にあります。武家風の落ち着きのある趣を楽しむことができます。また、加賀友禅は五彩と言われる藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫を基調とする紅系統を生かした多彩調であり、淡青単彩調の京友禅との違いがあります。

技法においてもボカシや虫喰いの技法もよく使われ、自然美を巧みに描き出しています。京友禅が内側から外側にボカシてあるのに対し、加賀友禅では逆に外側から内側に向かってボカシてあるのが一般的な特徴といえます。さらに技法のひとつ糸目糊。これは挿色の防線が主目的ですが、水で洗いおとすと草花の葉筋や水の流れなど繊細な白い線が浮かびあがり、装飾効果を高めています。

加賀友禅は加賀百万石の武家文化の中で育ち、人間国宝に指定された木村雨山師をはじめ多くの名工が生まれ、全国的に著名な作家を輩出してきました。その伝統はいまも受け継がれ、数多くの作家が精力的に創作活動を行っています。

加賀友禅 花夢館
http://www.hanayumekan.co.jp/







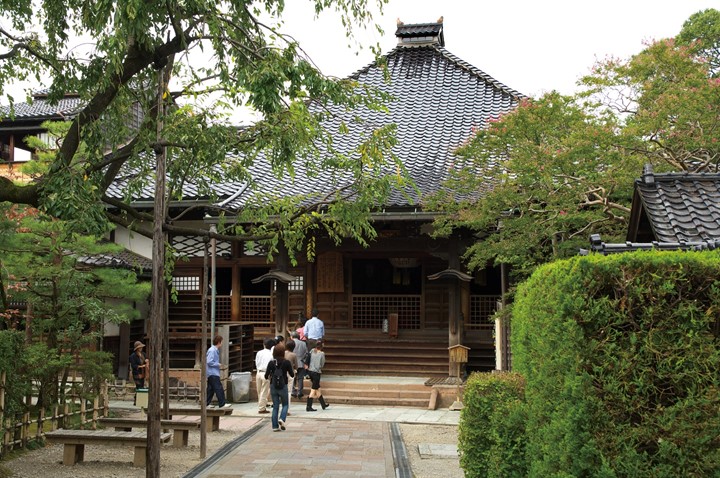















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

