こんな美術館があったのか! 杉本博司氏が手掛けた「江之浦測候所」の楽しみ方
関連キーワード

「江之浦測候所」をご存知ですか?
そのネーミングからイメージするのは、観測所? 測候所? 一体何? と感じてしまいますが、そこに広がるアートな世界は、一見の価値があり、見る者の感性さえ研ぎ澄まされる不思議な場所です。
そのネーミングからイメージするのは、観測所? 測候所? 一体何? と感じてしまいますが、そこに広がるアートな世界は、一見の価値があり、見る者の感性さえ研ぎ澄まされる不思議な場所です。
根府川に位置する江之浦測候所
アクセスは、東海道新幹線小田原駅もしくは熱海駅からJR東海道線に乗車。根府川駅という無人駅で下車。そこから無料送迎バスで10分ほどで到着します。
ただ、訪れる前に注意したいのが、チケットを購入して予約しておかなくてはならないこと。午前と午後の二部制になっており、ネット予約が基本となっていますが、当日に空きがある場合は、電話にて当日予約をすることができます。
ただ、訪れる前に注意したいのが、チケットを購入して予約しておかなくてはならないこと。午前と午後の二部制になっており、ネット予約が基本となっていますが、当日に空きがある場合は、電話にて当日予約をすることができます。
いつ、誰の、どんな思いのもとに創られたのか?

江之浦測候所は、構想10年、建設10年の年月をかけて2018年10月にオープンしました。写真家であり、建築家であり、現代美術作家の杉本博司氏が手掛けたもので、記憶にある原風景からこの地を選んだようです。
氏曰く、「悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。新たなる命が再生される冬至、重要な折り返し点の夏至、通過点である春分と秋分。天空を測候する事にもう一度立ち返ってみる、そこにこそかすかな未来へと通ずる糸口が開いているように私は思う」。
氏の思いの丈がすべて詰まったこの場所で、過ごしてみると新たな発見や自然の中で生かされている自身を見つめ直すことができるかもしれません。
行ってみて、体験するのが一番です。
氏曰く、「悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。新たなる命が再生される冬至、重要な折り返し点の夏至、通過点である春分と秋分。天空を測候する事にもう一度立ち返ってみる、そこにこそかすかな未来へと通ずる糸口が開いているように私は思う」。
氏の思いの丈がすべて詰まったこの場所で、過ごしてみると新たな発見や自然の中で生かされている自身を見つめ直すことができるかもしれません。
行ってみて、体験するのが一番です。
どんな造形美があるのだろうか?

現地に訪れて、まず目に付くのは明月門。明月門は鎌倉にある臨済宗建長寺派の正門として室町時代に建てられました。数度の解体移築を経たのち、根津美術館の正門として使用されていましたが、建て替えに伴い小田原文化財団に寄贈され、江之浦測候所の正門として移築再建されたものです。
待合棟でチェックインや館内の説明を受けますが、この建物は4面すべてがガラスで覆わられており、箱根外輪山が見渡せる造りになっています。
待合棟でチェックインや館内の説明を受けますが、この建物は4面すべてがガラスで覆わられており、箱根外輪山が見渡せる造りになっています。
夏至光遥拝100メートルギャラリー

海抜100メートルの地点に100メートルの長さを持つギャラリーが建っています。片側の壁には大谷石が使われており、反対面はガラス窓で形成され、突端部は展望スペースとして海に突き出すように設計されています。
夏至の朝、海から昇る太陽の光が数分間、この空間を駆け抜けるように造られており、杉本氏の計算しつくされた造形美を見ることができます。
夏至の朝、海から昇る太陽の光が数分間、この空間を駆け抜けるように造られており、杉本氏の計算しつくされた造形美を見ることができます。
冬至光遥拝隧道

冬至の朝には、相模湾から昇る陽光が70メートルの隧道を貫き、その先の対面にあたる巨石を照らされる造りとなっています。
光学硝子舞台と古代ローマ円形劇場写し観客席
隧道と平行にガラス舞台が配置されており、観客席となる部分は古代ローマ円形劇場遺跡を実測したうえに模してあり、この観客席からガラスの舞台がまるで海面に浮いているように見えます。
そのほか、見どころが数多く配置されており、所内に盛り込まれた、国内外を問わぬ貴重な石の数々は見る者を飽きさせず、それぞれが融合しているところがまた見事と言えるでしょう。
何度訪れても、楽しみ方は見る者次第で無限に拡がっていくのではないでしょうか。
時間・季節・天候によっても楽しみ方が変わり、雨の日には、雨粒が古井戸に落ちるさまに趣きを感じ、海・空・空間とコラボする様子には、心が洗われるようです。
また、3月には菜の花が咲き、静かな造形に黄色の味を加えている姿が春の息吹を感じさせてくれます。
そのほか、見どころが数多く配置されており、所内に盛り込まれた、国内外を問わぬ貴重な石の数々は見る者を飽きさせず、それぞれが融合しているところがまた見事と言えるでしょう。
何度訪れても、楽しみ方は見る者次第で無限に拡がっていくのではないでしょうか。
時間・季節・天候によっても楽しみ方が変わり、雨の日には、雨粒が古井戸に落ちるさまに趣きを感じ、海・空・空間とコラボする様子には、心が洗われるようです。
また、3月には菜の花が咲き、静かな造形に黄色の味を加えている姿が春の息吹を感じさせてくれます。

竹林エリアも地続きで併設されており、竹林だけではなく、みかんの道としても散策できるようになっており、みかんの花が咲く頃にはきっと、爽やかな香りを身に受け五感でも楽しめることでしょう。
小田原文化財団 江之浦測候所
住所:神奈川県小田原市江之浦 362-1
休館日:火曜日・水曜日、年末年始および臨時休館日
見学時間:1日2回:午前の部(10時~13時)、午後の部(13時30分~16時30分)
(各回定員制)
入館料:インターネットから事前に購入の場合
3000円(税別)
当日券利用の場合
3500円(税別)
※当日券は定員に達している場合、販売はありません。
小田原文化財団 江之浦測候所
住所:神奈川県小田原市江之浦 362-1
休館日:火曜日・水曜日、年末年始および臨時休館日
見学時間:1日2回:午前の部(10時~13時)、午後の部(13時30分~16時30分)
(各回定員制)
入館料:インターネットから事前に購入の場合
3000円(税別)
当日券利用の場合
3500円(税別)
※当日券は定員に達している場合、販売はありません。

















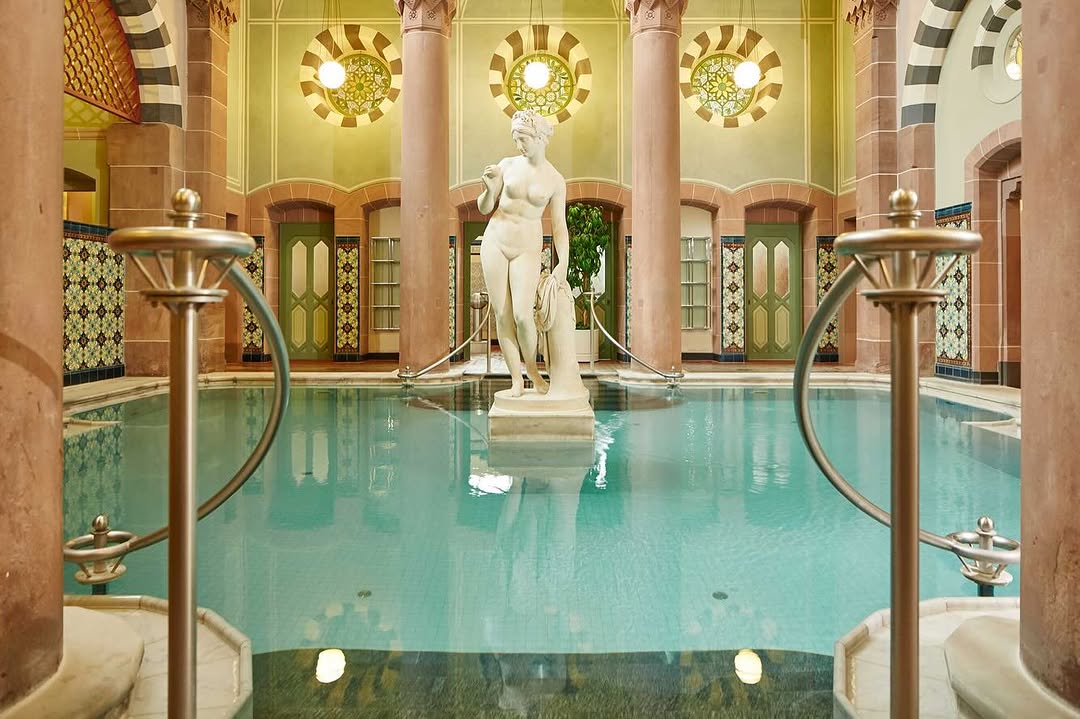






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

