キーワードでさぐる『孟子』の奥深さ!シンプルな中に隠された秘密!
関連キーワード
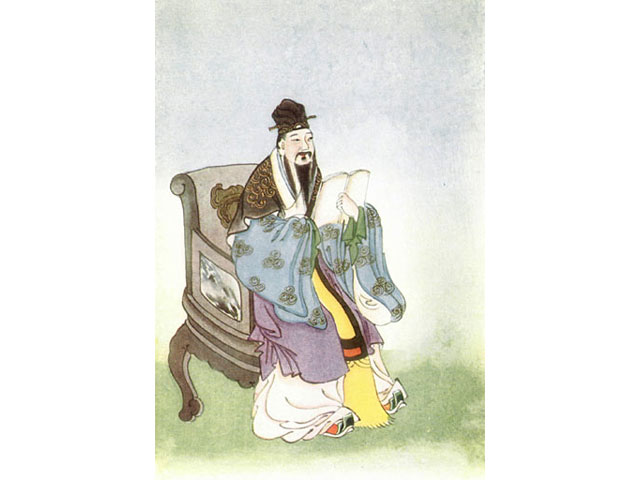
中国の儒教思想における重要な書物として、『論語』と並び称されてきた『孟子』。
作者とされる孟子は孔子に準ずるという意味で「亜聖」と呼ばれることもあります。孟子が生まれた時代は、群雄割拠の戦国時代。
「百家争鳴」と形容されるように、それまでの貴族に変わって、様々な新興思想家たちが目まぐるしく現れていた時代です。そんな混乱期生まれた『孟子』という書物は、政治のコツから日常生活の所作しきたりまで、幅広い分野に対する処方箋として、また、『論語』とともに儒教の基本文献として今日まで読み継がれてきました。
中国思想史における『孟子』の重要度は何人も疑わないものではありますが、『論語』と比べると認知度が高いとはいえません。
『孟子』と聞けば「性善説」とか、「浩然の気」といったキーワードこそ思い浮かびますが、さて実際どのような文脈で語られているかというと、なかなか知らないものです。
そこで、孟子の思想におけるキーワードを、それが語られる文脈と合わせて紹介していきたいと思います。
作者とされる孟子は孔子に準ずるという意味で「亜聖」と呼ばれることもあります。孟子が生まれた時代は、群雄割拠の戦国時代。
「百家争鳴」と形容されるように、それまでの貴族に変わって、様々な新興思想家たちが目まぐるしく現れていた時代です。そんな混乱期生まれた『孟子』という書物は、政治のコツから日常生活の所作しきたりまで、幅広い分野に対する処方箋として、また、『論語』とともに儒教の基本文献として今日まで読み継がれてきました。
中国思想史における『孟子』の重要度は何人も疑わないものではありますが、『論語』と比べると認知度が高いとはいえません。
『孟子』と聞けば「性善説」とか、「浩然の気」といったキーワードこそ思い浮かびますが、さて実際どのような文脈で語られているかというと、なかなか知らないものです。
そこで、孟子の思想におけるキーワードを、それが語られる文脈と合わせて紹介していきたいと思います。
性善説
孟子で一番有名な思想といえば「性善説」ではないでしょうか。
荀子の「性悪説」と対にして言及されることの多い「性善説」について、孟子はどのように語っているのでしょうか。「公孫丑章句 上6」を見てみましょう。
孟子は言いました。
「人間みな、人をあわれむ気持ち(人に忍びざるの心)があるものだ。(中略)人間みなが人をあわれむ気持ちがある、というのはどうしてか。
いま、井戸に落っこちそうな赤ちゃんを見たら、誰でもあたふたし、いたたまれずに助けに行くに違いない。これは、その赤ちゃんの父母と仲良くなろうとか、村人や仲間内で名誉を勝ち取ろうとか、助けなかった場合の非難がいやだったからとか、そういった気持ちからの行動ではない。」
このように、孟子は井戸に今にも落ちんとする赤ちゃんの例を用いて、誰しも、名誉心といった損得勘定を抜きにして、赤ちゃんをあわれみ、助けるだろう、と述べています。孟子はさらにこの例を敷衍し、「仁・義・礼・智」につながる四つの感情、すなわち有名な「四端」について語ります。
「このことを鑑みれば、あわれみの気持ち(惻隠の心)を持たないものは、人間ではないのだ。悪を恥じる気持ち(羞悪)を持たないものは、人間ではないのだ。譲る気持ち(辞譲)を持たないものは、人間ではないのだ。善し悪しを見分ける気持ち(是非)を持たないものは、人間ではないのだ。惻隠の心は、仁の端緒である。羞悪の心は、義の端緒である。辞譲の心は、礼の端緒である。是非の心は、智の端緒である。」
孟子は、「四端」を持っていることは特別なことではなく、この「四端」を拡充することを思い立ちさえすれば、「火が燃え始め、泉の源から水が流れ始めるように」この「四端」はやがて大きくなり、天下を安らかに治める(四海を安んずる)こともできる、とさえ言います。孟子が「天下を治めることもできる」とまで言っているのは、人徳によって天下を治めるという、「仁政」という考えが背後にあるからでしょう。政治の奥義もまた、基本的な「四端」に発するというわけです。
荀子の「性悪説」と対にして言及されることの多い「性善説」について、孟子はどのように語っているのでしょうか。「公孫丑章句 上6」を見てみましょう。
孟子は言いました。
「人間みな、人をあわれむ気持ち(人に忍びざるの心)があるものだ。(中略)人間みなが人をあわれむ気持ちがある、というのはどうしてか。
いま、井戸に落っこちそうな赤ちゃんを見たら、誰でもあたふたし、いたたまれずに助けに行くに違いない。これは、その赤ちゃんの父母と仲良くなろうとか、村人や仲間内で名誉を勝ち取ろうとか、助けなかった場合の非難がいやだったからとか、そういった気持ちからの行動ではない。」
このように、孟子は井戸に今にも落ちんとする赤ちゃんの例を用いて、誰しも、名誉心といった損得勘定を抜きにして、赤ちゃんをあわれみ、助けるだろう、と述べています。孟子はさらにこの例を敷衍し、「仁・義・礼・智」につながる四つの感情、すなわち有名な「四端」について語ります。
「このことを鑑みれば、あわれみの気持ち(惻隠の心)を持たないものは、人間ではないのだ。悪を恥じる気持ち(羞悪)を持たないものは、人間ではないのだ。譲る気持ち(辞譲)を持たないものは、人間ではないのだ。善し悪しを見分ける気持ち(是非)を持たないものは、人間ではないのだ。惻隠の心は、仁の端緒である。羞悪の心は、義の端緒である。辞譲の心は、礼の端緒である。是非の心は、智の端緒である。」
孟子は、「四端」を持っていることは特別なことではなく、この「四端」を拡充することを思い立ちさえすれば、「火が燃え始め、泉の源から水が流れ始めるように」この「四端」はやがて大きくなり、天下を安らかに治める(四海を安んずる)こともできる、とさえ言います。孟子が「天下を治めることもできる」とまで言っているのは、人徳によって天下を治めるという、「仁政」という考えが背後にあるからでしょう。政治の奥義もまた、基本的な「四端」に発するというわけです。
浩然の気
前項で見た、「四端」を大きくする(拡充する)という考えは、孟子の「浩然の気」の思想につながっていきます。
再び「公孫丑章句 上」の一節に視点を向けてみましょう。登場するのは孟子と公孫丑という人物。公孫丑は、孟子の弟子です。ある時、公孫丑が心の動揺について師である孟子に尋ねると、孟子は「40歳になったときから、動揺はしない」と告げます。そして、心の平静を保つための方法について、別の思想家告子の説などを引用しながら、説明する孟子。すると公孫丑は、「孟子と告子の違いはなにか」と問います。それに対し孟子は、「浩然の気」を挙げます。
公孫丑が問うことには、
「その浩然の気とはなんなのでしょうか。」
孟子は答えました。
「強いて言うならば、際限なく大きく、強く、正しいものだ。しっかり養うならば、天地に充満するほどになる。これが浩然の気である。」
続いて孟子は、「浩然の気」は正義と人道(義と道)によって養われると説きます。さらに孟子は、「浩然の気」は外部から生まれるのではなく、道義にしたがうことで内から自然と生まれてくるのだ、といいます。人間の内側から自然と育つ、という考えは「四端」の考えと似ているようには思いませんか。
再び「公孫丑章句 上」の一節に視点を向けてみましょう。登場するのは孟子と公孫丑という人物。公孫丑は、孟子の弟子です。ある時、公孫丑が心の動揺について師である孟子に尋ねると、孟子は「40歳になったときから、動揺はしない」と告げます。そして、心の平静を保つための方法について、別の思想家告子の説などを引用しながら、説明する孟子。すると公孫丑は、「孟子と告子の違いはなにか」と問います。それに対し孟子は、「浩然の気」を挙げます。
公孫丑が問うことには、
「その浩然の気とはなんなのでしょうか。」
孟子は答えました。
「強いて言うならば、際限なく大きく、強く、正しいものだ。しっかり養うならば、天地に充満するほどになる。これが浩然の気である。」
続いて孟子は、「浩然の気」は正義と人道(義と道)によって養われると説きます。さらに孟子は、「浩然の気」は外部から生まれるのではなく、道義にしたがうことで内から自然と生まれてくるのだ、といいます。人間の内側から自然と育つ、という考えは「四端」の考えと似ているようには思いませんか。
恒産なければ恒心なし
定まった収入源がなければ、落ち着いた心を持てない、という有名な言葉も『孟子』に由来します。『孟子』が「恒産なければ恒心なし」を語るのは、「梁恵王章句 上」です。梁恵王に政道のポイントを問われた孟子はつぎのように答えます。
孟子「恒産がなくて、しっかりと恒心を失わずにいられるのは、高潔の士のみにできることでございます。
一般の民は恒産がなければ、それによって恒心もなくなります。もし恒心がなくなると、わがまま・ひがみ・よこしま・ぜいたく(放辟邪侈)なんでもやってしまいます。(中略)古の君主が人民の生計を取り計らうやり方といえば、父母には十分な暮らしをさせることができ、妻子も十分養うことができ、豊年には苦しみなく、凶年でも餓死はしないようにしたものです。その上で君主が民を教化して善の道に引っ張ったからこそ、民はたやすくついてきたのです。」
ここでの孟子のポイントは、シンプルそのもの。まずは衣食住などの基本的な恒産を保障した上で、民を教化せよ、と孟子は言っているのです。言い換えれば「衣食足りて礼節を知る」といったところでしょうか。君主は仁によって、民を尊び、教化しなければならない、という思想は、「王道政治」として『孟子』のなかで一貫して説かれている考えです。この「王道」の考え方は、王の徳を重視し、民の意を天命として尊重する孟子の「易姓革命」の考えにも繋がっていきます。
以上、性善説と浩然の気、恒産なければ恒心なしという3つのキーワードを紹介しました。「性善説」と聞くと、人間は悪いことをしないかのように聞こえますが、四端や浩然の気について孟子が語るように、「養う」ことをおろそかにすれば、「放辟邪侈」に陥ります。
ここではあまり紹介できませんでしたが、『孟子』の魅力は(危険でもあるのですが、)その巧みな弁論術にもあります。もっとも、孟子自身は「わたしはどうして弁説を好もうか。やむを得ないのだ」と言ってはいますが。
孟子「恒産がなくて、しっかりと恒心を失わずにいられるのは、高潔の士のみにできることでございます。
一般の民は恒産がなければ、それによって恒心もなくなります。もし恒心がなくなると、わがまま・ひがみ・よこしま・ぜいたく(放辟邪侈)なんでもやってしまいます。(中略)古の君主が人民の生計を取り計らうやり方といえば、父母には十分な暮らしをさせることができ、妻子も十分養うことができ、豊年には苦しみなく、凶年でも餓死はしないようにしたものです。その上で君主が民を教化して善の道に引っ張ったからこそ、民はたやすくついてきたのです。」
ここでの孟子のポイントは、シンプルそのもの。まずは衣食住などの基本的な恒産を保障した上で、民を教化せよ、と孟子は言っているのです。言い換えれば「衣食足りて礼節を知る」といったところでしょうか。君主は仁によって、民を尊び、教化しなければならない、という思想は、「王道政治」として『孟子』のなかで一貫して説かれている考えです。この「王道」の考え方は、王の徳を重視し、民の意を天命として尊重する孟子の「易姓革命」の考えにも繋がっていきます。
以上、性善説と浩然の気、恒産なければ恒心なしという3つのキーワードを紹介しました。「性善説」と聞くと、人間は悪いことをしないかのように聞こえますが、四端や浩然の気について孟子が語るように、「養う」ことをおろそかにすれば、「放辟邪侈」に陥ります。
ここではあまり紹介できませんでしたが、『孟子』の魅力は(危険でもあるのですが、)その巧みな弁論術にもあります。もっとも、孟子自身は「わたしはどうして弁説を好もうか。やむを得ないのだ」と言ってはいますが。





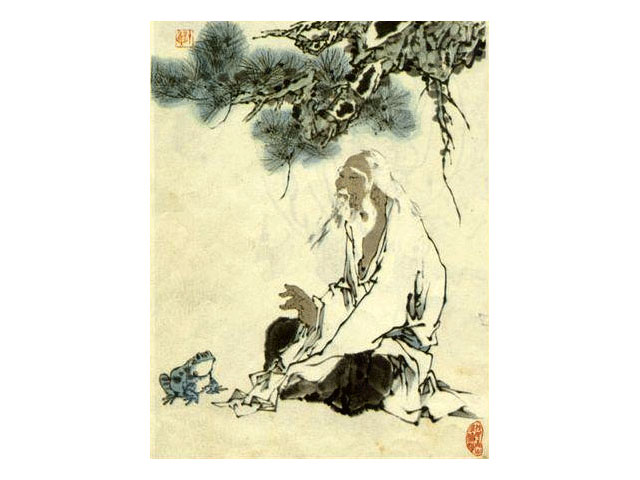



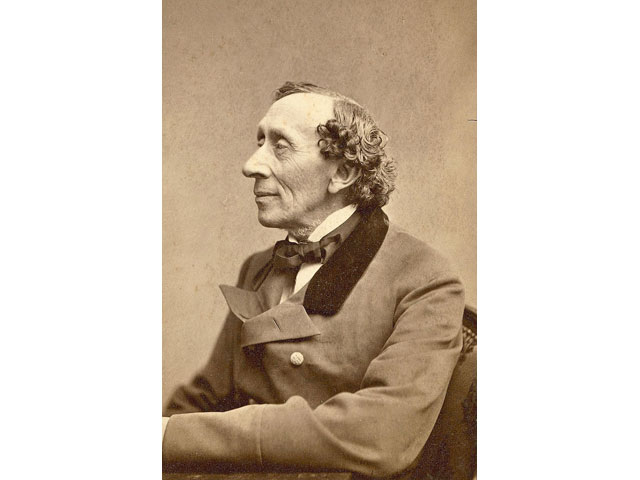













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

