その時歴史は動いた!知られていないマルティン・ルター以前の【宗教改革者たち】の不遇
関連キーワード

16世紀前半に起きた宗教改革は、世界史において十指に入るほどの大イベントでした。
古くから西洋の文化、政治に多大な影響を及ぼす根本的な制度となっていたキリスト教、そのキリスト教にテコを入れる、という事業は歴史に大変革をもたらしたことはいうまでもありません。現在でも、カトリックの地域、プロテスタントの地域、国教会の地域など、宗派によって文化や政治が異なるなど、500年の時を経ても宗教改革の重大さはいささかも減ずることはありません。
1517年、宣教師マルティン・ルターが、ヴィッテンベルクの教会に95ヶ条の提題を貼り付け、教会の贖宥状を批判した、というのが、一般的な宗教改革のはじまりとされています。しかし、既存の宗教体制を批判し、「宗教改革」を成し遂げようとした人物はルター以前にも存在しました。それらの人物の行動はルターに匹敵するような成功には至りませんでしたが、ルターに端を発する16世紀の宗教改革に影響を与えました。
宗教改革というと、普通マルティン・ルターの名前と強く結びついています。もちろんルターは歴史を動かしました。しかし、ルターの成功は同時代人の擁護だけではなく、歴史的な積み重ねを待ってはじめて実現したのだ、ということを忘れてはいけません。そこで、ルター以前の宗教改革者たちを取り上げていきたいと思います。
今回ご紹介する人物は、12世紀フランスのピーター・ワルドー、14世紀イギリスのジョン・ウィクリフ、15世紀チェコのヤン・フス、同じく15世紀イタリアのサヴォナローラ、の4人です。
古くから西洋の文化、政治に多大な影響を及ぼす根本的な制度となっていたキリスト教、そのキリスト教にテコを入れる、という事業は歴史に大変革をもたらしたことはいうまでもありません。現在でも、カトリックの地域、プロテスタントの地域、国教会の地域など、宗派によって文化や政治が異なるなど、500年の時を経ても宗教改革の重大さはいささかも減ずることはありません。
1517年、宣教師マルティン・ルターが、ヴィッテンベルクの教会に95ヶ条の提題を貼り付け、教会の贖宥状を批判した、というのが、一般的な宗教改革のはじまりとされています。しかし、既存の宗教体制を批判し、「宗教改革」を成し遂げようとした人物はルター以前にも存在しました。それらの人物の行動はルターに匹敵するような成功には至りませんでしたが、ルターに端を発する16世紀の宗教改革に影響を与えました。
宗教改革というと、普通マルティン・ルターの名前と強く結びついています。もちろんルターは歴史を動かしました。しかし、ルターの成功は同時代人の擁護だけではなく、歴史的な積み重ねを待ってはじめて実現したのだ、ということを忘れてはいけません。そこで、ルター以前の宗教改革者たちを取り上げていきたいと思います。
今回ご紹介する人物は、12世紀フランスのピーター・ワルドー、14世紀イギリスのジョン・ウィクリフ、15世紀チェコのヤン・フス、同じく15世紀イタリアのサヴォナローラ、の4人です。
1. ピーター・ワルドー (1140-c.1205 or c.1218)
ピーター・ワルドーは、フランスはリヨンの、裕福な商人として生活していましたが、ある日財産を投げ打って宗教家となりました。
裕福な商人が突然宗教家となる、という経緯はアッシジのフランチェスコを思わせます。ワルドーは300年後にルターがしたように、聖書を難解なラテン語から、現地の民衆たちの言葉に翻訳することで布教を行い、南フランスからイタリアにかけて信者を集めます。
信者たちは「リヨンの貧者」を自称し、ワルドー派(Waldensians)を形成します。
しかし、教会の支持はいっこうに得られず、ついに1180年代には教会から破門され、異端認定されてしまいます。以後、異端審問(Inquisition)による迫害に遭難する「リヨンの貧者」ことワルドー派の信者でしたが、山中などに離散して生き延びます。
しかし、迫害は収まらず、17世紀にはピエモンテでワルドー一派の虐殺が起こっています。『失楽園』の著者として有名なジョン・ミルトンはこの虐殺を題材とした、On the Late Massacre in Piedmontという詩を残しています。
このように多難を極めたワルドー派の遍歴ですが、2015年にローマ法王がワルドー派への歴史的な迫害を謝罪するなど、現在では1宗派として認められるに至りました。
裕福な商人が突然宗教家となる、という経緯はアッシジのフランチェスコを思わせます。ワルドーは300年後にルターがしたように、聖書を難解なラテン語から、現地の民衆たちの言葉に翻訳することで布教を行い、南フランスからイタリアにかけて信者を集めます。
信者たちは「リヨンの貧者」を自称し、ワルドー派(Waldensians)を形成します。
しかし、教会の支持はいっこうに得られず、ついに1180年代には教会から破門され、異端認定されてしまいます。以後、異端審問(Inquisition)による迫害に遭難する「リヨンの貧者」ことワルドー派の信者でしたが、山中などに離散して生き延びます。
しかし、迫害は収まらず、17世紀にはピエモンテでワルドー一派の虐殺が起こっています。『失楽園』の著者として有名なジョン・ミルトンはこの虐殺を題材とした、On the Late Massacre in Piedmontという詩を残しています。
このように多難を極めたワルドー派の遍歴ですが、2015年にローマ法王がワルドー派への歴史的な迫害を謝罪するなど、現在では1宗派として認められるに至りました。
2. ジョン・ウィクリフ(c.1320-1384)
14世紀イギリスでも宗教改革の兆しが見えます。その主導者となったのがウィクリフです。
ウィクリフは教会のもつ財産や豪奢な生活を批判し、聖書を重視することを訴え、聖書の英訳を行いました。また、教義に関してもローマ教会やオックスフォード大学と衝突し、ウィクリフには終生逆風のなか活動しました。彼の支持者はロラード派とよばれ、のちに封建社会を批判するワット・タイラーの乱につながります。
ウィクリフの死後も弾圧は続き、対抗宗教改革の一環を成す1414年のコンスタンツ公会議では、ウィクリフは改めて異端とされ、ウィクリフの亡骸は掘り起こされ火刑に処されました。
ウィクリフは教会のもつ財産や豪奢な生活を批判し、聖書を重視することを訴え、聖書の英訳を行いました。また、教義に関してもローマ教会やオックスフォード大学と衝突し、ウィクリフには終生逆風のなか活動しました。彼の支持者はロラード派とよばれ、のちに封建社会を批判するワット・タイラーの乱につながります。
ウィクリフの死後も弾圧は続き、対抗宗教改革の一環を成す1414年のコンスタンツ公会議では、ウィクリフは改めて異端とされ、ウィクリフの亡骸は掘り起こされ火刑に処されました。
3. ヤン・フス(c.1369-1415)
イギリスのウィクリフの活動に影響を受け、チェコの地において一人の宗教家が頭角を現しました。
フスは、プラハ大学の神学者として影響力のある人物として当時から有名でした。フスは説教において、贖宥状や聖職売買を批判しウィクリフの考えを広めました。当然、教皇の顰蹙を買い、破門されてしまいます。フスはウィクリフとともに1414年のコンスタンツ公会議において異端とされ、翌年火刑に処されます。
しかし、フスの死後、彼の考えに触発されたボヘミアの民衆たちは一斉に蜂起、1419年にフス戦争が開戦します。
しかし、フス戦争はフス派の敗北に終わり、17世紀の30年戦争によってフス派の影響力はほぼなくなります。しかし、19世紀以降、チェック人のナショナリズムの高まりのなかでフスの評価が進み、20世紀の終わりにはフスへの迫害への謝罪がなされました。
スメタナ作曲の連作交響詩『わが祖国』の終わりの二曲はフスをテーマにしています。
フスは、プラハ大学の神学者として影響力のある人物として当時から有名でした。フスは説教において、贖宥状や聖職売買を批判しウィクリフの考えを広めました。当然、教皇の顰蹙を買い、破門されてしまいます。フスはウィクリフとともに1414年のコンスタンツ公会議において異端とされ、翌年火刑に処されます。
しかし、フスの死後、彼の考えに触発されたボヘミアの民衆たちは一斉に蜂起、1419年にフス戦争が開戦します。
しかし、フス戦争はフス派の敗北に終わり、17世紀の30年戦争によってフス派の影響力はほぼなくなります。しかし、19世紀以降、チェック人のナショナリズムの高まりのなかでフスの評価が進み、20世紀の終わりにはフスへの迫害への謝罪がなされました。
スメタナ作曲の連作交響詩『わが祖国』の終わりの二曲はフスをテーマにしています。
4. ジロラモ・サヴォナローラ(1452-1498)
サヴォナローラはドミニコ会の修道士として、ピコ=デラ=ミランデラの紹介を通じて、メディチ家が治めていたフィレンツェで活動しました。
イタリア戦争によってフランス軍がメディチ家を追放すると、サヴォナローラは事実上のフィレンツェの支配者となり、神権政治を行いました。
彼の教義は、奢侈を諌め、清貧を重んじる、というものでした。サヴォナローラはメディチ家の批判やフランス侵攻を予見したことで民衆の支持を得ますが、それも長くは続かず、やがて民衆は彼を離れ、教会からは破門されてしまいました。そして1498年、火刑に処されました。
ルターはのちにサヴォナローラを高く評価しているように、サヴォナローラの活動はのちに、ルターに端を発する宗教改革へとつながっていくのです。
イタリア戦争によってフランス軍がメディチ家を追放すると、サヴォナローラは事実上のフィレンツェの支配者となり、神権政治を行いました。
彼の教義は、奢侈を諌め、清貧を重んじる、というものでした。サヴォナローラはメディチ家の批判やフランス侵攻を予見したことで民衆の支持を得ますが、それも長くは続かず、やがて民衆は彼を離れ、教会からは破門されてしまいました。そして1498年、火刑に処されました。
ルターはのちにサヴォナローラを高く評価しているように、サヴォナローラの活動はのちに、ルターに端を発する宗教改革へとつながっていくのです。





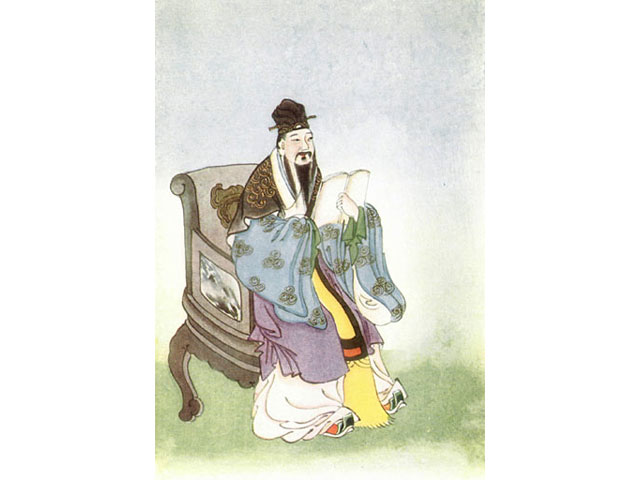
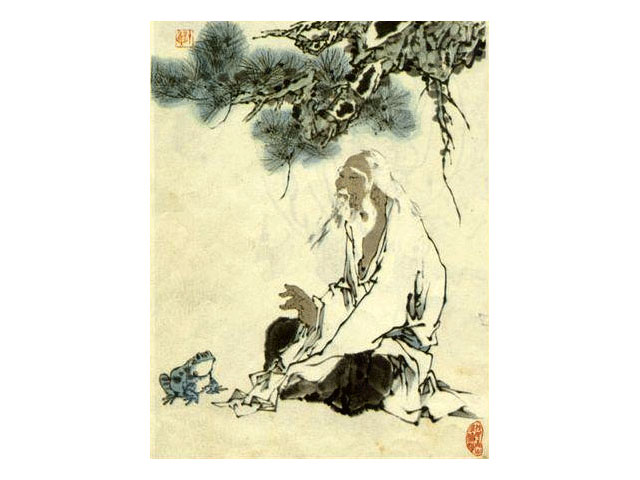



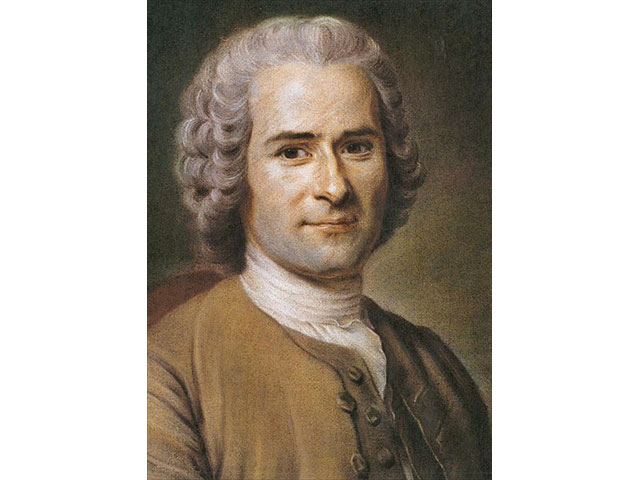













![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

