「炉辺談話」がF.ルーズベルトをアメリカ史上最長の大統領にした?
関連キーワード

1929年10月24日、ニューヨーク・ウォール街。自動車、ジャズ、映画にラジオ、華やかな1920年代アメリカの終結を物語るかのように、株価が突如暴落、そして29日の大暴落が追い打ちをかけます。この「暗黒の木曜日」と「悲劇の火曜日」とよばれる二度の市場危機は、ニューヨークのみならず、アメリカ、ひいては世界をも揺るがした大事件でした。当時の大統領ハーバード・フーヴァーは、ドイツへの賠償を支払いの猶予を与えるフーヴァー・モラトリアムなどの経済政策を打ち出しましたが、恐慌は悪化の一途をたどり、アメリカは家や職を失った人々で溢れかえりました。当時、路上生活者が防寒のために身にまとっていた新聞は、「フーバー毛布」とよばれていたといいます。
恐慌の嵐吹きやまぬ1933年、窮地のアメリカを立ち直すべく立ち上がったのが、フランクリン・デラノ・ルーズベルト(1882-1945)でした。ルーズベルトが打ち出した積極的な経済政策は「ニューディール政策」とよばれ、政策の賛否はありながらも、結果として一定の成果を挙げてアメリカを危機から救ったことはよく知られています。
ルーズベルトはアメリカ国民の支持を集め、結局、第二次世界大戦終結の直前に亡くなるまで、12年にわたって大統領を務めました。大統領に4選された人物はF.ルーズベルトをおいてアメリカ史に類を見ません。彼の人気の秘密は、積極的な政策や、第二次世界大戦であったことは間違いありません。しかし、もう一つ、F.ルーズベルトの高い人気を語る上で忘れてはならないのが、ラジオを通じた『炉辺談話』(Fireside Chat)です。1920年代に生まれたラジオを通して、米国大統領はなにを語ったのでしょうか。そして、急激に変わりゆく波乱の時代に、彼の肉声は国民の心にどう響いたのでしょうか。
恐慌の嵐吹きやまぬ1933年、窮地のアメリカを立ち直すべく立ち上がったのが、フランクリン・デラノ・ルーズベルト(1882-1945)でした。ルーズベルトが打ち出した積極的な経済政策は「ニューディール政策」とよばれ、政策の賛否はありながらも、結果として一定の成果を挙げてアメリカを危機から救ったことはよく知られています。
ルーズベルトはアメリカ国民の支持を集め、結局、第二次世界大戦終結の直前に亡くなるまで、12年にわたって大統領を務めました。大統領に4選された人物はF.ルーズベルトをおいてアメリカ史に類を見ません。彼の人気の秘密は、積極的な政策や、第二次世界大戦であったことは間違いありません。しかし、もう一つ、F.ルーズベルトの高い人気を語る上で忘れてはならないのが、ラジオを通じた『炉辺談話』(Fireside Chat)です。1920年代に生まれたラジオを通して、米国大統領はなにを語ったのでしょうか。そして、急激に変わりゆく波乱の時代に、彼の肉声は国民の心にどう響いたのでしょうか。
1. 『炉辺談話」のはじまり
1920年代、ラジオはアメリカ国民にとって身近なものとなりました。ルーズベルトは早くからこの新しいメディアに目をつけました。まだニューヨーク州知事(Governor of New York)だった1929年、ルーズベルトは、審議中の法案の重要性を国民に直接訴える手段として、すでにラジオ放送を活用しています。ルーズベルトにとって、改変や誤謬の危険がある新聞メディアとは違い、肉声がそのまま伝わるラジオは大きな魅力でした。
1933年3月12日、大統領となってまもなくのこと、ルーズベルトはさっそくラジオを通じて国民に語りかけます。それは「銀行危機について」(On the Banking Crisis)と題された13分の談話でした。当時はまだ恐慌が収まらず、国民の間には金融不安が広がり、銀行への不信からの銀行預金の減少が懸念されていました。また、ラジオ放送に先立つ3月6日から4日間は「バンクホリデー」に指定され、全ての銀行が閉鎖されました。そうした状況にあって、ルーズベルトは「緊急銀行法」(Emergency Banking Act)による銀行の安定を目指していました。3月9日に議会を通ったこの法律は、金融政策に関する大統領権限の拡大、復興金融公社(RFC)による資金投入などを内容とし、銀行の閉鎖も延長されました。この最中にルーズベルトはラジオを通じて国民に語りかけたのでした。
ルーズベルト大統領の記念すべき第一声は “My friends” でした。続いて銀行の仕組み、アメリカ経済の現状、バンクホリデー、緊急銀行法の内容と意図、銀行再開の見込みについて話しが移ります。翌13日から始まる銀行再開に関しては、国民の不安を払拭し預金を促すために、「お金を置くなら、マットレスの下よりも再開した銀行の方が安全だと請け合いますよ」と、砕けた表現も使われています。最後に、国民に協力を訴えます。アメリカ経済再建はなによりもまず国民の信頼と勇気にかかっていること、噂や憶測に乗せられないこと、不安を一団となって払拭すること、政策の成否は国民の支援次第であることを述べ、「これは私の問題以上にあなたがたの問題です。一致団結すればうまくいかないはずはありません。」と声をかけ、談話は終了します。
演説の効果はてきめんで、翌日に再開した銀行の前には預金のために列をなす人々の姿がありました。「米国大統領のスピーチ」は国民の心をつかんだのです。
1933年3月12日、大統領となってまもなくのこと、ルーズベルトはさっそくラジオを通じて国民に語りかけます。それは「銀行危機について」(On the Banking Crisis)と題された13分の談話でした。当時はまだ恐慌が収まらず、国民の間には金融不安が広がり、銀行への不信からの銀行預金の減少が懸念されていました。また、ラジオ放送に先立つ3月6日から4日間は「バンクホリデー」に指定され、全ての銀行が閉鎖されました。そうした状況にあって、ルーズベルトは「緊急銀行法」(Emergency Banking Act)による銀行の安定を目指していました。3月9日に議会を通ったこの法律は、金融政策に関する大統領権限の拡大、復興金融公社(RFC)による資金投入などを内容とし、銀行の閉鎖も延長されました。この最中にルーズベルトはラジオを通じて国民に語りかけたのでした。
ルーズベルト大統領の記念すべき第一声は “My friends” でした。続いて銀行の仕組み、アメリカ経済の現状、バンクホリデー、緊急銀行法の内容と意図、銀行再開の見込みについて話しが移ります。翌13日から始まる銀行再開に関しては、国民の不安を払拭し預金を促すために、「お金を置くなら、マットレスの下よりも再開した銀行の方が安全だと請け合いますよ」と、砕けた表現も使われています。最後に、国民に協力を訴えます。アメリカ経済再建はなによりもまず国民の信頼と勇気にかかっていること、噂や憶測に乗せられないこと、不安を一団となって払拭すること、政策の成否は国民の支援次第であることを述べ、「これは私の問題以上にあなたがたの問題です。一致団結すればうまくいかないはずはありません。」と声をかけ、談話は終了します。
演説の効果はてきめんで、翌日に再開した銀行の前には預金のために列をなす人々の姿がありました。「米国大統領のスピーチ」は国民の心をつかんだのです。
2. 戦争と『炉辺談話』
炉端に座った聞き手に語りかけるかのような大統領のラジオ談話は、いつしか“Fireside Chat”の名で親しまれるようになりました。1933年3月12日の第1回放送から2ヶ月、5月7日にはニューディール政策をテーマとした第2回目の放送を行い、その後も、政治と経済を中心としたテーマで30分前後の談話が不定期で放送されました。しかし、1939年9月1日を境に、ラジオ放送の内容は大きく変わります。ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が開戦したのです。同年9月3日に放送された『炉辺談話』第14回のテーマは「ヨーロッパ戦争について」(On the European War)。ルーズベルトは、この放送においてアメリカは戦争に反対すること、アメリカに戦火が及ばないように全力を尽くすことを国民に伝えます。
1940年9月に日独伊三国同盟が締結されると、ルーズベルトの戦争への態度も変化します。同年12月29日に国内および世界に向けて放送された「民主主義の兵器廠について」(On the “Arsenal of Democracy”)では、第1回放送が回想され、8年の時を経てアメリカが新たな危機に面していること、とりわけドイツがアメリカにとってもはや看過できない脅威となっていることが強調されます。そして、アメリカはこの未曾有の危機において、イギリスを中心とする連合国に対して武器を提供する「民主主義の兵器廠」とならなければならない、と訴えます。あくまでこの政策の意図が戦争をすることではなく、アメリカとその国民を戦火から守ることに向けられていることをルーズベルトは語りますが、1年前の放送と比べるとアメリカの戦争への態度が積極的になっていることは明らかです。残された録音には、忍び寄る戦火に対する緊張感に満ちたルーズベルトの肉声を聞くことができます。かつての「談話」は「演説」となったのです。
1941年12月7日(ハワイ時間)、日本からの真珠湾攻撃を受けて、12月9日、ルーズベルトは「日本への宣戦布告について」(On the Declaration of War with Japan)と題された『炉辺談話』を放送、戦争のための国民の一致団結を求めます。冒頭、“without warning”(警告なしに)という言葉を繰り返し、宣戦布告をしない日本とドイツの類似を強調するなど、全体として、日本とドイツの結びつき、日独伊と対照をなすアメリカを印象づける放送となっています。アメリカの参戦は侵略のためでも報復のためではなく、世界の安全保障のためだ、という姿勢もそれまで通り述べられています。
戦時にあって、『炉辺談話』はその性格を変えましたが、「国民にわかりやすく」という原点は失われていませんでした。ルーズベルトは1942年2月23日の「戦争の経過について」(On the Progress of the War)の放送前、国民に対して世界地図を用意するように求めます。戦場となっている耳慣れない場所を、国民が自らの目で確認することが大切だとルーズベルトは考えたからです。
「これは私の問題以上にあなたがたの問題です」という第1回放送の精神は戦時にあっても生き続け、ラジオから流れるルーズベルト大統領の声は、国民の不安や憶測を払底し、信頼と勇気とで結びつけました。1944年6月12日の第30回の放送が『炉辺談話』最後の放送となりました。
1940年9月に日独伊三国同盟が締結されると、ルーズベルトの戦争への態度も変化します。同年12月29日に国内および世界に向けて放送された「民主主義の兵器廠について」(On the “Arsenal of Democracy”)では、第1回放送が回想され、8年の時を経てアメリカが新たな危機に面していること、とりわけドイツがアメリカにとってもはや看過できない脅威となっていることが強調されます。そして、アメリカはこの未曾有の危機において、イギリスを中心とする連合国に対して武器を提供する「民主主義の兵器廠」とならなければならない、と訴えます。あくまでこの政策の意図が戦争をすることではなく、アメリカとその国民を戦火から守ることに向けられていることをルーズベルトは語りますが、1年前の放送と比べるとアメリカの戦争への態度が積極的になっていることは明らかです。残された録音には、忍び寄る戦火に対する緊張感に満ちたルーズベルトの肉声を聞くことができます。かつての「談話」は「演説」となったのです。
1941年12月7日(ハワイ時間)、日本からの真珠湾攻撃を受けて、12月9日、ルーズベルトは「日本への宣戦布告について」(On the Declaration of War with Japan)と題された『炉辺談話』を放送、戦争のための国民の一致団結を求めます。冒頭、“without warning”(警告なしに)という言葉を繰り返し、宣戦布告をしない日本とドイツの類似を強調するなど、全体として、日本とドイツの結びつき、日独伊と対照をなすアメリカを印象づける放送となっています。アメリカの参戦は侵略のためでも報復のためではなく、世界の安全保障のためだ、という姿勢もそれまで通り述べられています。
戦時にあって、『炉辺談話』はその性格を変えましたが、「国民にわかりやすく」という原点は失われていませんでした。ルーズベルトは1942年2月23日の「戦争の経過について」(On the Progress of the War)の放送前、国民に対して世界地図を用意するように求めます。戦場となっている耳慣れない場所を、国民が自らの目で確認することが大切だとルーズベルトは考えたからです。
「これは私の問題以上にあなたがたの問題です」という第1回放送の精神は戦時にあっても生き続け、ラジオから流れるルーズベルト大統領の声は、国民の不安や憶測を払底し、信頼と勇気とで結びつけました。1944年6月12日の第30回の放送が『炉辺談話』最後の放送となりました。
3. 『炉辺談話』その後
ルーズベルトは1945年4月に亡くなり、アメリカの戦勝は彼の声に勇気づけられた国民によって見届けられました。
ルーズベルトのラジオによる試みは、彼の死後も受け継がれ、レーガン大統領時代の1982年には毎週日曜日のラジオ放送 “Weekly Radio Address” がスタートしました。また、ラジオに限らず、テレビ、インターネットも活用され、オバマ大統領時代にはYouTubeを通じた発信もなされました。
世界恐慌と第二次世界大戦、二つの危機に面したアメリカにとって希望の声となった『炉辺談話』。未曾有の危機にあってアメリカはいかに行動したか、そのことを生々しく示すドキュメントとして、F.ルーズベルトの声は新たな意味をもって現代の人々に響くことでしょう。
世界恐慌と第二次世界大戦、二つの危機に面したアメリカにとって希望の声となった『炉辺談話』。未曾有の危機にあってアメリカはいかに行動したか、そのことを生々しく示すドキュメントとして、F.ルーズベルトの声は新たな意味をもって現代の人々に響くことでしょう。





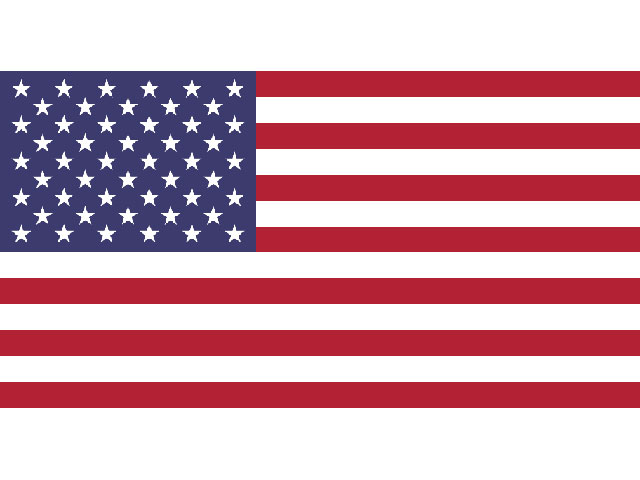
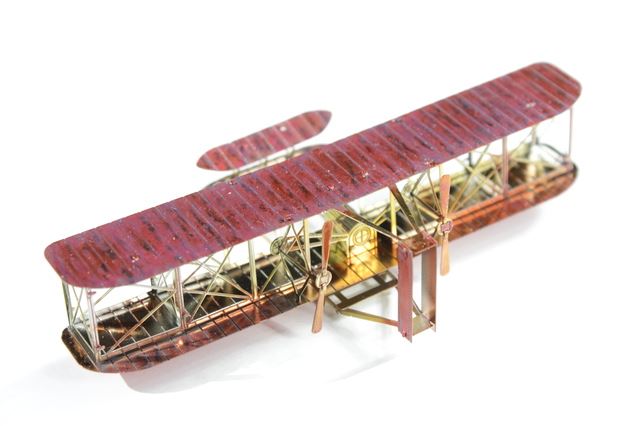
















![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

