戦国大名たちの拠点。舘と初期の山城
関連キーワード

戦国大名たちの拠点。舘と初期の山城
15~16世紀に幕府の支配力が衰えると、戦国時代の居城は政治拠点の役割がいっそう重要になりました。
甲斐武田氏の躑躅が崎の館はその例です。甲府市北辺にある舘の跡は、西・北・東の三方を山に囲まれ、南に甲府盆地が開ける要衝の地にあります。
16世紀初め、武田信虎は居館を石和からここに移し、領国経営の拠点としました。信虎は東郭と中郭の部分に舘をかまえ、周囲に土塁と水堀をめぐらせました。いざという場合に備えて舘の北東2km、標高770mの丸山に要害城を築きました。
続く信玄の時代から江戸時代のはじめまでに躑躅が崎の舘には西郭、隠居郭、味噌郭などが加えられ、その外側に一族や重臣たちの屋敷や代官の執務所などが設けられました。躑躅が崎館の南には家臣の屋敷があり、そこから離れて市場がある戦国期の二元的な城下町を構成していました。
16世紀の末、信玄の子、勝頼は居城を韮崎市の新府城に移しました。織田・徳川連合軍に追い詰められ、最後の砦としてかまえた山城です。新府城の西側は七里岩とよばれる断崖で、あとの三方は堀をめぐらし土塁を築いています。山上の本丸は東西90m、南北120mで、西に二の丸をつくり、南の大手へ向かって東西の三の丸をかまえています。北の郭には東出構・西出構が堀の中に突出し、鉄砲で防御するしくみでした。
戦国大名武田氏は政庁としての居館と戦時の軍事防塞を使い分けていたのです。
府中とか国府という地名は各地にありますが、まず古代に国府が置かれたところと考えられます。さらに駿河の府中は駿府、甲斐は甲府、長門は長府、周防は防府ということになり、水戸は近世の城下というので水府ともいいました。豊後の国府は現大分市ですが、鎌倉時代までは府中、そのあとは府内と称しています。
甲斐武田氏の躑躅が崎の館はその例です。甲府市北辺にある舘の跡は、西・北・東の三方を山に囲まれ、南に甲府盆地が開ける要衝の地にあります。
16世紀初め、武田信虎は居館を石和からここに移し、領国経営の拠点としました。信虎は東郭と中郭の部分に舘をかまえ、周囲に土塁と水堀をめぐらせました。いざという場合に備えて舘の北東2km、標高770mの丸山に要害城を築きました。
続く信玄の時代から江戸時代のはじめまでに躑躅が崎の舘には西郭、隠居郭、味噌郭などが加えられ、その外側に一族や重臣たちの屋敷や代官の執務所などが設けられました。躑躅が崎館の南には家臣の屋敷があり、そこから離れて市場がある戦国期の二元的な城下町を構成していました。
16世紀の末、信玄の子、勝頼は居城を韮崎市の新府城に移しました。織田・徳川連合軍に追い詰められ、最後の砦としてかまえた山城です。新府城の西側は七里岩とよばれる断崖で、あとの三方は堀をめぐらし土塁を築いています。山上の本丸は東西90m、南北120mで、西に二の丸をつくり、南の大手へ向かって東西の三の丸をかまえています。北の郭には東出構・西出構が堀の中に突出し、鉄砲で防御するしくみでした。
戦国大名武田氏は政庁としての居館と戦時の軍事防塞を使い分けていたのです。
府中とか国府という地名は各地にありますが、まず古代に国府が置かれたところと考えられます。さらに駿河の府中は駿府、甲斐は甲府、長門は長府、周防は防府ということになり、水戸は近世の城下というので水府ともいいました。豊後の国府は現大分市ですが、鎌倉時代までは府中、そのあとは府内と称しています。
2 中世から近世へ
動乱の中世から泰平の近世へ、時代は大きく変換します。ここで中世を通じて生き抜いた根城南部氏の根拠地を見てみます。
南部氏は甲斐源氏の流れで、建武政権下に現八戸市に根城を作ったといいます。根城南部氏は南北朝時代に南朝側についたので恵まれず、北朝側についた一族の三戸南部が有力となりました。豊臣秀吉は三戸南部氏を配下に入れ、根城南部氏はその家臣の地位におちます。そして1592年には根城も破壊されました。
江戸時代に三戸南部氏は盛岡城をかまえ、その流れから八戸南部氏が分かれます。こうして現八戸市には八戸城跡と根城跡との二つの城跡が存在することになります。
根城は標高20mの台地上に築かれた城館です。1978年以降の発掘調査で、ここには八つの郭があったことがわかりました。面積は31万㎡もありますが、中世から近世にかけて広げていったものと考えられています。
本丸地域では豊臣時代の政庁の跡が発掘されました。深さ約9mの薬研堀を渡ると、柵で囲まれた郭内に入ります。城主の館、馬屋、執務所、工作所などの跡が見られ、さまざまな遺跡も出土しました。
根城の北と東には侍屋敷・町屋敷も開かれました。それが八戸城への権力移行によって城下町も移っていくことになります。
ここでいう根城などの城の呼び名は位置・形状・機能などによって変わります。たとえば、根城とは一軍の本拠の城で本城ともいいます。領内要所におかれたのは支城です。
出城とは防御力増強をめざし、城の周囲へ張り出して築きます。これに対して攻撃用につくる臨時の城を付城といいます。小田原攻めの際の石垣山城などはこれにあたります。
詰ノ城とは最後に拠点になる城です。大阪の赤坂城は根城で、千早城は詰ノ城です。
南部氏は甲斐源氏の流れで、建武政権下に現八戸市に根城を作ったといいます。根城南部氏は南北朝時代に南朝側についたので恵まれず、北朝側についた一族の三戸南部が有力となりました。豊臣秀吉は三戸南部氏を配下に入れ、根城南部氏はその家臣の地位におちます。そして1592年には根城も破壊されました。
江戸時代に三戸南部氏は盛岡城をかまえ、その流れから八戸南部氏が分かれます。こうして現八戸市には八戸城跡と根城跡との二つの城跡が存在することになります。
根城は標高20mの台地上に築かれた城館です。1978年以降の発掘調査で、ここには八つの郭があったことがわかりました。面積は31万㎡もありますが、中世から近世にかけて広げていったものと考えられています。
本丸地域では豊臣時代の政庁の跡が発掘されました。深さ約9mの薬研堀を渡ると、柵で囲まれた郭内に入ります。城主の館、馬屋、執務所、工作所などの跡が見られ、さまざまな遺跡も出土しました。
根城の北と東には侍屋敷・町屋敷も開かれました。それが八戸城への権力移行によって城下町も移っていくことになります。
ここでいう根城などの城の呼び名は位置・形状・機能などによって変わります。たとえば、根城とは一軍の本拠の城で本城ともいいます。領内要所におかれたのは支城です。
出城とは防御力増強をめざし、城の周囲へ張り出して築きます。これに対して攻撃用につくる臨時の城を付城といいます。小田原攻めの際の石垣山城などはこれにあたります。
詰ノ城とは最後に拠点になる城です。大阪の赤坂城は根城で、千早城は詰ノ城です。
3 本格的な山城
南北朝期の争乱は本格的な山城を出現させました。南朝と北朝に分かれて各地で戦ったので、それに応じて山城を深く高い山に築きました。麓から本丸までの高さの差が400mを越えることもありました。高低差の大きな山に築城したことは南北朝期の山城の大きな特徴です。
山が高く地形が厳しかったので、南北朝の山城は戦国時代の山城と比べて人工的な工事は少ない量でした。また、山城の防御は堀ではなく人工的に削りだした急斜面・切岸によることが多くありました。切岸を主にした防御は平安末・鎌倉期の丘の舘城に見られ、そうした伝統を受け継いだものでした。こういった南北朝期の山城は非常に高い山の上に、戦いに備えて築いていたので日常的に住むことはできませんでした。このため戦いが終われば壊してしまう臨時の施設でもありました。
楠木正成が築いた大阪府の千早城・赤坂城は南北朝期の山城として特に有名です。しかし赤坂城は後の時代にも城として利用されたので、今見ることのできる堀や土塁は戦国時代のものが加わっています。
このように各地に南北朝時代の山城とされるものは多くありますが、地表面から見える遺構がそのまま南北朝期にさかのぼるものではないものが多くあります。
山が高く地形が厳しかったので、南北朝の山城は戦国時代の山城と比べて人工的な工事は少ない量でした。また、山城の防御は堀ではなく人工的に削りだした急斜面・切岸によることが多くありました。切岸を主にした防御は平安末・鎌倉期の丘の舘城に見られ、そうした伝統を受け継いだものでした。こういった南北朝期の山城は非常に高い山の上に、戦いに備えて築いていたので日常的に住むことはできませんでした。このため戦いが終われば壊してしまう臨時の施設でもありました。
楠木正成が築いた大阪府の千早城・赤坂城は南北朝期の山城として特に有名です。しかし赤坂城は後の時代にも城として利用されたので、今見ることのできる堀や土塁は戦国時代のものが加わっています。
このように各地に南北朝時代の山城とされるものは多くありますが、地表面から見える遺構がそのまま南北朝期にさかのぼるものではないものが多くあります。
4 室町・戦国時代の山城
室町時代になると、南北朝期とは異なり、日常の政治拠点としても使うため高低差が少ない山に築城することが主流となっていきます。室町時代以降には山城のほかに丘や平地の館城を土豪層が築きました。また守護大名の国の拠点は一辺が100m~200mもある舘型の城でした。その周囲には守護代の大型の舘城や寺院、武家屋敷がありました。こうした城と守護大名城下町の整備は応仁の乱の後に大きく進みました。
たとえば、福井市にある朝倉氏の舘の背後の山に築かれた山城は郭下の斜面に堀と土塁を交互に並べて築いた畝状空堀群を140本も備えていた戦国期に特徴的な防御施設でした。
天文期(1532~55)以降になると、国の中心の城は一斉に山城に変わっていきます。戦国期拠点城郭の成立であります。平地に拠点城郭が残った所でも、急激に舘から平城へ展開していきました。
戦国期の城郭はもともと並立的な郭配置でしたが、大名権力の進展とともに次第に本丸を核とした階層的で求心的な構造になりました。相対的に大名への権力集中が進まなかった東北と南九州には織田・豊臣時代まで並立的な城が残りました。これに対して関東から畿内地域はいち早く求心的な構造に進化し、そのなかの織田信長や豊臣秀吉の城が織豊系城郭として江戸時代の城の直接の原形となっていきました。
たとえば、福井市にある朝倉氏の舘の背後の山に築かれた山城は郭下の斜面に堀と土塁を交互に並べて築いた畝状空堀群を140本も備えていた戦国期に特徴的な防御施設でした。
天文期(1532~55)以降になると、国の中心の城は一斉に山城に変わっていきます。戦国期拠点城郭の成立であります。平地に拠点城郭が残った所でも、急激に舘から平城へ展開していきました。
戦国期の城郭はもともと並立的な郭配置でしたが、大名権力の進展とともに次第に本丸を核とした階層的で求心的な構造になりました。相対的に大名への権力集中が進まなかった東北と南九州には織田・豊臣時代まで並立的な城が残りました。これに対して関東から畿内地域はいち早く求心的な構造に進化し、そのなかの織田信長や豊臣秀吉の城が織豊系城郭として江戸時代の城の直接の原形となっていきました。















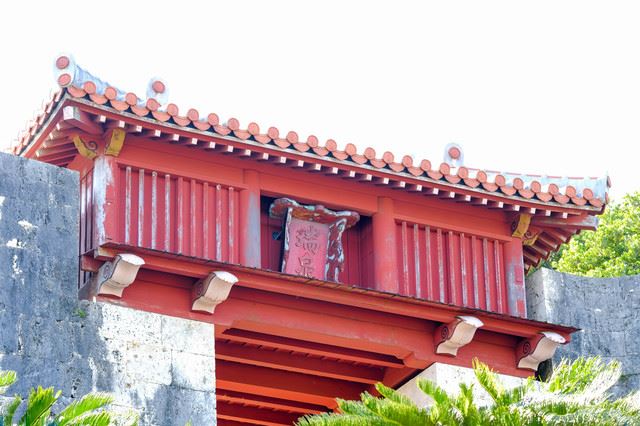






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

