郡上八幡城の歴史が語る妖艶な姿をご紹介!
関連キーワード

1 郡上八幡の歴史
長良川を北へ北へと美濃山中に分け入ったところに、江戸時代からの時間の流れを止めたかのようなたたずまいの郡上八幡の町があります。長良川はそこで支流の吉田川と分かれます。その町外れの八幡山山頂に三層の天守閣をそびやかしているのが郡上八幡城です。
鎌倉時代の承久二年(1220年)に郡上山田庄の地頭となった千葉氏の一族東中務入道胤行が、畔千葉城を築いたのが郡上の城の起源とされます。
南北朝時代になって東氏村が篠脇城を築いて移り、東氏累代の居城としました。胤行から数えて九代目の常縁は、武名よりも文名の高い異色の武将です。歌道に秀で、文明三年(1471年)に常縁を慕って郡上にやってきた連歌師宗祇に古今伝授をほどこしているほどです。古今伝授とは、「古今和歌集」の解釈の秘伝のことです。
すべての秘伝を授け終えた後、京に帰る宗祇を見送って、常縁は八幡山の西を流れる小駄良川のほとりまで、ともに歩きました。そして別れの歌を贈っています。
もみじ葉の 流るる竜田 しら雲の 花のみ芳野 みもひ忘るな
このときの常縁と宗祇の別れの古跡が、小駄良川に架かる橋のもとにある宗祇水と呼ばれる泉です。
常縁から二代後の常慶は八幡山と吉田川をへだてて向かいあう東殿山に新城を築いて移りました。ところが、永禄二年(1559年)常慶の子である常堯が支族の遠藤胤縁を殺すという事件が起こりました。常堯が胤縁の娘に懸想して断られた腹いせに胤縁を鉄砲で射殺したのです。怒った胤縁の弟である盛数は、兵を集めて東殿山城を攻撃し、激戦の末に落城させました。ここに東氏は二十三代340年の家譜に終止符をうちました。
代わって東殿山城主になった遠藤盛数が、新たに八幡山に築城したのが八幡山城です。数盛の子である慶隆は、天正十六年(1588年)に豊臣秀吉に城を取り上げられ、稲葉貞道が入城します。しかし貞道は慶長五年(1600年)の関が原の合戦で西軍に属したため、豊後に移され、東軍に属していた遠藤慶隆が旧領の郡上八幡に返り咲きました。
その後、城主は井上氏から金森氏に代わって、宝暦四年(1754年)金森頼錦のとき、世に宝暦一揆あるいは金森騒動と呼ばれる大規模な農民一揆が起こり、そのため頼錦は領地を没収され、南部に配流の身となりました。農民一揆が、このように藩主を没落に追い込んだことは珍しいことです。金森氏の跡へ青山幸道が四万八千石で入封してからは、子孫相次いで明治維新を迎えています。
鎌倉時代の承久二年(1220年)に郡上山田庄の地頭となった千葉氏の一族東中務入道胤行が、畔千葉城を築いたのが郡上の城の起源とされます。
南北朝時代になって東氏村が篠脇城を築いて移り、東氏累代の居城としました。胤行から数えて九代目の常縁は、武名よりも文名の高い異色の武将です。歌道に秀で、文明三年(1471年)に常縁を慕って郡上にやってきた連歌師宗祇に古今伝授をほどこしているほどです。古今伝授とは、「古今和歌集」の解釈の秘伝のことです。
すべての秘伝を授け終えた後、京に帰る宗祇を見送って、常縁は八幡山の西を流れる小駄良川のほとりまで、ともに歩きました。そして別れの歌を贈っています。
もみじ葉の 流るる竜田 しら雲の 花のみ芳野 みもひ忘るな
このときの常縁と宗祇の別れの古跡が、小駄良川に架かる橋のもとにある宗祇水と呼ばれる泉です。
常縁から二代後の常慶は八幡山と吉田川をへだてて向かいあう東殿山に新城を築いて移りました。ところが、永禄二年(1559年)常慶の子である常堯が支族の遠藤胤縁を殺すという事件が起こりました。常堯が胤縁の娘に懸想して断られた腹いせに胤縁を鉄砲で射殺したのです。怒った胤縁の弟である盛数は、兵を集めて東殿山城を攻撃し、激戦の末に落城させました。ここに東氏は二十三代340年の家譜に終止符をうちました。
代わって東殿山城主になった遠藤盛数が、新たに八幡山に築城したのが八幡山城です。数盛の子である慶隆は、天正十六年(1588年)に豊臣秀吉に城を取り上げられ、稲葉貞道が入城します。しかし貞道は慶長五年(1600年)の関が原の合戦で西軍に属したため、豊後に移され、東軍に属していた遠藤慶隆が旧領の郡上八幡に返り咲きました。
その後、城主は井上氏から金森氏に代わって、宝暦四年(1754年)金森頼錦のとき、世に宝暦一揆あるいは金森騒動と呼ばれる大規模な農民一揆が起こり、そのため頼錦は領地を没収され、南部に配流の身となりました。農民一揆が、このように藩主を没落に追い込んだことは珍しいことです。金森氏の跡へ青山幸道が四万八千石で入封してからは、子孫相次いで明治維新を迎えています。
2 郡上八幡城の天守
明治初年に城の建物は破却されましたが、昭和八年(1933年)に天守閣が再建されました。しかし、八幡城にはもともと天守閣は築かれませんでした。江戸時代の絵図を見ても、天守台しか記載されていません。したがって、この天守閣は模擬ということになりますが、昔からそこにあったように周囲の風景にぴたりとはまり込んでいます。
この天守は近くの大垣城の天守を模倣して造られたといいます。大垣城は美濃平野の中央に築かれた平城で、二段に築かれた本丸と二の丸が連郭で配され、それを取り囲むように三の丸、外郭が輪郭で巡る構造となります。関が原の合戦の後、石川康通が入城して三代にわたって普請を完成させました。その後、戸田氏が封じられて明治にいたるまで戸田氏の居城となりました。幅の広い水掘を三、四重に巡らせた姿はまさに水の城でした。そして本丸上段の北西隅には四重四階の層塔型天守が構えられていました。天守建築で四重構造は大変珍しい。国宝に指定されていましたが、太平洋戦争中に惜しくも空襲で焼失してしまいました。現在のものは昭和三十四年に復元されたものですが、四重天守の様子を知ることができる例です。
郡上の城下町は吉田川沿いに細長く東西にのびています。紅殻格子の目立つ民家や商家の風情は、いかにも小京都と呼ばれるのにふさわしい。このしっとりとした城下町が一年のうちもっとも賑わうのは、七月中旬にかけて町のあちこちでおこなわれる郡上踊りです。なかでもハイライトは八月十三日から十六日までの盂蘭盆会の四日間で、夕方から朝まで徹夜踊りがおこなわれ大変な人出です。
この天守は近くの大垣城の天守を模倣して造られたといいます。大垣城は美濃平野の中央に築かれた平城で、二段に築かれた本丸と二の丸が連郭で配され、それを取り囲むように三の丸、外郭が輪郭で巡る構造となります。関が原の合戦の後、石川康通が入城して三代にわたって普請を完成させました。その後、戸田氏が封じられて明治にいたるまで戸田氏の居城となりました。幅の広い水掘を三、四重に巡らせた姿はまさに水の城でした。そして本丸上段の北西隅には四重四階の層塔型天守が構えられていました。天守建築で四重構造は大変珍しい。国宝に指定されていましたが、太平洋戦争中に惜しくも空襲で焼失してしまいました。現在のものは昭和三十四年に復元されたものですが、四重天守の様子を知ることができる例です。
郡上の城下町は吉田川沿いに細長く東西にのびています。紅殻格子の目立つ民家や商家の風情は、いかにも小京都と呼ばれるのにふさわしい。このしっとりとした城下町が一年のうちもっとも賑わうのは、七月中旬にかけて町のあちこちでおこなわれる郡上踊りです。なかでもハイライトは八月十三日から十六日までの盂蘭盆会の四日間で、夕方から朝まで徹夜踊りがおこなわれ大変な人出です。
この郡上踊りは関が原の後、郡上八幡城主に復帰した遠藤慶隆が喜びのあまり領民に奨励したのが起こりとされていますが、起源はさらにさかのぼって平安時代の風流踊りにあるといいます。周囲を山に囲まれた土地の文化は、外に流れ出さず、いつまでも伝統となって行きつづけるものだということを、この郡上踊りは物語っているようです。
そしてこの城のすべては美観です。「悲しくなるほど美しい」歴史小説の大家である司馬遼太郎がこう称しました。この城は朝霧の雲のなかに浮かぶ「天空の城」としても知られていますが、それ以上に美しいのは秋の紅葉です。白亜の天守が真っ赤な紅葉の炎に燃え染められる情景は「天守炎上」と呼ばれます。夜にはライトアップされ、城下町からも妖艶な赤い炎が確認できます。司馬遼太郎が称賛するだけに一見の価値があります。
そしてこの城のすべては美観です。「悲しくなるほど美しい」歴史小説の大家である司馬遼太郎がこう称しました。この城は朝霧の雲のなかに浮かぶ「天空の城」としても知られていますが、それ以上に美しいのは秋の紅葉です。白亜の天守が真っ赤な紅葉の炎に燃え染められる情景は「天守炎上」と呼ばれます。夜にはライトアップされ、城下町からも妖艶な赤い炎が確認できます。司馬遼太郎が称賛するだけに一見の価値があります。
1 郡上八幡城の成り立ち

鵜飼いで有名な長良川の岐阜から60kmほど上流に八幡という町があります。この付近は郡上という郡名なので郡上八幡といわれています。長良川はここで二つに分かれて名前も変わってしまいます、北東のほうより流れてくる川を吉田川、北西より流れてくる川を上ノ保川といいます。
郡上郡は文徳天皇のとき、武儀郡から分離されて独立したものです。この地に遠藤盛数が犬鳴城を攻めるときに一時陣地を構えたのですが、本家の東常慶を滅亡させると、ここに本拠を移そうと、山上にあった八幡宮を南方山麓に移し、山上に新城を築城したのが郡上八幡城の始まりです。
遠藤盛数は郡上八幡城にいること三年で没し、そのあとを慶隆が継ぎましたが、幼年であったために母の再婚先である永井通利が後見しました。永禄七年、斎藤龍興が、竹中半兵衛のために一時、稲葉山城を追われて慶隆もその渦中に巻き込まれたとき、木越城主であった従兄弟が八幡城を奪うということがありましたが、のちに返還しています。
斎藤龍興が織田信長のために滅ぼされると郡上郡も動揺し鷲見氏などが侵入しますが、遠藤氏はこれを撃退しました。郡上郡には一向宗の寺が多くあったため、反織田同盟の拠点として使用されることもあったのですが、これを察知した信長が出兵してくると遠藤氏はすぐに降伏し、領土を安堵しました。
信長が明智光秀の謀反により討たれると、岐阜は織田信孝が治めるようになり、遠藤氏もその支配下にはいります。秀吉が信孝を圧していくと美濃の諸将は秀吉になびいていきますが、遠藤氏は信孝に忠義を通しました。そのため、秀吉がこの地を治めるようになると遠藤氏は追放され、郡上八幡城には稲葉一鉄の嫡男の貞通が入りました。貞通はおおいに城の改修を行い、山頂の本丸に天守台を設け、石塁を高くし、また山腹の二の丸を拡張して居館としました。
郡上郡は文徳天皇のとき、武儀郡から分離されて独立したものです。この地に遠藤盛数が犬鳴城を攻めるときに一時陣地を構えたのですが、本家の東常慶を滅亡させると、ここに本拠を移そうと、山上にあった八幡宮を南方山麓に移し、山上に新城を築城したのが郡上八幡城の始まりです。
遠藤盛数は郡上八幡城にいること三年で没し、そのあとを慶隆が継ぎましたが、幼年であったために母の再婚先である永井通利が後見しました。永禄七年、斎藤龍興が、竹中半兵衛のために一時、稲葉山城を追われて慶隆もその渦中に巻き込まれたとき、木越城主であった従兄弟が八幡城を奪うということがありましたが、のちに返還しています。
斎藤龍興が織田信長のために滅ぼされると郡上郡も動揺し鷲見氏などが侵入しますが、遠藤氏はこれを撃退しました。郡上郡には一向宗の寺が多くあったため、反織田同盟の拠点として使用されることもあったのですが、これを察知した信長が出兵してくると遠藤氏はすぐに降伏し、領土を安堵しました。
信長が明智光秀の謀反により討たれると、岐阜は織田信孝が治めるようになり、遠藤氏もその支配下にはいります。秀吉が信孝を圧していくと美濃の諸将は秀吉になびいていきますが、遠藤氏は信孝に忠義を通しました。そのため、秀吉がこの地を治めるようになると遠藤氏は追放され、郡上八幡城には稲葉一鉄の嫡男の貞通が入りました。貞通はおおいに城の改修を行い、山頂の本丸に天守台を設け、石塁を高くし、また山腹の二の丸を拡張して居館としました。
2 城主の変遷

その後、関ケ原の合戦が起こると岐阜城主の織田秀信は西軍に属し、美濃の諸将も西軍に属していきました。郡上八幡城主の稲葉貞通も西軍に属しました。遠藤氏にも西軍への誘いが来ますが、これを旧領回復の機会とみた遠藤慶隆は金森長近を通じて徳川家康に八幡城攻略の許しを得ました。
稲葉貞通はついに和議に踏み切り、遠藤氏が郡上八幡城に返り咲きます。その後、城主はさらに代わっていくことになります。
江戸中期ごろになると山城はみな外城を持つようになっていました。八幡城の場合も、慶長のころから山の中腹にあった二の丸のほかに外城を新設したものです。このときの工事は村山定右衛門などを奉行として作られました。これらが要害の新設というよりも政庁あるいは城主の住居の新設であることはあきらかでした。
金森氏改易のあと、八幡城は岩村城主松平氏が城番を命じられましたが、宝暦八年、宮津城主青山大膳亮幸道が入りました。
宝暦九年、青山幸道は南面中腹居館で本丸と称していたのを二の丸に移してここを本丸とし、さらに居館を新築してここを御殿と称するようにしました。こうして、八幡城は時代が下るにつれて居館や政庁が山の下へ下へと降りてきたのです。
青山氏は幸道より七代、約百年をうけついで幸直のときに明治維新を迎えています。その間民政に奮闘したものの大きな成果はあげることはできなかったようです。
稲葉貞通はついに和議に踏み切り、遠藤氏が郡上八幡城に返り咲きます。その後、城主はさらに代わっていくことになります。
江戸中期ごろになると山城はみな外城を持つようになっていました。八幡城の場合も、慶長のころから山の中腹にあった二の丸のほかに外城を新設したものです。このときの工事は村山定右衛門などを奉行として作られました。これらが要害の新設というよりも政庁あるいは城主の住居の新設であることはあきらかでした。
金森氏改易のあと、八幡城は岩村城主松平氏が城番を命じられましたが、宝暦八年、宮津城主青山大膳亮幸道が入りました。
宝暦九年、青山幸道は南面中腹居館で本丸と称していたのを二の丸に移してここを本丸とし、さらに居館を新築してここを御殿と称するようにしました。こうして、八幡城は時代が下るにつれて居館や政庁が山の下へ下へと降りてきたのです。
青山氏は幸道より七代、約百年をうけついで幸直のときに明治維新を迎えています。その間民政に奮闘したものの大きな成果はあげることはできなかったようです。
3 郡上八幡城の縄張り

八幡城のある城山は標高こそ380mありますが、比高は約110mほどの小さな山です。
しかしすべてが角岩で岩盤が堅く、傾斜は西面にゆるやかで南東面はきつく絶壁をなしているので、この方面から登ることは困難です。そのうえ、山の南面には吉田川が、西面には小駄良川が流れているので、本当に要害堅固な山ということができます。
この山の上に遠藤盛数によって、創築された郡上八幡城の本城があります。三百年の歳月を経ているのですが、土台が堅いので石垣はほとんど昔の姿をとどめています。残念なことに後世に建てられた本丸やその他の外城のほうはほとんど原形をとどめていませんが、これは平城の運命としてやむを得ないことと言えます。
現在は天守台跡に昭和八年に建てられた木造の模擬天守があります。これは木造の天守としては現存最古のものです。
ここに上ると東は和良筋を経て益田口方面、東北は明方筋を経て飛騨高山口方面、北は上保筋を経て越前大野および飛騨白川口方面、さらに南は下川筋を経て岐阜方面を一望のうちにおさめることができるという、稀にみる交通上の要衝となっています。
城の縄張りは中央部に天守台を置き、その左右に桜の丸と松の丸を配した、いわゆる連郭式城郭で、その周囲に腰曲輪をめぐらしています。そうして緩やかな西斜面には、要所に雛壇のようにさらに何段かの石塁を構築して厳重な抵抗線を構成しています。
しかし全般の構えは小大名の城郭の域は超えておらず、巨大な要害という城郭ではありません。
それでも小さい規模の山城にありがちな、たんなる逐次抵抗に終わることなく、常に敵を挟撃できるような工夫をして縄張りされていることは素晴らしく、間違いなく山城のなかでも秀作の部類に入る城なのです。
しかしすべてが角岩で岩盤が堅く、傾斜は西面にゆるやかで南東面はきつく絶壁をなしているので、この方面から登ることは困難です。そのうえ、山の南面には吉田川が、西面には小駄良川が流れているので、本当に要害堅固な山ということができます。
この山の上に遠藤盛数によって、創築された郡上八幡城の本城があります。三百年の歳月を経ているのですが、土台が堅いので石垣はほとんど昔の姿をとどめています。残念なことに後世に建てられた本丸やその他の外城のほうはほとんど原形をとどめていませんが、これは平城の運命としてやむを得ないことと言えます。
現在は天守台跡に昭和八年に建てられた木造の模擬天守があります。これは木造の天守としては現存最古のものです。
ここに上ると東は和良筋を経て益田口方面、東北は明方筋を経て飛騨高山口方面、北は上保筋を経て越前大野および飛騨白川口方面、さらに南は下川筋を経て岐阜方面を一望のうちにおさめることができるという、稀にみる交通上の要衝となっています。
城の縄張りは中央部に天守台を置き、その左右に桜の丸と松の丸を配した、いわゆる連郭式城郭で、その周囲に腰曲輪をめぐらしています。そうして緩やかな西斜面には、要所に雛壇のようにさらに何段かの石塁を構築して厳重な抵抗線を構成しています。
しかし全般の構えは小大名の城郭の域は超えておらず、巨大な要害という城郭ではありません。
それでも小さい規模の山城にありがちな、たんなる逐次抵抗に終わることなく、常に敵を挟撃できるような工夫をして縄張りされていることは素晴らしく、間違いなく山城のなかでも秀作の部類に入る城なのです。















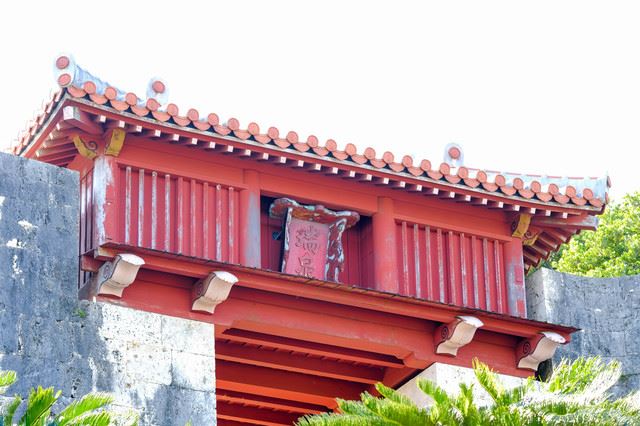






![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)

