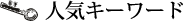音楽する哲学者? 知られざる音楽家ルソー
関連キーワード
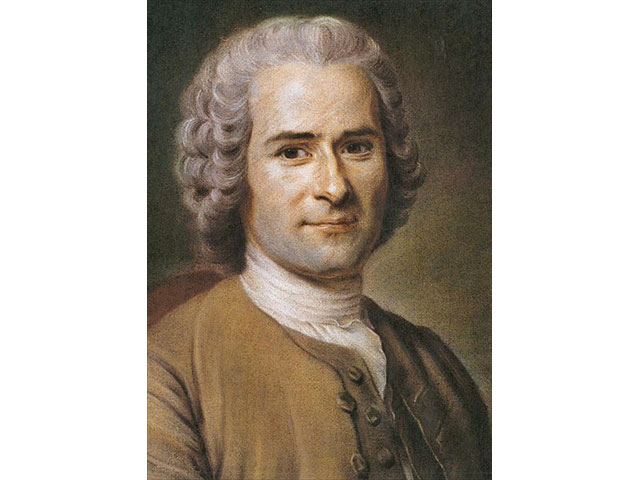
ルソーといえば、言わずと知れた『人間不平等起源論』に『社会契約論』、『エミール』などを書き残したフランスの思想家、哲学者。少なくとも世界史の教科書を見る限りはそうです。しかし、ここには人間ルソーを語る上で不可欠な一つの要素が欠けています。悪名高い変態エピソードではありません。
その要素とはズバリ「音楽」です。“No Music No Life”とはタワーレコードさんのキャッチフレーズですが、ルソーにとってはまさに“No Music No Life”でありました。ルソーの音楽家としての側面は彼の哲学の理解に欠かせないばかりか、実は日本人とも意外なつながりを持っています。
あまり聞かない「音楽家としてのルソー」を紹介します。
その要素とはズバリ「音楽」です。“No Music No Life”とはタワーレコードさんのキャッチフレーズですが、ルソーにとってはまさに“No Music No Life”でありました。ルソーの音楽家としての側面は彼の哲学の理解に欠かせないばかりか、実は日本人とも意外なつながりを持っています。
あまり聞かない「音楽家としてのルソー」を紹介します。
1. ルソーの音楽遍歴
まずは、ルソーがどのような音楽人生を送ったのか、簡単にまとめておきます。
ルソーは時計職人の息子として生まれたことはよく知られていますが、彼の父イザークはダンスをこよなく愛していました。また、母のジャンヌ・ベルナールは、よく歌を歌い、ときには弾き語りをしていたといいます。このように、専門的な音楽家家庭に生まれたわけではなかったルソーですが、幼いころから音楽に囲まれて育ちました。
ルソーの父イザークが、喧嘩がもとでジュネーブを去り、一旦は音楽環境が、ルソーから失われてしまいますが、1729年、ルソーはアヌシー大聖堂の聖歌隊養成所に寄宿することとなり、そこでは学長に音楽を教わりました。その後もルソーは、のちに彼の批判対象となるラモーの音楽書を読みこむなど、独学で研究に励み、作曲も始めました。ただ、ルソーの音楽教育はしかし不十分で、彼は楽譜を読むのがあまり得意ではなかったといいます。このことが後述する、1743年の『近代音楽論究』における彼の記譜法改革の提案につながります。
ルソーの『近代音楽論究』は評判になりませんでしたが、同じ年にヴェネチアで聞いた本場イタリアの音楽によって、ルソーはオペラに開眼します。帰国後、ルソーは中絶していたオペラに再び取り組み、1745年『優雅な詩の女神たち』を完成させます。このオペラはラモーに酷評されたものの、評判となり、リュシュリューにも気に入られました。1749年には『百科全書』の音楽関連の記事をディドロに依頼されています。そして、ルソーが40歳となる1752年に短期間で書き上げられた『村の占い師』が翌年の初演で大成功を収めます。その後は『エミール』や『社会契約論』などの執筆の傍、ラモーの音楽理論への(執拗な?)批判や、生前最後の著作となった『音楽辞典』の編纂に取り組みます。1770年代になると『ピグマリオン』(1770)を作曲、『ダフニスとクロエ』が未完のまま1778年、ルソーは死去しました。死ぬ直前も、ルソーは彼の最後の作曲である『柳のロマンス』を弾き語ったといいます。
ルソーは時計職人の息子として生まれたことはよく知られていますが、彼の父イザークはダンスをこよなく愛していました。また、母のジャンヌ・ベルナールは、よく歌を歌い、ときには弾き語りをしていたといいます。このように、専門的な音楽家家庭に生まれたわけではなかったルソーですが、幼いころから音楽に囲まれて育ちました。
ルソーの父イザークが、喧嘩がもとでジュネーブを去り、一旦は音楽環境が、ルソーから失われてしまいますが、1729年、ルソーはアヌシー大聖堂の聖歌隊養成所に寄宿することとなり、そこでは学長に音楽を教わりました。その後もルソーは、のちに彼の批判対象となるラモーの音楽書を読みこむなど、独学で研究に励み、作曲も始めました。ただ、ルソーの音楽教育はしかし不十分で、彼は楽譜を読むのがあまり得意ではなかったといいます。このことが後述する、1743年の『近代音楽論究』における彼の記譜法改革の提案につながります。
ルソーの『近代音楽論究』は評判になりませんでしたが、同じ年にヴェネチアで聞いた本場イタリアの音楽によって、ルソーはオペラに開眼します。帰国後、ルソーは中絶していたオペラに再び取り組み、1745年『優雅な詩の女神たち』を完成させます。このオペラはラモーに酷評されたものの、評判となり、リュシュリューにも気に入られました。1749年には『百科全書』の音楽関連の記事をディドロに依頼されています。そして、ルソーが40歳となる1752年に短期間で書き上げられた『村の占い師』が翌年の初演で大成功を収めます。その後は『エミール』や『社会契約論』などの執筆の傍、ラモーの音楽理論への(執拗な?)批判や、生前最後の著作となった『音楽辞典』の編纂に取り組みます。1770年代になると『ピグマリオン』(1770)を作曲、『ダフニスとクロエ』が未完のまま1778年、ルソーは死去しました。死ぬ直前も、ルソーは彼の最後の作曲である『柳のロマンス』を弾き語ったといいます。
2. ルソーと楽譜
ルソーと楽譜の関係についていくつかの切り口から紹介します。
・写譜師ルソー
ルソーが執筆のかたわら生業としたのは写譜師(Copyist)という仕事でした。いまいちピンとこないかもしれませんが、要するに楽譜の清書および筆写です。
ルソーにとって写譜は音楽の勉強の中心でした。もっとも、若きルソーが、リヨンで修道士に頼まれてしたカンタータの写譜は間違いだらけだったといいますから、写譜師として能力はあやしいものだったのかもしれません。しかし、晩年のルソーの写譜はなかなかにきれいで読みやすく、音楽家としてのルソー研究の第一人者である海老澤敏さんは、「几帳面な楽譜の書きぶりのなかで、一つ一つの音符は、細心の注意を払って、優雅に書かれている。まさに一種の芸術作品そのものとさえ言えはしまいか」と評価しています。
ルソーは『音楽辞典』(1767)において、「Copiste」(写譜師)という項目を設けており、9ページにわたる記事からは、ルソーの「写譜」への並々ならぬ情熱が感じられます。とりわけ、写譜師はどういう紙を使うべきか、どうすれば読みやすい譜面が書けるのか、といった細かい実務上のアドバイスも含まれているのが目を引きます。これはルソーの写譜師としての経験に基づいているといえるでしょう。さらに、写譜師のあるべき姿についてのルソー独自の意見も含まれており、たいへんユニークで興味深い記事となっています。
・「数字記譜法」
先述のルソーの記譜法改革について、もう少しく詳しく述べておきましょう。彼が『音楽に関する新記号案』(1742)や、『近代音楽論究』(1743)で表明した新しい記譜法は「数字記譜法」とよばれています。ルソーが新しい記譜法を考案しようと思い立った経緯は『告白』に書かれています。それによれば、彼は音楽の勉強、とくに読譜技術の習得において苦労した経験から、従来の五線譜記法に改良の余地があると考えたためだといいます。
1742年、ルソーは「数字記譜法」を発表するため、パリを訪れます。そして友人の紹介を介して、パリの学士院においてルソーは彼の新記法を発表する機会に恵まれます。この時朗読されたのが、『音楽に関する新記号案』でした。学士院はルソーの記法が「新しく」、「有用なもの」かどうか審査し、その「新しさ」には疑問を呈しながらも、その明快さやまとまりに対して、好意的な評価を与えています。しかし、器楽演奏に向かないことを指摘され、採用には至りませんでした。以下、ルソーの「数字記譜法」を簡単に紹介します。もっと詳しく知りたい方は海老澤敏著『ルソーと音楽』(ぺりかん社)を参考にしてください。
(1)調性、拍子、音階
ルソーの「数字記譜法」では、最初に調性および拍子が示されます。そして調性に従って「ド」から「シ」までの音階に1~7の数字をあて、0を休符にあてます。たとえば、ハ長調(C major)の場合は「ド(C)」が「1」となりますが、ヘ長調(F major)の場合は「ファ(F)」が「1」となります。
(2)オクターブ
オクターブが上がる場合は、その数字の上に点を打ち、オクターブが下がる場合は、その数字の下に点を打ちます。たとえば、ハ長調において、ピアノのまんなかの「ド」に、すぐ下の「ソ」が続く場合、「1」の次には下に点のついた「5」がきます。ハ長調で「1」「7」といえば、「ド」「シ」です。最初にどのオクターブから始まるかは、最初の音の前に、「c」や「d」というアルファベットで表されています。
(3)シャープ・フラット、拍節
シャープは数字に「/」を、フラットはその逆向きのアクセントをつけます。また、一拍は「、」で表されます。3連符は「123」などと表されます。トリル等は従来通りの記号が用いられています。
・写譜師ルソー
ルソーが執筆のかたわら生業としたのは写譜師(Copyist)という仕事でした。いまいちピンとこないかもしれませんが、要するに楽譜の清書および筆写です。
ルソーにとって写譜は音楽の勉強の中心でした。もっとも、若きルソーが、リヨンで修道士に頼まれてしたカンタータの写譜は間違いだらけだったといいますから、写譜師として能力はあやしいものだったのかもしれません。しかし、晩年のルソーの写譜はなかなかにきれいで読みやすく、音楽家としてのルソー研究の第一人者である海老澤敏さんは、「几帳面な楽譜の書きぶりのなかで、一つ一つの音符は、細心の注意を払って、優雅に書かれている。まさに一種の芸術作品そのものとさえ言えはしまいか」と評価しています。
ルソーは『音楽辞典』(1767)において、「Copiste」(写譜師)という項目を設けており、9ページにわたる記事からは、ルソーの「写譜」への並々ならぬ情熱が感じられます。とりわけ、写譜師はどういう紙を使うべきか、どうすれば読みやすい譜面が書けるのか、といった細かい実務上のアドバイスも含まれているのが目を引きます。これはルソーの写譜師としての経験に基づいているといえるでしょう。さらに、写譜師のあるべき姿についてのルソー独自の意見も含まれており、たいへんユニークで興味深い記事となっています。
・「数字記譜法」
先述のルソーの記譜法改革について、もう少しく詳しく述べておきましょう。彼が『音楽に関する新記号案』(1742)や、『近代音楽論究』(1743)で表明した新しい記譜法は「数字記譜法」とよばれています。ルソーが新しい記譜法を考案しようと思い立った経緯は『告白』に書かれています。それによれば、彼は音楽の勉強、とくに読譜技術の習得において苦労した経験から、従来の五線譜記法に改良の余地があると考えたためだといいます。
1742年、ルソーは「数字記譜法」を発表するため、パリを訪れます。そして友人の紹介を介して、パリの学士院においてルソーは彼の新記法を発表する機会に恵まれます。この時朗読されたのが、『音楽に関する新記号案』でした。学士院はルソーの記法が「新しく」、「有用なもの」かどうか審査し、その「新しさ」には疑問を呈しながらも、その明快さやまとまりに対して、好意的な評価を与えています。しかし、器楽演奏に向かないことを指摘され、採用には至りませんでした。以下、ルソーの「数字記譜法」を簡単に紹介します。もっと詳しく知りたい方は海老澤敏著『ルソーと音楽』(ぺりかん社)を参考にしてください。
(1)調性、拍子、音階
ルソーの「数字記譜法」では、最初に調性および拍子が示されます。そして調性に従って「ド」から「シ」までの音階に1~7の数字をあて、0を休符にあてます。たとえば、ハ長調(C major)の場合は「ド(C)」が「1」となりますが、ヘ長調(F major)の場合は「ファ(F)」が「1」となります。
(2)オクターブ
オクターブが上がる場合は、その数字の上に点を打ち、オクターブが下がる場合は、その数字の下に点を打ちます。たとえば、ハ長調において、ピアノのまんなかの「ド」に、すぐ下の「ソ」が続く場合、「1」の次には下に点のついた「5」がきます。ハ長調で「1」「7」といえば、「ド」「シ」です。最初にどのオクターブから始まるかは、最初の音の前に、「c」や「d」というアルファベットで表されています。
(3)シャープ・フラット、拍節
シャープは数字に「/」を、フラットはその逆向きのアクセントをつけます。また、一拍は「、」で表されます。3連符は「123」などと表されます。トリル等は従来通りの記号が用いられています。
3.『むすんでひらいて』はルソーの作曲か?
ルソーと音楽を語る上で有名な面白い話があります。それは、『むすんでひらいて』は本当にルソーの作品か?というミステリー。
『むすんでひらいて』とは、みなさんご存知、国民の歌の一つといっていいでしょう。この『むすんでひらいて』はルソーの作曲と言われることがあります。このルーツを探ったのが、海老澤敏さんの「『むすんでひらいて』考 -そのルーツを探る-」(1981)という、画期的な論考でした。以下、海老澤敏さんの研究の概要を紹介します。
・『見わたせば』~『むすんでひらいて』のルーツ(日本編)~
『むすんでひらいて』は明治後期にはすでに歌われ、第二次世界大戦後に歌唱の教材として採用され、文部省唱歌として広く浸透しました。しかし、『むすんでひらいて』は、さらにそれ以前、明治15年に伊沢修二を中心に編纂された『小学唱歌集』に収録されている『見わたせば』という歌にルーツをもちます。なお、『見わたせば』は岩波文庫の『日本唱歌集』に譜面とともに収録されています。
この唱歌『見わたせば』について、編纂者の伊沢修二は、「ルソー氏が睡眠中に作りたる曲」と解説しています。これがもととなって、『むすんでひらいて』は「ルソー作曲」といわれるようになりました。
・『グリーンヴィル』~『むすんでひらいて』のルーツ(海外編)~
『むすんでひらいて』と『見わたせば』のメロディーは、さらに別の曲、プロテスタントの賛美歌『グリーンヴィル』にも見出されます。この賛美歌は西洋から日本に伝来したもので、日本のさまざまな賛美歌集に収録され、ときに『ルソー』ともよばれこともありました。
さらに、英国で歌われる遊戯歌として紹介されているもののなかには『むすんでひらいて』のルーツと思われる楽曲も、翻訳歌集のなかに見つかっています。
・『ルソーの夢』~『グリーンヴィル』のルーツ~
これらの海外からやってきた『むすんでひらいて』のルーツは、どのようにしてルソーと結びついたのでしょうか。
伊沢修二が『見わたせば』をルソーが夢のなかで作曲した、と述べたことは、実は『グリーンヴィル』は『ルソーの夢』とよばれていたことに理由があります。そして、この『ルソーの夢』という名前の曲は別に存在します。それが、クラーマー(1751-1858)の手になる変奏曲。彼が『ルソーの夢』で用いた変奏主題は人気を集め、歌詞をつけられて広まりました。『グリーンヴィル』はそこにルーツを持つ一曲なのです。
・『村の占い師』~『ルソーの夢』のルーツ~
では、クラーマーはなぜ『ルソーの夢』と名付けたのでしょうか。答えは簡単で、クラーマーは『ルソーの夢』において変奏主題を『ルソーの新ロマンス』として流布していた旋律から取ったからです。そしてこの『ルソーの新ロマンス』、音楽家ルソーの成功を収めたオペラ『村の占い師』のなかの一曲が人気となり、編曲されて歌われたものなのです。
こうしてルソーの『村の占い師』は巡り巡って『むすんでひらいて』となり、時代も土地も遠く離れた日本の子供たちに歌い継がれることとなったのです。
ちなみに、この『むすんでひらいて』の起源を音楽で辿ることのできるCD、「むすんでひらいての謎」が2003年に登場しました。たいへん興味深い資料なのですが、新品の入手はおそらく困難。中古CD店をあたってみるしかなさそうです。
『むすんでひらいて』とは、みなさんご存知、国民の歌の一つといっていいでしょう。この『むすんでひらいて』はルソーの作曲と言われることがあります。このルーツを探ったのが、海老澤敏さんの「『むすんでひらいて』考 -そのルーツを探る-」(1981)という、画期的な論考でした。以下、海老澤敏さんの研究の概要を紹介します。
・『見わたせば』~『むすんでひらいて』のルーツ(日本編)~
『むすんでひらいて』は明治後期にはすでに歌われ、第二次世界大戦後に歌唱の教材として採用され、文部省唱歌として広く浸透しました。しかし、『むすんでひらいて』は、さらにそれ以前、明治15年に伊沢修二を中心に編纂された『小学唱歌集』に収録されている『見わたせば』という歌にルーツをもちます。なお、『見わたせば』は岩波文庫の『日本唱歌集』に譜面とともに収録されています。
この唱歌『見わたせば』について、編纂者の伊沢修二は、「ルソー氏が睡眠中に作りたる曲」と解説しています。これがもととなって、『むすんでひらいて』は「ルソー作曲」といわれるようになりました。
・『グリーンヴィル』~『むすんでひらいて』のルーツ(海外編)~
『むすんでひらいて』と『見わたせば』のメロディーは、さらに別の曲、プロテスタントの賛美歌『グリーンヴィル』にも見出されます。この賛美歌は西洋から日本に伝来したもので、日本のさまざまな賛美歌集に収録され、ときに『ルソー』ともよばれこともありました。
さらに、英国で歌われる遊戯歌として紹介されているもののなかには『むすんでひらいて』のルーツと思われる楽曲も、翻訳歌集のなかに見つかっています。
・『ルソーの夢』~『グリーンヴィル』のルーツ~
これらの海外からやってきた『むすんでひらいて』のルーツは、どのようにしてルソーと結びついたのでしょうか。
伊沢修二が『見わたせば』をルソーが夢のなかで作曲した、と述べたことは、実は『グリーンヴィル』は『ルソーの夢』とよばれていたことに理由があります。そして、この『ルソーの夢』という名前の曲は別に存在します。それが、クラーマー(1751-1858)の手になる変奏曲。彼が『ルソーの夢』で用いた変奏主題は人気を集め、歌詞をつけられて広まりました。『グリーンヴィル』はそこにルーツを持つ一曲なのです。
・『村の占い師』~『ルソーの夢』のルーツ~
では、クラーマーはなぜ『ルソーの夢』と名付けたのでしょうか。答えは簡単で、クラーマーは『ルソーの夢』において変奏主題を『ルソーの新ロマンス』として流布していた旋律から取ったからです。そしてこの『ルソーの新ロマンス』、音楽家ルソーの成功を収めたオペラ『村の占い師』のなかの一曲が人気となり、編曲されて歌われたものなのです。
こうしてルソーの『村の占い師』は巡り巡って『むすんでひらいて』となり、時代も土地も遠く離れた日本の子供たちに歌い継がれることとなったのです。
ちなみに、この『むすんでひらいて』の起源を音楽で辿ることのできるCD、「むすんでひらいての謎」が2003年に登場しました。たいへん興味深い資料なのですが、新品の入手はおそらく困難。中古CD店をあたってみるしかなさそうです。
人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感「孤独な散歩者」ルソーのことばとは?
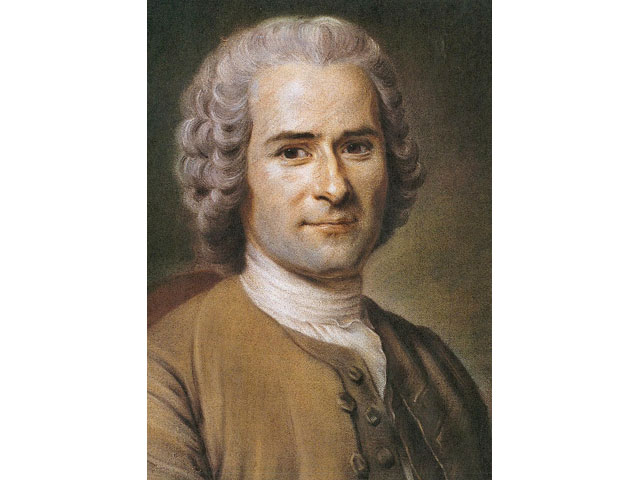
社会契約説を唱えた思想家として、しばしばホッブズとロックと並べられて登場するフランス人、ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)。
彼は革新的な思想家として歴史に名をとどめていますが、その奇矯な性格から晩年には社会から追放され、孤独な晩年を過ごしました。
ルソー晩年の作品『孤独な散歩者の夢想』Les Reveries du promeneur solitaireには彼の偽らざる老年の心境が吐露されています。ルソーは人生を振り返って何を思うのでしょうか。そして、老年をどのように過ごしたのでしょうか。美しいフランス語でも知られる『孤独なる散歩者の夢想』から、ルソーのことばを紹介します。(文中の引用は『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫より)
『孤独な散歩者の夢想』は次のようなことばではじまります。「要するに、僕は地上でただ一人きりになってしまった。もはや、兄弟もなければ隣人もなく、友人もなければ社会もなく、ただ自分一個があるのみだ。およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男が、全員一致で仲間はずれにされたのである。」
この悲愴的ともいえる一連の文章は『孤独な散歩者の夢想』全編の主題となり、『孤独な散歩者の夢想』を構成する「10の散歩」へと拡張・変奏されていきます。
この文章から孤独者ルソーがたどり着いた、晩年の境地を探ります。
彼は革新的な思想家として歴史に名をとどめていますが、その奇矯な性格から晩年には社会から追放され、孤独な晩年を過ごしました。
ルソー晩年の作品『孤独な散歩者の夢想』Les Reveries du promeneur solitaireには彼の偽らざる老年の心境が吐露されています。ルソーは人生を振り返って何を思うのでしょうか。そして、老年をどのように過ごしたのでしょうか。美しいフランス語でも知られる『孤独なる散歩者の夢想』から、ルソーのことばを紹介します。(文中の引用は『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫より)
『孤独な散歩者の夢想』は次のようなことばではじまります。「要するに、僕は地上でただ一人きりになってしまった。もはや、兄弟もなければ隣人もなく、友人もなければ社会もなく、ただ自分一個があるのみだ。およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男が、全員一致で仲間はずれにされたのである。」
この悲愴的ともいえる一連の文章は『孤独な散歩者の夢想』全編の主題となり、『孤独な散歩者の夢想』を構成する「10の散歩」へと拡張・変奏されていきます。
この文章から孤独者ルソーがたどり着いた、晩年の境地を探ります。
社会から孤立する散歩者ルソー
『孤独な散歩者の夢想』を一読した読者の目をひくのは、自分を疎外した社会に対するルソーの激しい怒りと軽蔑でしょう。
社会の不当に対する訴えと、ルソーの自己弁明、この二つの要素は、ルソーの穏やかな夢想の調和を打ち破る不協和音のごとく幾度も幾度も響きます。とくに、ルソーが「陰謀」や「罠」などの強い言葉を厭わずに書き連ねる、自分を疎外した社会に対する非難、告発は徹底を極め、読者にルソーには被害妄想癖があるのではないか、と思わせるほどです。
そして、「およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男」と述べているように、ルソーは、自分という人間は社会に受け入れられるには、愛情深く、正直・潔癖にすぎるのだ、といったような自己弁明を繰り返します。
こうした社会非難の背景にはルソーの哲学の基礎にある、性善説的な考えがあります。つまり、人間は善を備えて生まれてくるのであり、社会に交わる中で悪徳に染まっていくのだ、とルソーは考えるのです。
ルソーはこの考えを発展させた教育学の古典『エミール』において、子供の本分を尊重し、自由な養育を提唱しますが、『エミール』はパリで発禁処分を受け、ルソーが社会から孤立する一つの要因となるのです。
社会の不当に対する訴えと、ルソーの自己弁明、この二つの要素は、ルソーの穏やかな夢想の調和を打ち破る不協和音のごとく幾度も幾度も響きます。とくに、ルソーが「陰謀」や「罠」などの強い言葉を厭わずに書き連ねる、自分を疎外した社会に対する非難、告発は徹底を極め、読者にルソーには被害妄想癖があるのではないか、と思わせるほどです。
そして、「およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男」と述べているように、ルソーは、自分という人間は社会に受け入れられるには、愛情深く、正直・潔癖にすぎるのだ、といったような自己弁明を繰り返します。
こうした社会非難の背景にはルソーの哲学の基礎にある、性善説的な考えがあります。つまり、人間は善を備えて生まれてくるのであり、社会に交わる中で悪徳に染まっていくのだ、とルソーは考えるのです。
ルソーはこの考えを発展させた教育学の古典『エミール』において、子供の本分を尊重し、自由な養育を提唱しますが、『エミール』はパリで発禁処分を受け、ルソーが社会から孤立する一つの要因となるのです。
子供を愛するルソー
『孤独な散歩者の夢想』のなかで、ルソーは孤独の平穏をほめたたえ、自己正当化を繰り返しますが、それでもやはり、彼は社会を批判することをやめようとはしません。ルソーは心の奥底で実は、人間との交わりを求めているからです。社会に不信感、いな、敵意を覚えているルソーは、そうした交流を子供達のあいだに求めます。「第9の散歩」は、「子供」をテーマにして夢想が展開されます。
ルソーは「かわいい坊やたちが、遊び戯れているのを見るのが、僕ぐらい好きだった人間があろうとは思わない」と書いています。『エミール』で展開した教育論の根幹も子供の善性への信頼にありましたが、ルソーは社会に汚れる前の子供達との時間に老年の悦びを見出したのでした。しかし、「第9の散歩」にスケッチされる子供との愉しい時間の夢想もまた、ルソーの疑念によって乱されます。
ルソーは子供と戯れている時に「僕をつけているように誰かからか回された探偵とおぼしき」男の視線を感じるのです。
晩年のルソーは人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感のあいだで葛藤のなかで生きねばならなかったのです。
ルソーは「かわいい坊やたちが、遊び戯れているのを見るのが、僕ぐらい好きだった人間があろうとは思わない」と書いています。『エミール』で展開した教育論の根幹も子供の善性への信頼にありましたが、ルソーは社会に汚れる前の子供達との時間に老年の悦びを見出したのでした。しかし、「第9の散歩」にスケッチされる子供との愉しい時間の夢想もまた、ルソーの疑念によって乱されます。
ルソーは子供と戯れている時に「僕をつけているように誰かからか回された探偵とおぼしき」男の視線を感じるのです。
晩年のルソーは人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感のあいだで葛藤のなかで生きねばならなかったのです。
ルソーの幸福論
晩年のルソーは都会の喧騒をはなれ、楽譜写しで収入を得、博物学に熱中します。
植物学の喜びについては「第7の散歩」で詳しく語られていますが、ルソーは「自分でも考えてみると噴き出さずにはいられないくらい、いささか常軌を逸したほどの凝り方」で植物学に熱中します。彼にとって生命にあふれる自然の風景は「人間の目と心が永久に倦むことのない世界で唯一の景観」であるのです。ルソーの幸福観のカギはこの自然との一体感の認識にあります。
ルソーの幸福観が最も顕著に、そして最も美しいことばで示されているのが、ピエンヌ湖のサン・ピエール島での思い出とともに綴られる「第五の散歩」。ルソーは、幸福は一過的に訪れる強烈な享楽や快楽からは得られず、それらの感覚は「人生という線の中のまばらな点々にすぎない」と表現します。ルターにとっての幸福とは、「消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態」であるのです。
このような幸せをルソーは、豊かなサン・ピエール島の自然の最中で感じたとある恍惚、すなわち『孤独な散歩者の夢想』の冒頭で述べた、自然のなかで経験する「ただ自分一個があるのみだ」という認識のなかに見つけます。自然に身を任せながら夢想にふける、そうした境地において、人間が楽しむものは「自分以外の、自分の存在以外の何物でもない」のだ、そうルソーは語ります。
社会から逃れたルソーは、豊かな自然に囲まれて夢想に耽る、「孤独な散歩者」の中に幸福を見出したのです。
植物学の喜びについては「第7の散歩」で詳しく語られていますが、ルソーは「自分でも考えてみると噴き出さずにはいられないくらい、いささか常軌を逸したほどの凝り方」で植物学に熱中します。彼にとって生命にあふれる自然の風景は「人間の目と心が永久に倦むことのない世界で唯一の景観」であるのです。ルソーの幸福観のカギはこの自然との一体感の認識にあります。
ルソーの幸福観が最も顕著に、そして最も美しいことばで示されているのが、ピエンヌ湖のサン・ピエール島での思い出とともに綴られる「第五の散歩」。ルソーは、幸福は一過的に訪れる強烈な享楽や快楽からは得られず、それらの感覚は「人生という線の中のまばらな点々にすぎない」と表現します。ルターにとっての幸福とは、「消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態」であるのです。
このような幸せをルソーは、豊かなサン・ピエール島の自然の最中で感じたとある恍惚、すなわち『孤独な散歩者の夢想』の冒頭で述べた、自然のなかで経験する「ただ自分一個があるのみだ」という認識のなかに見つけます。自然に身を任せながら夢想にふける、そうした境地において、人間が楽しむものは「自分以外の、自分の存在以外の何物でもない」のだ、そうルソーは語ります。
社会から逃れたルソーは、豊かな自然に囲まれて夢想に耽る、「孤独な散歩者」の中に幸福を見出したのです。
ビブリオグラフィ
『孤独な散歩者の夢想』は多くの訳書が出版されていますが、手軽な文庫本は次の三種類が出版されています。
・『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫 1951
・『孤独な散歩者の夢想』今野一雄訳 岩波文庫 1960
・『孤独な散歩者の夢想』永田千奈訳 光文社古典新訳文庫 2012
・『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫 1951
・『孤独な散歩者の夢想』今野一雄訳 岩波文庫 1960
・『孤独な散歩者の夢想』永田千奈訳 光文社古典新訳文庫 2012
人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感「孤独な散歩者」ルソーのことばとは?
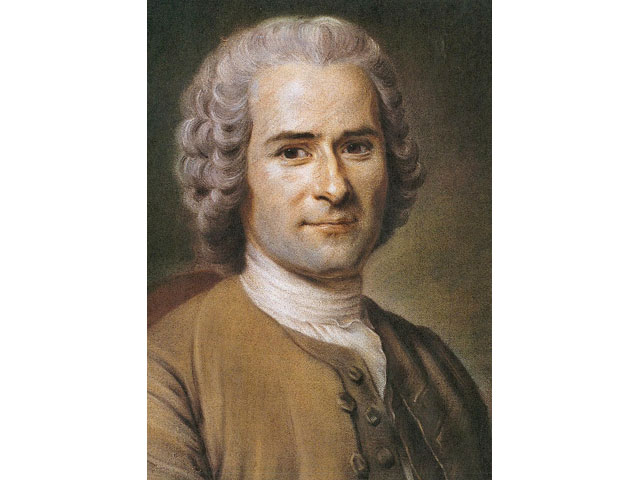
社会契約説を唱えた思想家として、しばしばホッブズとロックと並べられて登場するフランス人、ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)。
彼は革新的な思想家として歴史に名をとどめていますが、その奇矯な性格から晩年には社会から追放され、孤独な晩年を過ごしました。
ルソー晩年の作品『孤独な散歩者の夢想』Les Reveries du promeneur solitaireには彼の偽らざる老年の心境が吐露されています。ルソーは人生を振り返って何を思うのでしょうか。そして、老年をどのように過ごしたのでしょうか。美しいフランス語でも知られる『孤独なる散歩者の夢想』から、ルソーのことばを紹介します。(文中の引用は『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫より)
『孤独な散歩者の夢想』は次のようなことばではじまります。「要するに、僕は地上でただ一人きりになってしまった。もはや、兄弟もなければ隣人もなく、友人もなければ社会もなく、ただ自分一個があるのみだ。およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男が、全員一致で仲間はずれにされたのである。」
この悲愴的ともいえる一連の文章は『孤独な散歩者の夢想』全編の主題となり、『孤独な散歩者の夢想』を構成する「10の散歩」へと拡張・変奏されていきます。
この文章から孤独者ルソーがたどり着いた、晩年の境地を探ります。
彼は革新的な思想家として歴史に名をとどめていますが、その奇矯な性格から晩年には社会から追放され、孤独な晩年を過ごしました。
ルソー晩年の作品『孤独な散歩者の夢想』Les Reveries du promeneur solitaireには彼の偽らざる老年の心境が吐露されています。ルソーは人生を振り返って何を思うのでしょうか。そして、老年をどのように過ごしたのでしょうか。美しいフランス語でも知られる『孤独なる散歩者の夢想』から、ルソーのことばを紹介します。(文中の引用は『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫より)
『孤独な散歩者の夢想』は次のようなことばではじまります。「要するに、僕は地上でただ一人きりになってしまった。もはや、兄弟もなければ隣人もなく、友人もなければ社会もなく、ただ自分一個があるのみだ。およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男が、全員一致で仲間はずれにされたのである。」
この悲愴的ともいえる一連の文章は『孤独な散歩者の夢想』全編の主題となり、『孤独な散歩者の夢想』を構成する「10の散歩」へと拡張・変奏されていきます。
この文章から孤独者ルソーがたどり着いた、晩年の境地を探ります。
社会から孤立する散歩者ルソー
『孤独な散歩者の夢想』を一読した読者の目をひくのは、自分を疎外した社会に対するルソーの激しい怒りと軽蔑でしょう。
社会の不当に対する訴えと、ルソーの自己弁明、この二つの要素は、ルソーの穏やかな夢想の調和を打ち破る不協和音のごとく幾度も幾度も響きます。とくに、ルソーが「陰謀」や「罠」などの強い言葉を厭わずに書き連ねる、自分を疎外した社会に対する非難、告発は徹底を極め、読者にルソーには被害妄想癖があるのではないか、と思わせるほどです。
そして、「およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男」と述べているように、ルソーは、自分という人間は社会に受け入れられるには、愛情深く、正直・潔癖にすぎるのだ、といったような自己弁明を繰り返します。
こうした社会非難の背景にはルソーの哲学の基礎にある、性善説的な考えがあります。つまり、人間は善を備えて生まれてくるのであり、社会に交わる中で悪徳に染まっていくのだ、とルソーは考えるのです。
ルソーはこの考えを発展させた教育学の古典『エミール』において、子供の本分を尊重し、自由な養育を提唱しますが、『エミール』はパリで発禁処分を受け、ルソーが社会から孤立する一つの要因となるのです。
社会の不当に対する訴えと、ルソーの自己弁明、この二つの要素は、ルソーの穏やかな夢想の調和を打ち破る不協和音のごとく幾度も幾度も響きます。とくに、ルソーが「陰謀」や「罠」などの強い言葉を厭わずに書き連ねる、自分を疎外した社会に対する非難、告発は徹底を極め、読者にルソーには被害妄想癖があるのではないか、と思わせるほどです。
そして、「およそ人間のうちで最も社交的であり、最も人なつこい男」と述べているように、ルソーは、自分という人間は社会に受け入れられるには、愛情深く、正直・潔癖にすぎるのだ、といったような自己弁明を繰り返します。
こうした社会非難の背景にはルソーの哲学の基礎にある、性善説的な考えがあります。つまり、人間は善を備えて生まれてくるのであり、社会に交わる中で悪徳に染まっていくのだ、とルソーは考えるのです。
ルソーはこの考えを発展させた教育学の古典『エミール』において、子供の本分を尊重し、自由な養育を提唱しますが、『エミール』はパリで発禁処分を受け、ルソーが社会から孤立する一つの要因となるのです。
子供を愛するルソー
『孤独な散歩者の夢想』のなかで、ルソーは孤独の平穏をほめたたえ、自己正当化を繰り返しますが、それでもやはり、彼は社会を批判することをやめようとはしません。ルソーは心の奥底で実は、人間との交わりを求めているからです。社会に不信感、いな、敵意を覚えているルソーは、そうした交流を子供達のあいだに求めます。「第9の散歩」は、「子供」をテーマにして夢想が展開されます。
ルソーは「かわいい坊やたちが、遊び戯れているのを見るのが、僕ぐらい好きだった人間があろうとは思わない」と書いています。『エミール』で展開した教育論の根幹も子供の善性への信頼にありましたが、ルソーは社会に汚れる前の子供達との時間に老年の悦びを見出したのでした。しかし、「第9の散歩」にスケッチされる子供との愉しい時間の夢想もまた、ルソーの疑念によって乱されます。
ルソーは子供と戯れている時に「僕をつけているように誰かからか回された探偵とおぼしき」男の視線を感じるのです。
晩年のルソーは人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感のあいだで葛藤のなかで生きねばならなかったのです。
ルソーは「かわいい坊やたちが、遊び戯れているのを見るのが、僕ぐらい好きだった人間があろうとは思わない」と書いています。『エミール』で展開した教育論の根幹も子供の善性への信頼にありましたが、ルソーは社会に汚れる前の子供達との時間に老年の悦びを見出したのでした。しかし、「第9の散歩」にスケッチされる子供との愉しい時間の夢想もまた、ルソーの疑念によって乱されます。
ルソーは子供と戯れている時に「僕をつけているように誰かからか回された探偵とおぼしき」男の視線を感じるのです。
晩年のルソーは人とのつながりへの渇望と、生きにくい社会への反感のあいだで葛藤のなかで生きねばならなかったのです。
ルソーの幸福論
晩年のルソーは都会の喧騒をはなれ、楽譜写しで収入を得、博物学に熱中します。
植物学の喜びについては「第7の散歩」で詳しく語られていますが、ルソーは「自分でも考えてみると噴き出さずにはいられないくらい、いささか常軌を逸したほどの凝り方」で植物学に熱中します。彼にとって生命にあふれる自然の風景は「人間の目と心が永久に倦むことのない世界で唯一の景観」であるのです。ルソーの幸福観のカギはこの自然との一体感の認識にあります。
ルソーの幸福観が最も顕著に、そして最も美しいことばで示されているのが、ピエンヌ湖のサン・ピエール島での思い出とともに綴られる「第五の散歩」。ルソーは、幸福は一過的に訪れる強烈な享楽や快楽からは得られず、それらの感覚は「人生という線の中のまばらな点々にすぎない」と表現します。ルターにとっての幸福とは、「消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態」であるのです。
このような幸せをルソーは、豊かなサン・ピエール島の自然の最中で感じたとある恍惚、すなわち『孤独な散歩者の夢想』の冒頭で述べた、自然のなかで経験する「ただ自分一個があるのみだ」という認識のなかに見つけます。自然に身を任せながら夢想にふける、そうした境地において、人間が楽しむものは「自分以外の、自分の存在以外の何物でもない」のだ、そうルソーは語ります。
社会から逃れたルソーは、豊かな自然に囲まれて夢想に耽る、「孤独な散歩者」の中に幸福を見出したのです。
植物学の喜びについては「第7の散歩」で詳しく語られていますが、ルソーは「自分でも考えてみると噴き出さずにはいられないくらい、いささか常軌を逸したほどの凝り方」で植物学に熱中します。彼にとって生命にあふれる自然の風景は「人間の目と心が永久に倦むことのない世界で唯一の景観」であるのです。ルソーの幸福観のカギはこの自然との一体感の認識にあります。
ルソーの幸福観が最も顕著に、そして最も美しいことばで示されているのが、ピエンヌ湖のサン・ピエール島での思い出とともに綴られる「第五の散歩」。ルソーは、幸福は一過的に訪れる強烈な享楽や快楽からは得られず、それらの感覚は「人生という線の中のまばらな点々にすぎない」と表現します。ルターにとっての幸福とは、「消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態」であるのです。
このような幸せをルソーは、豊かなサン・ピエール島の自然の最中で感じたとある恍惚、すなわち『孤独な散歩者の夢想』の冒頭で述べた、自然のなかで経験する「ただ自分一個があるのみだ」という認識のなかに見つけます。自然に身を任せながら夢想にふける、そうした境地において、人間が楽しむものは「自分以外の、自分の存在以外の何物でもない」のだ、そうルソーは語ります。
社会から逃れたルソーは、豊かな自然に囲まれて夢想に耽る、「孤独な散歩者」の中に幸福を見出したのです。
ビブリオグラフィ
『孤独な散歩者の夢想』は多くの訳書が出版されていますが、手軽な文庫本は次の三種類が出版されています。
・『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫 1951
・『孤独な散歩者の夢想』今野一雄訳 岩波文庫 1960
・『孤独な散歩者の夢想』永田千奈訳 光文社古典新訳文庫 2012
・『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂訳 新潮文庫 1951
・『孤独な散歩者の夢想』今野一雄訳 岩波文庫 1960
・『孤独な散歩者の夢想』永田千奈訳 光文社古典新訳文庫 2012

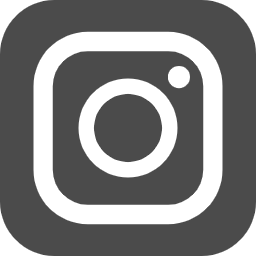
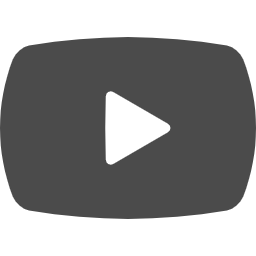

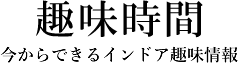
















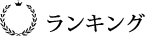

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)